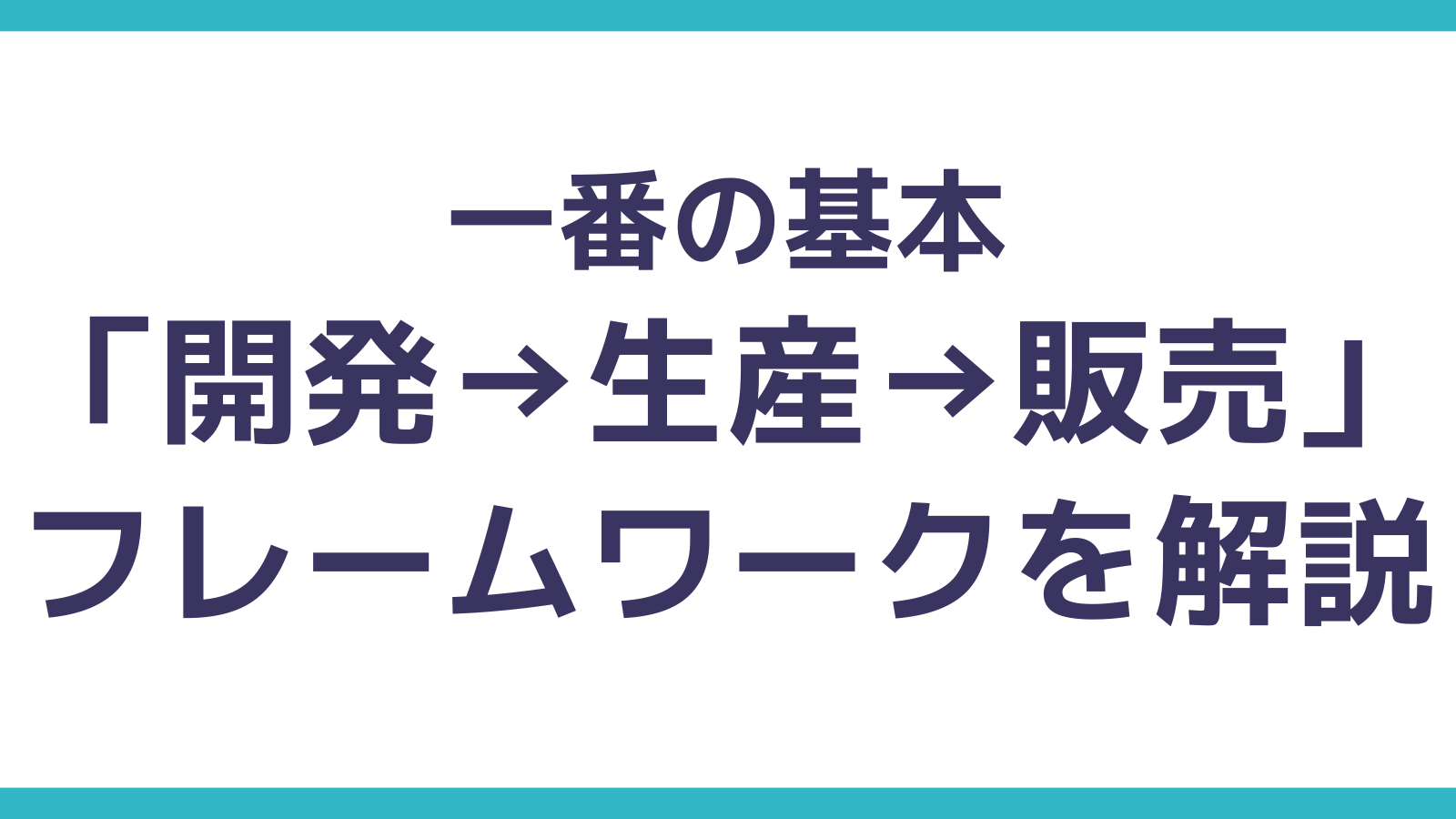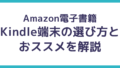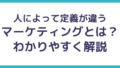ビジネスに関するフレームワークは数多く存在しますが、その中でも最も基本となるフレームワークがあります。
ビジネスの根幹をなすこのフレームワークを理解しておけば、ビジネスに関連するさまざまな事柄を整理しながら把握できるでしょう。
この記事では、この「開発→生産→販売」という最も基本的なフレームワークを、使い方含めてわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【概念の本質】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質)
ビジネスで一番基本となるフレームワークとは?
「開発→生産・仕入→販売」のフレームワーク
「開発→生産・仕入→販売」のフレームワークは、誰もが知っているようにごく当たり前のことです。
フレームワークというと大げさに聞こえるかもしれませんが、このシンプルさが実は「最強」なのです。
本記事では、このフレームワークを以下の3つのポイントに分けて解説します。
・なぜ「開発→生産・仕入→販売」が一番基本なのか?
・「開発→生産・仕入→販売」の詳細解説
・具体的な使い方
に分けてそれぞれ紹介します。
なぜ「開発→生産・仕入→販売」が一番基本なのか?
製品・商品・サービスを創って提供することがビジネスの基本だから
お客様に製品・商品・サービスを提供するには、「開発→生産・仕入→販売」という仕組みが不可欠です。
もし製品・商品・サービスがなければ、お客様から対価をいただくことはできず、ビジネスは成り立ちません。
したがって、「開発→生産・仕入→販売」こそがビジネスの根幹であり、最も基本となる要素なのです。
また、「開発→生産・仕入→販売」の各フローは、どれか一つでも欠けると製品・商品・サービスを提供できないため、この3工程は常にセットで考える必要があります。
「開発→生産・仕入→販売」の詳細解説
「開発→生産・仕入→販売」は、製品・商品・サービスを「創り(開発)」、創ったものを「安定的に届ける仕組みを作り(生産・仕入れ)」、そしてお客様に「購入してもらう(販売)」という一連の流れを指します。
以下、それぞれの工程について詳しく説明します。
・開発
・生産・仕入
・販売
開発
製品・商品・サービスを創り出す工程
開発とは、お客様の課題、願望、困りごとを解決する製品・商品・サービスを具体的に形にする工程です。
アイデアを形にしたり、新しい素材や技術を製品・商品・サービスに組み込んだりすることで、既存のものよりも優れた製品・商品・サービスを創り出します。
製造業ではイメージしやすいかもしれませんが、仕入れ販売業においても、どのような製品・商品・サービスを提供するかを考える重要な工程です。
生産・仕入
製品・商品・サービスを安定的に供給する工程
生産・仕入れは、開発された製品・商品・サービスを安定的に生産・調達する工程です。
開発されたものと同じ品質のものを安定的に作り続ける工程であり、主に工場での生産や、システム分野ではサーバーなどの構築・保守がこの工程に該当します。
販売
製品・商品・サービスを認知させ、購入へ繋げる工程
販売は、良い製品・商品・サービスが開発され、生産・仕入れ体制が整っていても、顧客に販売できなければビジネスとして成り立たないため、非常に重要な工程です。
具体的には、製品・商品・サービスを顧客に知ってもらい、興味を持たせ、「購入したい」と思ってもらい、実際に購入という行動を実行してもらうための一連の活動を指します。
具体的な使い方
このフレームワークがどれほど有用であるかを、具体的な使い方を交えてご紹介します。
各社の強みを把握する
本当の強みがわかる
会社には強みと弱みがあります。
その際に、「開発→生産・仕入→販売」それぞれのどの部分が強みなのか?を分析してみることで、本当の強みを把握できます。
例えば、年収の高さで知られるキーエンスを例に挙げましょう。
キーエンスといえば、「営業力が強い会社」というイメージを持つ方が多いかもしれません。
この「営業力がある」とは、「開発→生産・仕入→販売」のフレームワークの中で、「販売」が強いことを指すでしょう。
しかし、キーエンスの財務諸表を見ると、売上総利益率(粗利率)が80%を超えていることがわかります。この高い利益率を営業力だけで稼ぎ出せるでしょうか?
また、生産体制は外部に委託しているため、生産が同社の強みとはいえません。
確かに営業力も非常に強いですが、キーエンスの真の強みは「開発」にあるのです。
同社の製品開発ポリシーは、粗利率80%以上の商品を開発すること。
キーエンスのウェブサイトには多数の製品が掲載されていますが、それらすべてが粗利率80%以上を誇っています。
したがって、売れば売るほど大きな利益が得られるため、非常に高い収益性を実現しています。その潤沢な利益を人件費に充てているため、社員の給与水準も非常に高いのです。
このように、世間一般では営業力の強い会社とされていますが、このフレームワークで一つずつ紐解いていくと、実は開発にこそ真の強みがあることが見えてきます。
(詳しくは、「キーエンス高利益率の理由」をわかりやすく解説を参照)
会社の課題の発生場所を把握する
課題仮説が立つ
「開発→生産・仕入→販売」の流れの中で、特に課題が発生しやすいのはどの部分でしょうか?
最も頻繁に問題が起きるのは、このフローの「→」の部分です。
生産側は開発に対し、「なぜ開発はこんな難しい仕様にするんだろう?こんな仕様では安定生産できずに不良品が発生するではないか!」
生産側は販売に対し、「なぜもっと計画的に販売しないのだろう?急にたくさん生産しろと言われてもできないよ!」と感じることがあります。
販売側は開発に対し、「なぜこんな売れない製品を開発するんだ?」
販売側は生産に対し、「こんな生産体制では、せっかく販売しても不良品や納期遅れでクレームになるだけだ!」と感じることがあります。
開発側は販売に対し、「なぜお客様のニーズを把握できないのか?良い製品が開発できないじゃないか!」
開発側は生産に対し、「せっかく良いものを開発したのに、なぜきちんと生産してくれないんだ!」と感じることがあります。
このように、各部署が他の部署に対して抱く不満は、どの会社でも同様に発生するものです。
これらはまさに、「開発→生産・仕入→販売」の「→」部分における課題にほかなりません。
では、この「→」部分の課題は誰が解決する責任を持つのでしょうか?この点が曖昧になっているケースが多く見受けられます。
各部署内での課題は、開発部長、生産・仕入部長、販売部長(営業部長)がそれぞれ責任を持ちます。
しかし、部署間の「→」に発生する課題は、その上長である社長や事業部長の管轄となります。現実的には、それぞれの部長間の協議が必要となることが多いですが、利害関係が対立し、課題解決に至らないケースも少なくありません。
また、現場で働く人々は、各部署の最適化を図りがちです。
しかし、その最適化が会社全体にとって最適な方法となっていないことも多いのです。これこそが部分最適と全体最適の違いといえるでしょう。
(詳しくは、全く違う!全体最適と部分最適の違いをわかりやすく解説を参照)
だからこそ、「開発→生産・仕入→販売」のフレームワークで業務を捉え、自部署だけの最適化にとどまらず、全社としての最適化を視野に入れて考えることができるようになることが重要なのです。
組織図から戦略を予測する
他社の戦略を予測できる
組織の本質は、一人では達成できないことを実現することにあります。
(組織の本質の詳細は、「会社組織」の本質とは?をわかりやすく解説を参照)
そのため、役割を分担して業務を行います。この分業体制を視覚的に表したものが組織図です。
組織図を見ると、開発部、生産(工場)・仕入部、販売部(営業部)に分かれているケースが多く見られます。
企業によっては、会社全体をこれらの組織に完全に分業するパターンもあれば、事業部ごとに括り、その中に同様の分業体制を設ける事業部制もあります。
組織図に示された「開発→生産・仕入→販売」の体制を見ることで、その企業がどのような戦略を考えているかを予測できるのです。
(組織図の詳細は、「組織図」の見方・考え方・種類をわかりやすく解説を参照)
思い込みを排除する
言葉の思い込みを排除できる
「IT人材」という言葉を皆さんも耳にしたことがあると思いますが、具体的にどのような業務に携わる人を指すのでしょうか?
一般的にはエンジニアをイメージされるかもしれません。
しかし、このような場合も「開発→生産・仕入→販売」のフレームワークで捉えると、理解が深まります。
開発に関わるIT人材とは、例えばAIを活用したシステム開発をはじめ、新しいWebサービスの仕組みを開発する人です。
生産に関わるIT人材といえば、開発されたシステムの保守・維持管理を行う人のことです。
販売に関わるIT人材とは、SEO対策などにより、自社ウェブサイトへの流入数を拡大するWebマーケティングを行う人材です。
このように、一口に「IT人材」といっても、その仕事は開発だけでなく、生産、販売と多岐にわたります。このフレームワークで見ることで、言葉の思い込みを排除して理解することができるのです。
業務の目的を理解する
目的から仕事を整理できる
例えば広告宣伝は、「開発→生産・仕入→販売」のどの工程に当たるでしょうか?「販売」の一部ですね。
開発・生産された製品やサービスを「消費者に伝え、購入したいと思ってもらう」ことが広告宣伝の主な目的です。
広告宣伝と聞くと華やかな部署に感じられますが、実際には「販売」における一つの機能に過ぎません。
すでに開発・生産体制が構築されたものを、いかに効率的かつ効果的に伝えるか、という役割を担っています。
華やかに見える広告代理店業界も、その基本的な業務は販売活動を代行することであると理解できます。
マーケティングを理解する
よく使うが、人により意味の異なるマーケティングを理解できる
「開発→生産・仕入→販売」の流れ全体を考えることが、マーケティングの本質です。
しかし、「マーケティング」という言葉ほど、頻繁に使われるにもかかわらず、人によって定義が異なるものも珍しくありません。
マーケティングの一般的な定義は、「製品・商品・サービスが売れる仕組みを作ること」とされています。
この多義的な「マーケティング」という言葉は、広義・狭義・手法という3つの視点で捉えることで、その本質をより深く理解できます。
具体的には、広義では「会社の活動そのもの」を指し、少し狭義では「開発→生産→販売の流れ全体を設計すること」を意味します。そして手法としては、市場調査や広告宣伝などが挙げられます。
したがって、このフレームワークを念頭に置きながらコミュニケーションを取ることで、相手がどのような定義で「マーケティング」という言葉を使っているのかをイメージしやすくなり、より的確な対話が可能になります。
(マーケティングの詳細は、マーケティングとは?広義・狭義・手法に分けると理解できるを参照)
バリューチェーン、サプライチェーンを理解する
よく似たフレームワークをまとめて理解できる
バリューチェーンもサプライチェーンも基本的には、
「開発→生産・仕入→販売」の流れを最適化することが目的になります。
バリューチェーンはその工程ごとの付加価値に焦点を当てますが、サプライチェーンは、供給体制にスポットを当てているだけの違いです。
戦略を理解する
戦略立案のポイントが理解できる
会社の戦略を考える際も、「開発→生産・仕入→販売」のフレームワークを通して見ると、より深く理解できます。
戦略は大きく分けて、差別化戦略と時間戦略の2つに分類できます。
差別化戦略: 「開発→生産・仕入→販売」の中で、どの部分を強みにすることで、他社との製品・商品・サービスの差別化を図るか、という視点です。
時間戦略: 「開発→生産・仕入→販売」のサイクルをいかに早く回すか、という視点です。
製品・商品・サービスをベースとしたさまざまな戦略が存在しますが、優れた製品・商品・サービスを提供するために、特定の領域に特化する「差別化戦略」と、全体のサイクルを迅速に回す「時間戦略」があることを、このフレームワークで明確に理解できるでしょう。
ビジネスで一番基本となるフレームワークの「まとめ」
「開発→生産・仕入→販売」のフレームワーク
が一番の基本となるフレームワークです。
このフレームワークを理解し、ビジネスに関連する事柄をこの視点を通して見ることで、それぞれの役割や相互関係を深く理解できるようになるでしょう。
この記事に関するよくある質問
Q: スタッフの私は、この3つのどこにも当てはまらない気がします。
A: 決してそんなことはありません。スタッフ職(バックオフィス)のミッションは、現場の各担当者がこのサイクルを回すことに専念できる「基盤」を作ることです。
環境整備やデータ管理、システムの維持などは、いわばビジネスという土台を支える「インフラ」であり、欠かせない重要任務です。
Q:なぜこの3つは「セット」で考えないといけないのですか?
A:どんなに優れた「開発」をしても、売るための「販売」部隊がいなければ販売数が伸びません。逆に「販売」が先行しても、売る「モノ(生産)」がなければ販売できません。
一定水準以上のレベルでこの3つが揃って初めてお客様にサービスを提供することができるからです。
他にもこの記事に関するよくある質問をnoteで答えています。質問内容は以下です。
Q1: スタッフの私は、この3つのどこにも当てはまらない気がします。
Q2:なぜ「販売」だけ頑張ってもダメなのですか?
Q3:なぜこの3つは「セット」で考えないといけないのですか?
Q4: 「IT人材」になりたいのですが、何から手をつけるべきですか?
Q5:広告代理店は「派手」なイメージですが、結局は「販売」が中心なのですか?
Q6:営業(販売)と工場(生産)の仲が悪いのはなぜですか?
Q7:上司が「マーケティング」という言葉を多用しますが、意味が理解できません。
Q8:「部分最適」でしか仕事ができない環境です。
Q9:部署間の板挟みになった時、どう考えればいいですか?
Q10:開発が「売れないもの」を作ってくるのですが、どう伝えればいいですか?
Q11:キャリアアップのために、この3工程をすべて経験すべきでしょうか?
Q12:バリューチェーンとサプライチェーン、結局何が違うのでしょうか?
Q13: 会社の課題がどこにあるか見つける方法を教えてください。
Q14:利益率が高い会社はどの工程が強いのですか?
Q15:中小企業でもこのフレームワークは使えますか?
Q16:結局、一番大事な工程はどれですか?
以下から参照下さい。
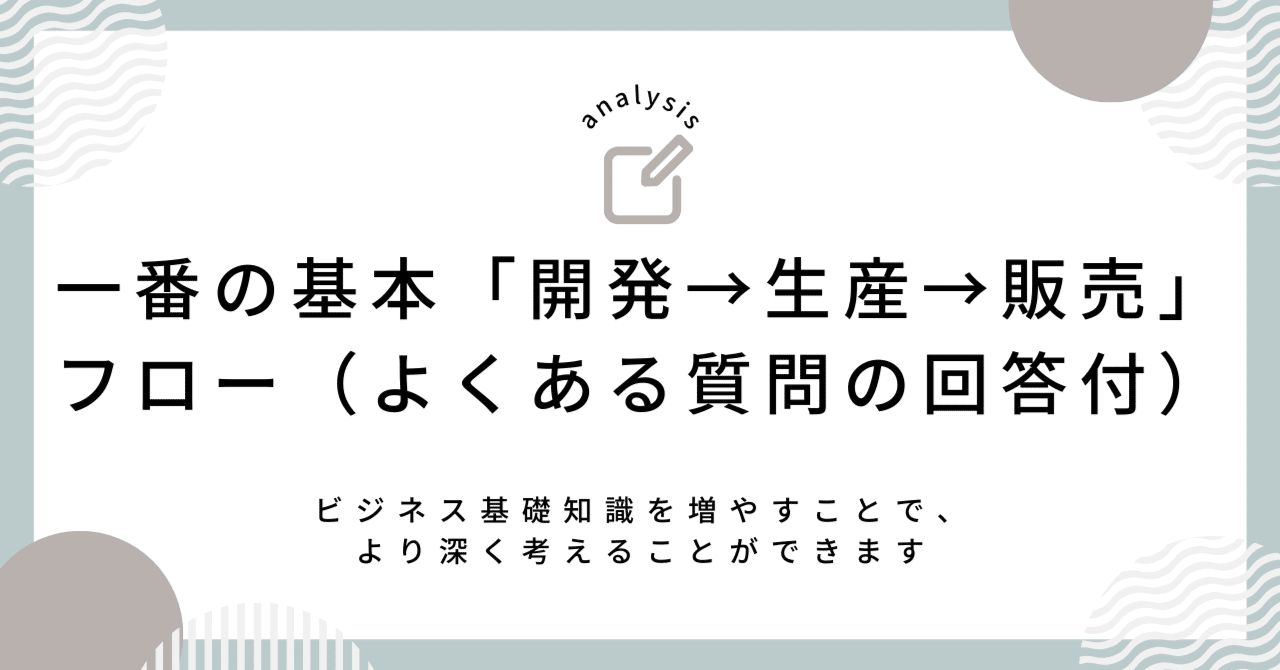
他にも「ビジネスの根幹」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。