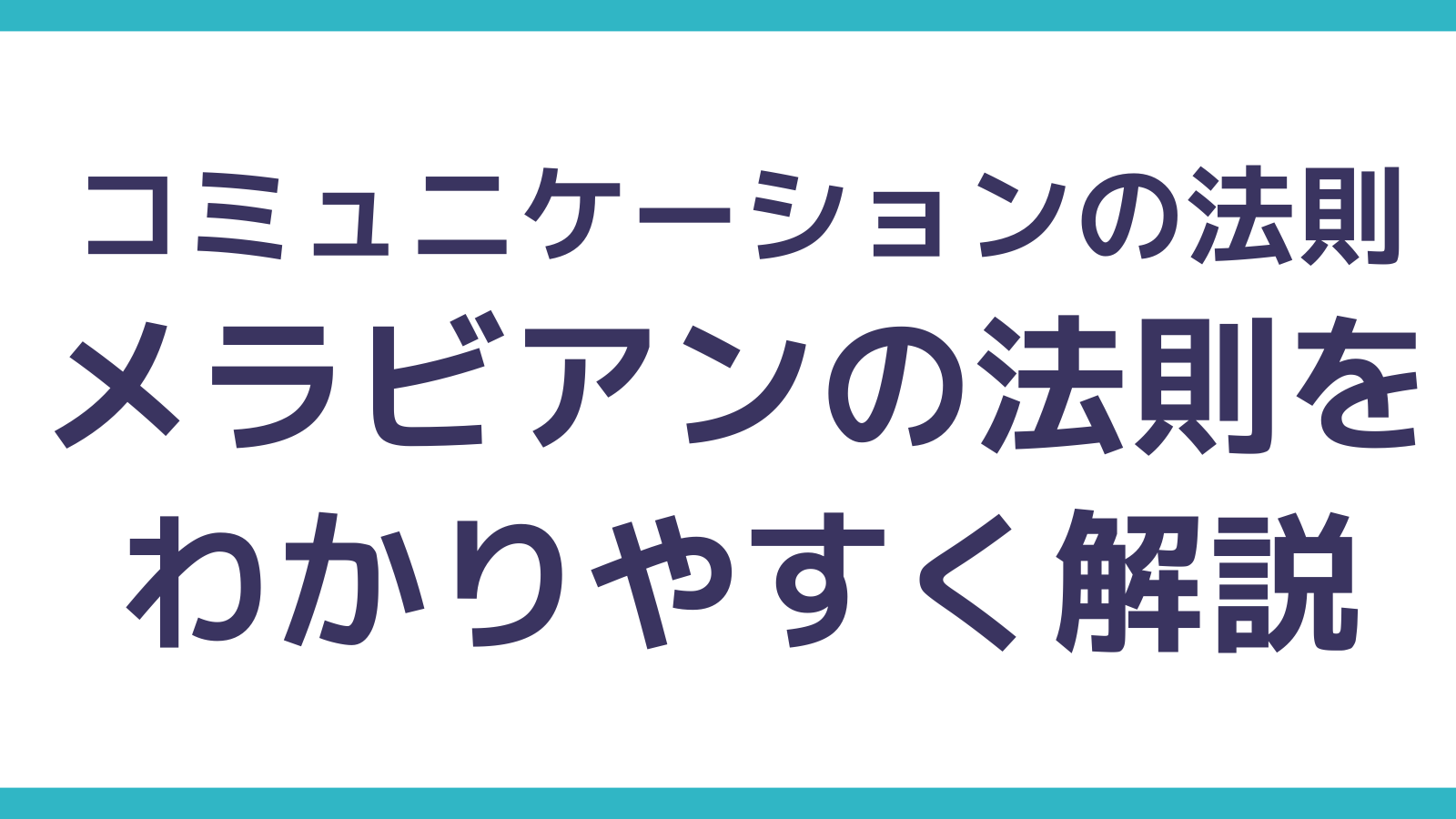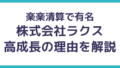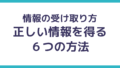電話やメールやチャットでミスコミュニケーションをおこしたことはないですか?
人は、言葉だけでなく全身を使ってコミュニケーションしているので、一部の機能だけではちゃんと伝わらない場合があります。
これらのことをわかりやすく法則化されたのがメラビアンの法則です。
この記事では、普段様々な手段を使ったコミュニケーションについての法則である、メラビアンの法則についてわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、ビジネスフレームワーク・法則を用途別に分けて紹介)
メラビアンの法則とは?
・コミュニケーションは言語情報・聴覚情報・視覚情報の3つで成り立つ
・それぞれの割合は7%:38%:55%
これがメラビアンの法則です。
人と人がコミュニケーションする際に、言語情報7%、聴覚情報38%、視覚情報55%という割合で影響するという実験結果を1971年にアルバート・メラビアンさんが発表しました。
別の呼称では「3Vの法則」、「7-38-55ルール」とも呼ばれています。
ポジティブな言葉を、ネガティブな表情(視覚)で正反対で表現した場合、この3つがどのように影響するかの実験を繰り返しおこなった結果、上記の数字が出てきたとのことです。
言語と非言語(聴覚・視覚)に分けた場合、非言語コミュニケーションが大事になるということを証明しています。
例えば、仕事の終わりに言語で「疲れた」と言った場合を考えてみます。
充実感たっぷりな表情と身振りで、「疲れた」という言葉を聞いた場合と、声が疲れていて疲労困憊の表情で、「疲れた」という言葉を聞いた場合の受け止め方は違います。
同じ「疲れた」という言葉でも、他の部分も含めてコミュニケーションしている証拠です。
メラビアンの法則の注意点
非言語だけが重要なのではなく「言語・聴覚・視覚」3つの組み合わせが重要
よく誤解される内容として、聴覚情報38%と視覚情報55%を足した非言語の合計が93%になるので、非言語だけが大事と解釈されることがあります。
ただ、メラビアンさんの実験の主旨は、言語・聴覚・視覚の3つがコミュニケーションの基本であり、その中で、判断基準として優先されやすいものは何かを検証したものです。
したがって、非言語のみが大事なのではなく、3つの組み合わせが大事なのだということを理解しておいてください。
メラビアンの法則の「使い方」
7%の言語を大事にする
メラビアンの法則から導かれる内容で考えると、よく知った仲ではない人とのコミュニケーションで大事にすべきことは、逆説的になりますが、7%である言語です。
なぜなら、言語はこのように解釈しようという決まりがあるからです。
いつもコミュニケーションを取っている人とは、癖や表現方法に慣れてるので、概ねミスコミュニケーションをおこしません。
ただ、それほどコミュニケーションを取っていない人とは、個々特有の表現の癖を理解していません。
結果、聞こえたもの、見えたものが、必ずしも発したものと同じ内容ではないことが起きるのです。
はじめて話をする人と昔からよく知っている人とのコミュニケーションを比べてみてください。
同じ言語のやり取りでも、後者の方がより、伝えたい内容を理解できます。
例えば、LINEでのやり取りを想像してみてください。LINEのやり取りは良く知っている人と、口語や絵文字の短文のやり取りですね。
その際に必ずその人を想像し、その人の表現方法をイメージしているから、コミュニケーションが成り立つのです。
何も知らない人とやり取りする時は、あの短いテキストでは何を伝えたいのか、想像できにくいのです。
したがって、よく知った人ではない人とコミュニケーションを取る際は、伝えたい内容を言語でちゃんと表現しないといけません。当然 言語が長くなります。
長い言語を理解するためには、わかりやすい言語でないと理解できませんので、相手に伝わりやすい言語にする必要があります。その方法として、ロジックやストーリーや、結論から話すことが大事になるのです。
コミュニケーション方法別対策
商談やプレゼンテーション
他社への商談やプレゼンテーションでは、よく知った仲ではない人が対象の場合が多いので、言語と聴覚と視覚の3つすべてに訴えかける必要があります。
言語は、ロジックやストーリーが大事になり、その話を理解してもらうために、どのように聞こえるか?どのような表情や身振り手振りを使えば、より伝わるか?を考える必要があるのです。
文章のみでのコミュニケーション
文章だけでのコミュニケーションを取る場合、聴覚と視覚が使えないため、文章の簡潔さと、文章自体のロジックやストーリーがより大事になりますが、いかんせん7%です。
文章だけで伝えようとすると、文章力を鍛える必要があります。それができないのであれば、文章で伝えるのはあきらめることです。
メール等のやり取りは、事実や連絡事項を伝えるだけにとどめて、議論や何かを伝える際は、別の手段で行いましょう。
電話でのコミュニケーション
電話では、言語と聴覚の2つが使えます。ただ、身振り等の視覚を伝えることができません。
半分くらいは伝わらないことを前提として、伝える努力をしましょう。
Web会議でのコミュニケーション
一見、言語と聴覚と視覚が揃っているので、しっかりしたコミュニケーションができるように感じます。
でも、一つ問題なのは、微妙な空気感が伝わりません。どうしても、対面と比べて、言語の比率が高くなります。
ということは、知らない人とのコミュニケーションを取る心持で、話す必要があるのです。
一見大丈夫そうに感じることで、伝える丁寧さが欠けて、コミュニケーションロスが実は起きやすいのです。
メラビアンの法則の「まとめ」
・コミュニケーションは言語情報・聴覚情報・視覚情報の3つで成り立つ
・それぞれの割合は7%:38%:55%
人は、50名~100名位の集団で長い間生活をしていたそうです。
だから、よく知っている仲の人と、直接会って、言語と聴覚と視覚を使ってコミュニケーションするように進化したのです。
今の時代は、メール、チャット、SNS、電話など様々なコミュニケーション手段がありますが、メラビアンの法則からするとどの手段も欠点があります。
これを踏まえて、相手に配慮しながら、コミュニケーションを取っていきましょう。
他にも沢山のフレームワーク・法則の記事を書いています。参照下さい。
「開発→生産→販売」、「分解して考える」、「ロジックツリー」、「PLC」、「キャズム理論」、「SWOT分析」、「ファイブフォース」、「リボン図」、「AISAS」、「AIDMA」、「ABC分析」、「4P」、「アンゾフの成長マトリクス」、「アップセル・クロスセル」、「ポーターの3つの基本戦略」、「PPM」、「ランチェスターの法則」、「コトラーの競争地位戦略」、「イノベーター理論」、「ロングテール」、「感度分析」、「262の法則」、「28の法則」、「マズローの5段階欲求」、「ジョハリの窓」
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
本を読む習慣がない方は、プロのナレーターが朗読した本をアプリ等で聴けるサービスがおススメです。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
アマゾンさんで電子書籍の定額読み放題サービスがあります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
何回も読んだおススメ本の紹介は以下を参照下さい。

何回読んでも学べた本厳選!ビジネスに役立つおすすめ本はこちら
記事一覧から探したい場合はこちら

用語から検索したい場合はこちら