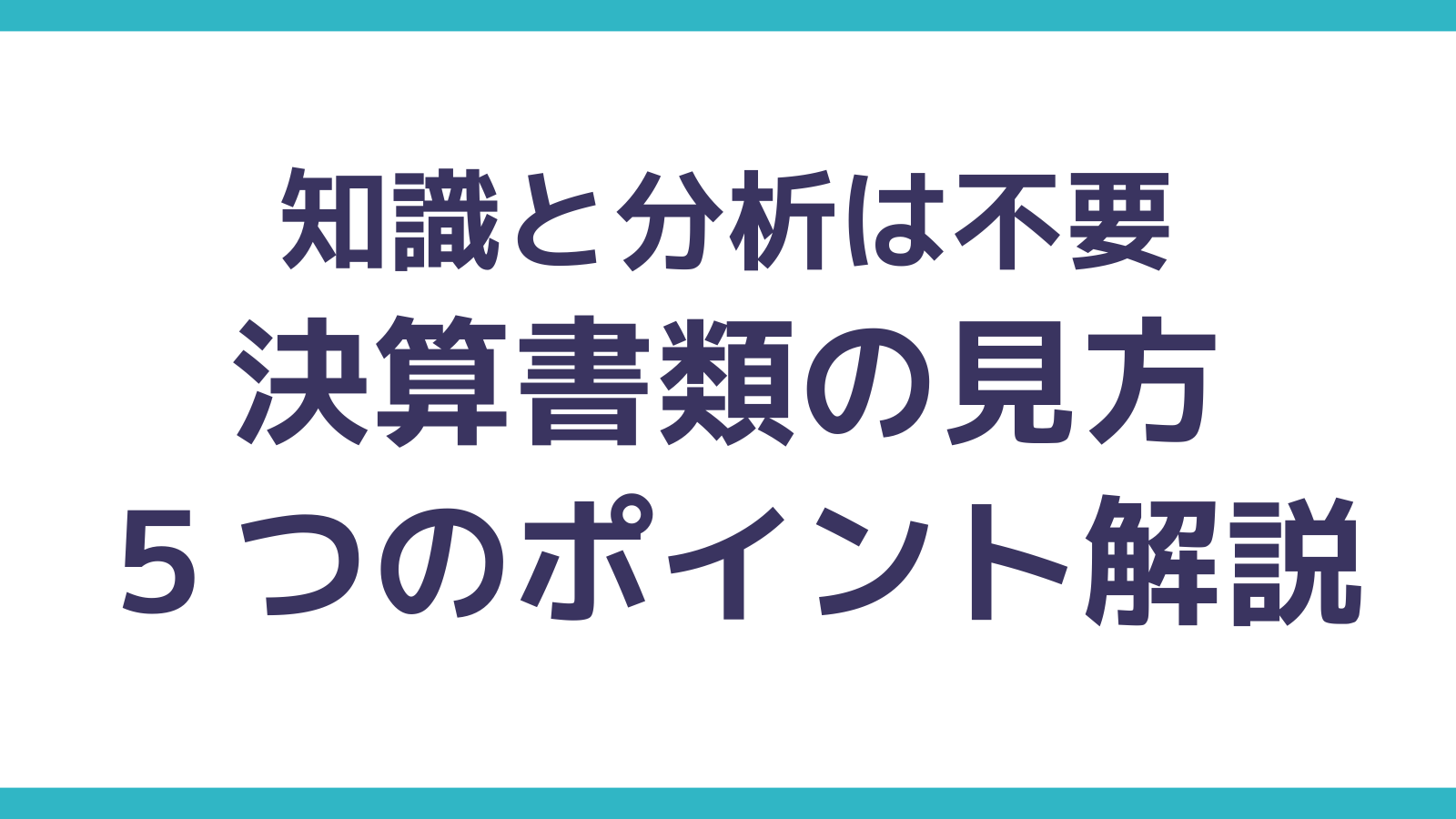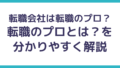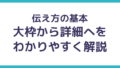決算書類って、難しく感じませんか?
見方を調べても、専門用語ばかりでうんざりしてしまいますよね。私もそうでした。
単純に会社のことを知りたいだけなのに、いつの間にか決算書類を読み解くこと自体が目的になってしまう、という方もいるかもしれません。
本記事では、こうした悩みを解決するため、決算書類の見方を詳細に解説するのではなく、見るべきポイントを5つに絞ってご紹介します。
これらのポイントを押さえれば、どのような会社か判断できるようになります。
専門知識や分析スキルがなくても、ここだけ押さえておけば大丈夫、という内容です。具体的な掲載場所も紹介していますので、安心して読み進めてください。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【企業会計】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析)
決算書類でチェックする5つの項目
1.売上が伸びているか?
2.粗利率が高いか?
3.お金の集め方は適正か?
4.一部の事業や顧客に依存していないか?
5.従業員の年齢が適切か?
上記の5項目です。
・なぜこの5項目だけでわかるのか?
・決算書類を見る目的
・決算書類の掲載場所
・5つの詳細説明
この順番で紹介していきます。
なぜこの5項目だけでわかるのか?
今後成長できる確率が上がる5つの要素だから
会社を見る目的はさまざまですが、共通して知りたいのは「今後儲かる可能性が高い会社かどうか?」という点でしょう。
今後儲かるためには、売上が伸びていく可能性が高いことと、事業が傾くリスクが少ないことが大事になります。
将来を完全に予測することはできませんし、会社の業績は非常に多くの要因が絡むため、あくまで確率論となります。
ただし、直近5年間で売上を伸ばしている会社とそうでない会社では、前者の方が今後も売上を伸ばす可能性は当然高くなります(1)。
利益率が高いと、少ない売上でも利益が出やすくなります(2)。
金利のかかる資金を多く借り入れていると、返済が負担となります(3)。
取引上位の会社やメイン事業の比重が高いと、それらに何かがあった時に一気に会社は傾きます(4)。
従業員の年齢が高くなると、組織全体の動きが鈍くなる傾向があります(5)。
したがって、この5つを見るだけで、ある程度のことは把握できるのです。
もちろん、これら以外にも多くの見るべきポイントはあります。例えば、所属する業界分析などが挙げられます。
ただ、業界分析は素人には簡単ではありません。
無理にできないことに手を出すと、誤った判断につながる可能性があります。
まずはこの5項目を見ましょう。
決算書類とは?
上場企業が自社の決算の数字を公表する資料
上場企業は決算情報の公開が義務付けられています。これは、投資家などが適切な投資判断を行えるようにするためです。
主に、決算短信と有価証券報告書の2つがあります。
決算後、原則として45日以内に決算短信が、そして3ヶ月以内に監査法人の会計監査を受けた有価証券報告書が公表されます。
本記事では、これら2つの書類を使って解説します。
この記事での決算書類を見る目的
今後伸びる可能性が高い会社かどうかを判断すること
本記事では、上記の目的を掲げています。したがって、決算書類を詳細に読み解けるようになることを目的とはしていません。
あくまで、決算書類から専門知識や分析スキルがなくても、今後伸びる可能性が高いかどうかを判断することが目的です。
繰り返しますが、将来を完全に予測することはできません。しかし、その確率を上げることは可能です。
使用する決算書類の掲載場所
各社のコーポレートサイトに格納
コーポレートサイトを見ればすぐにわかります。ただ、コーポレートサイトがわからない場合は、ECサイトのフッダー(トップページの一番下)にある「運営会社」をクリックするか、「〇〇(商品名) コーポレートサイト」で検索するとヒットします。
「IR」または「投資家の皆様へ」といった見出しの中から、IRライブラリーや資料一覧に決算短信と有価証券報告書が掲載されています。
期中のものではなく、通期(第一四半期、第二四半期、第三四半期といった表記がないもの)を参照してください。
例えば、2024年の通期データがなければ、2023年度のものを確認してください。
決算書類で見るポイントは5つ
・売上が伸びているか?
・粗利率が高いか?
・お金の集め方は適正か?
・一部の事業や顧客に依存していないか?
・従業員の年齢は適切か?
上記の5つが、見るべきポイントです。
それぞれ解説します。
1.売上が伸びているか?
売上の推移を見る
売上が伸びているということは、その会社の製品やサービスが顧客に受け入れられている証拠です。
競合に負けていたり、業界全体が衰退していたりすると、売上は落ちる傾向にあるからです。
掲載している場所
有価証券報告書の最初に、直近5年間の業績推移が掲載されています。
もし5年間分が掲載されていない場合は、次のページにある「提出会社の経営指標等」を参照してください。
記載がなければ、最近上場したばかりで過去分は公表されていないケースが考えられます。
数字の見方
5年間で伸びているか?を見ます。
まずは掲載されている最初の期(多くは5年前)と直近の期を比べてみましょう。
これだけで、どのような売上推移かがすぐに把握できます。
さらに毎年伸び続けている場合は、非常に良い状態だと言えるでしょう。
注意点
あくまで直近5年間の推移なので、これからどうなるかは予測できません。
ただし、今後伸びていく可能性については、直近5年間で成長している会社の方が高いと言えます。
2.粗利率(売上総利益率)が高いか?
粗利率(売上総利益率)が高い会社は儲かりやすい
粗利率(売上総利益率)とは、売上から製品、商品、サービスの製造に直接かかった原価を差し引いたものです。
(売上総利益の詳細は、財務三表はつなげて理解「損益計算書(P/L)」編を参照)
例えば、粗利率80%の会社と20%の会社で1,000万円の粗利を稼ぐ場合、前者は1,250万円の売上が必要ですが、後者は5,000万円の売上が必要になります。
このように粗利率が高いと利益が出やすいため、粗利率が高いかどうかを確認します。
掲載している場所
「決算短信」の中央付近にある損益計算書を確認しましょう。
ほとんどモノクロの書類ですが、財務三表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)の部分だけ青い網掛けが使われているケースが多いので、探す際の目印になります。
青い網掛けの表が3つあり、中央に「損益計算書」があります。
損益計算書の上から3つ目(一部の会社除く)に「売上総利益」の欄があります。
数字自体も重要ですが、電卓で「売上総利益 ÷ 売上」を計算してみてください。
その数字が粗利率(売上総利益率)です。
数字の見方
見たい会社と同じ業界の他社の数字と比較してみると、その数字が良いものかどうかが判断できます。
業界別では、ネットサービス系(代理販売を除く)やコンサル系が総じて高くなる傾向にあります。
逆に、実物商品の仕入れ販売や代理販売は低くなる傾向があります。
また、業界他社と比べて粗利率が高ければ、そのサービスが差別化できていると判断できます。
差別化された強いサービスを持っていると、価格競争に巻き込まれにくいからです。
3.一部の事業や顧客に依存していないか?
1つの事業しかない会社や、1社(もしくは数社)の顧客への売上依存度が高い会社があります。
事業環境の変化や上位顧客との取引に何か問題が生じれば、一気に業績が悪化する可能性があります。
したがって、これら2つのポイントをチェックしましょう。
掲載している場所
いずれも「決算短信」に掲載されています。「財務諸表の注意事項欄」にある「セグメント情報」を確認してください。
先ほど確認した財務三表のすぐ後に掲載されていることが多いです。
今期の事業ごとの売上と利益が掲載されており、多くの場合、前期の数字も併せて表示されています。
ただし、単一事業の場合は記載がないことがあります。
また、上記の後に、「主要な顧客ごとの情報」という欄があり、売上の10%以上を占める顧客については、社名と売上金額が掲載されています。
対象となる顧客がいなければ、記載されません。
見方
単一事業か複数事業かについては、掲載されている事業の数で判断できます。
記載がない場合は単一事業であるため、強力な競合の出現や業界全体の成長が鈍化すると、非常に苦戦する可能性が高いです。
また、複数事業があったとしても、最大の事業の売上規模が8割を超えている場合は、上記と大差ありません。
全体のバランスが良いかどうかも確認しましょう。メイン事業以外の事業が、現状売上は小さくても前年の伸び率が高ければ、今後に期待できます。
売上全体の10%以上を占める顧客が掲載されていれば、その顧客の動向に業績が左右されることになります。このリスクを開示するため、表示義務が課せられています。
強力な競合の出現や不祥事などがあれば、取引額に影響が出ることがあります。
その結果、値下げが必要となったり、利益が減少したりすることも考えられます。
最悪の場合、取引がなくなれば、その金額分の売上が失われることになります。
事業のバランスと同様に、1社に依存することで大きなリスクを負うことになります。
長く取引していたとしても、今の時代、他社が価格で攻勢をかけると、多くの場合、競争に負けてしまう可能性があります。
各社とも、もはや昔のように関係性だけで取引を行う時代ではなくなっているからです。
4.お金の集め方は適正か?
リスクの少ない資金調達をしているか?
会社には不可欠なものがあります。それは現金です。従業員への給与支払いや仕入先への支払いは、現金で行われます。
現金がなければ倒産につながります。
逆に、どれほど赤字でも現金さえあれば倒産しません。それほど、現金は重要なのです。
(倒産の詳細は、「倒産」の理由と種類をわかりやすく解説を参照)
したがって、どのように現金を調達しているか?という点が非常に重要になります。
お金を集める方法
・金融機関から借りる
・株を買ってもらう
・過去の利益の積み上げ
主にこの3つです。
「金融機関から借りる」がわかる場所と見方
金融機関からの借り入れがある場合、貸借対照表の右側の「負債の部」に「短期借入金、長期借入金」として記載されています。
(貸借対照表の詳細は、財務三表はつなげて理解「貸借対照表(B/S)」編を参照)
1年以内に返済する「短期借入金」と、1年以上先に返済する「長期借入金」に分かれます。
金融機関から借り入れると、現金が口座に振り込まれます。当然ながら、金利を上乗せして返済する義務が生じます。
当然、借入額が多ければ、返済だけでなく金利負担も非常に重くのしかかります。
また、返済を容易に猶予してもらうこともできません。
したがって、短期借入金や長期借入金が多ければ多いほど、経営環境は厳しくなります。
逆に、これらの借入金が少なければ、後述する返済義務のない資金を調達しているか、あるいは全く投資をしていないかのいずれかです。
当然、後者(全く投資をしていない場合)は成長が見込まれません。
「株を買ってもらう」がわかる場所と見方
貸借対照表の右側の「純資産の部」に「資本金」として記載されています。
また、決算期内に新株を発行して資金調達を行った場合は、「キャッシュフロー計算書」の財務活動によるキャッシュフローの欄に「株式の発行による収入」として記載されます。
新株を買ってもらうと、購入額が口座に入金されます。そして、返済義務はありません。
ただし、持ち株数により、さまざまな権利を株主に提供することになります。
当然、多くの株式を保有されると、株主の意見を聞く必要が出てくるだけでなく、経営権を剥奪される可能性もあります。
ただし、株を買ってもらうことができるということは、「今後この会社が伸びる」と投資家に期待されている証拠であり、良いことでもあります。
借入金がなく、資本金で資金調達を行い成長している会社は、非常に健全な状態だと言えます。
ただし、売上を大きく伸ばしているものの赤字の会社で、資本金が非常に大きな会社も存在します。
そのような会社は大きな期待を寄せられているため、多額の資金を投資してもらっています。
当然、将来的には大きな利益を出すという大きな期待を背負っているため、経営陣は非常に大きなプレッシャーを受けています。
ある意味、急激に成長する可能性も秘めていますが、同時にうまくいかないリスクも抱えている会社だと言えるでしょう。
「過去の利益の積み」がわかる場所と見方
過去の利益の積み上げは、「貸借対照表」の右側の「純資産の部」に利益余剰金として掲載されています。
自社で稼いだ利益の積み立て分(=内部留保)なので、最も自由に使える資金であり、他者に配慮する必要がありません。
この金額が大きければ大きいほど、継続的に利益を出している会社だと判断できます。
5.従業員の年齢は適切か?
従業員の年齢層は、会社にとって非常に重要な要素です。年齢層が高いと行動量は少なくなる傾向がありますが、経験は豊富です。
逆に、若いと行動は多くなりますが、経験が不足している場合があります。
どちらが良いか悪いかは、その会社が置かれている状況によって判断が変わります。
掲載している場所
有価証券報告書の前半部分に「従業員の状況」という欄があります。
こちらに記載されています。平均年齢だけでなく、従業員数、平均勤続年数、平均給与も確認できます。
見方
まずは平均年齢を見ましょう。22歳で入社し、60歳まで正社員として働く人が多いとして、中間値は41歳です。
まずはこの41歳を目安として考えましょう。
追加で確認してほしいのは平均勤続年数です。平均年齢と平均勤続年数の2つの数字を組み合わせることで、さまざまな仮説を立てられます。
創業から時間が経っているのに、平均年齢が若く平均勤続年数が5年程度だとします。
多くの社員が退職しているか、あるいは最近急激に売上が伸びて大量採用を行った、と想像できます。
平均年齢が高く、平均勤続年数も長い場合は、新卒から入社した社員がほとんどで、昇進・昇格が滞っていたり、昔ながらの風土や文化を形成している可能性があります。
このように、複数の情報を組み合わせて見ることで、さまざまな仮説を立てることができます。
5つの項目だけで会社がわかるの「まとめ」
・売上が伸びているか?
・粗利率が高いか?
・お金の集め方は適正か?
・一部の事業や顧客に依存していないか?
・従業員の年齢は適切か?
まずはこの5つを確認してみましょう。それ以外の難解な数字や文面は、一旦置いておいて構いません。
それだけでも、知りたい会社の全体像をおおよそ把握することができます。
もし、もう少し詳しく知りたい場合は、財務三表を以下の考え方で見てみる方法をおすすめします。
専門科目の知識がなくても理解できる方法です。
会社は「現金を使って現金を増やす活動」を行っており、その活動は以下の流れで構成されます。
1.現金を集める
2.集めた現金を使って投資する
3.投資したものを使って売上を上げる
4.売上を上げるために使った経費を差し引く=利益
5.これらの活動で現金がふえたのかどうかを確認する
1は貸借対照表(B/S)の右側。
2は貸借対照表(B/S)の左側。
3.4は損益計算書(P/L)。
5はキャッシュフロー計算書(C/F)
上記を見るとわかります。
具体的な見方は「財務三表(B/S、P/L、C/F)」はひとつの考え方でつなげて理解するを参照下さい。
他にも企業会計の「収益構造とコスト分析」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。