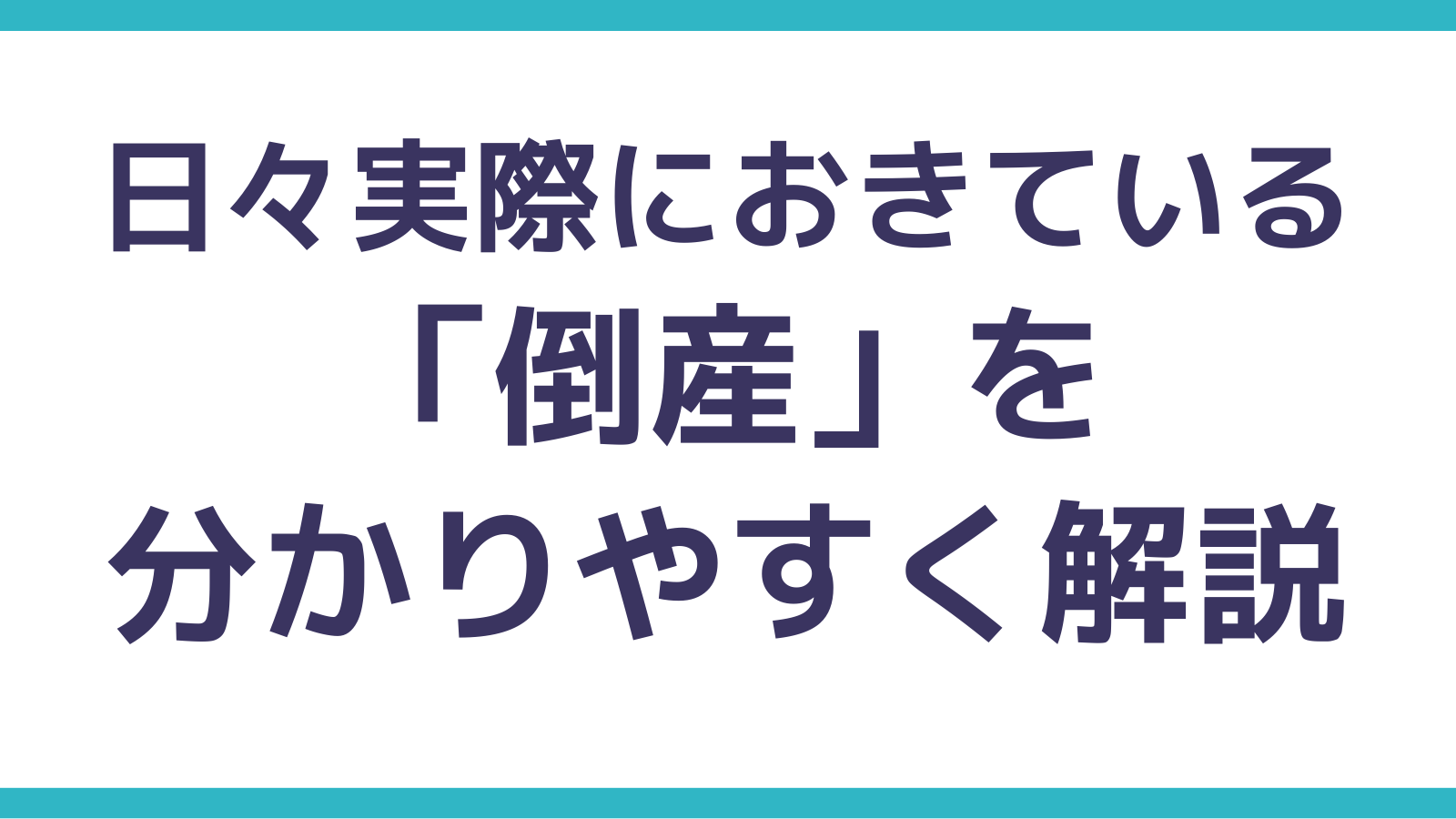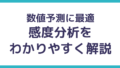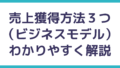倒産自体の言葉の定義は結構あいまいです。また、複数の法律が絡んでますので、ちゃんと理解するのは難易度が高くなります。
倒産は、余り遭遇したくないことですが実際に日々起きているのが現状です。
この記事では、倒産の最低限知っておきたいことに絞りわかりやすく解説します。
この記事を読むと、倒産がなぜ起こるのか?破産型と再建型のそれぞれの種類について理解できます。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【ビジネス用語】基礎用語解説)
倒産とは?
現金がなくなり、事業を継続できなくなった状態
上記の状態を倒産といいます。
倒産という言葉自体には法律上の統一した定義がないことで、上記のような曖昧な定義となります。
倒産の「これだけ知ろう」
・現金がなくなり、事業継続できなくなった状態
・清算型と再建型がある
・倒産という言葉に法律上の統一した定義がない
この3つを知っておきましょう。
倒産の「詳細解説」
上記3つをそれぞれ解説します。
現金がなくなり、事業継続できなくなる
倒産という状態は、現金がなくなることで起こります。逆に言えば、現金があれば倒産しません。
赤字=倒産というイメージがありますが、そうでない場合もあります。黒字倒産です。
黒字赤字というのは、損益計算書(P/L)での最終利益のことを言っていますが、損益計算書の利益と会社が持っている現金はイコールではないため、黒字でも倒産状態になることがあるのです。
借入れや新株発行によって得た現金は、損益計算書(P/L)には乗りません。したがって、損益計算書(P/L)だけでは、現金の増減がわかないため、キャッシュフロー計算書(C/F)があります。
(詳細は会社の現金を表す「キャッシュフロー計算書(C/F)」超簡単解説&使い方紹介を参照)
黒字倒産の多くの原因は、売上計上した日と実際に入金される日のタイムラグがあることです。タイムラグにより、入金まで時間がかかり、その間に仕入れ先に支払う現金がなくなり倒産になるのです。
(ライムラグの詳細は、「入金サイトと売掛金・買掛金」超簡単解説&使い方紹介を参照)
もう少し具体的に言うと、現金がなくなり、各種の支払いを期日通りに行うことができなくなると、販売する商品や原材料など、商売に必要なものの仕入れを止められてしまいます。
お金をもらえない取引先に商品を納入したくないからです。
その結果、販売するものがなくなり、事業を継続できなくなってしまうのです。
倒産の種類は清算型と再建型がある
清算型には大きく2つ
・破産
・特別清算
再建型も2つ
・民事再生法
・会社更生法
※上記以外にも事業再生ADRなどの方法もありますが、今回は基本的に、お金が払えず裁判所に申し立てる上記4つの場合の説明をします。
裁判所に申請したら、基本お金を貸している業者や、商品を納めている人たち(=債権者)は裁判所の命令により、お金の回収等の行動ができなくなります。
清算型の場合
倒産した会社に残っている、現金化できそうなものを集めて、債権額に応じて分配します。
債権額の5%にも満たない金額しか戻ってこない場合がほとんどです。100万円の債権があっても5万円未満しか支払ってもらえないのです。
再建型の場合
すでに支払うと確定しているものついては、一旦支払いを猶予(待ってもらう)してもらいます。
現金がないのは、過去の借金等の返済含めた問題である場合が多いので、過去分を一旦待ってもらい、これから発生する支払いは支払うことで事業再生を図ります。
これができなければ、清算型に移行するのですが、出来る場合は、事業を継続しながら、事業の再生計画を立てて、裁判所に認めてもらったら、再生に向けて正式に事業運営を開始します。
再生ができたら、元々の債権を少しずつ返済していきます。
例外はありますが、民事再生法は中小企業が中心、会社更生法は大企業が中心となります。基本の考え方は同じですが、運用ルールが違います。
そもそもなぜ再建型が存在するのか?
債権者にとって清算型で倒産してしまうと、5%未満しか戻りません。ただ、もし再生がうまく進めばもっと戻る可能性が出てきます。
また、現金がなくなった理由によっては、過去の借金支払いを一定期間猶予すれば、再生の可能性がある場合もあります。
例えば、今行っている事業では利益は出ているが、過去の失敗で多額の借金があり、その返済でお金が無くなる場合などです。
利益が出ているのであれば、現時点ではお金はないが、今後お金を生み出す力がある可能性があります。
他にも、例えば4つの事業を行っており、2つは利益が出ている場合も、利益が出ていない2つの事業をやめれば、今後お金を生み出す可能性があるなどの場合です。
このように、債券者への最終的な支払額増の可能性や、倒産した会社が再生することで、雇用を守ることができる、経営者も自己破産せずに再チャレンジできる等のメリットがあるので、このような法律が整備されました。
裁判所は総合的に判断して、再生計画を承認もしくは否認します。
否認された場合は、買収されない限り清算型に移行することになります。
民事再生や会社更生を申請し、裁判所が再生計画を承認するまでの期間についても、債権者が引き続き取引をする確率は実は高いです。
もし取引を止めてしまえば、事業運営ができなくなり、再生の可能性がなくなり、過去債権は無となります。ただ、再生したらお金が想定より多く戻ってくる可能性があるから、取引を継続するのです。
損を確定させるか、損が戻ってくる可能性にかけるかの各社の判断となります。
民事再生や会社更生の申請日以前の債権は、再生するまで支払ってもらえないですが、裁判所に申請日以降の取引については、お金を支払ってもらえますので、苦渋の選択として取引を続ける会社が多いのです。
わたしも債権者集会と言われる、今後の進め方の説明会に参加したことがありますが、取引額が多かった会社は本当に必死です。
それはそうです。倒産した会社からはお金はもらえないですが、仕入れ先には支払いをしないといけないからです。
その入金がないと、連鎖して倒産してしまうことにもなりかねません。
だから、取引する際には入金されない事態のならないように、与信管理が重要になります。
(詳しくは「与信管理」超簡単に解説&使い方紹介を参照)
取引会社によっての温度差が大きく出ますので、法律で規制をかけることで、再建計画をスムーズに進めることができ、再生の可能性が高まるのです。
倒産の「まとめ」
・現金がなくなり、事業継続できなくなった状態
・清算型と再建型がある
・倒産という言葉に法律上の統一した定義がない
昔は、倒産したら会社の備品等を各業者が持ち帰ったり、社長の家に押しかけたりすることもありました。
ただ、今は法整備が進み、そのようなことも少なくなりました。
私も30年前に倒産した会社のオフィスだけでなく、社長の自宅にも言ったことがありますが、ほんと辛くなります。
このような経験をする人が少なくなるように、もっと経済活動が活発になるといいですね。
他にもビジネス用語に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。