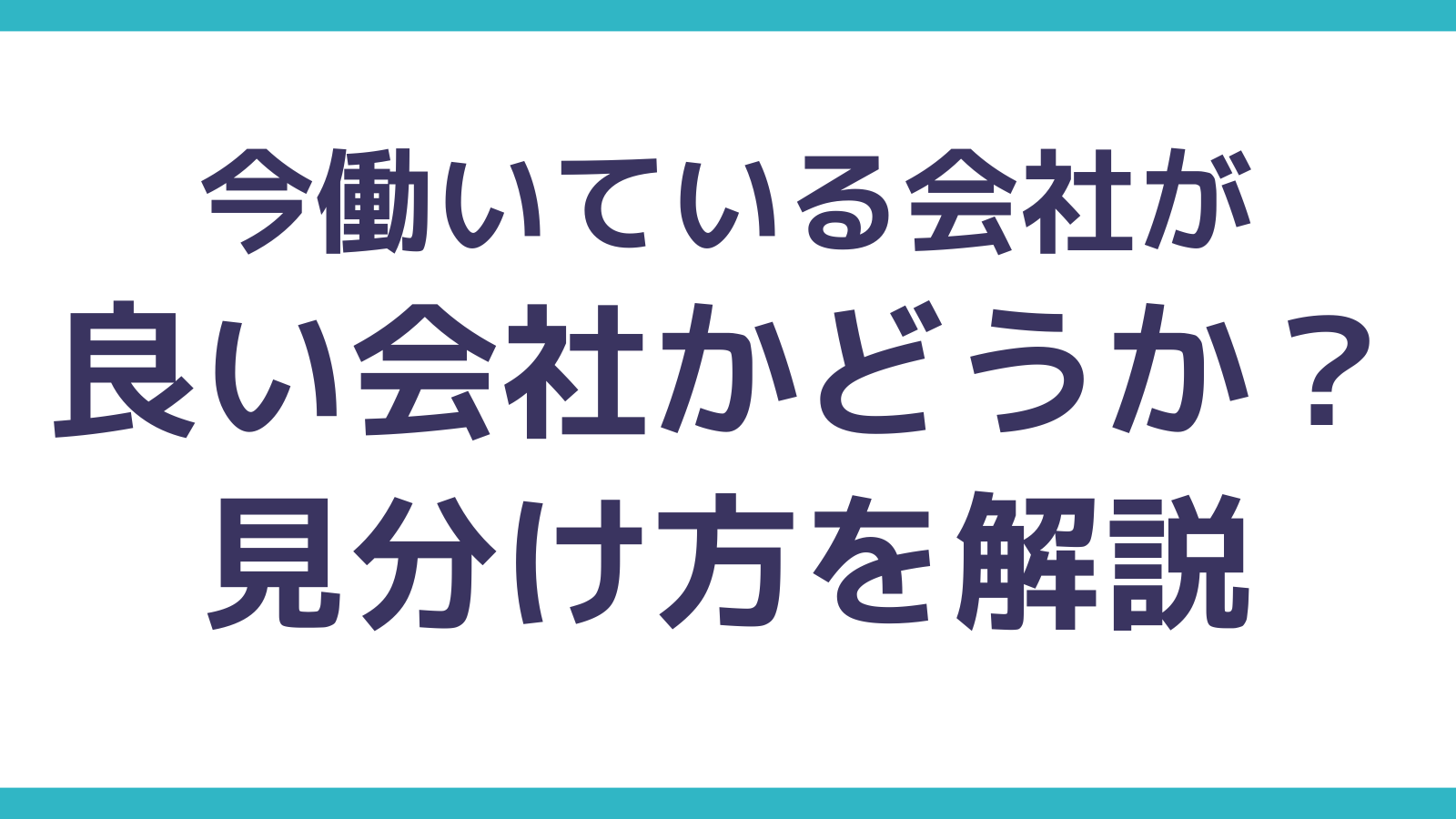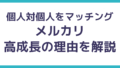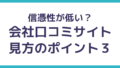働いた会社が1社しかない20代の皆さんは、自分の会社が良い会社かどうか?を客観的な基準で判断できますでしょ
うか?
世の中にはたくさんの会社があり、風土風習が本当にバラバラです。したがって、良い会社かどうかの判断は、とても難しいです。
パワハラやセクハラ、残業時間が長い、休日出社が多いなど明らかな内容であれば明確にわかりますし、判断を間違うこともありません。
ただ、上記は会社の見方の一部でしかありません。本当に良い会社かどうか?は、複数社で働いてやっとわかります。
1社の経験では、その会社特有のことなのか?そうでないのか?良いことなのか?悪いことなのか?が判断しきれない場合が多くあります。
良くない会社と判断して転職したら、実はそれほど悪くない会社だったということもあります。
この記事では、5社で働き、営業で数千社に訪問した経験を元に、どんな会社か良い会社か?を紹介します。
この記事は、
・風土の違う5社での経験
・中途採用の責任者の経験
・多数の書類選考・面接の経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・3回の転職経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが、実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、社会人の勉強 学ぶ方法と知っておきたい知識を紹介)
- 良い会社の定義
- 増収増益ができている会社
- 営業力に頼らない会社
- 「すべき」より「したい」が多い会社
- 恐怖より危機感で人を動かす会社
- 「無謬性(むびゅうせい)」が発症していない組織
- 上司ではなく、お客様に目を向けている会社
- 管理職が本来の仕事をしているかで判断
- 単純作業の効率化ができている会社
- 「良い人事評価制度」がある会社
- 人事評価のフィードバック面談に時間をかける会社
- 「人事異動が多い」会社
- 会社を好きになる2つのことがある会社
- 責任の所在が明確な会社
- 変わることに慣れている会社
- 強みがシンプルに表現できる会社
- 業種を一言で言えない会社
- 昔話が1年以内の会社
- 結果よりもプロセスを求める会社
- 雑談が多い会社
- 上司が懇切丁寧に教えてない会社
- 指示が具体的な会社
- 人事異動の多い会社
- 定量・定性両方を両方おこなう会社
- 社内呼称で肩書をつけて呼ばない会社
- 目的と方法をセットで指示をする会社
- 取締役構成で判断
- 新卒入社が多い古い会社でおきる一番の問題とは?
- 直接あって確認する方法
- 良い会社は少数しかない
- 様々な現象から会社の特徴を解説の「まとめ」
良い会社の定義
まずは、良い会社とはどんな会社なのかを明確にしておきます。
20代で転職経験のない方にとって、
一番大事なのは、時間当たりの経験数
持っている時間は全員同じなので、同じ時間の中で、沢山の有用な経験を積むことができる会社を良い会社とします。
分かりやすい例ですと、テレアポ率0.1%会社とテレアポ率5%の会社でどちらが沢山の有用な経験を積むことができるのか?です。当然後者です。
(詳しくは、20代で一番大事なこと「時間当たりの課題解決経験の多さ」をわかりやすく解説を参照)
では現象ごとにどんな会社がいい会社かを解説していきます。
増収増益ができている会社
従業員・経営者・お客様のハッピートライアングルが実現するから
増収増益を5年以上続けていれば良い会社です。なぜなら、会社のサービスがお客様に受け入れてもらえているからです。
また、会社にとって増収増益は投資できる余裕も生まれます。当然給料が上がる可能性も高くなります。
その上、①経営者の心の安定②従業員の市場価値向上③顧客サービスの安定供給でハッピートライアングルが成立するからです。
(詳しくは、「増収増益を目指す理由」をわかりやすく解説を参照)
営業力に頼らない会社
商品力が高いから
営業の能力に頼らない会社は良い会社です。営業の個々の能力に頼らなくても売れる商品があるからです。
逆に商品力が弱いのに、営業力で売上を上げていこうとする会社は悪い会社です。
効率が悪いだけでなく、売れる営業担当が退職したら、売上が下がってしまうからです。
ちなみに営業力があるといわれる会社で、商品力が低い会社を私は知りません。
(詳しくは、「営業力に頼らない会社は良い会社」をわかりやすく解説を参照)
「すべき」より「したい」が多い会社
「したい」と「すべき」の違いは、
自分の思いなのか?過去のノウハウなのか?の違い
「したい」が多い会社が良い会社の理由は、
自分の意思で行動できているから
思考停止に陥っていないから
「したい」を維持することは難しいから
上記3つがしたいが多い会社が良い会社の理由です。すべきが多い会社では逆のことが起きており、他責かつ変えることができないため悪い会社と言えます。
(詳しくは、「すべき」より「したい」が多い会社は良い会社を参照)
恐怖より危機感で人を動かす会社
成長できる
リーダーマネジャーが本物
会社の雰囲気が良い
この3つが恐怖より危機感であふれる会社が良い会社の理由です。
外圧でやらされる雰囲気ではなく、内圧で自分から動くからです。
両方の組織を経験していますが、恐怖で人を動かす組織では人は成長しません。言われた以上のことをすると逆に怒られる経験もします。
結果、言われたことしかしない癖がついてしまいます。この癖は、一旦つくとなかなか取れません。なぜなら楽だからです。
実際の現場を見てきた知見です。
(詳しくは、良い会社の条件 恐怖より危機感で人を動かす会社を参照)
「無謬性(むびゅうせい)」が発症していない組織
無謬性とは「思考や判断に誤りがないこと」
誤らないという人はいませんが、人が集まってできている組織でこの症状が現れます。
この症状が発生すると、過去のことすべて正しいことが前提となってしまい、組織をより良く変化させる肝となる、PDCAがまわらなくなります。
過去が正しいので、振り返って改善すること自体がおかしくなるからです。
当然組織がおかしくなっていきます。
(詳しくは、悪い組織に多く発症する「無謬性(むびゅうせい)」とは?を参照)
上司ではなく、お客様に目を向けている会社
当たり前だができなくなる
お客様が何を考えているかを一生懸命考えるのが良い会社です。悪い会社は上司が何を考えているかを一生懸命考えます。
当たり前だと感じることですが、お客様より上司を見ている会社は本当に多いです。
悪い会社ほど、社外を見ずに社内だけを見るのは、負けてしまっている社外を直視できず、負けている責任を取りたくないからです。
だから、自分の責任を回避するために、自分を守ってくれる人を確保しようとします。
そうすると社内政治が始まります。社内政治が始まると、上司の顔色がお客様の顔色より気になる状態となります。
(詳しくは「上司ではなく、お客様に目を向けている会社」は良い会社を解説を参照)
管理職が本来の仕事をしているかで判断
・管理職の本来の仕事を知る
・できているかできていないかを判断
・できていない場合の問題点を把握
上記の流れで判断することで、良い会社かどうかだけでなく、良い会社でない場合何か問題なのかが判断できます。
管理職の仕事は、以下2つです。
・担当する組織を通じて最大の成果を出す
・担当する組織力を上げる
これらの視点から、今の上司や経営陣の働きぶりを観察してみましょう。今までとは違った見方ができると思います。
(詳しくは、良い会社の見分け方 管理職が本来の仕事をしているかで判断を参照)
単純作業の効率化ができている会社
・生産性アップに対策が打てている
・単純作業をメイン業務にする社員がいない
よくマニュアルがあると自分で考えなくなるという思考の経営者が沢山います。
確かに、生産性を上げてほしい部分については当てはまる部分もありますが、単純作業についてはまったく間違っています。この区分けができていないだけです。
そして、この問題は時間がたてばたつほど、とても根深い問題になります。
単純作業の知識を能力と思ってしまう社員が現れて、生産性の低い業務が脈々と生産性が低いまま残るのです。会社が儲かるわけがないのです。
もしこのような現象がおきていたら、実は大きな根深い課題となっている悪い会社となっています。
(詳しくは「単純作業のマニュアルがない会社」は悪い会社をわかりやすく解説を参照)
「良い人事評価制度」がある会社
・人事評価制度は、会社組織の根幹をなす制度
・良い会社は、根幹の制度をちゃんと設計実行している
人事評価制度を見たらなぜ良い会社とわかるのは、この2点が理由です。
・個人の目標及び判断基準が明確かどうか?
・プロセスの項目が入っているか?
・上長との人事評価面談が年間4回以上あるか?
上記の3つを見れば良い人事評価制度かどうかがわかります。
(詳細は、会社の見分け方「良い人事評価制度」があれば良い会社を解説を参照)
人事評価のフィードバック面談に時間をかける会社
年に振り返り面談2回、FB面談2回それぞれ1時間おこない、清々しく終わる面談
もちろん、だらだら長くやってもしょうがないですし、叱られ続けるのも違いますが、上記が出来ている会社は良い会社です。
もちろん、だらだら長くやってもしょうがないですし、叱られ続けるのも違います。ちゃんとした内容であれば上記の時間が必ずかかります。
ただ、良いFB面談をおこなっている会社は、それほど多くはありませんので、上記の合致していれば、ラッキーと思いましょう。
逆に、上記条件ではまったくないFB面談の場合、自分が管理職になった時に苦労します。
(詳しくは、人事評価のフィードバック面談に時間をかける会社は良い会社を参照)
「人事異動が多い」会社
「人事異動が多い」会社が成長できる良い会社であるのは、以下3つの理由からです。
・学ぶ機会が増える
・変化に慣れる
・時間軸が短くなる
ただ、これらは成長を求める場合です。成長を求めないのであれば、異動の負荷はとても重くなりますので、おススメしません。
ただ、少しでも成長したいと考えるなら、自分で無理して頑張らなくても、結果として成長できる環境に身を置くことで上記3つを獲得してほしいと考えます。
本来はやりたいことがあり、そこに向けて成長していければ最高です。
しかし、20代のうちから「本当にやりたいこと」が明確な人は、そう多くありません。
異動の多い環境は、いわばキャリアの「基礎体力」を養う期間です。
この期間に成長の土台を築いておくことで、将来やりたいことが見つかった時に、誰よりも有利なポジションからスタートを切れるのです。
(詳しくは、「人事異動が多い」会社は成長できる環境がある良い会社を参照下さい)
会社を好きになる2つのことがある会社
会社を好きになるたった2つの理由は、以下2つです。
1.一緒に働く人が好き
2.商品が好き
一緒に働く人が好きになる会社の見つけ方は、以下4つです。
・採用担当者だけで判断しない
・できるだけ同世代が多い会社を選ぶ
・ノリが合う会社を選ぶ
・内定が出たらオフィスを見せてもらう
商品が好きになる会社の見つけ方は、以下の1つです。
「自分が嫌いな商品を除外する」
(詳しくは、良い会社の選び方「会社を好きになるたった2つの理由を知っておく」を解説を参照)
責任の所在が明確な会社
すべてが明確だから
良い会社は組織図がシンプルになっており、誰が何の責任を負うのかが明確です。
責任が明確なので、何をすればいいのかも明確になります。
組織の本質は分業なので、権限移譲と責任が分業という形で明確化されます。
(詳しくは「組織図」の見方・考え方・種類をわかりやすく解説を参照)
悪い会社は、明確化されていないのです。組織に所属する人が何をしたらいいか分からず非効率となります。
役職で言うと、次長、課長代理、プレイングマネジャーが多い会社です。
何事も明確にしすぎるとそれしか考えなくなる。だからあえて曖昧にしているという経営層がいますが、曖昧にされたら8割の人は動けなくなります。
社員全員が、自分で考えて自分で動ける人ではないことの理解不足か?組織運営をちゃんと考えるのが面倒か?のどちらかです。
(詳しくは良い会社の見分け方「責任の所在が明確」をわかりやすく解説を参照)
変わることに慣れている会社
会社は変わらないと存続できないから
変われる風土があるから
組織力が高くなるから
この3つが、変わることに慣れている会社が良い会社の理由です。
変わることが受け入れられる組織は、とても強い組織となるだけでなく、働く従業員も鍛えられ成長できるのです。
(詳しくは、変わることに慣れている会社は良い会社を参照)
強みがシンプルに表現できる会社
強みが明確だから
強みがシンプルであればあるほど、大きなマーケットで勝てているサービスを提供しています。悪い会社は、長々と説明しないと自社の強みを表現できません。小さなマーケットでしか強みがないからです。
ファッション通販で1番と言えば、ZOZOさんです。シンプルですね。小さなマーケットだと、ファッション通販でレディス向け・年配向け・普段着で強いサイトですと説明が長くなります。
強みがシンプルだと、誰が売ろうが売れ方のばらつきは少なくなります。
逆に弱い会社は、営業担当を変えるとサービス内容が変わり、受注できなくなるので、同じ顧客を10年20年担当している営業担当が沢山います。
会社都合で、営業担当を10年20年塩漬けして成長の機会を奪っているだけです。
業種を一言で言えない会社
新マーケットで差別化できているから
上記とは真逆に感じると思いますが、業種を一言で言えない会社は良い会社です。
なぜなら、新しい、もしくはニッチなマーケットで商売をしているからです。今まで存在する業種ではないから、一般的な名称がないのです。
昔話が1年以内の会社
悪い会社は時間軸が長いから
先輩達が昔話をしていて1年前位の話かな?と思ったら、10年前の話だった。この会社は悪い会社です。
市場で負けて、昔の資産で生き延びている可能性が高いです。
このような会社の一番のポイントは、仕事や思考の時間軸が長いのです。切羽詰まっていないのです。
負けている会社の方が、危機感がありそうですが、完全に逆です。負けている会社ほど時間軸が長いので、昔話も大昔ばなしなのです。
このような会社に転職した経験があるのですが、20年前の経験を昨日かのように話してくれました。
20年前と言えば、Googleが創業してまだ数年、上場前の頃です。その経験は今のネット社会では使えない経験なのですが・・・。
結果よりもプロセスを求める会社
管理職が従業員にちゃんと向き合っているから
20代前半の若手に、結果よりもプロセスを求める会社は良い会社です。プロセスを求めるって、上に立てば分かるが、かなり深く関わらないといけません。そこまで関わってくれるから良い会社なのです。
悪い会社は、深く関わることをしない、もしくは関わるスキルがないので結果のみで判断せざるをえなくなります。
そうして、社会人は結果がすべてだという常套句を言い訳にしてマネジメントや教育を放棄しています。
これもたまたま目撃したのですが、ある上場会社で、新入社員全員集めて、営業本部長がとても怖い顔で「社会人は結果がすべて。結果が出る仕事をしてください」とだけ伝えた光景を見ました。プロセスの話は皆無です。
プライム市場に上場している会社でもこんなものです。年間300名採用して300名やめている会社ですが。
(詳しくは良い会社の見分け方「結果よりもプロセスを求める会社」は良い会社を参照)
雑談が多い会社
話したくないと思う人が少ない
「すべき」ではなく「したい」が多い
頑張ろうと思える
上記が良い会社の理由ですが、前提条件があります。
仕事が個人に適切に割り振られている
上記が前提条件となります。
雑談で避けたいことは、無駄なおしゃべりが続くことです。
もちろん少しならいいのですが、長く何回も続く場合は問題となります。
その大きな理由が、仕事の割り振りがちゃんとできないことで、暇な人が周りを巻き込んで「時間つぶし雑談」をするからです。
したがってこの前提が大事になります。
(詳しくは、良い会社の条件 雑談が多い会社を参照)
上司が懇切丁寧に教えてない会社
考える機会を作ってくれるから
単純作業やルーチンワークはもちろん教えてもらいましょう。それ以外の相談で「どうしたらいいですか?」と聞くと、懇切丁寧に教えてくれない会社はいい会社です。
なぜなら聞く側の考える機会を奪っていることをわかっているからです。稚拙でもいいから自分の意見を持って相談しましょう。それを受け入れてくれるのが良い会社です。
逆にやさしく何でも教えてくれるのは、いい人たちでしょうが、人の成長を阻害していることを分かっていない会社です。
指示が具体的な会社
指示が的確で行動に移せる
若手社員に対して、良い会社は指示が的確だからです。
「資材が値上がりしているから、ちゃんと考えて動くように」という指示ではなく、「資材が値上がりしているから、原価で○○万円減らす案を作ること」という指示を出します。
そうすると指示された方は、行動に移せるからです。この差はとてつもなく大きい。
コスト削減策以外も求める場合は、「〇〇万円減らす案を提案してください。その上で、その他の方法で利益を確保する方法があれば追加で提案してください」と指示を出します。
伝えたとしても、ちゃんと伝わって行動をおこしてもらって初めて伝わった状態です。良い会社はこれをわかっています。
悪い会社は丸投げして、後で提案の内容がずれていると怒ります。そもそも伝わっていないのに。
人事異動の多い会社
仕組み化ができているから
良い会社は人事異動が多く、悪い会社は人事異動が少ないです。
人事異動が多いと人の経験値が活かせないと感じますが、誰が担当でも一定レベルとなる仕組み化ができるので強い組織となります。
仕事を人ではなく、組織に紐づけることで、組織に知見がたまります。
逆に異動が少ない会社は、人に仕事が紐づきます。結果、そのその人が退職したら何も残らなくなり、一からのスタートとなります。
定量・定性両方を両方おこなう会社
業績が上がり給料が上がる可能性が高まるから
定量・定性分析両方を扱っているということは、
経営者がちゃんと考えている
この証明になります。
経営者がちゃんと考え仕事をしていれば業績が上がる可能性が高まります。
また、ちゃんと考えて適切な判断材料があれば、正しい判断になる可能性が高まります。
結果、業績が良くなる可能性が上がり、給料が上がるだけでなく、お客様に喜ばれるサービスが提供できることで、やりがいも持てる可能性が上がるからです。
(詳しくは、良い会社の条件 定量・定性分析を両方おこなう会社を参照)
社内呼称で肩書をつけて呼ばない会社
風通しがいい
社内の風通りがとても大事だと知っているから
たかがこれ位でと思われますが、これだけで良い会社か悪い会社がわかります。
業績不振の会社ほど肩書で呼ぶことにこだわり、業績が良い会社ほど肩書にこだわない傾向が顕著です。
肩書で呼ばせるということは、風通しが悪くなることを会社として悪だと考えていないのです。
会社はどうしても役職等の差がありますので、どれだけ気をつけても風通しが悪くなります。結果、意見が活発に交換されなくなり、淀んだ組織風土となります。
目的と方法をセットで指示をする会社
方法には必ず目的があるから
良い会社は必ず目的とセットで指示がきます。悪い会社は指示のみです。
なぜこのようになるかと言うと、目的を明確にしないと人は動かないからです。
組織には指示命令系統が必ずあります。指示命令系統を通して人が人に指示を出します。
会社は、家族ではなく他人の集まりです。また、人は論理だけでは動きません。必ず感情が動いて初めて行動できます。
感情を動かすには、論理で伝えることで理解してもらい、その理解してもらったことで感情が動くかどうかが大事になります。
良い会社は、そんなめんどくさい人に動いてもらうために、目的を伝えることは当然のことになります。ただ、悪い会社は、もう一つの人に動いてもらう手段であり、ある意味簡単な方法である恐怖で人を動かします。結果指示だけの伝え方となります。
取締役構成で判断
・新卒入社の取締役の比率
・取締役に占める同族数
・親会社からの出向があるかどうか
上記を確認することで、
・組織の硬直度合がわかる
・3名以上の同族者がいれば、経営体制に問題あり
・親会社があると経営の制約がある
上記がわかります。
(詳しくは、良い会社の見分け方 「取締役の構成を見る」を参照)
新卒入社が多い古い会社でおきる一番の問題とは?
問題であることを問題と言えなくなる
会社は常に、環境にあわせて変化していく必要があります。そのためには、今抱える問題点解決が必要です。
ただ、新卒入社が多い古い会社の多くは、解決すべき問題を問題であると言えなくなります。
理由は以下の3点です。
・現経営陣の批判となる
・成功体験の呪縛
・気概がある人ほどやめていく
(詳しくは、新卒入社が多い古い会社でおきる一番の問題とは?を参照)
直接あって確認する方法
展示会でブースに訪問
様々な事象で判断する方法もありますが、思いきって直接接してみて、自分に合うかどうかを判断する方法があります。
面接等の採用における公の場ではなく、目当ての会社が展示会等に出展している場合、そのブースに訪問してみる方法です。
ブースが元気か元気でないか?
会場全体が元気か元気でないか?
ブースでの接点を持った際の印象
上記3つがポイントとなります。
また、ブースに立ち寄った際の見方のポイントは、
・会社や商品の強みをシンプルに話してくれているか?
・ブースにいる従業員(出展社というネックストラップをしています)の年齢層
・競合の悪口を言っていないか?
この3つとなります。
この内容を押さえておくと、その会社の本当の姿が見えてきます。
(詳しくは、良い会社の見分け方~展示会で直に接してみる~を参照)
良い会社は少数しかない
良い会社は少数しかありません。5社で働き、千社以上の会社に営業で訪問しました。その中で働いてみたいと心から思う会社は、5社だけです。
私の基準が高いわけではなく、これが実態です。
したがって、今の会社が「悪くない」と感じているのであれば、とても幸せであると思ってもらっても大丈夫です。
様々な現象から会社の特徴を解説の「まとめ」
パワハラやセクハラ、残業時間が長い、休日出社が多いなど明らかに悪い会社はあります。
ただ、それだけが全てではありません。実は辛い経験でも、意味のある経験もあります。当然その経験自体必要がない場合もあります。
1回目の転職ってとても大事です。
この記事の良い会社かどうかの見分け方と今働いている会社の上司が「良い上司かどうかの見分け方」8例を参考にして、本当に転職の必要があるかの判断の参考にしてみてください。
他のも転職を決める前に知っておきたいことの記事を書いています。参照ください。
今の会社が不安になり、転職のことを知りたくなった方へ
転職のことを知りたい方は、転職の判断、転職活動、入社判断をすべて網羅した以下の記事を参照下さい。
失敗するポイントをわかった上で転職活動ができます。
まずは、キャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録してみるのもおススメです。
登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。