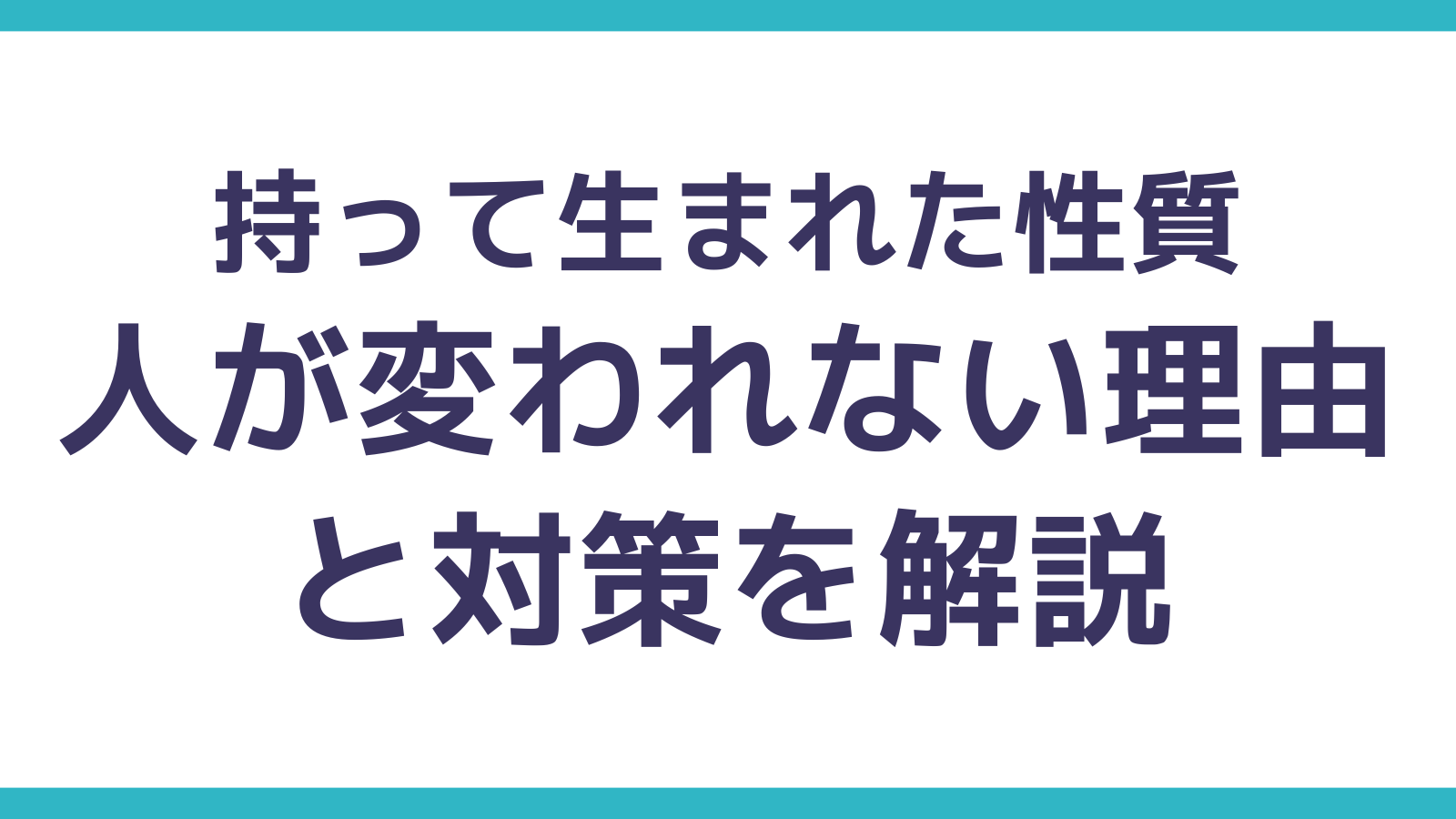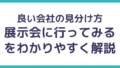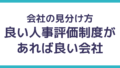なぜ私たちは、大切だとわかっていても行動に移せなかったり、たとえ始めても継続できなかったりするのでしょうか?
新しい知識や能力を身につけ、「今とは違う自分」になれるとわかっていても、多くの人が同じような悩みを抱えているのではないでしょうか。
実は、こうした行動の背景には、人が簡単に変われない「根本的な理由」が隠されています。その理由を理解し、適切な対策を講じなければ、本当の意味で自分を変えることはできません。
この記事では、人が変わることの難しさの根本原因と、それを踏まえた上で実践できる具体的な対策をわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【概念の本質】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質)
人が変われない根本の理由とは?
人は変わることに適合していないため
いきなり結論からお話しすると、残念ながら人間は根本的に「変化」に適合していません。
この性質は、私たちのDNAに先祖代々刻み込まれているものです。
もちろん、変化できる人もいますが、それはあくまで少数派。大多数の人は、変化することに苦手意識を持っています。
「変わる方法」に関する記事や書籍が世の中に溢れていること自体が、多くの人が変化に悩んでいる(=読者層が非常に厚い)ことの証と言えるでしょう。
人が変われない根本の理由の「詳細解説」
人が変われない根本の理由について、
・人が変わるとは?
・変わることができる人とできない人の差
・遺伝で変われない性質が受け継がれている
上記3つに分けて解説します。
人が変わるとは?
そもそも人が変わるとはどのようなことなのか?をまずは説明します。
今とは違う自分になること
シンプルに言えば、この一言に集約されます。
実はこの概念は、「成長する」ということと非常に近い意味を持っています。
(詳しくは「成長とは?」「成長する方法とは?」をわかりやすく解説を参照)
「成長」という言葉には「良い方向に変わる」というニュアンスが強く含まれますが、「良い方向」の定義は人それぞれ異なります。
そのため、「今とは違う自分」という表現が、より適切であると言えるでしょう。
変わることができる人とできない人の差
今とは違う自分になるには、
行動ができるか?できないか?
じっとしているだけでは、人は変わりません。つまり、「変化のための行動を実行できるかどうか」が、変わるための決定的な条件となるのです。
遺伝で変われない性質が受け継がれている
人の性質は、DNAで引き継がれている
現在、人類は地球上で繁栄を謳歌しています。私たちは、その繁栄を可能にした先祖たちのDNAを受け継いでいるのです。
世の中の多くの人が変化を苦手としている現状を考えると、過去の環境においては、「変わらないこと」が子孫を残す上で有利な特性だったのかもしれません。
これまでの行動を変えることは、集団からの孤立や生命の維持に関わるリスクを伴ったと推測されます。
また、人間は変化に対して不安や恐怖といった感情を抱くものです。これらの感情は、変化を避け、安全な現状維持を選択するための本能的なアラートとして機能してきたとも考えられます。
しかし、そうした性質がメリットとして働いた時代から、長い年月が流れ、現代社会は大きく様変わりしました。
現代において組織が求めるのは、変化に適応できる人材です。なぜなら、彼らは新しい知識を習得し、新たな能力を身につけるという変化に臆することなく対応できるからです。
ただし、現在の人の性質がおおよそ1万年前に形成されたと言われています。そして、1万年という期間は、人の性質が大きく変化するには短すぎる期間なのだそうです。
したがって、過去の環境に適応した「変わらない」特性を持つ人々が、現代においても依然として大多数を占めているのが実情なのです。
ビジネスフレームワークでも立証
変われない人の存在は、ビジネスのフレームワークでも立証されています。
イノベーター理論
イノベーター理論では、人を5分類に分けます。さらに5分類を2つのグループに分けます。
新しいものを受け入れる2分類16%と、受け入れない3分類84%です。
世の中の84%の人は新しいものを自分から受け入れないのです。
新しいものを受け入れないということは、現状維持なので、変わらないこととイコールです。
(詳しくは、人を5分類化し商品の広がりを理論化「イノベーター理論」についてわかりやすく解説を参照)
262の法則
262の法則とは、組織の中では、上位2割、普通6割、下位2割の分布となる経験則です。
上位2割の人は、能力が高い人です。能力が高いとは、自分自身を変化させることができるから能力を上げることができます。
だから、この262の法則でも実は変化する人が2割でそうでない人は8割となります。
イノベーター理論とは少し数字が違いますが、大体2割となります。
(詳しくは、なぜかこの分布に「262の法則」をわかりやすく解説&使い方紹介を参照)
スイッチングコスト
上記のような人数分類ではないのですが、変化を簡単には受け入れないことを説明する言葉がスイッチングコストです。
人間は本質的に物事を変えることを避けたいと考える生き物です。そのため、何か新しいことを取り入れようとすると、「金銭的」「物理的」「心理的」という3つの負荷がかかります。
人は、3つの付加がかかることで変わりにくい性質を持っているのです。
(詳しくは、何かを変える時に負荷となる「スイッチングコスト」を人の心理を踏まえてわかりやすく解説を参照)
変われない根本の理由の「まとめ」
これらのことから、人間は根本的に変化を苦手とする生き物であり、変わろうと試みると、様々な感情がその邪魔をする性質を持っていることがわかります。
結果として、「やろうとしても行動に移せない」「始めたとしても続かない」といった現象が頻繁に起こるのです。
たとえ良いことだと理解していても、それが実際の行動に結びつかないのは、ある意味必然的な結果と言えるでしょう。
しかし、それでは困るはずです。そこで、このような人間の根本的な性質を踏まえた上で、「どうすれば人は変われるのか」その具体的な方法を次に解説していきます。
変わるための方法
変わるための方法について、前提と方法に分けて解説します。
変わるための前提
「変化は容易ではない」という事実を受け入れる
人間はそう簡単に変われるものではありません。だからこそ、変化を望むのであれば、まず「変わることのメリット」を明確に認識する必要があります。
「どのような自分になりたいのか?」「なぜそうなりたいのか?」を具体的に掘り下げ、その目標達成へ向けて強い決意を固める必要があります。
生まれ持った「変化を避ける」という性質と向き合い、戦う覚悟も必要です。しかし、少なくとも「変化は簡単ではない」という事実を知っておくだけで、その後の取り組み方や心の準備が大きく変わってくるでしょう。
もちろん、無理に変わる必要はありません。もし「変わりたくない」と考えるのであれば、現状維持のままでも問題はないでしょう。
ただし、その場合は成長機会を失うというデメリットも受け入れる必要があります。
変わるための方法
行動を変える
変わるためには、行動を変えることが必要です。
その行動を変えるために方法ですが、
自分自身の努力
変化できる環境に身を置く
上記が2つの方法です。
それぞれを説明します。
自分自身の努力で頑張る
どのように変わりたいか?なぜ変わりたいか?の思いがあることが前提です。
その前提を踏まえながら、自分で努力するのです。具体的には、知識を増やしその知識を能力に変えましょう。
知識と能力が上がることで、できないことができるようになる経験を積むことができます。
その結果、変わることで得られるメリットを実感でき、その実感が変わることに対するモチベーションにつながり、変わり続けることができます。
変わるための2つのおススメな行動
能力とは、知識をインプットし、そのインプットした知識を使ってアウトプットすることで上げることができます。
(詳しくは、「知識と能力とスキルの関係」をわかりやすく解説を参照)
では、知識をインプット・アウトプットするには、どのような方法がいいのでしょうか?
・ビジネス書を読む(インプット)
・文章を書く(アウトプット)
上記2つから始めることをおススメします。一番基礎となる方法だからです。
(詳しくは「社会人の勉強法」たった2つだけ!をわかりやすく解説を参照)
Webサイトではなくビジネス書を読むことを勧めるのは、より深い知識が得られるからです。一つのテーマに対する情報量が圧倒的に異なります。
また、動画ではなくビジネス書が良いのは、同じ時間で脳の使う量に差が出るためです。例えば、1時間動画を視聴するのと、本を読むのとでは、どちらが疲れますでしょうか?
多くの方が本を読む方が疲れると感じるはずです。それは、それだけ脳を沢山使っている証拠です。
そして、文章は1テーマで3,000文字以上書けるようになることを目指しましょう。
これにより、論理的思考力が身につくだけでなく、文章を通して自分自身の考えを深く整理し、確固たる意見を持つことができるようになります。
さらに、文章はアウトプットの最たるものであり、インプットした知識を実践的な能力へと昇華させる効果があります。
文章が苦手な方でも、まずは1,000文字程度から始め、徐々にステップアップしていくことで、必ず3,000文字の文章が書けるようになります。
実行する方法
知識と能力を身につける方法は前述の通りですが、実際に「始めること」と「続けること」が次の大きな壁となります。
正直なところ、ここには「気合と根性」が必要です。 自分がどう変わりたいのかを具体的にイメージしながら、その行動が習慣になるまで、やめようとする自分自身と戦い続けるのです。
しかし、何もかもを「気合と根性」だけで乗り切ろうとすると、かえって続かなくなってしまいます。そのため、「気合と根性を発揮するポイント」を絞ることが重要です。
例えば、以下のような工夫がおすすめです。
・家に帰る前にカフェやファストフード店に30分立ち寄る。
・通勤電車の中を勉強時間と決める。
こうした特定の時間と場所を決め、そこでビジネス書を読んだり、文章を書いたりする行動に集中して「気合と根性」を発揮するのです。
この行動を継続していれば、やがてその行動をしないと「何か物足りない」「気持ち悪い」と感じるようになるでしょう。そうなれば、目標達成は目の前です。
ビジネス書を読む習慣をつける方法について詳しく書いた記事があります。
(ビジネス書の習慣化の詳細は、ビジネス書を読む習慣がつかない3つの理由とその解決策をわかりやすく解説を参照下さい)
また、ビジネス書を読んで学ぶ領域は限りなくあるのですが、私の経験上4つの領域を学べばよいと考えます。この4領域の詳細は、以下を参照下さい。
(ビジネスで学ぶ必要がある領域は、学ぶ範囲がわかる!「ビジネス学びの4領域」を1枚の図でわかりやすく解説を参照)
文章力の鍛え方は、以下で分かりやすく解説しています。
(文章力の鍛え方の詳細は、「文章力」の誰でもできる鍛え方をわかりやすく解説を参照)
変化できる環境に身を置く
自分を強制的に変えるためには、「変化せざるを得ない環境」に身を置くことが非常に効果的です。
例えば、停滞した企業ではなく、成長意欲が高く、活気のある会社で働くといった選択です。
自分で自分を律することが苦手な人(私を含め、ほとんどの人がそうでしょう)にとって、環境の力は絶大です。
日々の大半を過ごす会社の環境が、たとえ最初は辛く感じたとしても、そのような刺激的な環境で揉まれることで、自然と知識量や能力が向上していくものです。
(会社の選び方は、自分にあった会社の見つけ方!やりたいことが見つかっていない20代向けに解説を参照)
人が簡単には変われない根本の理由と対策の「まとめ」
人は変わることに適合していないため
人が変われない根本の理由です。
人は元来簡単には変われない生き物であり、変わろうとすると、様々な感情が邪魔をする性質を持っているのです。
その行動を変えるための方法は、自分自身の努力でビジネス書を読む(インプット)、文章を書く(アウトプット)の2つ。
もうひとつは、変化せざるを得ない環境に身を置くことです。
他にも「人の本質」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。