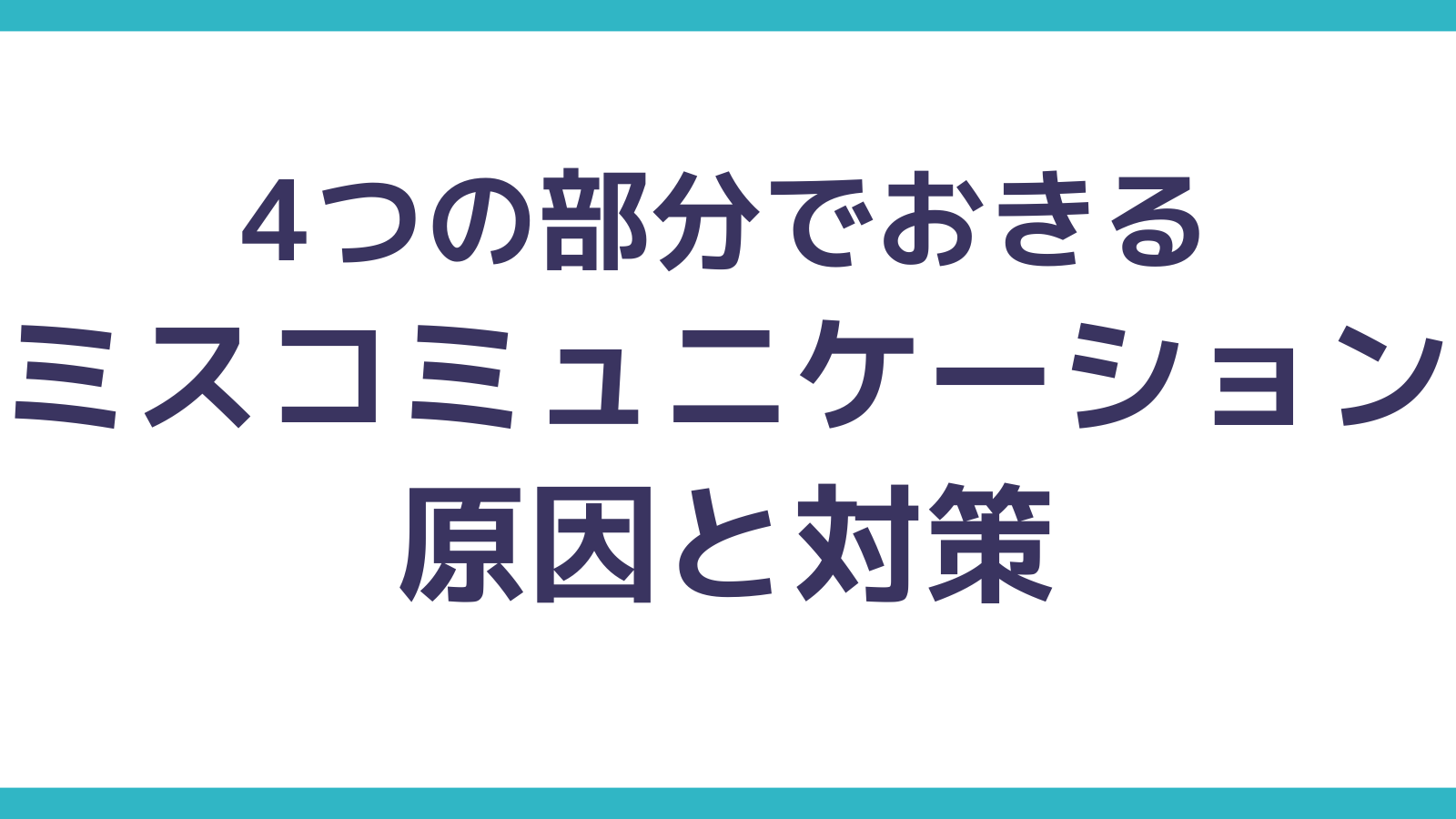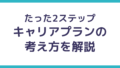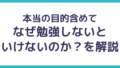「伝えたのに、なぜか伝わっていない」「意図と違うように受け取られてしまった」。
こんな経験、あなたにもありませんか?
ミスコミュニケーションは、時に人間関係にヒビを入れたり、大きなトラブルに発展したりすることもあります。
なぜ、このような残念なすれ違いが起きてしまうのでしょうか。
この記事では、コミュニケーションの流れの中で起こりがちな4つのミスコミュニケーションの原因と、その具体的な対策を分かりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい 考え方・意識・スキル)
ミスコミュニケーションが起きる理由と対策
齟齬がおきる部分がとても多い
ミスコミュニケーションとは、伝えた人と受け取った人に認識の齟齬が出ることです。
1回のコミュニケーションの中で齟齬が起きる部分が多く、1つクリアしたとしても、それ以外で起きてしまう可能性があります。
分解して考えないと正しい対策にたどりつかない
1回のコミュニケーションでも齟齬が起きる部分が多くあるので、1回のコミュニケーションを分解して考えないと、本当の原因にたどり着かず、間違った対策を考えてしまうことになります。
例えば、「売上の低迷」という言葉には沢山の原因があります。商品力が落ちたのか?営業力が落ちたのか?悪い情報が流布されたのか?強い競合が現れたのか?などです。
同じように、ミスコミュニケーション自体を対策が打てる大きさに分解しすることで、原因と対策を考えることができます。
・ミスコミュニケーションが起きる部分
・特定した部分における原因と対策
上記の順番で詳しく解説します。
ミスコミュニケーションが起きる部分とは?
・頭に思ったことを言葉に変える際のミス
・言葉を伝えるか伝えないかの判断のミス
・適切な言葉が選択できないミス
・言葉の解釈でおきるミス
上記4つでミスコミュニケーションが起きます。
ミスコミュニケーションがおきる4つの部分の詳細
・コミュニケーションの流れ
・各部分でどのようなミスが発生するか
上記の流れで解説します。
コミュニケーションの流れ
① (自分)頭の中にあることを言葉に置き換える
↓
② (自分)相手に伝えるかどうか判断する
↓
③ (自分)伝えようと思った言葉を発する
↓
④ (相手)言葉を受け止め解釈する
↓
⑤ (相手)頭の中で思ったことを言葉に置き換える
↓
⑥ (相手)相手に伝えるかどうかを判断する
↓
⑦ (相手)言葉を発する
↓
⑧ (自分)言葉を受け止める
↓
一番上に戻る
これらは、たった1回のコミュニケーションの中で、送り手と受け手の間に8つもの行動があることを示しています。
つまり、1回のやり取りだけでも8か所もミスコミュニケーションが発生する可能性があるのです。これが、コミュニケーションのすれ違いが頻繁に起こる大きな理由です。
① から⑧について何が起きているのかを深堀していきます。
① (自分)頭の中にあることを言葉に置き換える
言葉と言う記号に置き換える際のミス
言葉は、あくまで記号です。なんの記号かというと、感じたことや思ったことを相手に伝えることができるように変換した記号です。
したがって、頭にあることを的確な言葉に置き換える際に問題が発生する可能性があります。
② (自分)相手に伝えるかどうか判断する
伝えるか伝えないかを判断する際のミス
人は思ったことを言葉に変換しますが、それをそのまま伝えるかどうかを判断します。
相手の立場や機嫌、自分自身の保身など真っすぐそのまま伝えることをためらう場面は常にあります。
その判断で文脈がつながらず、問題が発生する可能性があります。
③ (自分)伝えようと思った言葉を発する
相手に合わせた適切な言葉が選択できないミス
言葉には、人により解釈の違う言葉がたくさんあります。
例えば、「課題」という言葉の意味を10名に聞けば、10名それぞれの答えがあります。戦略、原因なども同じです。
その上、言葉に多く含まれる形容詞も不明瞭な言葉です。
あの人は背が高いといった場合、人により、背が高い基準は190cmの場合や170cmの場合もあります。
このように、相手が想定する言葉の意味をイメージできずにミスを起こす可能性があります。
④ (相手)言葉を受け止め意味を解釈する
言葉の解釈でおきるミス
発した言葉を受け取った際に、発した人が想定した解釈とは違う解釈をする場合があります。
これにより、違った意味でとらえてしまい、ミスを起こす可能性があります。
⑤ (相手)頭の中で思ったことを言葉に置き換える
言葉と言う記号に置き換える際のミス
① と同じことが言葉を聞いた受け手にも起きる可能性があります。
頭にあることを的確な言葉に置き換える際に問題が発生する可能性があります。
⑥ (相手)相手に伝えるかどうかを判断する
伝えるか伝えないかを判断する際のミス
② と同じことが、言葉を聞いた受け手にも起こる可能性があります。
伝えるかどうかの判断で問題が発生する可能性があります。
⑦ (相手)言葉を発す
相手に合わせた適切な言葉が選択できないミス
③ と同じことが、言葉を聞いた受け手にも起こる可能性があります。
伝えようと思って選択した言葉がミスを起こすことになる可能性があります。
⑧ (自分)言葉を受け止め意味を解釈する
言葉の解釈でおきるミス
④ と同じことが、言葉を聞いた受け手にも起こる可能性があります。
違った意味でとらえてしまい、ミスを起こす可能性があります。
ミスコミュニケーションがおきる部分の「まとめ」
頭に思ったことを言葉に変える際のミス
言葉を伝えるか伝えないかの判断ミス
相手に合わせた適切な言葉が選択できないミス
言葉の解釈でおきるミス
まとめると上記8工程で起きるミスをまとめると、上記4つが自分自身もしくは相手に起きています。
上記のように1対1であれば8部分ですが、1対1の複数ターンや、1対多数になれば飛躍的にミスコミュニケーションがおきる部分が増えます。
したがって、この4つのミスに対する対策をおこなう必要があります。
それぞれ解説します。
4つのミスの原因と対策
4つのミスに対する原因と対策を紹介します。
頭に思ったことを言葉に変える際のミスの原因と対策
ミスの原因
・知識量の不足
・アバウトなまま思考を止める
それぞれを説明します。
知識量の不足
知識量が不足していることで、伝えたい内容を表現する的確な言葉に置き換えることができない場合です。
アバウトなまま思考を止める
変換した言葉が、専門用語や形容詞のように、人により捉え方がちがうものに置き換えてしまうことで伝わりづらい言葉になる場合です。
ミスの対策
・言葉をたくさん覚える
・できるだけ専門用語・形容詞に変換しない
それぞれを説明します。
言葉をたくさん覚える
文章をたくさん読み、語彙や表現の引き出しを増やしましょう。
さらに、書いた文章を生成AIで校正してもらうのも非常に効果的です。
AIは、より適切な表現案を提示してくれるだけでなく、その理由も教えてくれます。このプロセスから得られる学びは計り知れません。
できるだけ専門用語・形容詞に変換しない
専門用語や形容詞に置き換えた場合はもう少し具体的にするという意識を持ちましょう。
専門用語は置き換えできない場合もありますが、形容詞は極力使わないようにするだけでも、具体的な表現が身に付きます。
言葉を伝えるか伝えないかの判断ミスの原因と対策
ミスの原因
・過剰な配慮や遠慮で辻褄があわなくなる
言ってはいけない、こんなことを言うと失礼かも?などの思いにより、伝えるべき内容のストーリーが崩れる場合です。
ミスの対策
・あきらめるのも一手
・ストーリーで判断する
それぞれ説明します。
あきらめるのも一手
伝えたい内容に大きな制約がかかる場合、その原因は会社の風土や慣習にあることが多いです。
これらを一個人で変えるのは非常に困難なため、時には「あきらめる」という選択も有効な一手となります。
もし「あきらめる」ことが難しく、その状況が苦痛であれば、転職などで環境を変えることも検討してみてください。
これは個人の努力だけでは解決できない問題だからこそ、私自身の経験からも強く実感していることです。
ストーリーで判断する
制約を感じた場合、話のストーリー全体をイメージしましょう。その部分が欠けても大丈夫そうなら抜く、そうでなければ、思い切って伝えましょう。
相手に合わせた適切な言葉が選択できないミスの原因と対策
ミスの原因
捉え方で変わってしまう言葉の不理解
曖昧な言葉を深堀せず使ってしまう
それぞれ説明します。
捉え方で変わってしまう言葉の不理解
ビジネス用語の多くは正解がありません。大枠の定義はありますが、人により違う意味で使われることも多くあります。
この事実を知っておかないと、自分の解釈で伝えてしまい、違う意味でとらえられる可能性が高まります。
曖昧な言葉を深堀せず使ってしまう
相手の考え方や思考でどのようにも解釈される言葉を使うことで、違う意味でとらえられる可能性が高まります。
ミスの対策
・自分なりの言葉の定義を設定する
・形容詞を使わず、数字を使う
それぞれを説明します。
自分なりの言葉の定義の設定
ビジネス用語の自分なりの定義を持つようにしましょう。あまりこの部分を深く定義する人は多くはありません。
だからこそ、自分なりの定義を持ってコミュニケーションするだけで、相手との定義が違うことがわかりやすくなります。
違いが分かれば、「私はこの言葉の定義をこのような意味で使っていますがどうですか?」と確認できます。
特に転職等で環境が変わった場合は本当にびっくりする位言葉の定義が違います。
形容詞を使わず数字を使う
人により捉え方の大きく変わる言葉を、できるだけ使わないことがとても重要です。
特にとても使いやすい形容詞が危険です。人により、大きくととらえ方が変わるからです。
逆に数字をできるだけ使いましょう。数字でのミスコミュニケーションは起きにくいからです。
1は1ですし、100は100だからです。
言葉の解釈でおきるミスの原因と対策
ミスの原因
・受け取った言葉の意味のとらえ違い
言葉のとらえ方が沢山ある言葉はたくさんあります。長く一緒にいる人では、意味が一致しやすいですが、そうではい場合は簡単にミスコミュニケーションがおきます。
ミスの対策
・意図と文脈の流れを意識して聞く
受け取った言葉を言葉尻ではなく、意図や文脈の流れでとらえるようにしましょう。
それだけで、流れに不自然なところがわかります。その際は言葉の意味を質問してみましょう。
全体を通しての対策
・自分も相手にもどちらにも原因があるという認識を持つ
・自分が会話している動画をとる
上記の意識と行動で自分を知ることができます。特に、話している自分の姿を動画に撮ってみることをお勧めします。
もし抵抗がある場合は、一人で「相手に何を伝えたいか」を想定して話す場面を録画するだけでも構いません。
客観的に自分の話し方を見ることで、意外な発見や、時には「稚拙だな」と感じる部分が見えてくるでしょう。
この自己認識こそが、ミスコミュニケーションが起こる前提を避ける第一歩となります。
「ちゃんと伝えたのに」という無意識からくる上から目線を改める有効な手でもあります。
4つのミスに対する原因と対策の「まとめ」
1.頭に思ったことを言葉に変える際のミス
2.言葉を伝えるか伝えないかの判断ミス
3.相手に合わせた適切な言葉が選択できないミス
4.言葉の解釈でおきるミス
4つのミスは上記です。
このように多くの要因が存在しますが、ミスコミュニケーションのメカニズムを理解しているかどうかで、日々のコミュニケーションは大きく変わります。
ぜひ、「自分にも原因があるかもしれない」という「自責」の視点を持って取り組んでみてください。それだけで、あなたのコミュニケーション能力は飛躍的に向上するはずです。
他にもビジネス基礎スキルについて書いた記事があります。参照下さい。
- 「伝え方の基本 大枠から詳細へ」
- 「前提をそろえる」
- 「正しい情報を得る6つのコツ」
- 「具体化と抽象化を使い分ける」
- 「手段の目的化」
- 「論理と感情の関係」
- 「人の思考の癖」
- 「人が変われない理由と対策」
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。