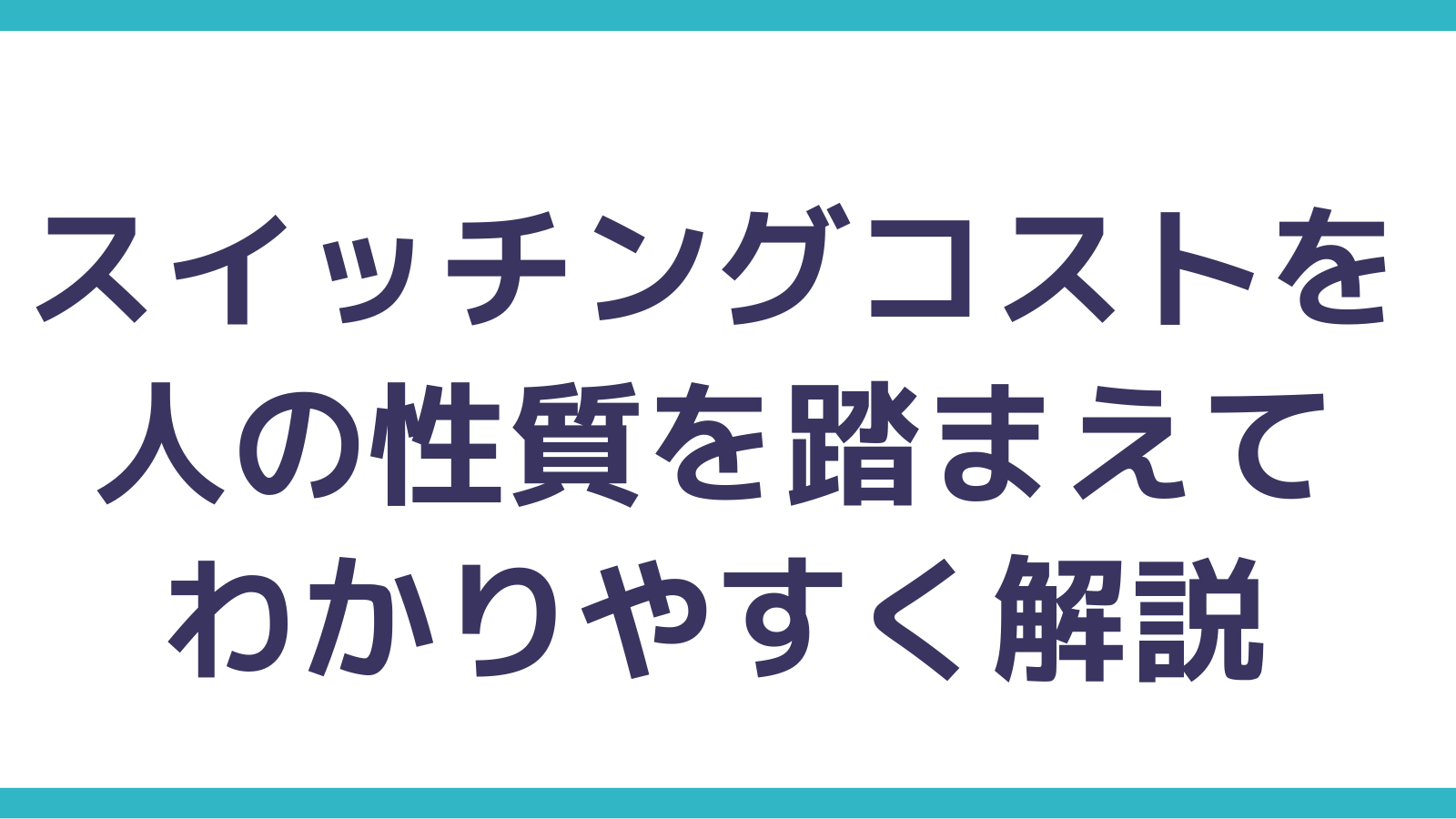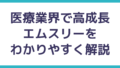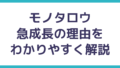他社の商品を自社の商品に変えてもらうことは簡単ではありません。なぜなら他社から置き換えてもらう際に様々な負荷がかかるからです。
この負荷=コストのことを、スイッチングコストと言います。
この記事では、スイッチングコストとは何か?なぜスイッチングコストかかるのか?どう乗り越えたらいいのか?を人の心理を踏まえて、わかりやすく解説していきます。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい ビジネス基礎知識)
スイッチングコストとは?
・人は物事を変えたくない生き物
・人が何かを変える時、3つの負荷がかかる
・この負荷のことをスイッチングコストという
上記がスイッチングコストのポイントです。皆さんもそうだとは思いますが、人は基本的に物事を変えたくない生き物なのです。それぞれを詳しく解説します。
人は物事を変えたくない生き物
遺伝子に組み込まれている
スイッチングコストが発生するのは、物事を変えることを嫌うように、遺伝子に組み込まれているからです。
変化したくないと感じる人の方が生き残って子孫を残す可能性が高かったため、変えたくない性質を持っている人が多いのです。
有名な理論でも証明されています。
イノベーター理論と言いますが、新しい商品やサービスをすぐに受け入れるかどうかで人を5分類に分けています。
新しい商品やサービスを、積極的に受け入れるタイプであるイノベーター・アーリーアダプターと言われる分類に入る人たちは、人口全体の16%しかいないという理論です。
その他の84%の人は、物事を変えることを嫌がる層となります。
(詳しくは人を5分類化「イノベーター理論」についてわかりやすく解説を参照)
このような比率になったのは、昔の生活環境の中で子孫を残せた比率がそのまま反映しています。
大昔は、多くても100名までのそれほど大きくない集落で、人は過ごしていたと言われています。
その中で変化を好む人は、その集落の外に出て行ったり、その集落内の出来上がったルールを変えたいと考えたでしょう。
結果、変化を好む人は、外敵との遭遇率が上がったり、集落の中で仲間外れにされたりして、長く生きることと、子孫を残す確率が低かったのです。
もちろん、食料確保のため時にはチャレンジも必要となりますので、全員が変化を嫌う集落だと、全滅し、子孫を残すことができないのです。
したがって、少数ながらも、一定数変化を好む人混じる集落が生き延びて、子孫を残すことができたのです。
ちなみに人類の進化では、1万年前は一瞬のことだといわれています。結果、今の時代になっても、同じような比率で変化を好む人と変化を好まない人がいるのです。
上記のような性質を持っているので、何かを変える時には、遺伝子に組み込まれている自己防衛能力が発揮され、負荷がかかるのです。
人が何かを変える時、3つの負荷がかかる
・金銭的コスト
・物理的コスト
・心理的コスト
上記3つが3つの付加です。それぞれ解説します。
金銭的コストとは?
金銭的コストとは、商品を置き換える際に、今まで払っている金額より高くなる場合に発生するコストです。
当然高くなると、その分のメリットが本当にあるのか?が気になります。安くなるのは簡単に認めますが、高くなることは簡単に認めません。
物理的コストとは?
物理的コストとは、商品の置き換える際に作業等で業務増えてしますことによるコストです。
例えば、検討・実行する際に、新しい商品を選ぶための時間、購入するための手続き、入れ替えの際の作業等、商品を置き換える等の業務にかかるコストです。
心理的コストとは?
心理的コストとは、めんどくさいという気持ち、手間だと思う気持ちを乗り越えるコストです。
商品の置き換えを検討する際に、作業の発生に嫌だと思う気持ち、新しい商品の使い方に慣れる必要性、以前の商品の方が良かったという思うだろうな等の、心の中に発生するネガティブな気持ちをコストとして表現しています。
3つのコストを乗り越えてもらうために
心理的コストをクリアしてもらうために、変える方が良いことを正しく認識してもらい、その結果、変えるほうがいいと感じてもらうことです。
心理的コストのクリアが前提条件
3つのコストの関係性ですが、金銭的コスト物理的コストをクリアする前提条件が心理的コストとなります。
金銭的・物理的コストがクリアしやすいものであっても、心理的コストをクリアしないと、変える行動をとりません。
逆に、心理的コストがクリアできたら、金銭的・物理的コストが高くても、何とかしようと考えるのも人の特徴です。
心理的コストをクリアするためには?
では、心理的コストをクリアするためにどうすればいいのでしょうか?
まずは、納得してもらうことです。では納得するためには、どうすればいいか?
正しく理解してもらうことです。では、正しく理解してためにはどうすればいいか?
頭で理解できる状態で情報を伝えることです。そのためには、ロジック=論理が必要となります。
そのロジックを伝えることで、理解してもらい、その結果、相手の感情が動けば、人は行動をおこしてくれます。
感情が動かなければ何もしません。もしくは、何もしない行動を取るとも言えます。
ロジックが良くても、感情が動かなければ人は動きません。ただ、そもそも伝わらないと絶対に感情は動きませんので、正確に伝えるためにロジックが必要になります。
「これ絶対いいよ!」とだけ言われても人の感情は動きません。
「〇〇〇〇なので、効果があるからいいよ」と言われて初めて理解できる=感情が動く前提条件が整うのです。
このように言うと、信頼する人に「これ絶対いいよ!」と言われるだけで感情が動くといわれます。
でもこれは、信頼する人が話すことで「信頼する人がうそをつくはずがなく、私にとって本当に必要な物をすすめてくれる」と思っているのです。
正しく伝わっても感情が動かないのは、その人にとって必要がないからです。
(詳しくは、「論理」と「感情」の関係をわかりやすく解説を参照)
スイッチングコストとは?の「まとめ」
・人は物事を変えたくない生き物
・人が何かを変える時、3つの負荷がかかる
・この負荷のことをスイッチングコストという
ロジックで理解して、感情が動けば行動(物事を変える行動)をとるのです。
ただ、わかってはいるけど行動できないことってありますよね。
早寝早起きにはじまり、嗜好品を取らない等様々なことがあります。これは、理解しているけど、心が動いていない(もしくは心がやらないように命令している)のです。
他にもたくさんのビジネス記事を書いています。まずは、知っておきたい ビジネス基礎知識51選を参照してみて下さい。
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。