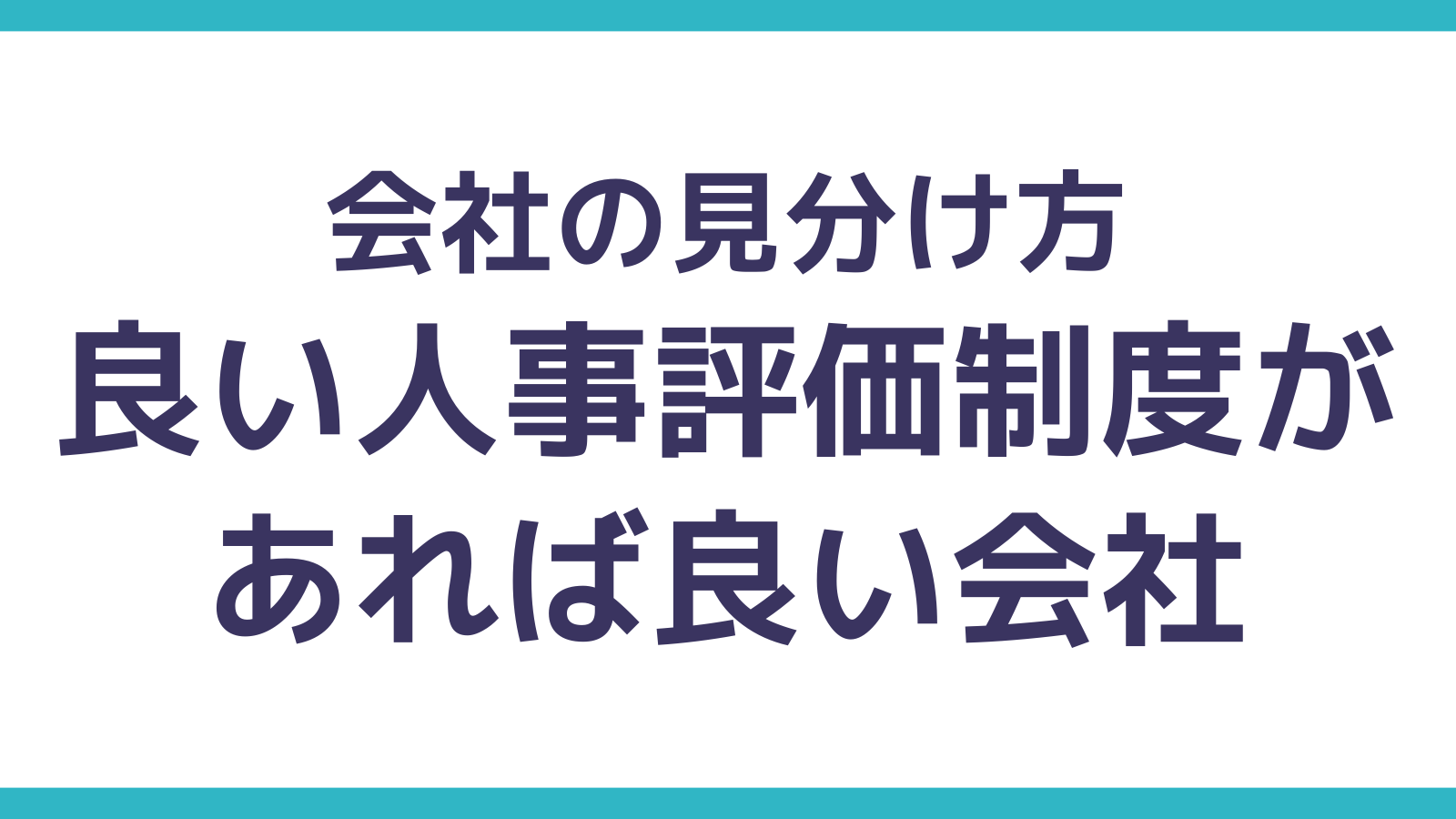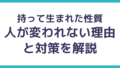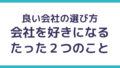会社の見分け方には様々な方法がありますが、どんな人事評価制度を持っているか?で良い会社かどうかがわかります。
なぜなら、人事評価制度は、会社の根幹となる制度なので、経営層の考え方が色濃く反映されているからです。
ただ、1社2社でしか働いていない若手社会人の皆さんにとっては、具体的に知っている人事評価制度は1つもしくは2つなので、良い人事評価制度と悪い人事評価制度の区別ができないでしょう。
この記事では、経験社数が少ない方でも、人事評価制度の良悪の判断ができる方法を解説します。
この判断ができると、今働く会社や転職しようとする会社が良い会社か?悪い会社か?を見分けるスキルがつきます。
この記事は、
・3回の転職経験
・中途採用の責任者の経験
・多数の書類選考・面接の経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい いい会社の判断方法)
人事評価制度でなぜ良い会社かどうかがわかるのか?
・人事評価制度は、会社組織の根幹をなす制度
・良い会社は、根幹の制度をちゃんと設計実行している
上記2点の理由で、人事評価制度を見たら良い会社かどうかがわかります。
人事評価制度の目的は、「従業員が組織に貢献すること」「従業員自身が成長すること」を同時に実現することです。
(詳しくは、「人事評価(人事考課)の目的」をわかりやすく解説を参照)
また、なぜ人は会社組織を作るのでしょうか?
ひとりでできないことができるからです。
そのために大事なことは、
・人が集まること
・共通の目的があること
・分業されていること
・仕組みやルールが整備されていること
この4つが大事になります。
(詳しくは、「会社組織の本質とは何?」をわかりやすく解説を参照)
この4つに人事評価制度がすべて絡んでいるのです。
上記から、人事評価制度は会社組織の根幹をなす制度だと言えます。
したがって、その根幹となる人事評価制度を、どこまでちゃんと設計し実行できているかを見ると、その会社の経営層が組織運営をどこまで深く考えているかがわかります。
経営層がちゃんと考えていると良い会社である場合が多いです。ただ、ちゃんと考えていない経営層の会社なら、ほぼ間違いなく悪い会社です。
人事評価制度の良悪を見極めるポイント3つ
・個人の目標及び判断基準が明確か?
・プロセスの項目が入っているか?
・上長との人事評価関連の面談が年間4回以上あるか?
上記の3つで良い人事評価制度かどうかがわかります。
それぞれを解説します。
個人の目標及び判断基準が明確か?
個人の目標及び判断基準が明確かについて、
・明確かどうかが大事な理由
・明確かどうかの判断方法
上記2つに分けて解説します。
明確かどうかが大事な理由
迷いなく働くことができ、適切な評価を受けることができる
個人の目標及び判断基準が明確であれば、働く人は、迷いなく働くことができ、その上適切に評価を受けることができます。
人が集まって活動するのが会社組織です。その組織の活動の最大化を図るには、適切な分業体制を築くことが大事になります。
分業体制では、抜けもれダブりが生じないようにすることが一番大事になります。
したがって、各個人の分業がちゃんと設計され、個人の目標が明確にあり、個人の目標が計れるような判断基準が必要です。
逆にこれができないと、抜けもれダブりが生じるだけでなく、働く人が何をすればいいのかが不明確になります。
その結果、組織活動の最大化が図れなくなります。
ただ、これができている会社はごく一部です。
私は、出向も含めて5社で働いていますが、できている会社1社だけです。
ただ、このように言うと、あまり細分まで決めると、それしかやらなくなるし考えなくなるという反論がよく出ます。
ただ、絶対そんなことはありません。
経営者や役職者が、本来組織運営を考える=分業体制を構築する責任を逃れているだけですし、それしかやらなくならない目標設定にすればいいだけだからです。
(詳しくは、会社の見分け方「責任の所在が明確」なら良い会社をわかりやすく解説を参照)
明確かどうかの判断方法
対象期間の数値目標と評価方法を設定する方式かどうか
人事評価の設定項目には、大きく2つの設定方法があります。
1.責任感、協調性、遂行能力などの業務態度や個人の能力を設定し、上長が5段階で評価する方法(個人のスキルや能力にフォーカス)
2.具体的な目標(予算達成、新規獲得社数、企画立案件数)を設定し、それぞれの項目で評価する方法(個人の役割進捗にフォーカス)
上記で2を採用していると、目標等が明確な会社と言えます。
ただ、長い歴史を持っている会社の多くは、圧倒的に1の方法を採用しています。
個人が長く一つの会社で務めることを前提に、個人の業務態度や能力に主にスポットを当てる考え方を取ると1の評価制度になります。
2の方法を採用している会社は、会社の歴史も長くない場合が多いです。
こちらは、個人の役割にスポットを当て、期間内でどのような役割を実現できたのかにフォーカスしています。
当然、1より2の方が明確になりますし、それ以上に個人への業務の割り振りを、経営者や役職者が明確にする必要があります。
業務の割り振りのためには、戦略と戦術が明確である必要があります。
ゆえに、精緻に考えないと運用できないのが2なので、制度設計運用をちゃんと考えている会社と言えるのです。
今働く会社はわかると思いますが、転職先の会社では、内定をもらうまでは人事評価制度の説明はない場合がほとんどです。
したがって、面接時に「人事評価シートの具体的な項目はどのような内容でしょうか?また、その項目は誰が決めますでしょうか?」と聞いてみましょう。
その答えで1か2を判断できますし、そもそも人事評価制度があるのか?どのような設定方法か?までわかります。
(詳しくは、転職面接の逆質問で「絶対聞きたい3つのこと」をわかりやすく解説を参照)
プロセスの項目が入っているか?
プロセスの項目が入っているがどうかについて、
・プロセスが大事な理由
・プロセス項目の具体例
に分けて解説します。
プロセスが大事な理由
長距離走のため、その場その場の結果ではなく、継続して結果が出続けることが大事だから
社会人は結果が大事です。これに異論はありません。
ただし、会社は、短距離走ではなく長距離走です。短期的に結果が出ても、結果が出続けなければ会社は存続できません。
継続的に結果を出すためには、結果の出る正しいプロセスをおこない続けることが必要になります。
したがって、プロセスの項目が人事評価に入っていることが大事になるのです。
では、誰がプロセス目標を設計するのか?
この部分で考え方が大きく分かれます。経営者や役職者が設計するのか?役職を持たない人に考えさせるのか?
もちろん前者です。経営者や役職者は、役職を持たない人の活動を通して、組織全体の結果を出すことが仕事です。
この部分が会社組織に基本的な役割の考え方ですが、ちゃんとした仕組みになっていない会社が大多数です。
この部分についても、私の働いた5社では、プロセスを大事にしているのは1社だけです。
なぜこのようなことになるのか?
上記のことを理解していないこともそうですが、プロセスを設計し、設計した内容を実行することがとても難しいからです。
プロセスを設計するためには、暗黙知を形式知化しないといけません。
また、形式知について、感情を持っている部下に実行してもらう必要があるからです。
これは実に難しいことです。結果、経営者や役職者は、自分の仕事を放棄し役職を持たない人の結果のみで評価しようとするのです。
それしかできないし、楽だからそうなるのです。
だからこそ結果指標もありながら、プロセス指標もちゃんと設計し指標化することが大事だし、それができている会社は良い会社なのです。
プロセスの具体例
具体的な例で言うと、例えば営業担当で結果指標が個人に課せられた売上目標達成率だとします。
その売上目標を達成するためには、訪問社数、提案回数や新規アプローチ数、スキルアップのための勉強会開催などが大事になります。
このような結果を出すためのプロセスが評価項目に入っているかで判断できます。
ちなみに、役職が上がれば結果指標の比率が上がり、役職が下がれば、プロセス指標が多くなります。
上長との人事評価面談が年間4回以上あるか?
人事評価には対象期間(多くは半年)に2回の面談が必要
1回の評価に対して、評価対象期間を振り返る面談、査定結果のフィードバックと次の目標をすり合わせる面談の2回が必要です。
したがって、年二回の評価であれば年4回の個人面談が最低回数となります。
人事評価でとても大事なことは、目標指標の納得性及び結果判断の納得性の2つがとても大事です。
ボーナス等の給与に関わることは当然ですが、個人の成長にも関わるからです。
当然ながら、人は納得しないと動けませんし、納得しないと不満が残り続けます。
したがって、目標指標の納得感の醸成で1回、目標指標の結果のすり合わせで1回の面談が必要になるのです。
そして人事評価をちゃんと運用している会社は、最低上記の個人面談設定をおこなっています。
(詳しくは、人事評価のフィードバック面談に時間をかける会社は良い会社を参照)
良い会社の条件 ちゃんとした人事評価制度がある会社の「まとめ」
・人事評価制度は、会社組織の根幹をなす制度
・良い会社は、根幹の制度をちゃんと設計実行している
人事評価制度を見たら良い会社とわかるのは、この2点が理由です。
・個人の目標及び判断基準が明確かどうか?
・プロセスの項目が入っているか?
・上長との人事評価面談が年間4回以上あるか?
人事評価制度の良悪を見極めるポイントはこの3つです。
上記の3つを見れば良い人事評価制度かどうかがわかります。もし、今働いている会社の人事評価制度がこれらにあてはまらない場合は、転職を検討するのも一つの選択肢です。
他にも良い会社を見分ける方法を書いています。参照下さい。
- 「責任の所在」が明確な会社」
- 「人事異動が多い会社」
- 「すべき」より「したい」が多い会社
- 「恐怖より危機感で人を動かす会社」
- 「管理職が本来の仕事をしているか?」
- 「変わり慣れている会社」
- 「結果よりもプロセスを求める会社」
- 「単純作業のマニュアルがある会社」
- 「エクセルが使える人が多い会社」
- 「定量・定性分析を両方行う会社」
- 「取締役の構成を見る」
- 「良い上司かどうかの見分け方」
今の会社が不安になり、転職のことを知りたくなった方へ
転職のことを知りたい方は、転職の判断、転職活動、入社判断をすべて網羅した以下の記事を参照下さい。
失敗するポイントをわかった上で転職活動ができます。
まずは、キャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録してみるのもおススメです。
登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。