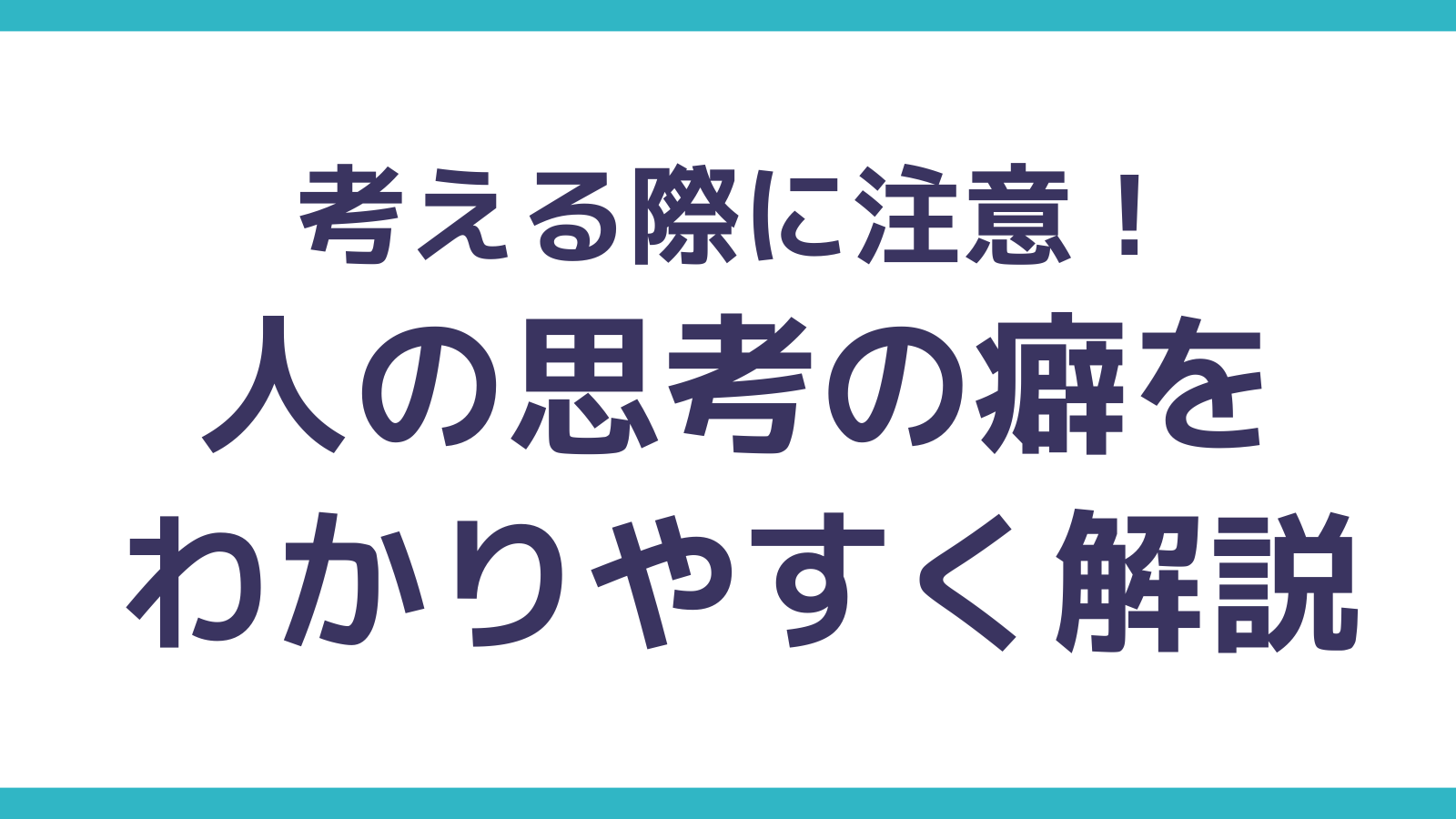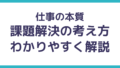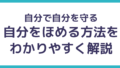物事を考える際に、誰もが自分自身の思考の癖を使って考えています。
ロジカルに考えていても偏って考えていることは多くあります。
したがって、人にはどんな思考の癖があるのか?をしっかり認知しておくことが、この偏りを是正する方法となります。
この記事では、人にはどのような思考の癖があるのか?となぜそのような癖があるのか?について、わかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい 考え方・意識・スキル)
なぜ人の思考には癖があるのか?
・数万年前の狩猟採集時代の思考から進化していない
・当時は先入観や経験則でまずは判断することが大事だった
この2つが今生きている人に引き継がれています。昔の時代に最適化さえた思考で今を生きているので、今求められる客観的は思考ではなく、本来持っている主観的な思考が得意なのです。
それぞれを紹介します。
数万年前の狩猟採集時代から思考は進化していない
数万年前から持っている本能は変わっていない
今私たちが持っている本能は、数万年前の狩猟採集時代からもっている本能とあまり変わっていないそうです。
沢山の「人」が今この現代に生きているのは、各時代において生き延びて子孫を残すことができたからです。
例えば、お腹が空けばイライラするのは、イライラすることで闘争心が湧き出て、獲物を獲得しやすくなるためです。
このような性質を持っていた人が食欲を満たすことができて、生き延びて子孫を残しやすかったのです。
また、他人に共感できることで、集団生活の中で仲間外れにならずに、生き延び子孫を残すことができたのです。
それ以外にも、急に物音がしたら、考えていたことや行動をすべてストップして、反射的に逃げたり、身構える行動ができるのは、危険が押し寄せる可能性を感じることで生きる可能性が高かったのでしょう。
人類は、生物の中では、1世代あたりの寿命が長い方です。そのため、進化のスピードは、1万年間では、ほんの少しなのだそうです。
結果、今私たちが持っている本能は、今でも数万年前の狩猟採集時代からもっている本能をベースに現代を生きているのです。
当時は先入観や経験則でまずは判断することが大事だった
生き延びるためには、先入観や経験則で判断する方が有利だった
狩猟採集時代は、生き延びて子孫を残すために、外敵から身を守る必要がありました。
定住せずに、常に食料を求めて、移動して暮らしていました。そのようないつ襲われるかわからない環境で過ごしていたので、ロジックで考えるのではなく、先入観や経験則で判断する必要があったのです。
あの山を越えたら鬼がいるぞという言い方で、山の向こうに行かないようにしていました。山を越えると、外敵や他の集団がいるので、殺されてしまうかもしれないことを経験則で得ていたのです。
このように、狩猟採集時代に得た、先入観や経験則で考える性質が私たちに遺伝しています。
公平に見たり、客観的に見たり、数値で事実をおさえたりすることが苦手なのです。
結果、主観で判断する思考の偏りを持っているのです。
具体的な思考の癖
では、ここからは、具体的な思考の癖の事例を見ていきます。
あくまで、基本的は性質なので、人により大小はあります。
ただ、この思考の偏りを認識しておくことで、こんな時に偏りがでるんだと思えることが大事です。
自分に都合にいい情報ばかり集める
自分が正しいと思った情報を肯定する情報に、目が行く傾向があります。
人は、基本変わりたくない性質なので、自分を守るために、このようなバイアスがかかるようになっているのです。
自分の行動でもよくあります。
例えば、このようなブログを書く際も、自分の意見があり、その意見と同じものを探して、自分の意見が正しいことを証明する思考回路によくなります。
このことを専門用語で言うと確証バイアスと言います。
特徴的なことに引っ張られて全体を判断
対象物のある特徴的なことに引きずられて、対象物を見てしまう傾向があります。
人は、獣と遭遇した時に、過剰反応であっても、すぐに対応したほうが生き残れたのでしょう。
結果、何か特徴的なものでまずは印象を抱き、すぐに対応する性質をもっているのです。
具体例では、テレビCMなどで、出演しているタレントさんのイメージで、宣伝されている商品をとらえてしまうなどです。
テレビCMで、さわやかなイメージのタレントさんが紹介する商品は、なぜかその商品もさわやかなイメージで受け取ってしまいます。
このことを専門用語では、ハロー効果と言います。
沢山の人が支持している内容が更に支持される
多数の人が支持している物事が、より一層支持される傾向があります。
人は、他の人との共感性がある方が、集落の仲間とうまくやっていくことができ、生き残れたのです。
具体例は、流行っている商品が更に売れる例です。人がいいと思ったものは自分にも合うと考えるのです。
このことを専門用語では、バンドワゴン効果といいます。
自分の所属する組織の意見を信じる
自分の所属する組織の人のことを肯定的にとらえる傾向があります。
組織内外で同じ意見だったとしても、組織内の意見を肯定的に、組織外を否定的に見る傾向があります。
バンドワゴン効果と同じく、人は、他の人との共感性がある方が、集落の仲間とうまくやっていくことができ、生き残れたのでしょう。
したがって、仲間のことを良く感じたり、受け入れたりする傾向があるのでしょう。
社外ではなく、社内の人の意見を受け入れやすいことが典型的な例です。
同じ故郷や国の人の意見を受け入れるのも、この傾向の特徴です。
このことを専門用語で、内集団バイアスといいます。
結果が出た後に事前にわかっていたように感じる
結果が出ると、なぜそうなったが理解でき、その理解できたことが、事前に考えていたことのように感じる傾向があります。
結果が出ると、事前に予測していなかったとしても、そのように普通は考えるだろうと考えます。
このことと予測時の曖昧な記憶が交じってしまい、あたかも考えていたように感じることでこのような思考となります。
具体的には、同僚がミスをしたときに、絶対にミスをすると思ったと思う場合です。
事前に考えていなくても、ミスが起きた結果に影響されてしまうのでしょう。
このことを専門用語では、後知恵バイアスといいます。
投資を無駄にしたくない気持ち
投資してしまったものに対して、元に戻らないことがわかっていても、損を取り返そうと更に投資してしまう傾向にあります。
もったいないと思うことが、もったいないと思ない人よりも、自分の立場や財産などを守ることができたのでしょう。
結果、このような性質が我々に遺伝されているのです。
ギャンブルが典型的です。損し始めると損を取り返そうと無茶をし、更に損をする場合です。誰もが経験していると思います。
このことを専門用語では、コンコルド効果といいます。
ちなみにコンコルドとは、あの飛行機のコンコルドから来ています。
ものすごい投資をして開発し続けたが、結局今は使われなくなった事から命名されました。
最初の提示が基準となる
最初に示された数字や条件が基準となり、無意識にその後の判断に影響及ぼす傾向があります。
人は論理的に考えるより、経験則で判断する傾向があります。
まず提示されたものが論理にどうかではなく、まずは経験則として信じる傾向があります。
具体的には、定価の半額というと、定価の根拠ではなく半額という部分に注目し、安く感じる場合です。
このことを専門用語では、アンカリング効果と言います。
考える際に注意が必要!よくある思考の癖の「まとめ」
思考の癖は
・数万年前の狩猟採集時代の思考から進化していない
・当時は先入観や経験則でまずは判断することが大事だった
この2つが原因です。
そして、この2つによって、
・自分に都合にいい情報ばかり集める
・特徴的なことに引っ張られて全体を判断
・沢山の人が支持している内容が更に支持される
・自分の所属する組織の意見を信じる
・結果が出た後に事前にわかっていたように感じる
・投資を無駄にしたくない気持ち
・最初の提示が基準となる
上記のように考える傾向があるのです。
このように思考には癖があることを理解しておきましょう。
対策は、正直難しいです。なぜなら、本能だから。
ただ、これらを少しでも緩和するために、客観性が担保されやすい数字で物事をとらえることが大事なります。
他にもビジネスの基本を書いた記事があります。参照下さい。
- 伝え方の基本 大枠から詳細へ
- 前提をそろえる
- ミスコミュニケーションの原因と対策
- 迷った時の考え方「極端に振って考える」
- 正しい情報を得る6つのコツ
- 具体化と抽象化を使い分ける
- 手段の目的化
- 論理と感情の関係
- 人が変われない理由と対策
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。