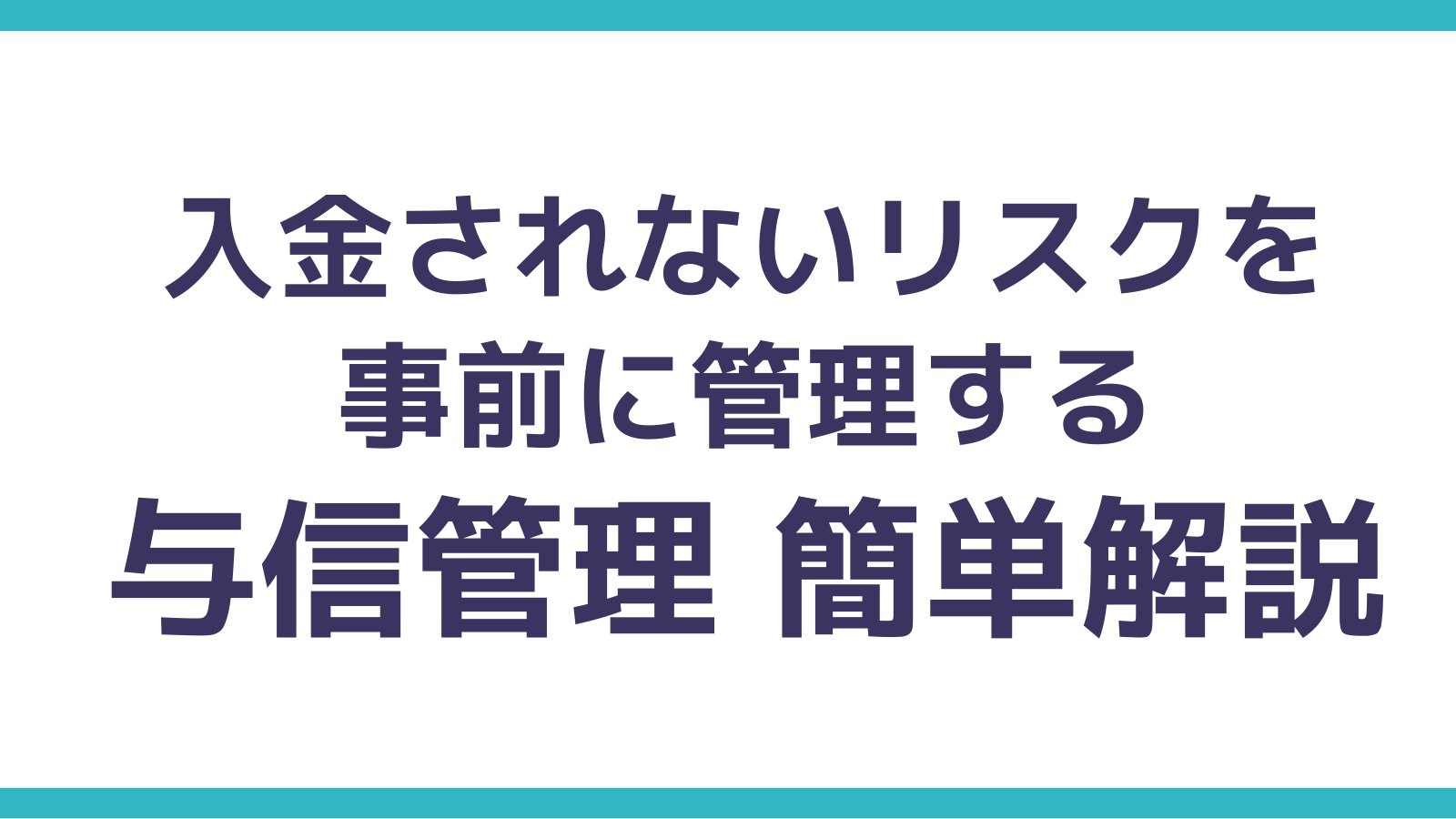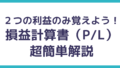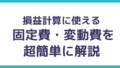ビジネスで取引する際には、必ずお金のやり取りが発生します。
製品・商品・サービスが販売したのに、お金を支払ってもらえないと、製品・商品・サービスの原価や販売にかかった経費が丸ごと損になります。
法人対法人の取引では取引額が大きくなりますので、取引する前に入金されないリスクを管理することが重要になります。
この記事では、未入金リスクを管理する考え方「与信管理」をわかりやすく解説します。
この記事を読むと与信管理の基礎がわかりますよ。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション)
与信管理とは?
取引する前に未入金となるリスクを判断し、判断に応じた対策をおこなう
受注する前に、この顧客はどれくらいの未入金となるリスクがあるのか?を想定し、取引するしないも含めた、リスク対策をおこなう一連の行動を与信管理といいます。
リスク判断により、通常の取引を行う、納品時にすぐ払ってもらう、そもそも取引をしないなどの判断を行います。
当然条件を厳しくすればするほど、未入金のリスクは減りますが売上は減ります。
条件を緩くすればするほど、売上は上がりますが、未入金のリスクが増えます。
この最適解を考えることが与信管理の肝となります。
与信管理の「詳細説明」
入金されないとどれくらい損をするか?
仕入代や原材料等の外部に支払う額が実損となる
100万円の商品を1つ買って納品しましたが支払ってもらえませんでした。商品の仕入れ値は80万円です。この場合で考えてみましょう。
100万円の売上がなくなるのはもちろんですが、、すでに商品を仕入れていますので、仕入れ先に80万円をお支払う必要があります。
当然、入金されなかったので支払いません!とは言えません。
ということは80万円が実際の損害となります。これ以外にも販売にかかった費用が無駄になり、収益がマイナスになります。
仮に、この損害を挽回しようとしたら、この商品を何個売らないといけないでしょうか?
1個当たり20万円の粗利(100万円-80万円)なので、4個(80万円÷20万円)販売する必要があります。売上としてはなんと400万円(100万円×4個)も必要です。
ただ、これだけ販売しても損害を取り戻しただけです。入金してもらえないとこれだけの損害が出てしまうのです。
なぜ与信管理が必要なのか?
法人対法人の取引では、通常納品と支払いに時間差がある「掛取引」を行うため
法人対法人の取引では、製品・商品・サービスを納品してから、一定期間後に販売代金をいただく「掛取引」が一般的です。
納品してから一定期間後に代金を支払ってもらいますので、すべての取引にリスクがあります。
会社によりますが、当月の納品物の請求書を月末に処理し、翌月末日に代金を支払うという取引が基本となります。
請求ごとに処理していると経理業務が煩雑となりますので、まとめて処理できるように、このような方法が一般的となりました。
(詳しくは、「入金サイトと売掛金・買掛金」超簡単解説&使い方紹介を参照)
納品から入金までタイムラグがあることで、その間に何が起きるかは誰もわかりません。したがって、リスクを回避する対策=与信管理が必要なのです。
与信管理の「方法」
1.取引をしない
2.納品前に支払ってもらう
3.納品後すぐに支払ってもらう
4.支払ってもらう金額により取引条件を変える
5.先方の支払いサイトで支払ってもらう
与信管理の方法には大きく5つあります。リスクが大きい順番でのリスク対策です。それぞれを説明します。
1.取引をしない
一番簡単な方法です。取引をしなければリスクを負うことはありません。ただ、取引しなければ会社は儲かりません。
唯一お金をいただけるのは、顧客です。
2.納品前に支払ってもらう
製品・商品・サービスを納品・提供する前に販売代金をいただく方法です。この方法では、未入金リスクはありません。お金をいただけない場合は納品しなければいいからです。
ただ、取引するお客様がこれを認めてくれるどうか?がポイントとなります。
初めて取引する際に、まだ納品もされていないのに、支払うことを了承してもらえるか?がポイントです。お客様側にも、お金を払ったが、ちゃんとした製品・商品・サービスが提供されるか?のリスクが発生するからです。
3.納品後すぐに支払ってもらう
製品・商品・サービスを納品・提供した直後に販売代金を支払ってもらう方法です。
この方法では、販売側は、すぐに入金してもらえるので、リスクを減らすことが出来ます。お客様側では、納品物を見てから入金出来ます。
ただし、お客様側の経理に手間が発生します。このことをどのようにお客様側が判断するかがポイントとなります。
4.支払ってもらう金額により取引条件を変える
製品・商品・サービスの販売価格により、取引方法をそれぞれ設定する方法です。
例えば、100万円以上の取引なら、納品後すぐに払ってもらう。100万円未満なら、通常の支払いサイトで払ってもらうなど、取引金額に応じて取引方法を変える方法です。
5.先方の支払いサイトで支払ってもらう
お客様が指定した支払いサイト(末日〆翌月末日払等)で取引をおこなう方法です。
信用のおける会社は、リスクが低いので、お客様の規定に従い取引します。
取引会社の判断方法
・支払いサイトを確認する
・信用調査会社の情報を購入する
支払いサイトの把握することと、帝国データバンク等の信用情報を活用することが一般的です。
支払いサイトを把握する
受注する前に、どのような条件で取引するかを事前に判断しておきます。納品から支払いまでの期間を把握するためです。
お客様の支払いサイトを把握することが最初のステップとなります。
商談の初期に「御社を当社のシステムに登録したいので、支払サイトを教えてもらえますか?」などとと聞くことで支払いサイトを把握します。
すぐ支払ってくれるのか?翌月末支払いなのか?翌々月末支払いなのか?手形支払いなのか?を把握することで、リスク期間を把握することができます。
この時点で、教えてくれなかったり、何か不穏な対応があれば、その時点で最初の判断ができます。
信用調査会社の情報を購入する
信用調査会社は独自の基準で会社を評価しており、お金を支払うと、取引したい会社の評価内容を知ることができます。各社の評価を数値化しています。
すべての会社ではないのですが、多くの会社の評価を知ることができます。
信用調査でよく使われるのは、帝国データバンクの企業データベースです。1件当たりの契約(数百円から数万円)や月間契約など様々な契約方法があります。
信用にかかわる情報を一民間企業の帝国データバンクが持っているのは、各企業へ売上や利益などの重要情報を調査員が各社にヒアリングしているからです。
では、なぜ各企業はこのような重要情報を一民間会社に教えるのでしょうか?
大企業から中小企業まで、基本与信管理をおこなっています。その際に、情報がない=不安な会社と思われることで、取引のチャンスを逃したくないからです。
支払いサイトと信用情報会社のデータを活用することで、未入金リスクを減らすことが出来ます。ただ、リスクは残ります。
どこまでリスクを負うかは各社の判断となります。判断方法については、各会社でルールが決まっているかと思いますので、それに従ってください。
与信管理の「まとめ」
請求した売上が入金されないと、大きな損害が出る
納品から入金までにタイムラグがあるため、リスク管理の必要がある
事前に取引するかしないか、取引するならどんな条件かを判断する必要がある
商品を納品するときに、急に「明日入金して下さい」と言えば怒られます。できるだけ早いタイミングで判断及び条件伝達の必要があります。
支払いサイトを聞けば、ほとんどの会社はちゃんと答えてくれますので、普通に確認すれば大丈夫です。
他にもビジネススキルが上がる「必須スキル」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。