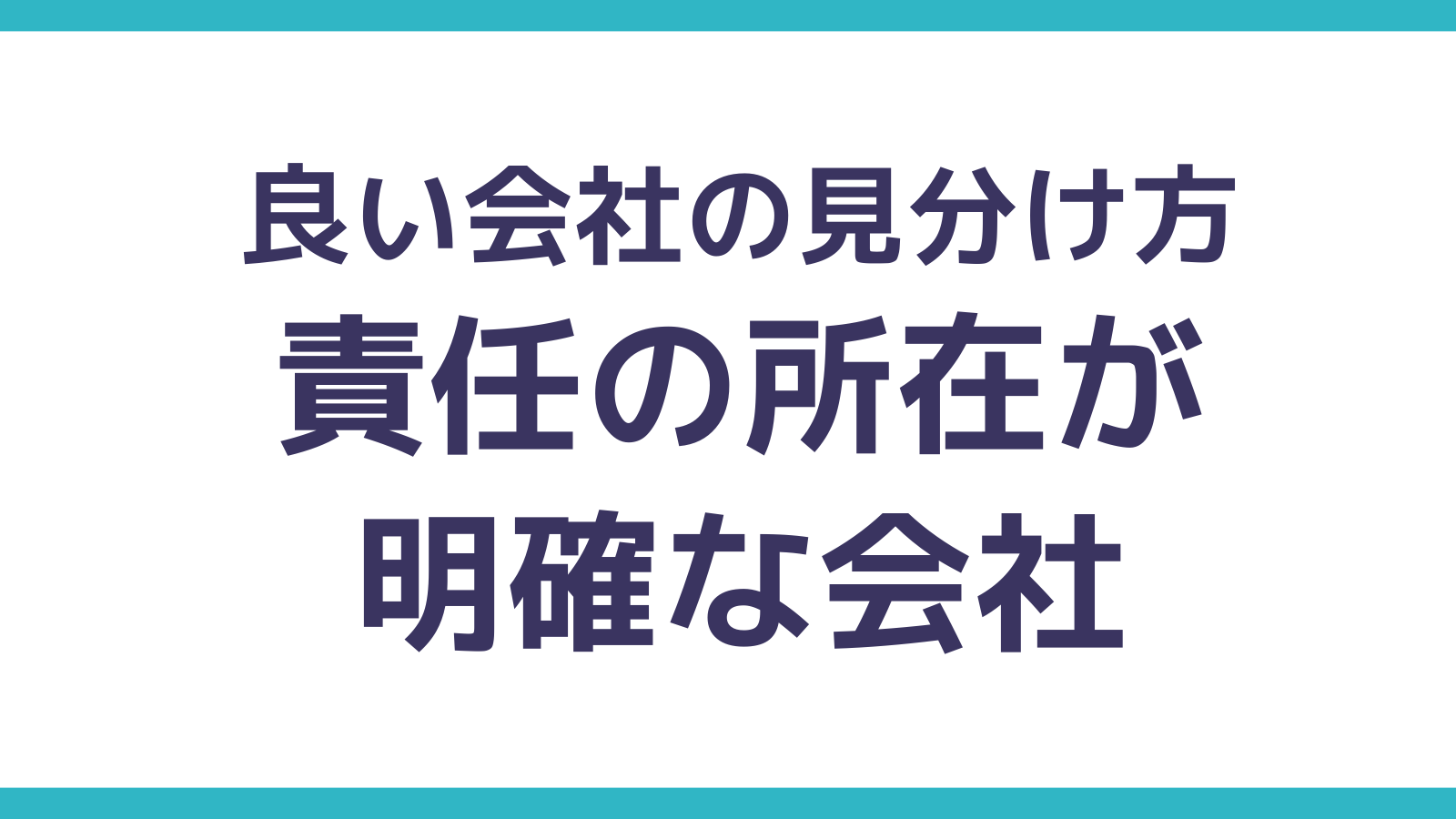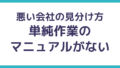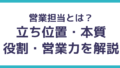責任の所在が明確な会社は良い会社です。そうでない会社は悪い会社です。
責任の所在を明確にしすぎると、自分の責任の範囲でしか仕事をしなくなるという意見もありますが、そもそも個々人が何をしたらいいのか?を定義できていない状態で組織は動きません。
この記事では、責任の所在が明確だとなぜ良い会社と言えるのか?をわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい いい会社の判断方法)
責任の所在が明確だとなぜ良い会社なのか?
働きやすい会社だから
なぜ働きやすいのか?
・分業設計ができている
・従業員が何をすればいいかが明確
責任の所在が明確だと、上記2点ができているので働きやすくなります。
それぞれを解説します。
分業が設計できている
・分業が設計できている状態とは?
・分業の条件
・分業ができているとなぜ良いのか?
上記の順番で解説します。
分業が設計できている状態とは?
・1人1人まで業務が分業されている状態
・人と人の間、組織と組織の間の責任が明確
分業が設計できている状態とは、上記2つが両方ともできている場合です。
それぞれ解説します。
1人1人まで業務が分業されている状態
まずは、個人に明確に業務が割り振られている状態となっていることです。当たり前のように感じると思いますが、できている会社は少数です。
なんとなくふわっとしている部分があったり、本来担当を設定する業務に担当がいない場合がよくあるからです。
ただ、これを設計する立場になり、実際におこなうとわかりますが、1人1人まで落とし込むのはかなり難しい仕事となります。
単に割り振るなら簡単ですが、ヌケモレをなくし個人間の難易度をあわせる必要があります。
したがって、この設計ができているということは、ちゃんと精緻に考えて組織運営していると言えます。
人と人の間、組織と組織の間の責任が明確
組織の課題は、人と人、組織と組織の間に多く存在します。なぜならば、個人で手を付けることができにくいからです。
人と人の間には、お互いが担当外のものが存在します。また、組織と組織の間にはもっと大きな課題があります。
例えば、営業部と生産部の「間」には各部のメリットとデメリットが二律背反し、各部の部長では対応できない課題がたくさんあります。
本来は、人と人の間は課長、組織と組織の間は一階級上の責任者が解決する役割となるのですが、利害関係や適切な組織設計になっていないことで、責任が不明確になる場合が多くあります。
その上、課題解決の難易度が高く簡単には解決できない問題が多くあります。
ただ、この部分に真摯に向きあう会社もあります。そのような会社の共通点は、上記のように浮いてします課題についても、分業がちゃんと設計されており、誰がどの部分まで自分の業務かが明確になっていることです。
分業の条件
他人の集まりだから仕組みやルールが必要
会社という組織は、自然と集まった「身近な人・近縁な人」の集まりではなく、「他の人」が集まった組織です。
普通に生活していれば出会えない人が集まって、組織を構成していますので、育った環境や考え方が違います。
このような人の集まりとなる会社では、自分の考えを元に個人が自由に動くと組織が成り立ちません。
したがって、各自の役割を明確にすることが必要になります。そのために人事制度などの仕組みと組織運営ルールなどの設計と運用が必要となるのです。
分業設計ができるとなぜ良いのか?
効率が良くなる
分業された限られた業務を繰り返しおこなうことで、専門性が上がり、短時間でできるようになる、成果の質が上がるなどメリットがあります。
専門性が上がった個人がそれぞれの分野の仕事をすることで、結果、全体の生産性が上がることになります。これが効率が良くなる理由です。
従業員が何をすればいいかが明確
やることが明確なので実行に集中できる
何をすればいいかが明確にわかっていれば、実行に集中できます。浮いている業務の押し付け合いもおきにくく、正直ものがバカを見ることも少なくなります。
ただ、会社によってはとても不明瞭になっていて困ることもとても多くあります。
例えば典型的な例として、次長とが課長代理があります。
この役職が多い会社も、上記の責任の所在が不明確です。部長でも課長でもない次長の責任は、何だと思われますか?
会社は良かれと思って、上位の役割をあたえて給料もアップさせているのですが、役割が不明瞭なので結局前職の課長時代と同じ仕事をするのです。
そうなると今の課長が困ります。課長が更に下の仕事をするのか?次長が課長より下の仕事をするかになります。
また、課長がプレイングマネジャーの場合も上記と同じ構造です。
課長だから給料はアップしよう、でも今までのプレイヤーの仕事に加えて課長の仕事もしてくださいね、と言って両方できる人はいません。
結局本来の課長の仕事をおこなわず、慣れたプレイヤーとしての仕事を行い、組織運営がマネジメント不在となるのです。
このように役割が明確になっていないと、人は動けなくなるだけではなく、慣れた業務に逃げることが起きます。
本人もそうですし、会社にとっても良い事ではありません。
責任を明確にすると自分の業務しかしなくなる?
分業設計と役割定義ができていないだけ
責任を明確にするとその範囲でしか物事を考えなくなるので、明確にしないという経営者がいます。このように発言する経営者は自分の仕事を放棄しています。
なぜなら、役割や業務を明確に与えたうえで、業務間に浮いている仕事を半年で2つ見つけて解決するという役割を与え、人事評価の評価項目に入れるだけで解決します。
解決の方法があり、それをおこなう権限もあるのに実施していないだけなのです。本来自分でおこなうことを個人におしつけるから組織がおかしくなるのです。
責任の所在が明確だと良い会社の「まとめ」
働きやすい会社だから
なぜ働きやすいのか?
・分業設計ができている
・従業員が何をすればいいかが明確
責任の所在が明確だと、上記2点ができているので働きやすくなります。
皆さんの会社はどうですか?査定用の目標設定シートが個人ごとに明確になっているかで簡単に判断できます。
目標シートがしっかりしていたら当然良い会社です。目標シートが曖昧なら悪い会社です。
また、従業員20名以上で目標設定シートを使った査定がない会社は、最悪な会社となります。
他にも良い会社を見分ける方法を解説しています。参照下さい。
- 「良い人事評価制度がある会社」
- 「人事評価のFB面談が長い会社」
- 「人事異動が多い会社」
- 「営業力に頼らない会社」
- 「すべき」より「したい」が多い会社
- 「恐怖より危機感で人を動かす会社」
- 「上司ではなく、お客様に目を向けている会社」
- 「変わり慣れている会社」
- 「結果よりもプロセスを求める会社」
- 「雑談が多い会社」
- 「単純作業のマニュアルがある会社」
- 「エクセルが使える人が多い会社」
- 「定量・定性分析を両方行う会社」
- 「取締役の構成を見る」
- 「展示会で直接に接してみる」
- 「良い上司かどうかの見分け方」
今の会社が不安になり、転職のことを知りたくなった方へ
転職のことを知りたい方は、転職の判断、転職活動、入社判断をすべて網羅した以下の記事を参照下さい。
失敗するポイントをわかった上で転職活動ができます。
まずは、キャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録してみるのもおススメです。
登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。