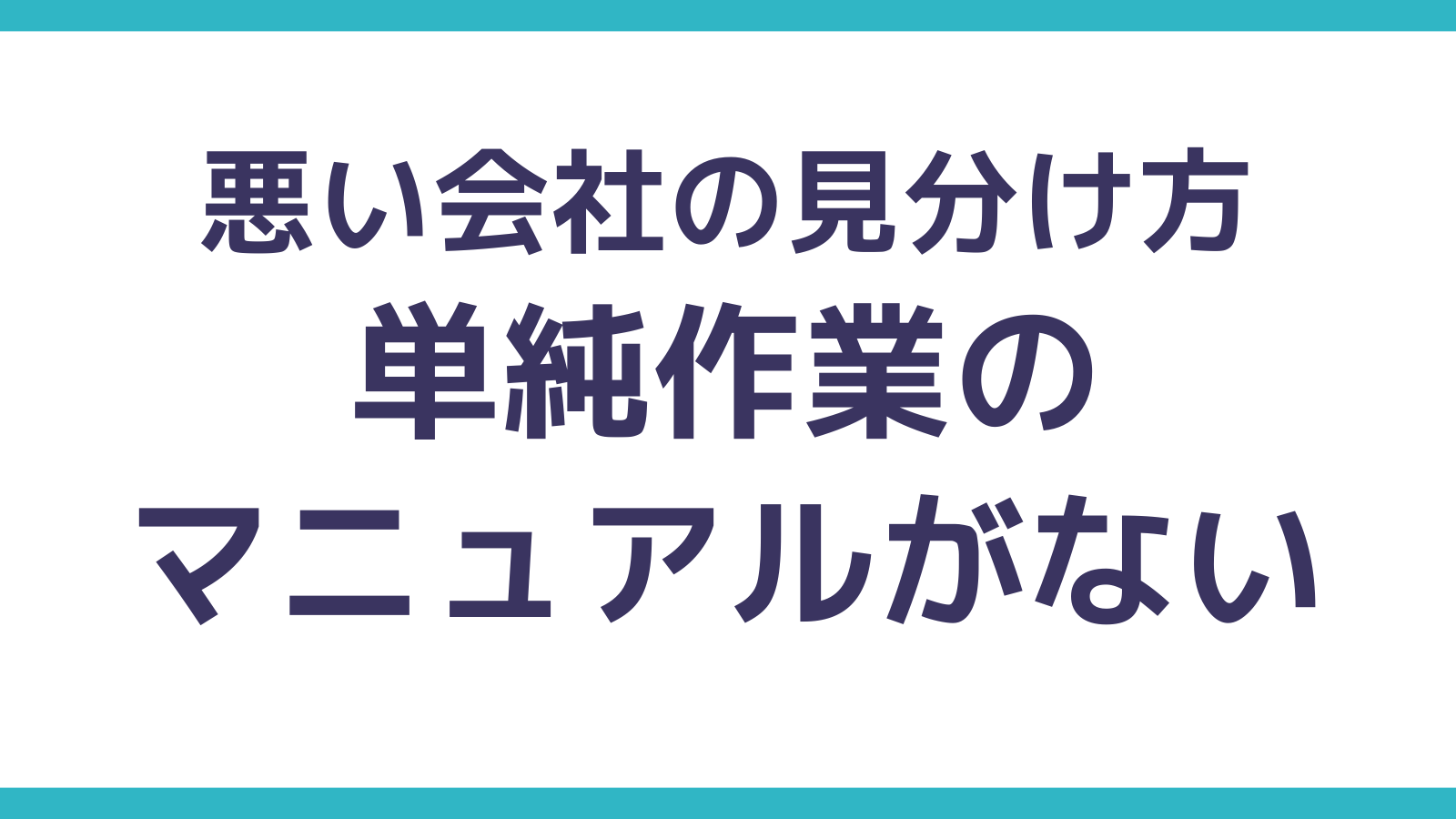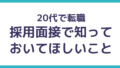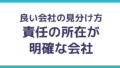上場している会社でも単純作業のマニュアルがなく、いちいち上司や先輩に口頭で教えてもらう会社が多くあります。また、中小企業ではほぼマニュアルはないと思います。
実はこの1つの現象で、良い会社か悪い会社かを見分けることができます。もちろん、マニュアルがある会社が良い会社です。なぜなら、会社運営にとても重要な要素に対する対策をおこなっているからです。
この記事では、単純作業のマニュアルがあるとなぜ良い会社なのかをわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい いい会社の判断方法)
単純作業のマニュアルがある会社が良い会社の「理由」
・生産性アップに対策が打てている
・単純作業をメイン業務にする社員がいない
上記2つが単純作業のマニュアルがある会社が良い会社の理由です。それぞれ解説します。
生産性アップに対策が打てている
・先輩社員の時間を奪わない
・業務が見える化でき改善につながる
マニュアルがあることで上記2点の理由で生産性アップとなります。会社は限られた時間でどれだけ成果を出すか重要なので、生産性アップはとても大事なことです。
それぞれを解説します。
先輩社員の時間を奪わない
先輩社員の教える時間を削減できる
単純作業は、基本誰が実行しても同じ内容=成果物になります。したがって手順が決まっています。人により、交通費精算伝票の書き方が違えば困るからです。
また、教えてもらう人もマニュアルを見るだけで人に聞かなくてもできます。ただ、マニュアルがなければ誰かに教えてもらう必要があります。
当然先輩社員が教えることになるのですが、マニュアルがあれば1人でできることをわざわざ時間を使って教えることになります。
この一部分だけを見ると些細な時間ですが、全社でこの些細なことがおこなわれており、塵も積もればとても大きな時間を使っていることになります。
同じ時間働いたとして、この誰がやっても同じ成果にしかならない無駄な時間を使わずに、売上アップや効率アップにつながる仕事に時間を使った方が、会社は間違いなく儲かり良い会社になります。
業務が見える化でき改善につながる
手順が文章化される過程で手順が改善される
各業務をマニュアルという文章に落とす作業をおこなうとわかりますが、内容があやふやな状態では文章化できません。
これにより、業務を各論に落とすことができるだけでなく、客観的に見ることができ、問題点を把握し改善につなげることができます。
上記2つをおこなわない会社は、従業員が非生産的な仕事をすることを当たり前と思っているか?、ダメだと思っていても問題を先送りし、対策が打たれることなく過ごしているかのどちらかです。
中小企業では、人手が足りないので、大手のようにマニュアルが整備できないという声も聞こえます。
その考えのもと、単純作業に沢山時間をかけて本来すべきことができていないか?たくさん残業して無理やりおこなっているか?のどちらかとなります。
本来は商品力含めた総合力が弱い中小企業こそ、単純作業を効率化しないと生きていけないはずです。
ただ、経営層含めてこの課題の重さを理解できないので、課題として残ってしまい、生産性の高い業務に時間を使えずに、業績低迷となるのです。
単純作業をメイン業務にする社員がいない
知識のみでできる仕事だけをする人が現れないようにしている
マニュアルがないと必ず業務を知っている人が重宝されます。その内容が誰でもできることにも関わらずです。
そうして時間がたつと単純作業をメイン業務にする社員が現れます。
そうすると何がおきるか?
その方々はその仕事がメイン業務になります。生産性ゼロですが誰かがやらないといけない業務を、正社員の人件費を使っておこなうことになります。
悪いことに、その担当になった人は、その仕事を効率化してなくすことをしません。効率化しようとすれば徹底的に阻止しようと動きます。
なぜなら、単純作業しかできないので、その仕事がなくなると自分の仕事がなくなり、居場所がなくなるからです。
また、悪いことにこのような会社ではこの担当者が昇進します。例えば係長とかになります。
部署ごとの係長の仕事を並べてみると、仕事内容の難易度はまったく違うのに給料は一緒となります。
難易度の高い仕事をしてる人はばかばかしくなるだけでなく、非効率な業務運営を見て会社の将来を案じ退職していきます。
単純作業の効率化という、一見大きな課題ではないように感じることでも、対策を打たないととても大きな課題となり、優秀な人が退職する原因となるのです。
その上、このような非生産的な仕事をする人が異動や退職すると、その業務を若くて元気な社員が担当することになります。先輩社員には引き継がせることができない簡単な内容だからです。
担当した若手は、仕事が単純作業なので成長できる機会が減り、時間がたつと年齢を重ね、その仕事が楽で手放さくなる思考になってしまいます。
大げさなように感じると思いますが、以下の人々を見てきた私の実感です。
・売上が200億円位のBtoBの会社で、経理業務が手作業のために経理部に30名の正社員がいる
・45歳のお客様対応の電話しかしない正社員(係長)がいる
・エクセルで式を組めば、瞬間にできることを手書きかつ電卓で作業をしている
・手書き伝票がいまだに沢山残っている
単純作業のマニュアルがある会社は良い会社の「まとめ」
・生産性アップに対策が打てている
・単純作業をメイン業務にする社員がいない
よくマニュアルがあると自分で考えなくなるという思考の経営者が沢山います。
確かに、生産性を上げてほしい部分については当てはまる部分もありますが、単純作業についてはまったく間違っています。この区分けができていないだけです。
そして、この問題は時間がたてばたつほど、とても根深い問題になります。
単純作業の知識を能力と思ってしまう社員が現れて、生産性の低い業務が脈々と生産性が低いまま残るのです。会社が儲かるわけがないのです。
もしこのような現象がおきていたら、実は大きな根深い課題となっている悪い会社となっています。
このような現象が多い会社は、基本変わらないので転職を検討することをお勧めします。
他にも良い会社を見分ける方法を解説しています。参照下さい。
- 「良い人事評価制度がある会社」
- 「人事評価のFB面談が長い会社」
- 「責任の所在」が明確な会社」
- 「営業力に頼らない会社」
- 「すべき」より「したい」が多い会社
- 「恐怖より危機感で人を動かす会社」
- 「上司ではなく、お客様に目を向けている会社」
- 「変わり慣れている会社」
- 「結果よりもプロセスを求める会社」
- 「雑談が多い会社」
- 「エクセルが使える人が多い会社」
- 「定量・定性分析を両方行う会社」
- 「取締役の構成を見る」
- 「展示会で直接に接してみる」
- 「良い上司かどうかの見分け方」
今の会社が不安になり、転職のことを知りたくなった方へ
転職のことを知りたい方は、転職の判断、転職活動、入社判断をすべて網羅した以下の記事を参照下さい。
失敗するポイントをわかった上で転職活動ができます。
まずは、キャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録してみるのもおススメです。
登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。