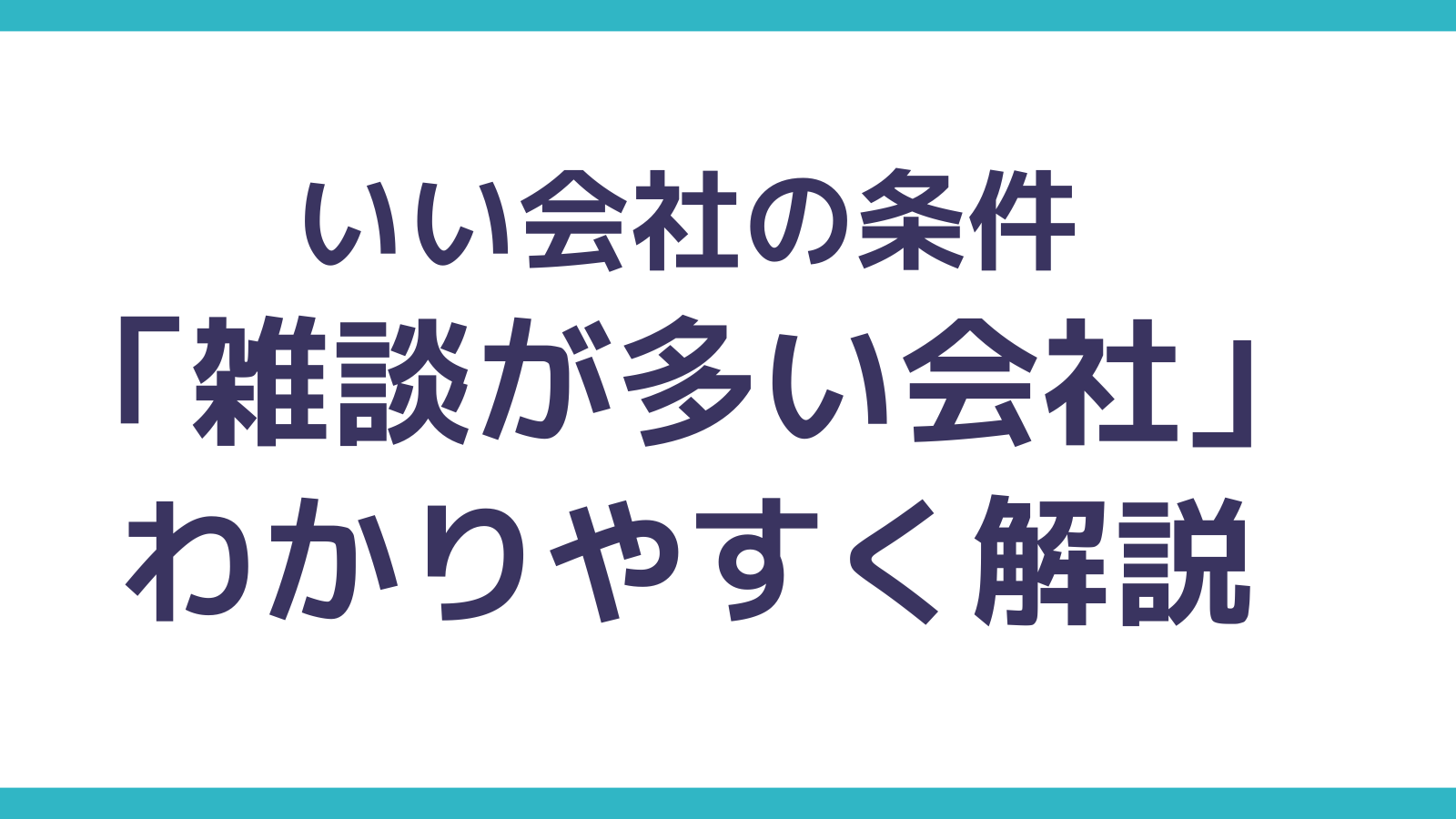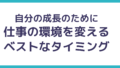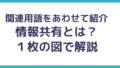皆さんの会社は、雑談が多いですか?
実は、ある前提条件を満たしていれば、「雑談が多いかどうか」だけで良い会社かどうかをある程度判断できます。
良い会社を見極めるには、複数の会社で働いた経験がないと難しいと感じるかもしれません。
私自身は、5社での勤務経験と数千社への営業活動を通じて、さまざまな会社の内情を見てきました。その経験から、「雑談が多い会社は良い会社」であると考えています。
この記事では、「雑談が多い会社がなぜ良い会社なのか」について、前提条件も含めてわかりやすく解説します。
読むことで、良い会社を見分けるための一つの具体的な判断軸を知ることができます。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい いい会社の判断方法)
雑談が多い会社が良い会社の理由
話したくないと思う人が少ない
「すべき」ではなく「したい」が多い
頑張ろうと思える
上記が良い会社の理由ですが、前提条件があります。
仕事が個人に適切に割り振られている
雑談において最も避けるべきは、単なる「無駄なおしゃべり」が際限なく続いてしまうことです。
もちろん、息抜き程度の短い雑談は問題ありませんが、長時間にわたって頻繁に続くようであれば、それは健全な状態とは言えません。
その主な原因として考えられるのが、仕事の割り振りが適切に行われていないために、時間を持て余した人が周囲を巻き込み「時間潰しのための雑談」を誘発してしまうケースです。
したがって、この前提条件がクリアされていることが、雑談のポジティブな側面を評価する上で非常に重要になります。
まずは、雑談のメリット・デメリットを紹介した後に、上記3つの理由の詳細を解説します。
雑談のメリット・デメリット
メリットとデメリットを紹介します。
雑談のメリット
・コミュニケーションがしやすくなる
・適度なリフレッシュができる
・新しい発想が生まれる
上記3つがメリットです。
コミュニケーションがしやすくなる
業務外の事柄について言葉を交わした経験がある相手とは、純粋に仕事の話しかしたことがない相手に比べて、互いの心理的な壁が低くなり、結果として業務上のコミュニケーションも円滑に進みやすくなります。
適度なリフレッシュができる
人間の集中力には限りがあるため、業務の合間に適度な休憩を挟むことは不可欠です。
その際、気軽に雑談を交わすことができれば、気分転換になり心がリフレッシュされます。
新しい発想が生まれる
肩の力を抜いたフランクな会話は、形式張った業務上の会話よりも思考を柔軟にし、活性化させる効果があります。
これは、リラックスした状態の方が脳の働きが活発になり、自由な発想が生まれやすくなるためです。
雑談のデメリット
・時間の消費につながる可能性
・生産性の低下
上記2つがデメリットです。
時間の浪費につながる可能性
雑談に時間を使いすぎてしまい、本来やるべき仕事が進まないことがあります。
生産性の低下
高い集中力が求められる作業の最中に、頻繁な雑談によって中断が生じると、作業効率の低下やミスの増加を招く恐れがあります。
雑談のメリット・デメリットまとめ
このように、雑談には非常に大きなメリットがある一方で、ともすれば時間を浪費したり集中力を削いだりするデメリットも存在します。重要なのは、これらのバランスを適切に保つことです。
雑談が多い会社が良い会社の理由詳細
話したくないと思う人が少ない
すべきではなくしたいが多い
頑張ろうと思える
上記それぞれを解説します。
話したくないと思う人が少ない
誰もが嫌な人と雑談したいとは思わないでしょう
あなたが普段雑談をする相手は、どのような人でしょうか。おそらく、嫌いな人ではない場合がほとんどでしょう。
なぜなら、苦手な相手とは、業務上必要最低限の会話に留めたいと考えるのが自然だからです。
前述の前提条件が満たされず、仕事の分担が不適切であれば、好ましくない相手との雑談に不本意に巻き込まれることもあるかもしれません。しかし、仕事が適切に配分されていれば、そのような状況は大幅に減るはずです。
また、同じ職場で働いていても、全く面識のない相手といきなり雑談を始めることは稀でしょう。
通常、業務を通じて初めて言葉を交わす際に、意識的か無意識的かは別として相手に対する評価を行い、その後の関わり方を判断するものです。
つまり、組織内で雑談が活発に行われているという事実は、裏を返せば「この人とは話したくない」と感じる人が職場に少ない状態を示唆しているのです。
「すべき」ではなく「したい」が多い
「規範」よりも「本質的なメリット」を重視
一般的な社会通念として、勤務時間中に業務と無関係な雑談をすることは、必ずしも推奨される行為とは言えません。
「~すべき」という規範意識に基づいて判断すれば、雑談は控えるべき対象となるでしょう。
このような規範意識が強い人に、雑談がもたらすメリットを説明しようとしても、多くの場合、建設的な議論には発展しにくいものです。
なぜなら、彼らの判断の拠り所が「社会通念」という、容易には覆せない大きな規範にあるためです。
その結果、雑談が少ない会社というのは、往々にしてこのような規範重視の企業文化が根付いている傾向にあります。
一方で、雑談が多い会社はどのような企業文化なのでしょうか。
そこでは、社会通念として私語を慎むべきという考え方を認識しつつも、それを絶対的な制約とは捉えていません。
なぜなら、形式的な規範に縛られること以上に、雑談がもたらす実質的なメリットを理解しており、その価値を組織として認めているからです。
したがって、雑談が多いかどうかで「すべき」が多い会社か?「したい」が多い会社かわかるのです。
(詳しくは、良い会社の条件 「すべき」より「したい」が多い会社を参照)
頑張ろうと思える
信頼できる仲間と、心理的安全性の高い環境
もし、経営陣や上司、同僚との間に人間関係の問題を抱え、苦手な人が多い職場だとしたら、心から「この会社のために頑張ろう」という気持ちになれるでしょうか。
給与分の仕事は最低限こなすとしても、それ以上の貢献意欲を持つことは難しいのではないでしょうか。
私たちは一日の多くの時間を職場で過ごします。その時間を、会社や同僚のために積極的に貢献したいという前向きな気持ちで過ごせるか、あるいはそうでないかは、働きがいやパフォーマンスに大きく影響するでしょう。
雑談が活発であるということは、職場に信頼できる仲間が多く、心理的安全性が高い環境である可能性が高いと言えます。そのような環境は、社員が自然と「頑張ろう」と思える状態に近いことが多いのです。
そして、そのような良好な人間関係と心理的安全性が担保された環境で働くことは、不満を抱えながら働くよりも、個人の能力開発やスキルアップにも繋がりやすくなります。
結果として、社員は良好な職場で自己成長も実現できるという、好循環の中に身を置くことができるのです。
雑談が多い会社が良い会社の理由の「まとめ」
話したくないと思う人が少ない
すべきではなくしたいが多い
頑張ろうと思える
上記が良い会社の理由ですが、前提条件があります。
これらの理由が成り立つ大前提として、「仕事が各人に適切に割り振られている」ことが不可欠であると繰り返し述べてきました。
実は、この「仕事の適切な割り振り」という前提条件は、経営者の経営能力の高さを測る一つの指標ともなり得ます。
なぜなら、効果的な分業体制を構築し、それを円滑に運用していくことは、組織運営における経営の根幹をなす非常に重要な業務だからです。
これができていない=しっかりした経営ができていないと言えるのです。
他にも以下のように良い会社の見分け方を書いた記事があります。参照下さい。
- 「良い人事評価制度がある会社」
- 「責任の所在」が明確な会社」
- 「すべき」より「したい」が多い会社
- 「恐怖より危機感で人を動かす会社」
- 「管理職が本来の仕事をしているか?」
- 「変わり慣れている会社」
- 「結果よりもプロセスを求める会社」
- 「単純作業のマニュアルがある会社」
- 「エクセルが使える人が多い会社」
- 「定量・定性分析を両方行う会社」
- 「取締役の構成を見る」
- 「良い上司かどうかの見分け方」
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。