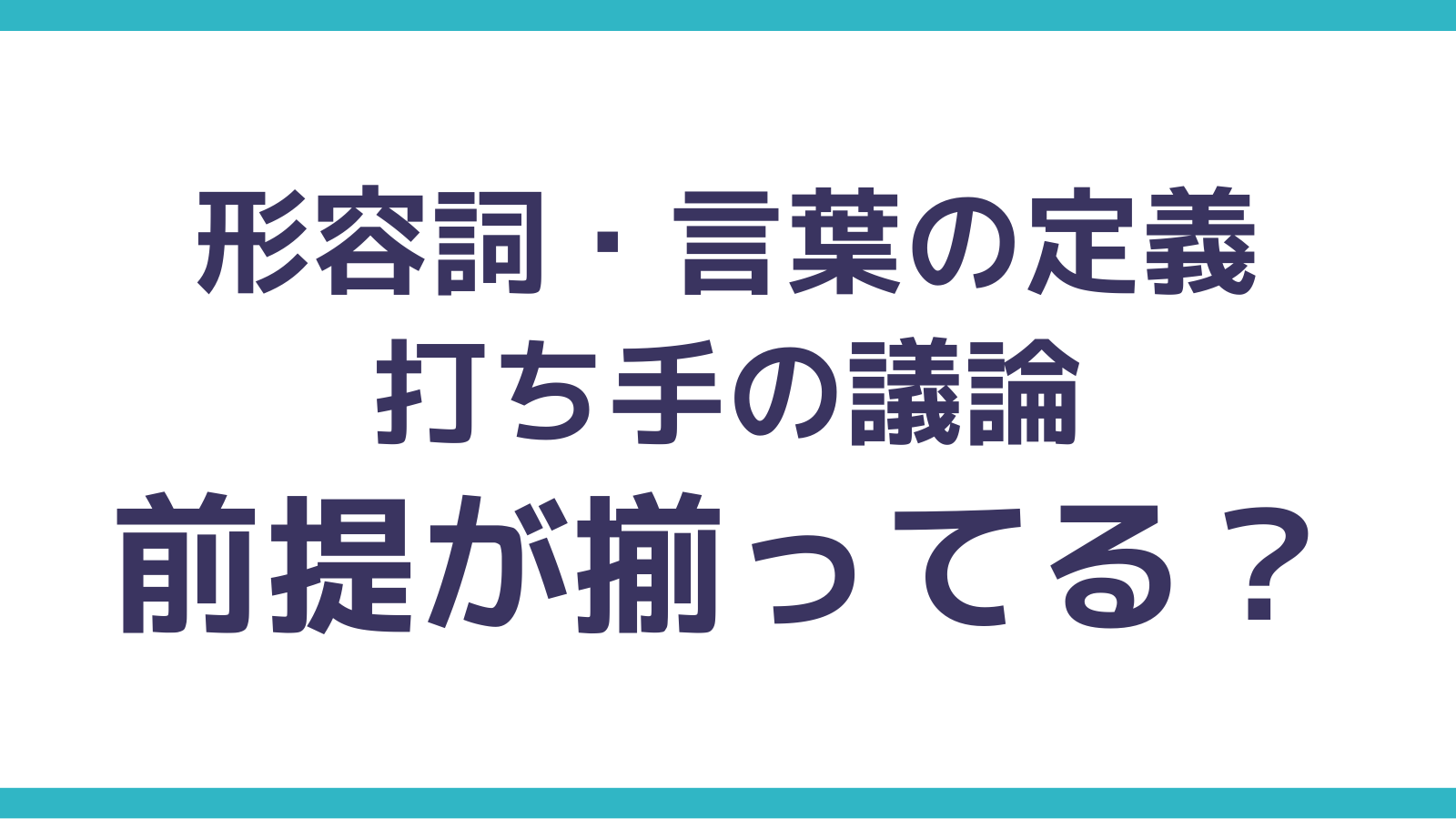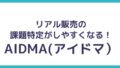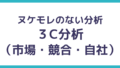公式・非公式の場を問わず、さまざまな会話が行われています。
その中で、私たちは時にコミュニケーションロス(情報のズレ)を経験します。
もしその場でズレが発覚すれば良いのですが、実際にはそうではないケースが非常に多いのが実情です。
お願いした側は「理解してくれた」と思い、お願いされた側も「理解した」と思い込み、そのまま作業に着手します。
後日、成果物を持っていくと、依頼した側の意図と全く異なっていた、という経験はないでしょうか。
この原因の多くは、お願いする側とお願いされる側の間で「前提がそろっていない」ことにあります。
昔はほぼ全員が新卒で入社し、会社で一生を過ごすことが一般的でした。そのため、会社の風習や文化を深く理解できていることが多く、この問題は今より少なかったと言えます。
ただ、今のように、転職が当たり前で、様々な経験を持つ人たちと一緒に働く場合には、学んできた環境や考え方の癖が違うので、コミュニケーションロスがおきやすいのです。
この記事では、コミュニケーションロスを減らす手段となる「前提をそろえる」ついてわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション)
コミュニケ―ションロスが起こる原因
前提の不一致に気づけない「推測能力」の存在
私たちは驚くべき能力を持っています。それが「推測する能力」です。
「昨日のあの件だけど」という一言だけで、私たちは多くの事柄の中から「あの件」を特定できてしまいます。
この能力があるからこそ円滑なコミュニケーションが図れるのですが、同時にこの能力は万能ではありません。
例えばとても些細なことですが、言葉の前提の解釈が変わる例を上げます。
毎週月曜日に定例会議があるとします。月曜日は祝日の場合、会議が中止になるか、翌日の火曜日になるかどちらでしょうか?
当然正解はなく、会社の考え方により違います。このような些細なことでも、各自が勝手に推測し人により判断が変わってしまうのです。
「前提をそろえる」これだけを気をつけよう
・形容詞に注意
・言葉の定義に注意
・打ち手議論に注意
この3つがコミュニケ―ションの前提として注意することです。それぞれを解説します。
形容詞に注意
形容詞は人の主観だから
形容詞が使われたら必ず注意です。前提を揃える必要があります。
例えば「あの人は背が高い」という言葉を聞きました。あなたは、何センチだと思いますか?背丈が170㎝の人は、180㎝と答えるでしょうし、背丈が160㎝の人は170㎝と答えるでしょう。
売上が厳しい、スケジュールが短い、予算が高い等々日常会話に、形容詞が多数含まれています。
上記の通り、形容詞は人によって解釈が変わるため、「背の高さ=〇〇cm」のように、できるだけ数字に置き換えて話す意識を持つべきです。
ただし、すべての形容詞について逐一認識を合わせていると、コミュニケーションが円滑に進みません。
そこで、会話の中に形容詞が出てきたら、頭の中に「黄色信号」を灯すだけで、すべてを数字にしなくても多くのコミュニケーションロスを未然に防ぐことができます。
言葉の定義に注意
ビジネス用語は正解が多数
皆さんが以下のような提案を求められた場合、どう答えますか?
「この商品は赤字だ。解決策を提案してほしい」
赤字ってどのような基準で赤字と言っているのでしょうか?また、解決策は販売数量アップなのか、単価アップなのか、原価削減なのか何をすればいいでしょうか?
きっとオーダーしている人は何かを想定しているでしょうから、勝手に判断して提案した際、方向性があっていればいいですが、そうでない場合は解決提案が間違ってしまいます。
もっと言うと、そもそも「赤字」とは何を指しているのでしょうか。
会社の数字では、売上総利益(粗利)や営業利益(損失)、経常利益(損失)、純利益(損失)など、一口に損失=赤字と言ってもたくさんの意味があります。
(上記各利益の詳細は「損益計算書(P/L)」超簡単解説&使い方紹介参照)
個々の商品に目を向けると販売価格は明確ですが、原価を厳密に割り振ることは困難です。
例えば私たちの人件費はどう振り分けられるのでしょうか?
100個売れたときと10個売れたとき、歩合制でない限り全体でかかる人件費は変わりません。
給与が月20万だとしたら、100個売れたら1個当たりの人件費は2,000円、10個なら20,000円などのような簡単な計算はできません。
会社には、大きく分けて、売上とともに変わる費用(変動費)と売上に関係なくかかる費用(固定費)があります。
変動費は、売上に応じて増減するのでわかりやすいですが、固定費は、会社の独自ルールにより案分され原価に上乗せされます。
固定費の案分方法により赤字の出方が変わってしまいます。
ここでは長くなるのでこれ以上の説明は控えます。
(詳細を知りたい方は、変動費と固定費の詳細を書いた「変動費と固定費」超簡単に解説&使い方紹介を参照下さい)
上司が想定している赤字って何でしょうか?
実は会社ではこのようなことが頻発しています。若手の皆さんの目線、課長さんの目線、部長さんの目線、社長さんの目線。全然違います。
したがって、このようなアバウトな話が来たときは、前提の確認(赤字の基準・解決策の方法性)が大事になります。
打ち手議論に注意
課題設定がなく、打ち手の議論をおこなう
これもよくあるのですが、「この打ち手がいいよね」「いやこっちの打ち手の方がいいよね」と打ち手や施策の優劣を議論することがよくあります。
そんな時に、「そもそもどんな課題を解決するための打ち手なのか」が議論されずに話をしていることが本当に多くあります。
結果として、個人ごとに想定した課題での打ち手議論になるのです。課題がすり合っていない状態では、議論が噛み合うことは絶対にありません。
例えば、広告を打つ場合、TVCMをやろう、いやネット広告をやろう、いや、新聞広告をやろうなどの議論がされていた場合、どれも正解でありどれも不正解。
なんの課題を解決したいのか?まずは出来るだけたくさんの人の認知を上げることが課題なのか?ターゲットとした人の認知を上げることが課題なのか?によって広告媒体は変わります。
まずは課題を議論し決めることが大事です。
このように書くと当たり前ですが、打ち手の議論でかみ合わないと感じたら、課題って何か?と考えてみてください。きっと課題がすりあっていない場合が多くあります。
「前提をそろえる」のまとめ
形容詞
言葉の各自の定義
打ち手議論
話を聞く際は前提を揃える意識を常に持ちましょう。できない場合は、頑張って何を前提にしているか考えましょう。
例えば、上記の「この商品は赤字だ。解決策を提案してほしい」という場合は、最低、「売上アップの方向でしょうか?コスト削減の方向で考えればいいでしょうか?」位は聞くと方向性が少し揃ってきますね。
この問題は、新卒や中途で会社に入った際によく悩みます。周りの人は一緒に仕事を長くしている経験で、前提が揃いやすいので、前提の議論はしません。
私も5社で働いてきた経験から、この課題にひどく悩まされました。
前の会社で当たり前に使っていた言葉が、今の会社では全く違う意味を持っていたり、一般的な言葉でもその会社特有の意味で使われていることがあるからです。
前提が揃わないことで議論が噛み合わないケースは非常に多いため、常にこの意識を持って仕事を進めましょう。
他にもビジネススキルが上がる「思考方法」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
- 打ち手を考える前に必ず必要な「たった一つのこと」
- 「分解して考える」
- 「枝葉でなく幹をつかむ」
- すぐに検索せずに「一旦考える」
- 「極端に振って考える」
- 「具体化と抽象化」を使い分ける
- 「正しい情報」を得る6つのコツ
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。