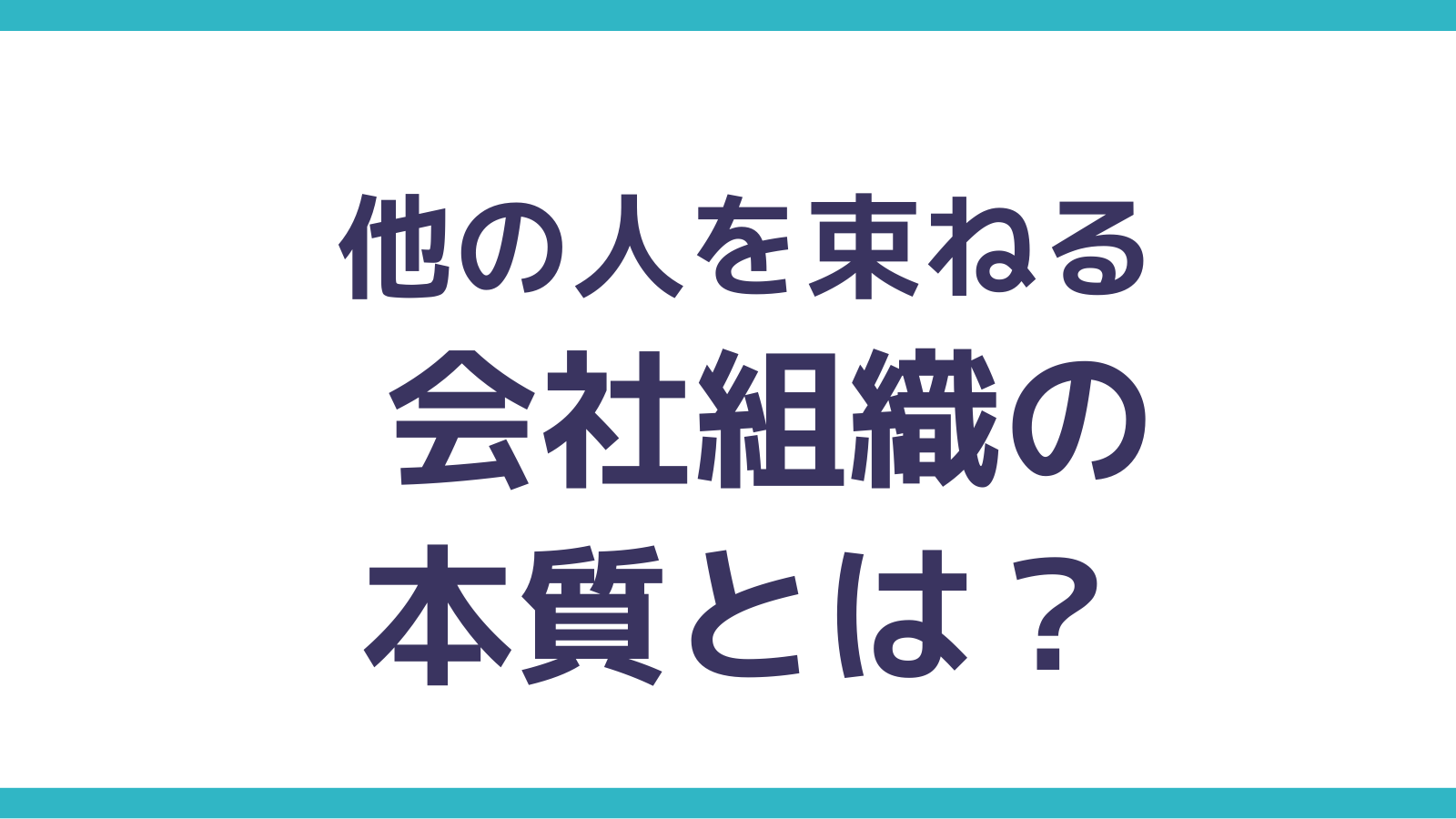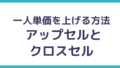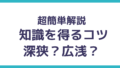世の中には沢山の会社組織があります。
それぞれの会社組織には経営者・従業員がいて、組織化されています。
では、そもそもなぜ会社組織ってあるのでしょうか?
とても簡単なようで、実は奥深いこの問い。私自身もあまり深く考えたことがありませんでした。
しかし、自分なりの答えを見つけた時、会社組織という目に見えない存在を深く理解できるようになったのです。
この記事では、この会社組織の本質についてわかりやすく解説しています。
この記事を読むと、会社組織の本質的な理解がすすみます。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【概念の本質】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質)
会社組織の本質
1人ではできないことができること
会社組織を作る理由は、人が集まることで、1人ではできないことができるからです。
理由は2つです。
1つ目は、物理的な限界を突破できること。
人が集まれば、1人でできる作業量を圧倒的に増やせます。
2人集まれば「1+1=2」になり、3人集まれば「1+1+1=3」と、人数が多いほど多くのことができます。
2つ目は、専門性を高められること。
同じ業務を繰り返し担当することでスキルが上がり、「1+1=2」以上の成果を生み出せるようになります。
また、ある業務が苦手な人でも、得意な人に仕事を割り振ることで、全体の専門性を効率よく上げることができます。
会社はこのメリットがあるため、組織に人を沢山集めるのです。
会社組織を運営するための条件
・人が集まること
・共通の目的があること
・分業されていること
・仕組みやルールが整備されていること
会社組織を円滑に運営するには、上記4つの条件が欠かせません。
まず人が集まらないと何も始まりませんし、適切な分業や配置がなければ、抜け漏れや重複が発生して非効率になります。
これらの問題を解決するために、これから解説する4つの条件が重要になります。
まずは、そもそも会社組織とは何かと、会社組織の成り立ちを説明した後に、それぞれ解説します。
会社組織とは?
会社組織とは、共通の目的をもった2人以上の集まりのことです。共通の目的があることがポイントです。
ただ、この境界線は人により変わりますので、厳密に考えずに、なんとなく共通の目的があり、2人以上なら会社組織と考えましょう。
会社組織の成り立ち
他人が協力し合える社会の仕組み作りが進みました。その結果、時代の移り変わりとともに、今の会社という組織が出来上がりました。
どのような流れでできたのかを紹介します。
人類は農耕が始まる1万年前まで、近親者を中心とした100名ほどの集団で移動しながら生活していました。
彼らは危険な場所を歩き回り、食料を確保する狩猟採集生活を送っていました。
この時代は、組織というよりは「集団生活」でした。
時代が変わり、農耕時代=定住生活がはじまりました。
定住するということは、その集団の中で生活に関する必要なものを調達する必要があります。
ただ、定住している以上現実的は、限界があります。その環境を克服するために、お金が発明されました。
そして、お金を得るために他に人に役立つことをおこなうことが必要となり、会社という仕組みが開発されました。
人が集まること
2名以上の人が集まらないとそもそも組織になりません。人が2名以上集まることが大前提となります。
当たり前ですが、今の時代では、採用できずに倒産する会社がある時代です。
共通の目的があること
会社組織の多くは、近親者ではない他人の集まりなので、人は所属する組織を選択できます。
その際に、なぜその組織に所属するかが選択のひとつの理由になります。
その理由がないと入社してくれませんし、入社したとしても、方向性がバラバラになってしまいます。
したがって、共通の目的が必要になるのです。
ただ、ここで言う目的とは、社会に役立つなどある意味崇高な目的だけでなく、お金を稼ぎたいという目的も共通の目的になります。
分業されていること
分業することで、抜け漏れや重複がなくなり、集まった人の力が結集され、効率よく成果を出すことができます。
まったく同じことしかできない人が集まった場合、その業務はとても効率的にまわりますが、他の必ず必要な業務ができないことになります。
したがって、適切な分業設計と適切な配置が必要になります。
その上、分業の大きなメリットは、担当する業務の経験を積むことで、スキルが上がることです。
会社に必要なさまざまな業務をおこなう人のスキルが上がれば、会社としてできることが増えていき、成果が出しやすくなります。
仕組みやルールが整備されていること
会社組織は、家族や友人といった「身近な人」の集まりではありません。見ず知らずの「他人」が集まってできています。
特に、「やりたいこと」「評価」「報酬」といった重要な要素が絡むため、曖昧な運用では不満が溜まりがちです。
だからこそ、ビジョンやミッションなどの目指すべき姿を共有し、人事評価や各種ルールを整備して、仕組みで動く組織を構築する必要があります。
会社組織の本質とは?「まとめ」
1人ではできないことができること
これが会社組織の本質です。
この本質を理解することで、「なぜ会社にたくさんの人がいるのか?」「なぜ分業しているのか?」といった素朴な疑問の答えが見つかりやすくなります。
また、あなたの会社組織に対する見方や考え方が一段と深まり、表面的なことだけでなく、物事の根本を捉えられるようになります。
何かを考えるときに、この本質を意識するだけで、これまでとは違った視点を持つことができるでしょう。
他にも基礎用語の「本質」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。