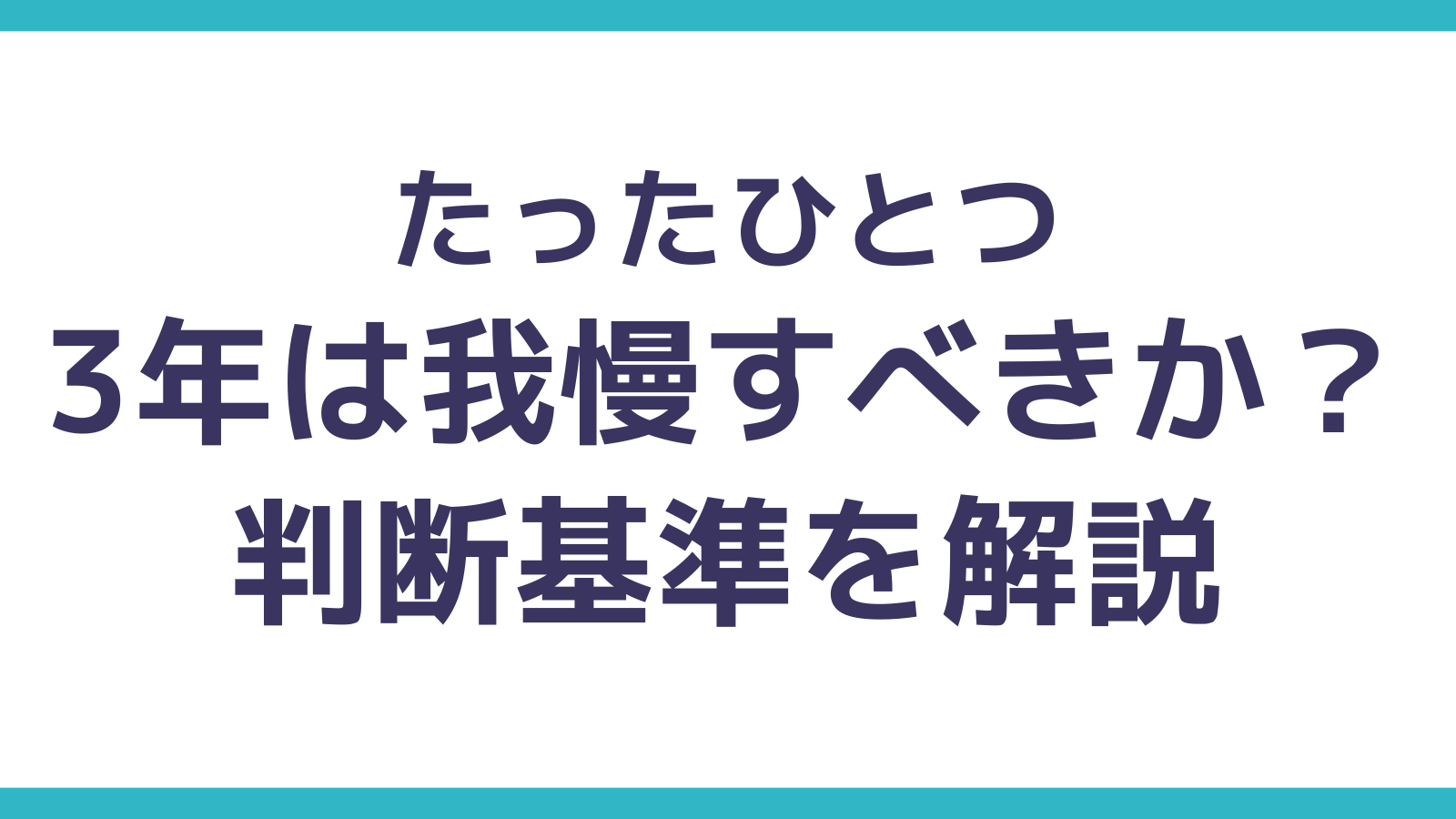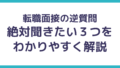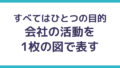「今の会社、辞めたい…でも、入社して3年は我慢すべき?」──そう悩んで、周囲に相談した経験がある方も多いのではないでしょうか。
この問いに決まった答えはありません。なぜなら、あなたが働く環境によって、その答えは大きく変わるからです。
本当に考えるべきは、「どんな会社なら3年我慢して働くべきなのか?」という問いです。
この記事では、あなたの会社が「3年間我慢して働く価値があるか」を判断できる、具体的な基準をわかりやすく解説します。
この記事は、
・3回の転職経験
・中途採用の責任者の経験
・多数の書類選考・面接の経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ)
入社後3年我慢する?のたったひとつの判断基準
「課題解決」がたくさん経験できる会社かどうか?
これが判断基準になります。
なぜなら、その3年間であなたの仕事の能力をどれだけ高められるかどうかが、将来のキャリアを大きく左右するからです。
(課題解決の詳細は、課題解決とは?意味・考え方・進め方をわかりやすく解説を参照)
「課題解決」がたくさん経験できることがなぜ大事なのか?
・3年は我慢という説ができた背景
・転職のリスク
・課題解決経験が大事な理由
・課題解決経験を積めないとどうなるか?
・3年は我慢の理由の検証
上記の順番で解説します。
3年は我慢の背景
昔は会社をやめずにがんばるしかなかった
昔は「会社を辞めずに頑張るしかない」という時代でした。
「石の上にも3年」ということわざが生まれた頃から、現在の40代後半以上の世代とそれより若い世代では、働き方を取り巻く環境に大きな違いがあります。
その最も大きな違いは、転職が当たり前であるかどうかです。
「3年は我慢」という言葉は、一つの会社で長く働くことが常識だった時代に生まれたノウハウと言えます。
当時の考え方は、「今やっていることが無駄に思えたり、嫌だと感じても我慢しなさい。そうすれば3年後には多くのことを学び、成長できる」というものでした。
転職という選択肢がなかったからこそ、「会社を辞めない理由」として語り継がれてきたノウハウなのです。
この前提を理解しておくことは重要です。
もちろん、この考え方を全否定するつもりはありません。長く伝承されているということは、そこに重要なエッセンスが含まれているからです。
転職のリスク
3回目の転職は書類通過率が大きく下がる
転職の目的は、多くの場合、今の会社よりも良い環境や条件の会社で働くことでしょう。
しかし、残念ながら最初の転職(2社目への転職)で失敗してしまう人は少なくありません。
もし、やむを得ず再び転職活動をすることになった場合、書類選考の通過率は著しく下がってしまいます。特に20代で3社目を探すとなると、その傾向は顕著です。
採用側は、1回目の転職であれば「会社選びに失敗したのかもしれない」と考え、ひとまず面接を検討することもあります。
しかし、2回目の転職となると、「この人に何か問題があるのではないか?」と書類の段階で判断されてしまうケースが多いのです。
私自身も中途採用に携わっていますが、この理由から2度目の転職者(2社退職者)の書類はほとんど通過させません。このように、20代での転職には大きなリスクがあることを理解しておく必要があります。
もちろん、転職をすべきではないと言っているわけではありません。ただ、そこに大きなリスクが存在することを、あらかじめ知っておいてほしいのです。
たくさんの課題解決経験が大事な理由
仕事において最も重要視される能力が課題解決能力
ここではまず、その「課題解決経験」について定義した上で、なぜ重要なのかを解説します。
(課題解決の詳細は、課題解決とは?意味・考え方・進め方をわかりやすく解説を参照)
課題解決経験とは?
「課題解決経験」とは、知識だけでこなせる仕事ではない業務を経験することを指します。
多くの仕事には、マニュアルを見れば誰でもこなせるような、知識だけで対応できる業務が存在します。しかし、ここでいう課題解決経験とは、そのような受動的な業務とは一線を画します。
自ら問題を見つけ、課題を設定し、その解決策を考案・実行し、実際に課題を解決できた一連のプロセスこそが「課題解決経験」なのです。
自分の知識や経験を活かしながら、どうすれば目的を達成できるかを自力で考え、解決へと導く過程で、あなたの能力は飛躍的に向上します。
(詳しくは、「知識と能力とスキルの関係」をわかりやすく解説を参照)
例えば、マニュアル通りに業務を進めるのではなく、より効率的なマニュアルそのものを作成する業務がこれに当たります。
誰でも同じ成果を出せるマニュアルを作ることは、業務の属人化を防ぎ、質問する側・される側双方の効率を格段に向上させます。
これこそが、まさに「課題解決」と言えるでしょう。
課題解決能力が上がる
課題解決能力は課題解決を経験しないと上がりません。
仕事とは何か?を一言で言えば課題解決です。
会社には、目指したい姿があります。そして、そこにたどりついていない現状があります。
現状とのギャップが問題であり、その問題の中で解決する必要がある問題が課題です。
その課題を解決することで、目指したい姿になります。
(詳しくは、「目指す姿・現状・問題・課題・戦略・戦術」をたった1枚の絵で表すを参照)
会社は常に目指すべき姿を追い求めており、だからこそ私たちに求められるのは「課題解決」なのです。この課題解決の経験を豊富に積むことで、会社で確かな成果を出せる能力が身につきます。
課題解決能力を分解すると以下になります。
| 課題設定スキル | ・目指したい姿を設定するスキル ・「現象」と「原因」を分けるスキル ・「現象」の「原因」を把握するスキル ・様々な「原因」の「真因」を見つけるスキル |
| 打ち手立案スキル | ・複数の打ち手を立案するスキル ・打ち手を決定するスキル |
| 打ち手実行スキル | ・打ち手を他の人に理解してもらうスキル ・他の人に動いてもらうスキル |
(詳細は、【ビジネススキル一覧付】ビジネススキルとは?をわかりやすく解説を参照)
これらそれぞれのスキルが上がることで、課題解決能力が上がります。
課題解決経験を積めないとどうなるか?
3年間が無駄になってしまう可能性が高くなる
本来、最初の3年間で得るべき経験や能力が身につかず、その後のキャリア形成や自己成長に大きな影響を及ぼします。
新社会人に期待される理想的な3年間の成長ステップは以下の通りです。
(1年目)1つの成功体験を経験する
(2年目)成功体験で得た1つのノウハウを横展開
(3年目)新しいノウハウを得る方法を習得・実行
このステップを踏むことで、4年目以降の持続的な成長が保証されます。そして、この「成功体験」は、まさに「課題解決経験」からしか得ることができません。
だからこそ、課題解決経験が非常に重要なのです。
(詳しくは、社会人最初の3年間で踏んでほしい「成長のステップ」をわかりやすく解説を参照)
よく言われる「3年は我慢」の理由の真偽を検証
「3年は我慢すべき」という言葉には、様々な理由が挙げられます。ここでは、その中でもよく言われる理由について、一つずつ検証していきましょう。
仕事が覚えられない
確かに3年間同じ仕事をすれば、多くのことを学べるでしょう。しかし、重要なのは「何を」学べるか、その内容です。
もし「仕事が覚えられない」という状況が、課題解決能力の向上につながる学びであれば問題ありません。
しかし、そうでない単なるルーティンワークの習熟であれば、その3年間は「無駄」になってしまう可能性があります。
仕事の本当の面白さが分からない
「仕事の本当の面白さ」を定義するのは、確かに難しいことです。
しかし、本記事で説明した「新社会人の3年間で踏んでほしい理想のステップ」を実践することで、仕事が面白くなることは間違いありません。
つまり、たくさんの課題解決経験を積めるのであれば、その3年間は意味のあるものとなるでしょう。
しかし、それが叶わないのであれば、やはりその3年間は「無駄」になってしまう可能性が高いと言えます。
転職に不利になる
結論から言うと、新卒から3年働いていなくても、それ自体が不利になることはありません。
私自身、普段中途採用の面接を担当していますが、新卒から3年働いているかいないかで合否を判断することはありません。
ただし、20代で既に3社目(2社退職)を探している場合は、非常にネガティブに捉えられます。
1社目の退職であれば、それが本人の理由なのか、会社の理由なのかが判断しづらいため、面接で詳しく話を聞いてみようという気になります。
しかし、既に2社を辞めているとなると、「きっと本人に問題があるのだろう」と判断してしまうことが、これまでの面接経験からも多いです。
また、「新卒から3年間働いていない人を採用しない」という判断をする会社は、一体どのような基準で人を評価しているのでしょうか?
「すぐに諦める」「我慢強さがない」「入社してもすぐに辞めるのでは」といった短絡的な思考が背景にあるのかもしれません。
しかし、履歴書だけで一度の失敗からそのような判断を下すことは、非常に難しいと私は考えます。
さらに言えば、たったそれだけの情報で人を判断するような会社であれば、入社後に苦労する可能性が高いでしょう。そのような会社は、人材を「減点主義」でしか見ていない方針が透けて見えるからです。
3年は我慢すべきか?の判断基準の「まとめ」
課題解決経験をたくさん積める会社かどうか?
最終的に「3年我慢すべきか?」を判断する基準は、このことただ一つです。。
つまり、入社からの3年間で、あなたの課題解決能力をどれだけ高められるかどうかが唯一の判断基準となります。
もし、その会社で能力を向上させられると確信できるなら、我慢して働き続けましょう。しかし、それが難しいと感じるのであれば、無理に我慢する必要はありません。
他にもキャリアプランの「軸とタイミング」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
- 20代で一番大事なこと 「時間当たりの課題解決経験」
- 「会社を好きになる」たった2つの理由
- 「好きなことを仕事にしたい」と思った時に知っておきたいこと
- 社会人になった時に知っておきたい「本当に大事なこと」
- 「やりたいことを見つける方法」
- 「3年は我慢すべきか?」の判断基準
- 「仕事の環境を変えるタイミングとは?」
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。