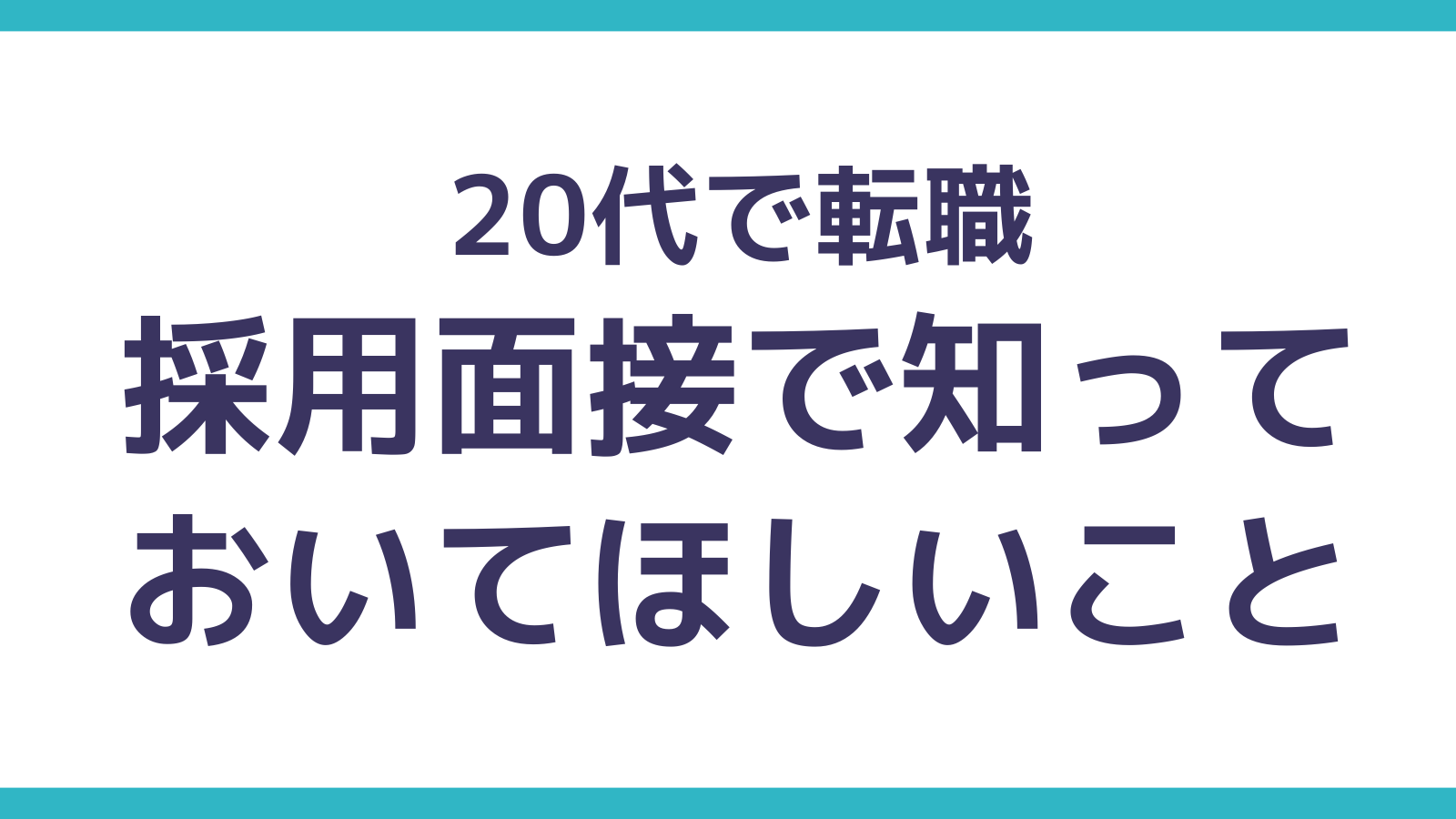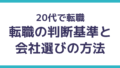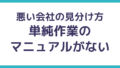20代で正社員として採用される確率をご存知でしょうか?応募何名中何名採用になるかの数字です。
2%から5%といわれています。100名受けたら2名~5名が採用という数字です。中々厳しい数字です。当然人気企業とそうでない企業では大きく変わります。
ただ、大多数が内定をもらえないことは事実です。
100名中80名が通る採用なら、ネットにあふれているトークを一生懸命覚えるのが一番の近道です。
間違わなければ内定をもらえるのですから、ネットにあふれている想定問答集で答えればいいのです。
ただ現実は2名~5名なのです。想定問答集を答えるだけでは内定はもらえません。
この記事では、この事実を踏まえて、20代で初めての転職を検討されている方向けに、採用面接に望むスタンスや考え方を2つにまとめて解説します。
この記事は、
・3回の転職経験
・中途採用の責任者の経験
・多数の書類選考・面接の経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・1,000冊近い読書経験
上記経験を元に書いています。採用する側から見た視点も含めて書いていますので、参考にしてください。
(あわせて読みたい、知っておきたい 転職の知識(転職判断から入社まで)
20代の転職の採用面接で知っておきたい「2つのこと」
・採用側から見た中途採用面接の実態を知る
・採用されるではなく、出会うという考え方で活動する
この2つを知っておいてください。それぞれ解説します。
採用側から見た中途採用面接の実態を知る
・現在の転職マーケットは採用される側が有利
・採用基準は2つ。最低限の基準をクリアしているか?どんな行動特性を持っているか?
知っておきたいことは、上記の2つです。それぞれを解説します。
現在の転職マーケットは採用される側が有利
採用される側が圧倒的に有利
まずは、現在のマーケットをおさえておきましょう。
会社により、違いはありますが、総論は採用される側がとても有利な状況が続いています。
ということは、企業側からすると採用したいが採用できない状況が続いています。有名企業も同じ状態です。
結果マーケットで起きていることは、どの会社も受け身ではなく積極的に転職希望者にアプローチしています。
結果、採用に不利な知名度のない中小企業は、更に厳しい状況となります。
したがって、採用される側から見たときには、有名企業・中小企業とも、内定の確率は上がります。また、中小企業の優良会社も採用に苦戦しているので、狙い目となります。
(会社の選び方は、自分に合う会社の見つけ方!大事にすべき4つの基準をわかりやすく解説を参照)
中途採用面接担当者の現状
採用される側が有利なので、面接方法にも影響が出ています。
・2回面接で採用決定しないといけない
・様々な方法で面接数を増やす活動をしている
この2つが顕著な動きとなります。
2回面接で採用決定しないといけない
採用に時間をかけることができません。なぜなら、時間がかかればかかるほど、他社との取り合いになる可能性が高いからです。
採用側は、すぐに内定を出し、すぐに判断してもらうことが大事になります。
したがって、内定までの面接回数が2回の企業がほとんどです。1回目は担当者レベル、2回目は経営者や責任者レベルです。
そして圧迫面接にならないように面接官は2名までに抑える会社が多いです。
正社員を採用したら基本解雇はできないので、できるだけ回数多く会うことと沢山の人でチエックしたいです。ただ、採用成功率を上げるためにはこれらに制約がかかっている状況です。
様々な方法で面接数を増やす活動をしている
今の時代、企業側は採用をしてあげようという上から目線では採用できません。
1つの転職サイトに広告出稿をして終わりではなく、複数の転職サイトに広告掲載したり、転職エージェントなどにも声がけして採用をしようとしています。
したがって、メインの転職サイトとメインの転職エージェントをおさえておけばある程度の企業の情報は入ります。
どのサイトやエージェントに登録すればいいかは失敗しない転職エージェント・転職サイトの選び方と活用方法に書いていますので参照ください。
ただ、2回の面接なので、お化粧がばれない可能性がある反面、1回1回の面接がとても大事になります。
採用基準は2つ。最低限の基準をクリアしているか?どんな行動特性を持っているか?
採用基準は2つです。最低限の基準をちゃんとクリアしているか?どんな行動特性を持っているか?が採用側が考える基準と合っているかです。
まずは採用担当者の置かれている状況、そして、最低限の基準、どんな行動特性の順番で解説していきます。
採用担当者の置かれている状況
中途採用担当者はあくまで仲介業者であることをまずはおさえておきましょう。
中途採用担当者の仕事は、まさしく、計画した中途採用人数を採用することです。
採用部署(人事部等の採用担当部署)で働く場合もありますが、基本は、その他の部署で働く採用活動となります。
したがって、仲介業者なのです。
この立ち位置の中で、中途採用担当に起きる二律背反問題があります。
採用数は確保しなければならないが、採用のレベルを落としてはいけない。この二律背反問題が重くのしかかっています。
採用の質を下げると、配属となった現場の部署ですぐやめたり、教育に時間がかかりすぎて困るなどの問題が発生し、配属部署からのクレームとなります。
ただ、採用の基準が高いままでは採用数が限られます。採用担当者の立ち位置はこのような板挟みな状態であることを理解しておきましょう。
採用の最低限の基準とは?
・見た目である服装、髪型、靴といった外見のマナー
・時間を守ること
・メール返信・電話折り返しはすぐに対応
・転職の理由はちゃんと着飾ってほしい
上記4つが最低限の基準です。採用担当者は仲介業者です。変なリスクを負いたくないのが実情です。
したがって、最低限のマナー(と世間一般が思っていること)が守れない人・知らない人は怖くて採用できません。
見た目である服装、髪型、靴といった外見のマナー
スーツを着てこない、スーツだけどよれよれのシャツやネクタイ、ネクタイを緩めている、靴が汚い、鞄がカジュアルなどは、性格もルーズと見られてしまいます。
時間を守ること
面接時間に遅れるのは絶対ダメです。私は採用面接の際は、基本30分前までにその会社の徒歩圏内まで行くようにしていました。
電車が止まることも珍しくなく、しょうがない理由で遅れる場合があります。
ただ、しょうがない理由だとしても、なぜこの人は、大事な面接でこのようなリスク管理ができないのか?というマイナス評価からのスタートとなってしまいます。
メール返信・電話折り返しはすぐに対応
面接設定の際の連絡に対するクイックレスポンスがとても大事です。
自分にとって大事な転職でのレスポンスが遅いということは、すべての行動はもっと遅いと思われます。
採用担当は、当然複数の人の面接設定調整をおこなっています。この業務をやればわかりますが大変です。
そのような心理状態なので、返信に時間がかかるだけで悪い印象を持ってしまいます。
スマホはこまめに見ることです。でもどうしても見ることができない場合は、仕事の都合で、9-12時 13時-18時は電話及びメール対応ができないことを必ず伝えておきましょう。
転職の理由については、ちゃんと着飾ってほしい
転職したいということは、今の会社が嫌だからやめた(やめたい)と採用する側では分かっています。
したがって、ちゃんと着飾って話をする準備をしておきましょう。ネットにのっている想定問答集を参考にしてください。
採用担当者が社内で最終面接に挑む上長に事前に、この応募者の転職理由を伝えるためです。
採用担当者に稟議を上げやすくなるネタを提供してあげるのです。
ありきたりなのですが、これらが次の面接には進む前提条件となります。
先ほども言いましたが、あくまで採用担当者は仲介業者です。
社内に採用候補を紹介する際に、問題のある人を紹介すると、その採用担当者自体の評価が下がってしまうという呪縛があることを知っておいてください。
どんな行動特性を持っているか?
前提条件をクリアした人に対する採用する側の判断は、その人の行動特性を元に判断します。
行動特性は、何をやってきたかではなく、どんな判断をしてきたか?に顕著に表れます。
採用する側は、社会人経験3年位であれば、前職の経験は気にしません。
例えば、営業を3年していたとしても、その営業力が新しい会社で使えるほどの営業力かどうかは未知数です。
逆に、3年以上たっていたら、前の会社の変な癖がついていないか心配になります。一度ついた癖は抜けにくいからです。
したがって、経験自体はアピールポイントにはなりません。もし、面接者の今後伸びる可能性ではなく、少ない経験等の表層を大事にする会社なら入社しない方がいいです。
採用は会社のコアな業務です。このコアな業務の判断が表層であれば、他の判断の表層の判断が多いからです。
ただ、面接時に前職での経験の話を必ず聞きます。これは経験自体を聞きたいのではなく、その人がどんな判断をしてきたかを知りたいのです。
私が面接をする際は、学生で力を入れたこと、前職の会社に決めた理由、退職しようと考えた理由、前職での成功体験のプロセスを聞くようにしています。
正直、話した内容がどんな答えでもあまり気にしません。答えが、どのような考えておこなったのか?どんな理由で判断・決断をしたか?を推測するようにしています。
人の本質は大きな判断の場面で顕著に表れますので、この部分がわかればその人の行動特性がわかります。
この部分は盛ることはできませんが、このような見方をしていることを知っておくことと、できるだけネガティブな話にならないように気をつけましょう。
通過するという考え方ではなく、出会うという考え方
時間がかかっても出会うを優先する
選ばれる・通過するという考え方で臨むのではなく、出会うという考え方で面接に望んだ方が、時間はかかりますが、適正が合致した会社に入ることができます。
出会うという考え方とは?
選ばれるという考え方だとどうしても自分を大きく見せようとします。したがって、どんなトークをしたら採用されるか?という思考になります。
盛りすぎると、どうしても嘘くさく見えます。若い担当であれば、わからない場合もありますが、ある程度経験を積んだ人にはバレます。
また、転職あるあるなのですが、選ばれようとしていて内定がもらえないと、自分がダメな人間だと勝手に思い始めます。そして焦って妥協して転職先を決めてしまう負のスパイラルに入ります。
したがって、恋人を見つける時のように、あくまで対等である意識=出会うという考え方を心の中心においておいてください。
こちらは求愛したから、そっちはどう判断するんですか?というスタンスで行きましょう。
時間はかかります。でも、遠回りのようで、自分自身の経歴を汚さない最適な方法となります。
採用活動に時間をかける
面接の際に目安としていつ位までに次の会社で働きたいですか?聞くのですが、大体3か月後という答えが多いです。
3ヶ月後というと、2か月間で決定して、会社に退職の意思を伝え、一か月後にやめるスケジュールになります。
とても短すぎます。半年は最低かけましょう。
そして、出来る限り、今の会社で働きながら、転職活動をおこないましょう。退職してからだと、どうしても、焦ることになり、間違えた判断をしてしまうことになります。
採用面接で知っておいてほしいことの「まとめ」
・採用側から見た中途採用面接の実態を知る
・採用されるではなく、出会うという考え方で活動する
とにかく時間をかける覚悟をしてください。健康状態等に問題がないのであれば、この覚悟なく、1社目をやめる判断はしないでほしいです。
その上で、面接では、少し盛る必要はありますが、できるだけありのまま話す方が2社目の失敗の確率は格段に下がります。
大きく盛るなら周到なトークの準備をしてください。そして、入社後きついことは覚悟を決めて入社してください。
おすすめはしないですが。
他にも転職活動時に知っておきたいことの記事を書いています。参照下さい。
- 「転職エージェント・転職サイトの選び方」
- 「企業研究のやり方」
- 「求人募集内容の裏の見方」
- 「会社口コミサイトの見方の注意点」
- 「書類通過率を上げる考え方と方法」
- 「面接の逆質問で絶対聞きたい3つのこと」
- 「条件通知で知っておきたいこと」
- 「内定後入社を決める前に大事にしたいこと」
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。