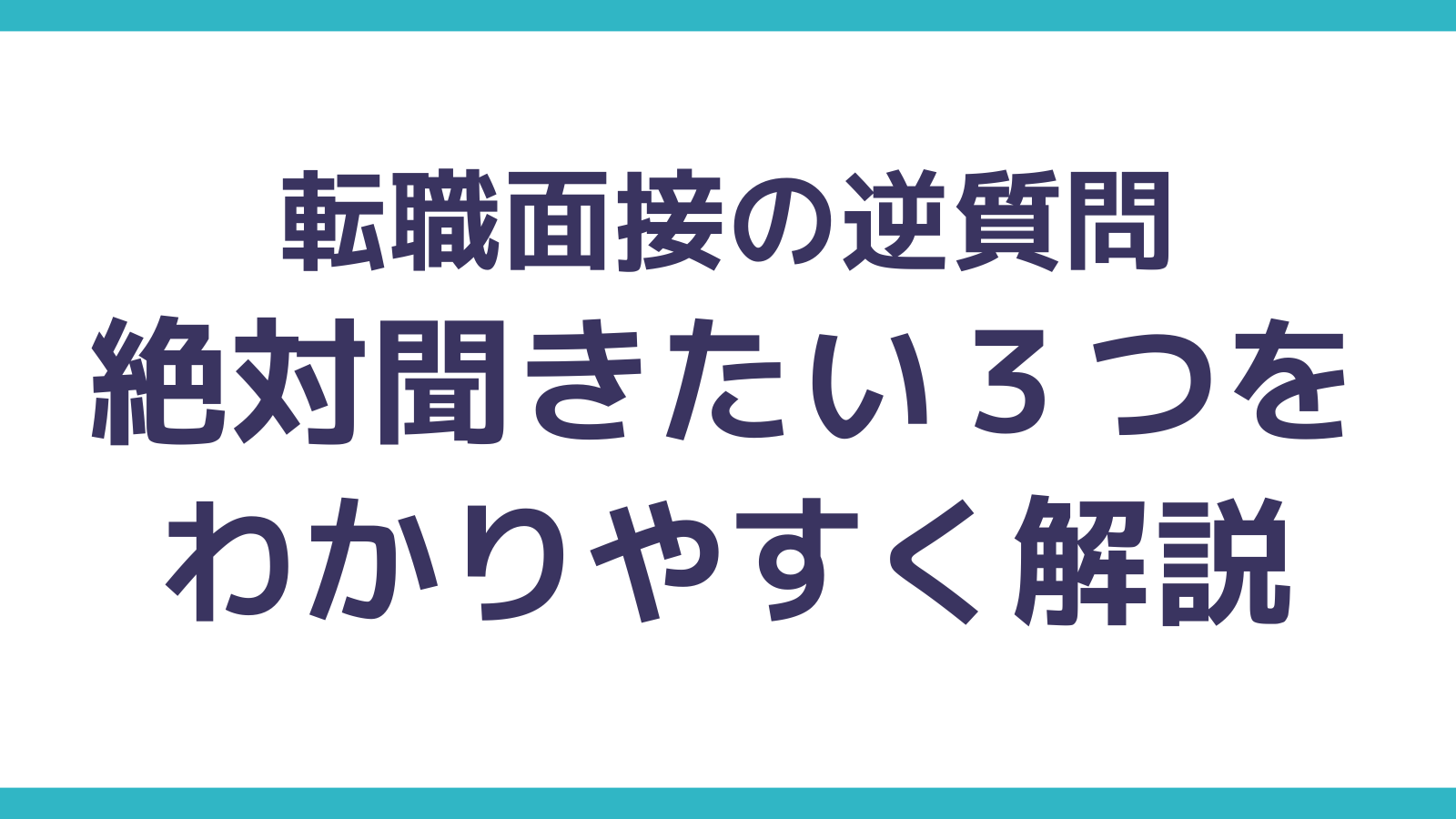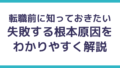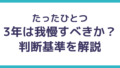転職面接では、企業からの質問が終わった後に、求職者側から質問できる時間が設けられます。
この「逆質問」は、会社を深く知るための貴重な機会です。
会社情報は、これまではウェブサイトや面接官の印象でしか把握できませんでした。
しかし、この逆質問を効果的に活用することで、応募先の「本当の姿」を見抜けます。
「どこまで突っ込んだ質問をしていいのか?」「たくさん質問しすぎて大丈夫か?」といった不安を感じるかもしれませんが、この記事では、数ある質問の中から特に重要な3つを厳選。
その質問への回答から、会社をどう判断すべきかをわかりやすく解説します。
この記事は、
・3回の転職経験
・中途採用の責任者の経験
・多数の書類選考・面接の経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい 転職の知識(転職判断から入社まで)
絶対聞きたい3つとは?
・どんな人事評価制度か?
・キックオフミーティングの開催の有無
・同じ部署の年齢構成
この3つが絶対に聞きたいことです。
逆質問の時間は限られています。この制約の中で会社の「本質」を知るには、「経営者の考え」と「働く人の実態」を把握することが重要です。
会社には経営者の考え方が色濃く反映され、年齢層が分かれば職場の雰囲気がおおよそ掴めます。
これらの情報を少ない質問で得るには、経営者の考えが最も表れる人事評価制度と、経営者の考えが従業員に伝わっているかを示すキックオフミーティングの有無を聞くのが効果的です。
また、年齢構成を知ることで、自分と同世代が多いかどうかがわかり、その会社の雰囲気に合う可能性を判断できます。
まずは、面接と逆質問の基本を解説し、その後、上記の3つの質問について詳しく見ていきましょう。
面接とは?
・面接の目的
・面接のスタンス
それぞれに分けて説明します。
面接の目的
受ける会社が自分にあっているかどうかを判断すること
企業側は自社に合った人材かを判断し、求職者側は自分に合った会社かを判断するための場といえます。
面接にのぞむスタンスとは?
募集会社と求職者は対等
どちらにも選択権があるため、対等に臨む意識が重要です。つい「選んでもらおう」とへりくだりがちですが、心の中では「対等である」という意識をしっかり持っておきましょう。
現在の採用市場では、多くの企業が人手不足に悩んでおり、求職者にとって非常に有利な状況です。
だからこそ、対等な意識で面接に臨むことが求められます。
逆質問とは?
採用面接時に面接者から質問すること
面接では、採用側からの質問が中心になります。最後の面接を受けている人から質問ができる場合があり、その際の質問を逆質問と言います。
逆質問の目的は、
応募した会社の本当の姿を把握すること
これが逆質問の目的です。
よく「自己アピールや志望度を伝える場」だと言われますが、私自身、採用責任者として中途採用の面接を行ってきた経験からすると、企業側の質問が終わった時点で、合否判断はほぼ完了しています。
判断ができないまま質問を終える面接はありえません。なぜなら、求職者が自社に合っているかを判断するのが面接だからです。
だからこそ、逆質問の時間は、もし内定が出た場合に「自分が入社すべき会社かどうか」をあなたが会社を評価するために使いましょう。
これらを踏まえて、前述の「どんな人事評価制度か?」「キックオフミーティングの開催有無」「同じ部署の年齢構成」の3つが、なぜ絶対に聞きたい質問なのかを解説します。
どんな人事評価制度か?
人事評価制度があり、目標が明確で、フィードバックもある
上記であれば合格です。
・なぜ人事評価制度を聞くのか?
・質問の答えからわかること
それぞれを解説します。
なぜ人事評価制度を聞くのか?
人事評価制度は、経験の根幹なので経営者の考え方がわかるから
従業員に対する経営者の本当の気持ちは、この制度設計に明確に現れます。なぜなら、経営者は自分が評価したいことしか評価しないからです。
質問の答えからわかること
経営者の本心がわかる
人事評価制度は、まさに経営者の従業員に対する本心そのものです。
したがって、普段人事評価を受けている面接官が答えてくれる内容に、その本心が見え隠れします。
返答ごとに、どのような本心があらわれているかを紹介します。
そもそもちゃんと制度設計されていない
「御社の人事評価制度はどのような制度ですか?」とストレートに質問してみましょう。
わかりやすく具体的に答えてくれれば合格です。
もし、聞いてもあいまいな答えや、「まだこれから」「試行錯誤中」といった回答であれば、制度設計がきちんとできていないと判断できます。
これは、その会社がすべてにおいて従業員に優しくない可能性が高いことを示唆します。
経営者は従業員に仕事を分業させる以上、従業員がきちんと働いてくれないと困るはずです。
人事評価は、きちんと働いた従業員には賞与などで報い、そうでない場合は改善を促すための重要な仕組みです。
制度設計がなかったり、不十分だったりするのは、この当たり前のことを考えていないか、あるいは個人の好き嫌いで評価したいと考えているからです。
(詳しくは、良い会社の見分け方 ちゃんとした人事評価制度がある会社を参照)
結果主義
「プロセスで評価される項目は設定されていますか?」と質問してみましょう。
この答えで、会社が従業員とどう向き合っているかがわかります。
ここでいう「結果主義」とは、結果のみで評価を行う会社を指します。
結果は良いことも悪いこともあり、顧客や外部環境にも左右されます。
結果の測定は基本的に目標達成度合いで行われますが、その目標が全従業員にとって難易度が均一で適切であれば問題ありません。
しかし、目標設定の難しさを考えると、適切な目標設定はほぼ不可能です。
上役の人が結果で判断されるのは当然ですが、20代の皆さんが結果のみで判断されるということは、会社や上長が皆さんのプロセスを見に行かなくなることを意味します。
結果として、上長はプロセスに興味を失い、簡単な結果だけで判断するようになり、皆さん一人ひとりと向き合うことをしなくなるでしょう。
(詳しくは、良い会社の見分け方「結果よりもプロセスを求める会社」を参照)
目標の達成基準が明確でない
「目標はすべて数字での評価ですか?」と質問してみましょう。
評価である以上、明確な達成基準があるはずです。結果指標はもちろん、プロセス指標についても、何をどこまでやれば評価されるかを数字で設定する必要があります。
そうしないと、評価される人の納得感は得られません。
多くが数字で答えてくれるのであれば、良い人事制度だと言えます。
一見、結果主義のように感じるかもしれませんが、会社によっては「提案能力が上がった」「周囲と協力して仕事ができるようになった」といった定性的な項目を設定している場合があります。
これらを上司の主観で評価されてボーナスが決まるのは、正直なところ厳しいでしょう。
評価結果のフィードバックがない、もしくは結果のみ
「評価のフィードバックはありますか?フィードバックの平均時間はどれくらいですか?」と質問してみましょう。
人事評価の目的は、「従業員が組織に貢献すること」と「従業員自身が成長すること」を同時に実現することです。
(詳しくは「人事評価(人事考課)の目的」をわかりやすく解説を参照)
もし「評価結果のフィードバックがない」、または「短時間で結果のみしか話さない」のであれば、その会社は「従業員自身の成長」をまったく考えていないことがわかります。
従業員の普段の活動を成長につなげようと考える企業であれば、フィードバックがない、あるいは結果のみの伝達にとどまることは絶対にないからです。
キックオフミーティングの開催の有無
開催されていて、業績だけでなく会社の方針の話もしてくれる
キックオフミーティングが開催されていて、業績だけでなく、会社の方針についても話してくれる会社であれば、合格です。
経営者の仕事の核は、自らが行う仕事を従業員に分業して実行してもらうことです。
分業するということは、経営者が「何をしたいか」が明確にあり、それを実現するために「どうしたいか」も明確にあるはずです。
当然、経営者は従業員に対して「どうしてほしいのか」「なぜこの仕事を行ってもらうのか」を伝えたいと考えるのが普通です。
その結果、従業員に直接伝える場として、キックオフミーティングが設定されます。
もし、キックオフミーティングを設定しないのであれば、それは「話したくない」か「話す内容がない」かのどちらかです。どちらにしても、従業員にとっては良くない状況と言えるでしょう。
また、キックオフミーティングがあったとしても、売上や利益の数字のみの報告であれば、なぜその数字を達成する必要があるのかが語られていないことになります。
もし、大きな会社の場合は、経営者ではなく事業責任者でも同じことが言えます。
同じ部署の年齢構成
同世代が多い会社
「同じ年齢層が多い会社が良いのか、それとも年齢が高い会社が良いのか?」
20代の皆さんにとっては、間違いなく同世代が多い会社の方がメリットが多いです。
会社内でのコミュニケーション、会社外での飲み会といった交流、さらには昇進のしやすさなど、多くの利点があります。
したがって、「同じ部署の年齢構成はどのような感じですか?」と尋ねてみましょう。
転職の逆面接で絶対聞きたい3つのことの「まとめ」
どんな人事評価制度か?
キックオフミーティングの開催の有無
同じ部署の年齢構成
この3つの質問をすることで、応募した会社の「本当の姿」がほぼ把握できます。
内定が出た際、入社するかどうかを判断する上で、これらの情報を理解しているかどうかで、後悔する確率が大きく変わってくるでしょう。
今回紹介した聞き方でこれらの質問をすることは、まったく問題ありません。正々堂々と質問しましょう。
逆に、これらの質問をされて嫌がる会社は、何か後ろめたい気持ちがあるのかもしれません。それは、それだけの会社だということを示しています。
他にも転職活動時に知っておきたいことの記事を書いています。参照下さい。
- 「転職エージェント・転職サイトの選び方」
- 「企業研究のやり方」
- 「求人募集内容の裏の見方」
- 「会社口コミサイトの見方の注意点」
- 「書類通過率を上げる考え方と方法」
- 「採用面接で知っておいてほしいこと」
- 「条件通知で知っておきたいこと」
- 「内定後入社を決める前に大事にしたいこと」
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。