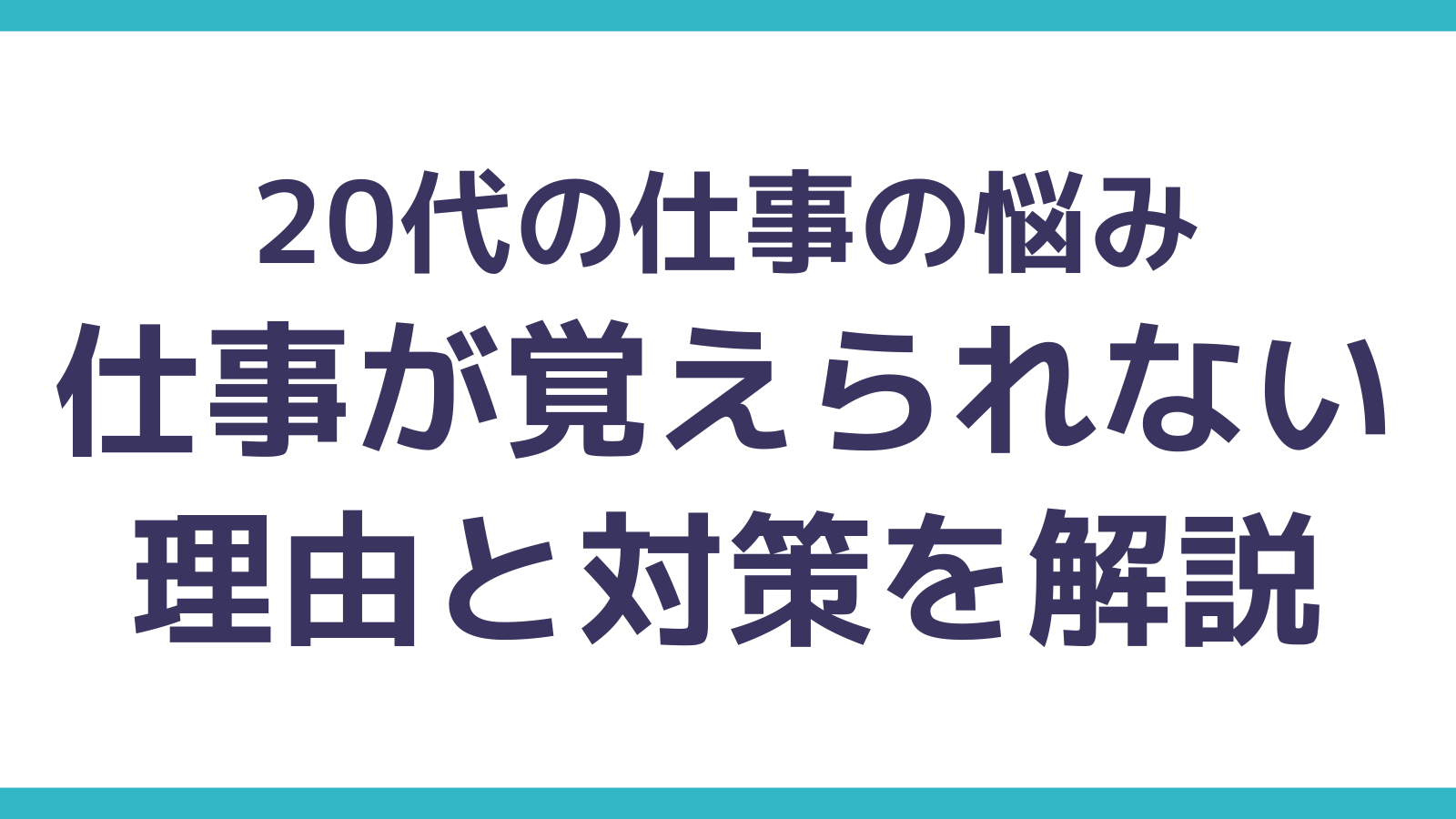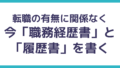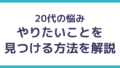「仕事が覚えられない」と悩んでいませんか?
20代の社会人なら、誰もが一度は経験する悩みかもしれません。
「メモを取ろう」「主体的に考えてみよう」といったアドバイスはよく聞きますよね。
でも、メモを見返しても状況が少し違うだけで役に立たなかったり、主体的に考えると言われてもどうすればいいか分からず困ったりした経験はありませんか?
この記事では、そんな20代が抱える「仕事が覚えられない」という悩みの原因と、具体的な対策を分かりやすく解説していきます。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【社会人の悩み】素朴な悩み・よくある悩みと対策)
「仕事が覚えられない」と感じる人への最初のアドバイス
今は気にしない 2年後できている
まずは、この記事の最初のアドバイスです。仕事はそう簡単に覚えられるものではありません。だから、今悩む必要はないんです。
ただ、仕事が覚えられない「原因」と「対策」を知識として知っておくことは非常に大切です。これを知っているだけで、仕事を覚えるスピードは格段に上がります。
「仕事が覚えられない」原因
「仕事が覚えられない」と感じる原因は、人それぞれですが、大きく分けて「定型業務」と「課題解決業務」の2つの種類で考えると、その原因が見えてきます。
まずは、定型業務と課題解決業務の違いを説明し、その後それぞれについて解説します。
仕事には「定型業務」と「課題解決業務」の2種類がある
それぞれを解説します。
定型業務とは?
誰がやってもほぼ同じ成果となる業務
いわゆる単純作業や、決まったルーティン業務のことです。
例えば、交通費伝票の作成、各種申請書の作成、毎日行うデータ入力などが代表的です。
誰がやっても同じ成果となる(=できないと問題になる)業務であり、マニュアル化が可能な業務と言い換えることができます。
課題解決業務とは?
定型業務以外のすべての業務
仕事の本質は、課題解決です。
どんな仕事にも、ありたい姿と現状のギャップである問題が沢山あります。課題とは、問題の中で解決すべきものです。そして、この課題をどのように解決するかが仕事なのです。
(仕事の本質の詳細は、仕事の本質を分かりやすく解説!なぜ仕事が必要?なぜ給料が違う?を参照)
「定型業務」で仕事が覚えられない原因
・マニュアルがない場合は「会社の問題」
・マニュアルがある場合は「皆さんの問題」
定型業務が覚えられない場合は、マニュアルがあるかないかで判断が変わります。
マニュアルがない場合は、業務を覚えられないのは会社の問題です。あわせて、マニュアルがあっても不完全な場合も会社の責任です。
ちゃんとしたマニュアルがあるのであれば、皆さんの問題です。
対策はたった1点。マニュアル通りにやることです。こうした方がいいなどと感じても、まずはマニュアル通りにやりましょう。
そうすれば、仕事内容は覚えなくても、できるようになります。
改善提案等は、できるようになってからおこないましょう。そうすることで、自分で実際おこなった経験を生かした提案ができます。
課題解決業務で「仕事を覚えられない」理由
・やったことのある方法しかできないから
・教えてくれる人が人に教える経験値が多くない
課題解決業務で仕事を覚えられないのは上記2点が原因です。
それぞれを解説します。
やったことのある方法しかできないから
誰もが経験することですが、一度教えてもらったことを次に自分でやってみようとしたときに、うまくいかないことはよくあります。
これは、やり方だけを覚えているため、少しでも状況が変わると応用が利かなくなるためです。
たとえ同じ内容でも、手順を一つ間違えるだけで結果が変わってしまうこともあります。
「目的を理解して対応しよう」とアドバイスされても、目的と具体的な対応策が結びつかないからこそ困っている、という声もよく聞きます。
教えてくれる人が人に教える経験値が多くない
新人に色々と教えてくれる教育担当は、自分とあまり年の離れていない先輩が担当することが多いでしょう。
ということは、その先輩自身も「人に教える経験値が多くない」と言えます。
さらに、その先輩が課題解決業務において、どこまで深く理解しているか疑問に感じることもあるかもしれません。
つまり、「ちゃんと教えてもらえないから、できるようにならない」という状況も少なからずあるのです。
仕事が覚えやすくなる方法
定型業務と課題解決業務に分けて解説します。
定型業務で仕事が覚えやすくなる方法
・マニュアル通りやる
・マニュアルを作る
定型業務はマニュアルがあれば、何も考えずにマニュアル通りやることです。
マニュアルがない場合は、自分でマニュアルを作るしかありません。
教えられたことをメモしても後から見返すと「結局どうすればいいんだ?」となるのは、それがマニュアルになっていないからです。
しかし、大掛かりに考える必要はありません。教えられた内容をそのままメモするのではなく、作業の手順を軸に業務を文章化していくのです。
注意すべきは、作業途中で発生する手順の分岐をしっかりと洗い出し、記載することです。
そして、「こうすればもっと良くなる」と感じたことがあれば、実際に検証し、本当に改善できるのであれば会社に変更提案をしてみましょう。これは、後述する課題解決業務への第一歩となりま
課題解決業務で仕事が覚えやすくなる方法
今は気にしない、2年後ちゃんとできてると考える
大小様々な課題解決業務がありますが、こればかりは経験を積まないとできるようになりません。
なぜなら、全く同じ課題解決の場面に出くわすことはほとんどないからです。
ただ、さまざまな課題解決経験を積むことで、業務の抽象化ができ、経験しないことでもこうやればできるとイメージできる時期が必ずきます。
まるでバケツに水が溜まるように、経験を積み重ねていくと、それが満杯になって溢れ出した時に、突然「できる」ようになるイメージです。
すぐに結果は出なくても、ある時を境に一気にできるようになる感覚を掴めるはずです。
ただ、より早くこの時期をむかえる方法はあります。
以下の2点を日々おこなうことです。
・知識を沢山インプットしつつアウトプットする
・常に業務の目的を意識
それぞれ解説します。
知識をたくさんインプットしアウトプットする
得た知識を自分で使える能力に変えるには、まずはたくさんの知識を得ること、そして得た知識を実際の業務で使うことが大事です。
ビジネス知識は、先人たちがビジネスを行う中で築き上げてきたノウハウの宝庫です。これらを積極的に獲得しましょう。
また、インプットした知識を使うとうまく使えないことがあります。これは、まだ知識が「能力」に変わっていないことがわかることで能力にできるきっかけとなります。
(詳しくは、「知識と能力とスキルの関係」をわかりやすく解説を参照)
インプットとアウトプットの方法には
・ビジネス関係書を読むこと
・文章を書くこと
この2つがおススメです。
ビジネス関係書を読むことで知識を大量に深くインプットでき、文章を書くことで知識をアウトプットできます。
文章を書く際は、長文(3,000文字以上)と要約文(140文字程度)の2種類を意識することをおすすめします。
長文はブログ記事として、短文はX(旧Twitter)への投稿として実践してみるのが良いでしょう。
(詳しくは、社会人の勉強法として「おすすめするたった2つのこと」をわかりやすく解説を参照)
常に業務の目的を意識
業務には必ず目的があります。
業務の進め方や「やり方」を教えてもらうことが多いと思いますが、その「やり方」には必ず目的や解決すべき課題が前提にあります。
これらを理解しておくことで、自分で新しい方法を考える際に、的外れな案を出してしまうリスクを大幅に減らせます。
さらに言えば、教えてくれる先輩自身が、その業務の目的を明確に理解していないケースも少なくありません。
もし、誰に聞いても目的がはっきりしない業務であれば、それはあなた自身が「そもそもの目的」を考えてみるチャンスです。こうした思考を重ねることで、あなたのスキルは格段に向上します。
会社には、このような目的が誰もわからない業務が沢山あります。
(目的の大切さは、打ち手を考える前に必ず必要なたった一つのことを参照下さい)
まとめ
今は気にしない 2年後できてる
時間がたてば仕事を覚えられない問題は解決します。そのスピードを速くするかどうかは努力となります。
他にも社会人の悩み「よくある悩みと対策」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。