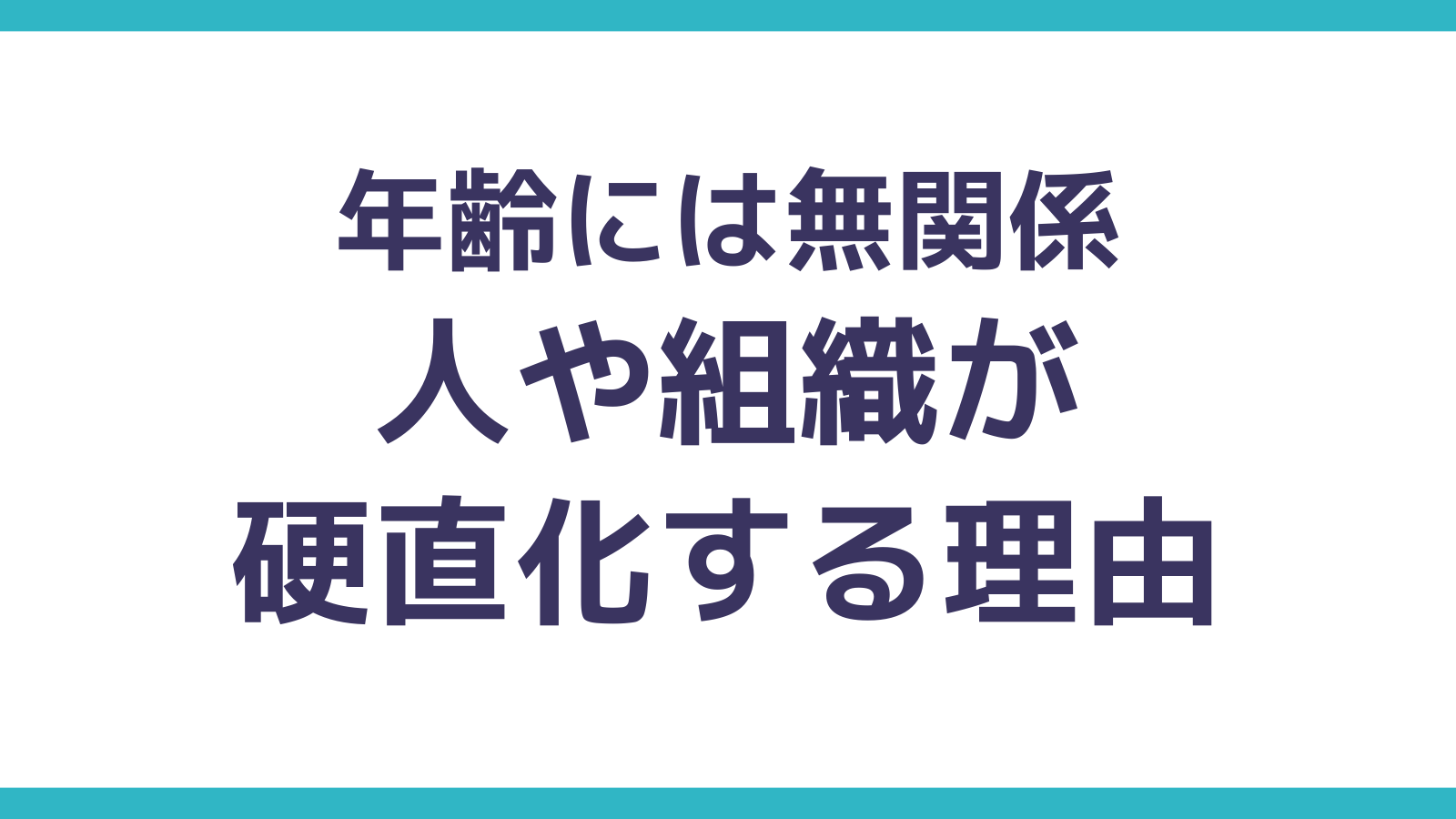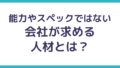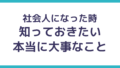思考が硬直化しているかどうかを自分で判別できるでしょうか?
かなり難しいことです。単に頑固なのか、融通が利かないのか、あるいは意思が固いだけなのか、自分では判別しづらいものです。
ただ、人や組織の思考が硬直化すると、変われない、新しいことを受け付けない、自分本位・会社本位になるなどの現象が起こります。
常に変化している外的環境に適合できず、人や組織の衰退の直接な原因になります。
更に悪いことは、一度硬直化すると治りにくいことです。
では、なぜ人や組織の思考が硬直化するのでしょうか?
この記事では、思考の硬直化の原因をわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
この記事を読むと自分自身や働いている会社の硬直化具合がわかります。
(あわせて読みたい【自己成長】定義から効率的な学びの方法を紹介)
人や組織の思考が硬直化する原因
変化しない環境に身を置いているから
したがって、年齢には関係なく硬直化します。
原因は、
・脳の思考方法には癖がつきやすい
・脳の特性上思考の自動化が起きる
上記2点の脳の特性により、長く同じ環境にいると、癖や自動化が強固になり思考が硬直化します。
また、組織は人の集まりなので、働く人が硬直化すれば当然組織も硬直化します。
脳を働かせるには、非常に大きなエネルギーが必要です。そのため、普段はできるだけエネルギー消費を抑えようとするのが人の脳の特徴です。
したがって、慣れた環境においては、上記2つの特性によってさまざまなことに対応できるようになっています。
よく言われる、脳を通さず考えるという状態は、人間の強みであると同時に、弱みにもなり得ます。
ただ、硬直化は誰にも訪れます。これは人として避けられないことですが、人により異なるのは、硬直化が早く訪れるかどうかです。
確かに高齢の方が硬直化しやすいですが、若くても硬直化している人も多くいます。
今まで、5社で働いて、数千人の方と直接接点を持って仕事をしてきましたが、20代でも硬直化している人を多く見てきました。
思考が硬直化する上記2つの原因をわかりやすく解説した後に、硬直化を遅らせる方法を紹介します。
脳の思考方法には癖がつきやすい
同じ手順で考えるようになる
ゼロから考え方を生み出すことと、過去に使った考え方ではどちらが楽でしょうか?当然後者です。
当然対処すべき内容により、答えの出し方は変わってきます。
ただ、私たちは、日頃沢山の対処すべきことに追われます。その中で、過去に使ったことがある考え方を使うことで、脳に負担をかけずに対処できます。
また、ある考え方がうまくいくと、その考え方を使いがちになります。
所属する会社等の組織の影響も受けます。組織ごとに考え方の癖があり、それが移るのです。
脳の特性上思考の自動化が起きる
過去の経験から自動的に同じ答えを出す
ある一定期間同じことをしていれば、慣れてきて楽になります。
理由は、経験値が上がることで、さまざまことに簡単に対応できるようになるからです。
その上、更に同じ環境に居続けると、脳を使わずとも、自動的に答えを出すことができるようになります。
過去の経験から答えがわかるからです。
同じ環境にいればいるだけさまざまな経験を積み、自動化できる内容が増えていきます。
とても素晴らしい能力ですが、行き過ぎると自動化のみで対応しがちになります。
2つの原因からわかること
短期的には良いが、中長期では問題となる
2つの原因からわかることは、同じ環境に居続けることで、考え方が固定しやすいことと、答えの自動算出ができるようになることです。
仕事を回す上ではとても重要なことで、間違いなく効率が上がるだけでなく、正しい答えを出しやすくなります。
ただ、問題があります。外部環境は必ず変わってしまいます。
結果、今までの考え方や自動算出した答えが使えなくなる時がくることです。
答えが変わっているのに、それに気づかずに同じ考え方を使い続けるのです。
皆さんの会社のベテランさんにいませんか?昔の方法にこだわって、今の時代に合わないのに変えようとしない人が。
特に経営や上司にいれば、その方法を変えることができないので困ります。
本来、方法は課題や目的を達成するための手段ですが、課題や目的は忘れられてしまい、そもそもの議論ができずに方法に従わざるを得なくなることが起きるからです。(または、手段が目的化してしまうのです。)
したがって、短期ではとても良いことですが、中長期では悪いことになります。
硬直化を自覚する方法
人の話を一旦受け止めることができるか?
これができているかどうかで、ある程度自覚できます。人の話を聞くことは、癖や自動化が起きている脳が反発を起こすことが多々あります。
会話しているのに、相手が話を聞いてくれていないと感じることがあると思います。この逆のことが起きています。
間違っていると話を拒絶したり、会話の途中に反論するなどの行動をしてしまうことが受け止められていない典型的なパターンです。
癖や自動化の気持ちいい状態を崩されることが、受け入れられないのです。
硬直化を遅らせる方法
変化し続ける
人や組織の硬直化を防ぐ方法は上記の通りシンプルです。ただ、脳の特性から常に変化を意識する必要があります。
具体的には下記2つが変化し続ける方法です。
・環境を変える
・知らないことを知る、おこなう
それぞれ解説します。
環境を変える
一番手っ取り早い方法
強制的に環境を変えてしまう方法です。他の部署に異動する、転職するなどがわかりやすい方法です。
新しい知識や方法などを得ないといけませんし、初めて会う人ともコミュニケーションを取らないといけません。
自分で意識しなくても、環境が変われば変化しないといけないので、ある意味楽な方法とも言えます。
もし、そこまでできない場合は、趣味などのプライベートで新しいコミュニティに入る等でも、同じ効果を得ることができます。
知らないことを知る・おこなう
新しい知識を入れ続ける
今知らないことを知る、今やっていないことをやることで変化することができます。
新しい知識を得ることで、今のやり方を変えるきっかけになりますし、そのきっかけを元に行動することで、初めておこなうことができます。
本を読むなどが最適です。
ただ、ネットのリコメンドには注意してください。ほとんどのSNSや動画は過去の閲覧情報から興味があるものをおススメとして提示してきます。
これにより、変化するに至らない情報しか得ることができなくなるので、まったく違うテーマで検索するようにしましょう。
ビジネスに役立つおススメの本を4領域13のテーマでまとめた記事を書いています。
詳しくは、何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介を参照下さい。
変えることに対する疑問
定期的に変化し続けることは理解していただけたと思いますが、さまざまな疑問が沸いている方もいると思います。
代表的な質問に回答します。
専門知識の習得が中途半端になるのでは?
この質問に関しては、専門知識をどこまで得たいですか?に対して自分なりの答えを持つ必要があります。
簡単には答えることができない質問です。
同じ問いを別の言い方で聞くと、あなたはゼネラリストとスペシャリストのどちらを目指していますか?という質問になります。
人により答えは変わりますが、どちらを目指すかによって、専門知識をどこまで得るかが変わります。
当然スペシャリストを目指すのであれば、かなり深い知識とその分野での能力が必要です。
ただ、ゼネラリストを目指すのであれば、ひとつの深い知識よりも、さまざまな仕事を経験する方が将来の役に立ちます。
まずは、どちらを目指すかを決めることができれば、おのずと答えが出ます。
スぺシャリストとジェネラリストについて書いた記事があります。
詳しくは、たった2ステップ キャリアプランの考え方をわかりやすく解説を参照下さい。
そもそも変化する必要があるか?
個人の判断によりますが、私自身の経験から言えば、変化しないことのデメリットを多く見てきたため、変わることをお勧めします。
5社で働いているので、同じ仕事で同じ担当業務を10年以上やっている人をたくさん見てきました。
多くの人は、本人が持っているポテンシャルに見合った能力を得ていません。
新しく知識を得る機会が少ないからです。
本人が高い意識を持ち続ければいいのですが、私を含めて多くの人はできません。
さらに長く時間がたってしまっていると、本人自ら新しい部署や職場へチャレンジすることに対しても躊躇します。
その上、上司も異動させることに躊躇します。他部署でやっていけるか心配だからです。
結果、ポテンシャルに見合った能力を得る機会が少ないまま、年齢を重ねてしまうことになります。
それでもいいのであれば、その道を選ぶのも自己判断ですが、そうなりたくなければ変化することをおススメします。
変えるタイミングは?
質問された多くのことに答えることができると感じた時、条件反射で答えを出せる状態になったら、環境を変えるタイミングです。
知っていることが武器にはならない時代ですし、学べることが減るからです。
(詳しくは、仕事で環境を変えるベストなタイミングとは?を参照)
変化することにいつかは慣れますか?
考え方の固定化と自動化を逆に活用することで慣れます。
最初はしんどいですが、変わり続けると、変わり続けることがスタンダートになります。
脳は優秀です。
人や組織の思考が硬直化する原因の「まとめ」
人や組織の思考が硬直化するのは、
変化しない環境に身を置いているから
原因は、
・脳の思考方法には癖がつきやすい
・脳の特性上思考の自動化が起きる
上記2点の脳の特性により、長く同じ環境にいると、癖や自動化が強固になり、思考が硬直化します。
したがって、年齢に関わらず硬直化します。
気を付けても、気づかないことも多いため、明確にスペシャリストを目指したい人以外は、環境を定期的に変えることをおススメします。
転職のことを詳しく知りたくなった方へ
転職には知識とノウハウが必要です。たくさんの要素を総合的に判断しなければなりません。
まずは、以下の記事を参照下さい。
他にもキャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録して相談してみるのもおススメです。
登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。
他にも自己成長の「定義と効率化」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
- 「成長とは?成長する方法とは?」
- 少しの工夫で「成功体験」を積む方法
- 「成長しているかどうか」の自己チェック4つの方法
- 徹底的に「真似る・パクる」
- 「知識を得るコツ」 深狭?広浅?
- お金・時間を使う際「投資かコストか」を意識する
- 「ブラック企業減」が、人の成長のブラック会社を増やす理由
- 「自分で自分をほめる」方法
- 同じ時間で「多くの業務経験」が積める方法
- 歴史「を」学ぶではなく、歴史「に」学ぶ
- 人や組織が「硬直化する理由とは?」
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。