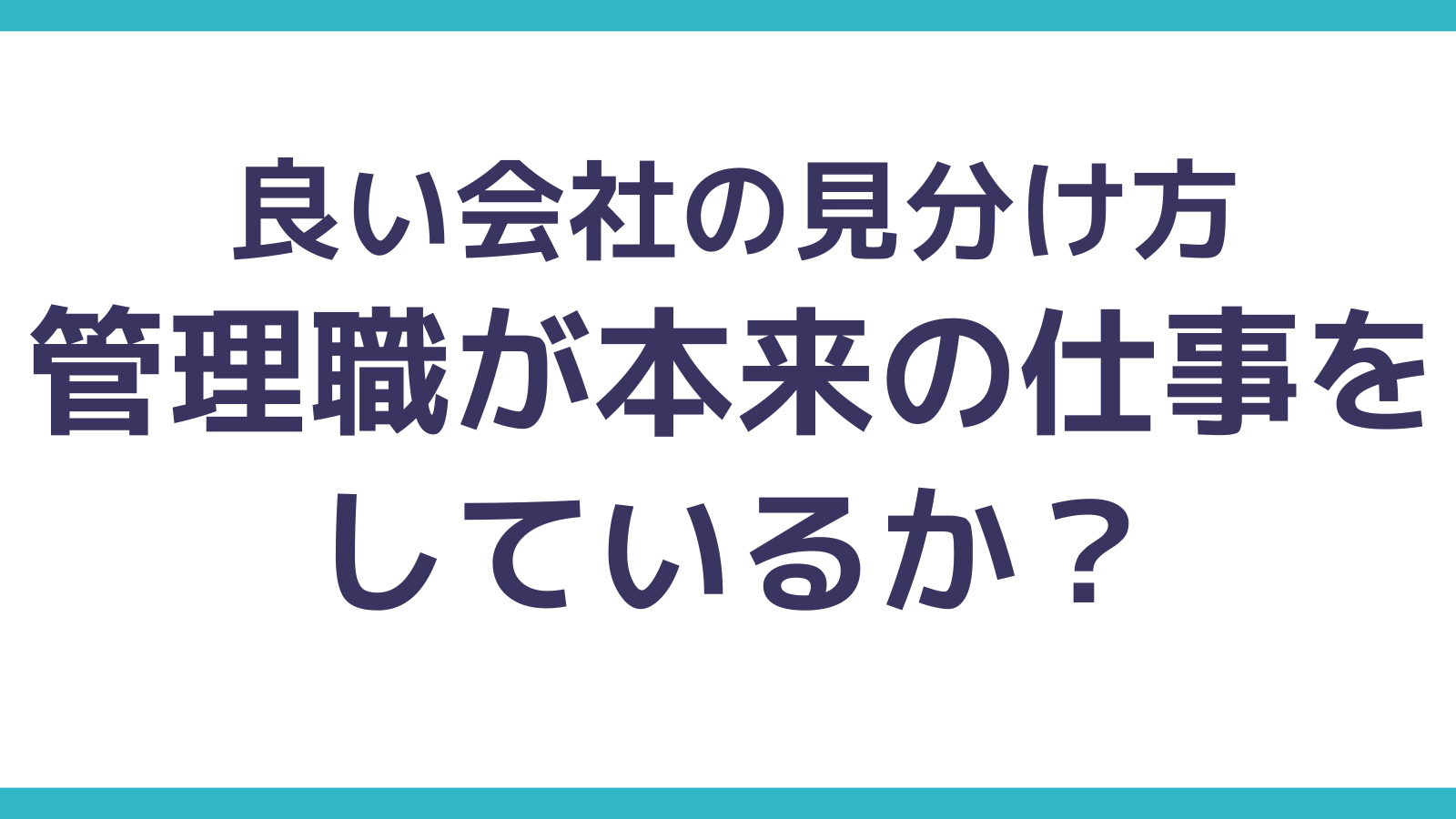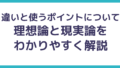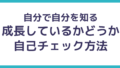皆さんの会社では、管理職の皆さんが本来の管理職の仕事をしていますか?
この質問に明確に答えを出せる知識を持っていると、今働く会社が良い会社かどうかがわかります。
良い会社には必ず良い管理職がたくさんいます。そして、その管理職のサポートを受けて皆さんが成長します。
また、管理職になったら、同じ方法で部下に向き合います。
良い会社はこの好循環がまわっているのです。
この記事では、皆さんの上長である管理職の方が、本来の役割を果たしているかどうかを判断するためのポイントをご紹介します。
好き嫌いで判断されがちですが、この視点で判断することで管理職の良し悪しだけでなく、会社の良し悪しもわかります。
この記事は、筆者「よしつ」が持つ以下の実務経験や知見に基づいて執筆しています。
・営業担当から執行役員まで、様々な役職での実務経験
・企業文化の異なる5社での実践経験
・数百名規模のチームマネジメント経験
・数千社におよぶ顧客への営業経験
・100回以上の研修・勉強会での講師経験
(あわせて読みたい【会社の環境】良い会社の特徴)
管理職が本来の仕事をしているかの判断方法
・管理職の本来の仕事を知る
・できているかできていないかを判断
・できていない場合の問題点を把握
上記の流れで見ることで、良い会社かどうかだけでなく、良い会社でない場合何か問題なのかを判断できます。
それぞれ解説します。
管理職の本来の仕事とは?
・担当する組織を通じて最大の成果を出す
・担当する組織力を上げる
この2つが管理職の仕事です。
課長は課内の課員が対象となり、部長は部内の課長及び課員が対象となります。
管理職の仕事とは?と検索すれば、「部下を指導・管理し、組織の運営を円滑に進めること」という内容の文言が多くみられます。
確かにそうですが、何のために部下の指導等おこなうかと言えば、「最大の成果を出すこと」と「組織力を上げること」が目的だからです。
打ち手には必ず目的があります。目的に立ち返って理解することがとても大事な例です。
このように考えないと、手段実行することが目的となる「手段の目的化」が起きてしまいます。
(手段の目的化の詳細は、「手段の目的化」の原因と対策を具体例を含めて解説を参照)
ちなみに一般社員の仕事は、以下2つです。
・自分の力を使って最大の成果を出す
・自分の力を上げる
管理職と基本同じですが、自分以外の社員を含めるのか、自分だけなのかの違いです。
一般社員と違い、管理職の仕事の難易度が大きく上がるのは、他の人に行動してもらう必要があるからです。
担当する組織を使って最大の成果を出す
自分が所轄する組織に働きかけ、動いてもらうことで、売上やコスト削減等の目標を実現することが業務となります。
組織の方針や戦略を立案し、最適な業務分担を行い、メンバーに行動を促します。成果がでなければ問題を突き止めて解決する一連の業務となります。
担当する組織力を上げる
もう一つは、組織全体の力を高めることです。
組織力とは、「個人力」×「個人以外力」の掛け算です。
「個人力」を上げる方法と、商品力、ブランド力、集客力などの「個人以外の力」を上げる方法に分けることができます。
一般的には、前者の「個人力」に注目が集まりがちですが、後者も組織力を上げる上で非常に重要な要素です。
(組織力の詳細は、組織力とは?「個人力」と「個人以外力」に分けてわかりやすく解説を参照下さい)
所属する個人の力を上げるのか、個人以外の力を上げるのか、あるいはその両方かを選択し、施策を立案・実行する業務です。
これら2つの本来の仕事をどのようにおこなうかが、管理職には求められています。
できているかできていないかを判断する
・所属組織で結果が出ているか?
・皆さんが成長できているか?
この2つが同時に実現できているかで判断できます。それぞれ解説します。
所属組織で結果が出ているか?の判断基準
所属組織で結果が出ているかの判断は、全社や事業部で「増収増益」ができているかが第一のポイントです。
第二のポイントは、所属する組織(課とグループなど)の目標が達成できているかどうかで判断できます。
営業部門はもちろんですが、スタッフ部門でも目標が達成できているかで判断します。
スタッフ部門で目標がなければ、結果を測定できないため、成果が出ているかどうかが分かりません。
したがって結果が出ていないと判断します。
皆さんが成長できているか?の判断基準
・この半年でどれ位の課題を解決しましたか?
・できないことが上司のサポートを受けてできましたか?
この2つで判断できます。それぞれ解説します。
この半年でどれ位の課題を解決したか?
仕事とは課題解決です。課題の大小に関係なく各従業員には課題解決が求められます。
(詳しくは、求められる人材とは?を参照)
その課題解決をどれくらいできたかで判断します。
具体的な回数は会社の業務内容によって異なりますが、小さな課題解決も含め、複数回の経験があることが望ましいでしょう。
なぜなら、成長するためには、「時間当たりの課題解決経験の多さ」が必要だからです。
(詳細は、20代で一番大事なことは「時間当たりの課題解決経験の多さを参照」
できないことで上司のサポートを受けてできたか?
上司のサポートを受けて以前はできなかったことができるようになった事例や、新たに任された業務を遂行できた事例で判断できます。
前者は判断しやすいと思います。後者は、上長があえてその仕事を振ってきたかどうかで判断できます。
一般社員への仕事の割り振りは管理職の仕事です。
新しい経験を積ませるために、あえて難易度の高い仕事を任せることも、上司の意思決定であり、部下育成のサポートの一環だからです。
上記の両方実現できていれば、管理職が本来の仕事をしている良い会社と言えます。
ただ、これらは難易度が高い内容ですので、「はい」と断言できなくても、管理職がこの2点を意識して業務に取り組んでいると感じられる場合は、一定の評価はできるでしょう。
次第点にもならない場合は、残念ながら、良い会社とは言えません。
できていない理由ごとの問題点
会社の問題と個人の問題に分けて、それぞれ解説します。
会社の問題でできない
会社側の理由で管理職が本来の仕事ができていない場合、主に以下の3つの問題が考えられます。
・役職が不明確
・全社戦略の問題
・制度設計の問題
これらはすべて会社組織の問題であり、経営層が適切な判断や整備を行わないことによって発生します。
それぞれを紹介します。
役職が不明瞭
管理職は2つに分かれます。部下を直接持つ管理職と持たない管理職です。
全社は社長・部長・課長という役職です。後者は、部長代理、専任部長、次長、課長代理などの部下を直接持たない管理職です(会社により役職名は違う場合あり)。
年功序列やポストの固定化により、仕事の有無に関係なく管理職が配置されている場合に多く見られます。
「肩書をつけるためのポスト」になっており、実態は権限も責任も曖昧です。
部下を持たないため、部下育成やチームを通じた成果創出といった、本来の管理職の仕事を行うことが難しくなります。
このようなポストが多い会社は、組織の分業が明確でなく、役割が不明確になります。
現場や経営層に業務が集中し、中間管理職が形骸化している場合が多く見受けられます。
また、プレイングマネジャーと呼ばれる、現場業務と管理業務を兼務する役職もあります。
業務量がとても多くなり、どちらの業務も中途半端か、もしくは、慣れた現場の仕事に注力し、管理職の仕事はあまりしない状態になります。
そもそも分業体制に無理があるパターンです。
分業体制の全体設計は経営者か事業責任者の仕事です。
このレイヤーの人たちの考え方が変わらないとこの問題は解決しません。
全社戦略の問題
全社戦略が存在しない、あるいは非常に抽象的であるケースです。
会社組織の本質は、ひとりでできないことができるようになることです。
そのために分業をおこないます。
分業とは、社長が目指すことを分解し、下の役職に権限を委譲し、さらにその下の役職へと業務を段階的に委譲していくことです。
結果、ピラミッド状の三角形が形成されます。
このピラミッド構造が機能するためのポイントは、会社として「やりたいこと(目標)」が明確であり、それを実現するための分業体制が適切に設計されていることです。
したがって、全社戦略がないもしくは抽象的だと分業設計が曖昧になり、管理職の方の業務目標が不明確になります。
結果として、従業員の力が結集されず、皆がそれぞれ頑張っていても会社全体としての成果が出ない、という状況に陥ります。
全社戦略は経営者が作り判断する必要があります。
つまり、経営者が経営に対して真摯に向き合い、戦略を明確にするという意識改革が必要になります。
制度設計の問題
組織オペレーションの仕組みが貧弱なので、やることが明確になったとしても、どこまでやれば目標達成なのかが不明確になる場合があります。
代表的な組織オペレーションの仕組みは人事評価制度です。
組織で働く人は、結果を出す、または結果をサポートするために行動します。これを評価するのが人事評価のコアです。
したがって、結果と行動の両面で評価することが基本ですが、各社の考え方で比重が変わります。
また、学校の試験のように全員が同じ環境・同じ問題・同じ目標で業務を行うわけではないため、同じ役職や職階の人々を公平に評価できるような目標設定が不可欠です。
しかし、各個人や各部署の目標の難易度を適切に調整することは非常に難しい課題です。
この難しい問題にどこまで向き合うかで人事評価の良し悪しが決まります。
各個人の業務内容や目標が曖昧な場合、会社が人事評価制度という非常に重要な仕組みの構築を軽視している可能性があります。
管理職の本人の問題でできない
管理職本人の理由で、本来の仕事ができていない場合には、主に以下の2つの理由が考えられます。
・管理職としての適性がない
・管理職業務の理解の欠如
多くは管理職に向いていない性質と本人の学ぶ努力不足です。
個人の問題が主ですが、任命した組織の問題でもあります。
それぞれを解説します。
管理職としての適性がない
代表的なパターンは、以下の3つです。
・他者への関心が薄い
・自分一人で完結する業務を好み、チームで何かを成し遂げることに関心が薄い
・自己中心的な考え方
そもそも、人の上に立つと本人も周りも苦労する特性を持った人を管理職に任命することが問題です。任命する会社の責任でもあります。
このような人は仕事の相談をすればほぼ見分けがつきます。
部下が相談しても教えてくれなかったり、パソコンを見たまま目も合わせずに対応したり、反対に質問攻めにして相談にならなかったり、いきなり結論だけを押し付けたりするなどの対応が見られます。
管理職業務の理解の欠如
代表的なパターンは、以下の3つです。
・業務の根本的な理解不足
・学ぼうとする姿勢の欠如
・マネジメントされた経験の不足
そもそも管理職とは何をする役割なのかを真剣に考えておらず、学ぼうとする姿勢も見られない人も少なくありません。
このような考えの人が管理職になると、プレイングマネジャーでない限り、本来行うべき管理業務をしないため、結果として時間を持て余してしまうことがあります。
現場仕事がなくなるが、管理職の仕事をしないからです。
上記で紹介した本来の管理職の仕事をするととても時間もかかりますし、考えないといけないことも多くなります。
しかし、本来の管理職の仕事内容を理解していないため、それらを実行することができません。
その状態に不安を感じる人もいますが、その方の典型的な行動パターンが慣れ親しんだ、現場の仕事をすることです。
これにより、本人は「仕事をしている」という感覚を得られるため一時的に満足してしまい、管理職としての成長が止まるという悪循環に陥ります。
本来であれば、さらに上位の管理職が指導すべきですが、その上位管理職自身も本来の管理職の役割を理解しておらず、指導できないケースも見られます。
また、本来のマネジメントを一般社員の時に経験していないことも要因となります。体験していないのでわからないのです。
このような会社で働いていると、皆さんが管理職になった時に同じことが起きます。
環境を変えることを考える必要もあります。
まとめ
・管理職の本来の仕事を知る
・できているかできていないかを判断
・できていない場合の問題点を把握
上記の流れで判断することで、良い会社かどうかだけでなく、良い会社でない場合何か問題なのかが判断できます。
管理職の仕事は、以下2つです。
・担当する組織を通じて最大の成果を出す
・担当する組織力を上げる
これらの視点から、今の上司や経営陣の働きぶりを観察してみましょう。今までとは違った見方ができると思います。
他にも「良い会社の見分け方」で以下の記事を書いています。参照下さい。
転職のことを詳しく知りたくなった方へ
転職には知識とノウハウが必要です。たくさんの要素を総合的に判断しなければなりません。
まずは、以下の記事を参照下さい。
他にもキャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録して相談してみるのもおススメです。
登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。