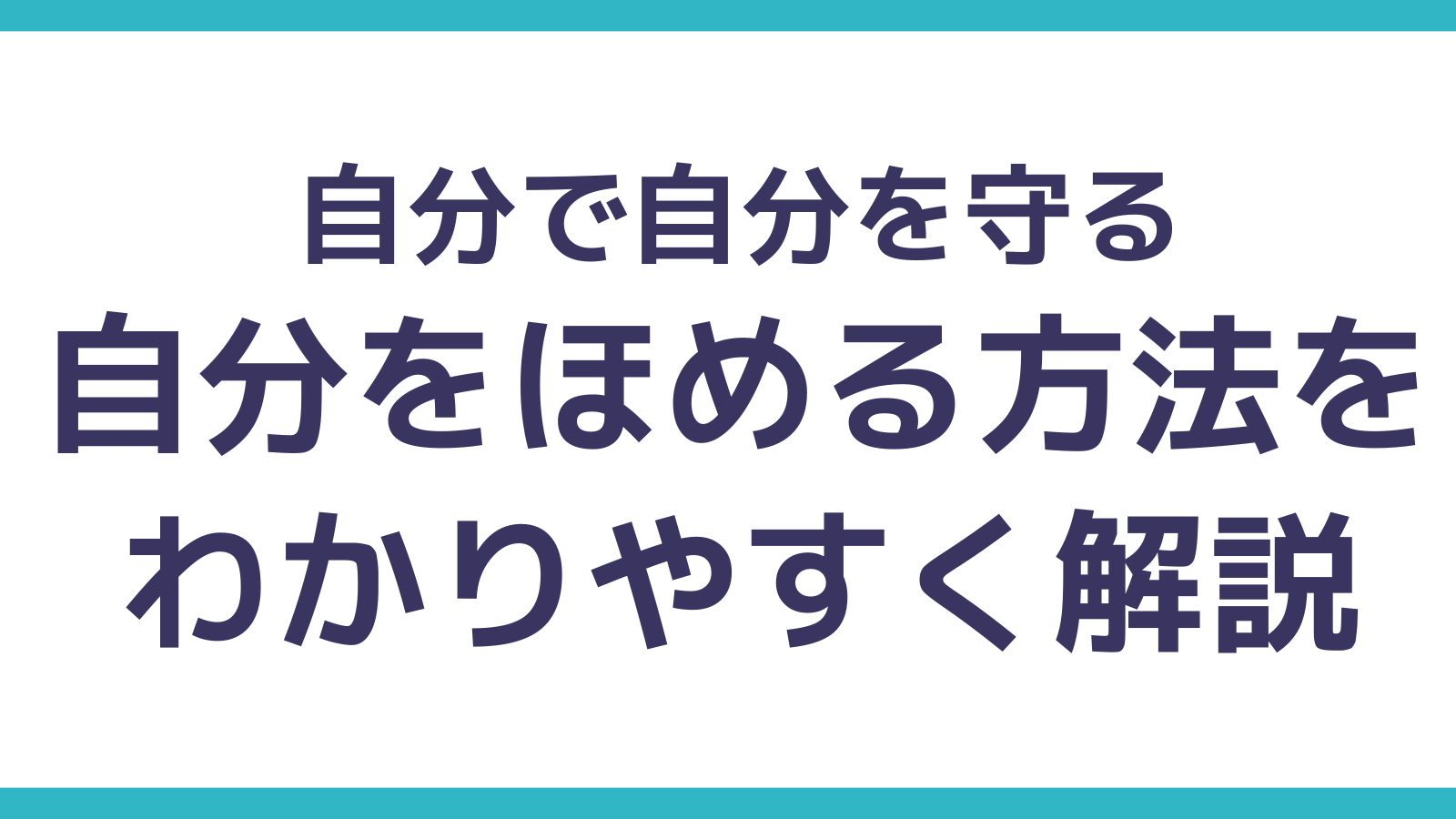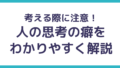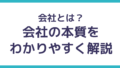テレワークの増加や飲み会の減少で、会社の人と深く関わる機会が減っています。
煩わしい人間関係がなくなる一方で、成長に欠かせない「褒められる機会」も減っているのが現状です。
褒められる機会が減ると、正しい自己認知ができなくなり、行動への意欲も薄れてしまいます。
では、どうすれば良いのでしょうか。それは、自分で自分をほめるしかありません。この記事では、少なくなった褒めを自分で補う必要性と具体的な方法についてわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【自己成長】定義から効率的な学びの方法を紹介)
自分で自分をほめる方法が「必要な理由」
・ほめられない方向に環境が移行している
・ほめられることが自分自身の成長につながる
ほめられない環境で褒められる回数を増やすには、自分で自分をほめる方法を習得することが必要です。
まずは上記2つを解説した後に、自分で自分をほめる方法を紹介します。
ほめられない方向に環境が移行している
物理的な距離と働く環境の変化とハラスメントの浸透
上司や先輩からほめられることでモチベーションが上がったり、改善のための具体的なフィードバックを受ける機会があることで、認知できていないことを知ることだけでなく、具体的な改善方法を知る機会になります。
時には指摘だけでなく叱られることもあるでしょう。
しかし、Web会議システムの発達によるテレワークの増加で、接点は1on1などの設定されたコミュニケーションが多くなりました。
これにより、上司や先輩が皆さんの良い行動を偶発的に見つける機会が減っています。
また、ハラスメント意識の高まりから、上司が部下との指導的なコミュニケーションを遠慮してしまうことも起きています。
結果、褒められることだけでなく、成長につながる指摘を受けることについても、心が動く深いコミュニケーションになりづらくなっています。
その上、このような環境で業務をおこなった人が上司になっていきます。当然、上司から指導の機会が少ないので、逆に立場になった際に、自分の経験を元にしたメンバーへの指導がしにくくなります。
(詳しくは、ブラック企業減が、「人の成長」に対するブラック会社を増やす理由を参照)
ほめられることが自分自身の成長につながる
ほめられることと成長の関係を解説します。
ほめられることの効能
内的モチベーションの向上と行動促進
ほめられることで、助言やアドバイスの様々なフィードバックを受け入れる状態となるだけでなく、自分で考えて行動することができるようになります。
これは、今まで5社でたくさんの人と仕事をしてきて痛切に感じることです。ちゃんとほめられて育った人の成長スピードとそうでない人の成長スピードには大きな差があります。
叱られるだけだと、叱られたくない気持ちで行動に自分で制限をかけます。
また、外圧で動かされた場合、外圧がなくなれば行動が止まってしまいます。
ただ、ほめられることで、自分自身で動く「内的モチベーション」が高まります。
前向きな行動量が増えることで、たとえ失敗しても、それを前向きに捉えて改善できるようになります。
こうした経験を積み重ねていくことこそが、成長スピードが上がる何よりの理由なのです。
ほめられることが成長につながる理由
・できないことがわかり、出来るようなるきっかけとなる
・出来ていることを認知し、自信を持って行動できる
・逃げている課題に向き合うことができる
この3つが成長につながる理由です。これらの起点となるのが、すべてほめられることなのです。
それぞれを説明します。
できないことがわかり、出来るようなるきっかけとなる
自分の行動を客観的に見てもらい、自分の認識していないできていない部分を指摘してもらうことで、気づかなかったことを気づくことができます。
気づけば対策が打てますので、できるようになる可能性が上がります。
出来ていることを認知し、自信を持って行動できる
できているが自分ではできていないと感じることや、無意識・無自覚でできていることを自覚することがとても大事なのです。
すでにできている自分の行動を認知することで、その行動をおこなえばできるとわかり、再現性が上がり、自信をもって行動できます。結果、更にできるようになります。
逃げている課題に向き合うことができる
出来ていないことを認知しているが、そのことに向き合えていない=逃げている状態は多くあります。
ただ、このようなことに対しても、ほめられることで得ることができる「内的モチベーション」により、向き合うことができるようになるので、出来るようになる可能性が格段に上がります。
自分で自分をほめる「具体的な方法」
今の環境の中で、ほめられる機会を増やすには、自分で自分をほめるしかありません。そのために、2つの方法を紹介します。自分で自分をほめる内容を自分で把握することと、自分で自分をほめてあげることが大事になります。
ほめる内容を自分で把握する
結果につながる行動(プロセス)を数値目標化する
とにかく自分の行動と結果を数字で把握することです。
ここで大事なのは、結果だけを数字で捉えないことです。
結果はあくまで最終地点です。結果を出すためには行動が不可欠です。そのため、行動量を数字で捉えるようにします。結果は様々な要素が絡みますが、行動は自分で管理できます。
結果がすべてであり、プロセスを軽視する意見もありますが、これは若手を間違わせるアドバイスだと私は考えます。
確かに結果は大事ですが、新入社員や若手の内は、圧倒的に結果につながる行動を学ぶ必要があります。なぜなら、仕事は長距離走なので、安定して結果を出す必要があり、そのためには結果ができプロセスを知っておく必要があるからです。
その行動となる結果を出すためのプロセスを数値目標化するのです。そうすると、できたかできていないかを自分で把握できます。
例えば営業なら、1日〇件既存顧客のアポを入れる、新規に〇件電話する、などの行動を追い続けるのです。
1日5件の商談が可能だとすれば、1日5件既存顧客のアポを入れることにこだわります。
また、新規営業についても受注という結果でなく、テレアポ件数を決めるのです。必然と新規商談が入り、結果新規受注が増えます。
また、マーケティングの仕事をしているなら、上司に自分の担当領域の改善提案数を自分で決めて実行する。
総務の仕事であれば、社内フロア環境の改善提案数を自分で決めるなどです。提案数は実現された数の結果ではないプロセスなので、実行しようと思えばできます。
行動を数字で目標設定することで、出来たかできなかったかは自分で把握することができます。
結果、自分で自分をほめてあげる機会が増えるのです。
何か1年間継続する
継続が自信になる
何でもいいので1年間継続するという経験も大きな自信につながります。
私も含め、多くの人が大事にしたいのは、「コツコツ継続」です。
この継続こそが、誰もが再現性をもって大きな成果を出せる方法だと考えます。
ウサギと亀の話が示す通り、地道な継続は強力な武器になります。短期間で結果が出なくても、1年、5年、10年と続ければ、想像以上の高みに到達できるのです。
例えば、本を読む習慣でも、SNSやブログで毎日仕事に関する発信をするのでも構いません。
何かを1年間継続できる率は10%に満たないと言われています。
ということは1年続ければ、上位10%に入ることができます。
コツは先を見ずに毎日10分を継続です。できたら毎日自分をほめます。そして、1年立てば盛大にほめてあげます。
そうすれば、自分を毎日ほめてあげることになります。その上、1年間継続できる経験と自信と方法をつかむことができます。
自分で自分をほめる方法の「まとめ」
自分で自分をほめる方法が必要な理由
・ほめられない方向に環境が移行しているため
・ほめられることが自分自身の成長につながるため
ほめられることが成長につながる理由
・できないことがわかり、出来るようなるきっかけとなる
・出来ていることを認知し、自信を持って行動できる
・逃げている課題に向き合うことができる
上司や先輩からの手厚いサポートがあれば理想的ですが、残念ながら環境は変化しています。
だからこそ、「行動と結果を数値で把握する」「1年間継続する」という方法で、自ら褒める習慣を身につけてください。
皆さんには大きな可能性があります。その可能性を最大限に伸ばす起点は、「ほめる・ほめられる」という行為にあります。
さあ、ぜひとも自分で自分をほめ続け、成長の原動力を手に入れましょう。
他にも自己成長の「定義と効率化」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
- 「成長とは?成長する方法とは?」
- 少しの工夫で「成功体験」を積む方法
- 「成長しているかどうか」の自己チェック4つの方法
- 徹底的に「真似る・パクる」
- 「知識を得るコツ」 深狭?広浅?
- お金・時間を使う際「投資かコストか」を意識する
- 「ブラック企業減」が、人の成長のブラック会社を増やす理由
- 同じ時間で「多くの業務経験」が積める方法
- 歴史「を」学ぶではなく、歴史「に」学ぶ
- 人や組織が「硬直化する理由とは?」
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。