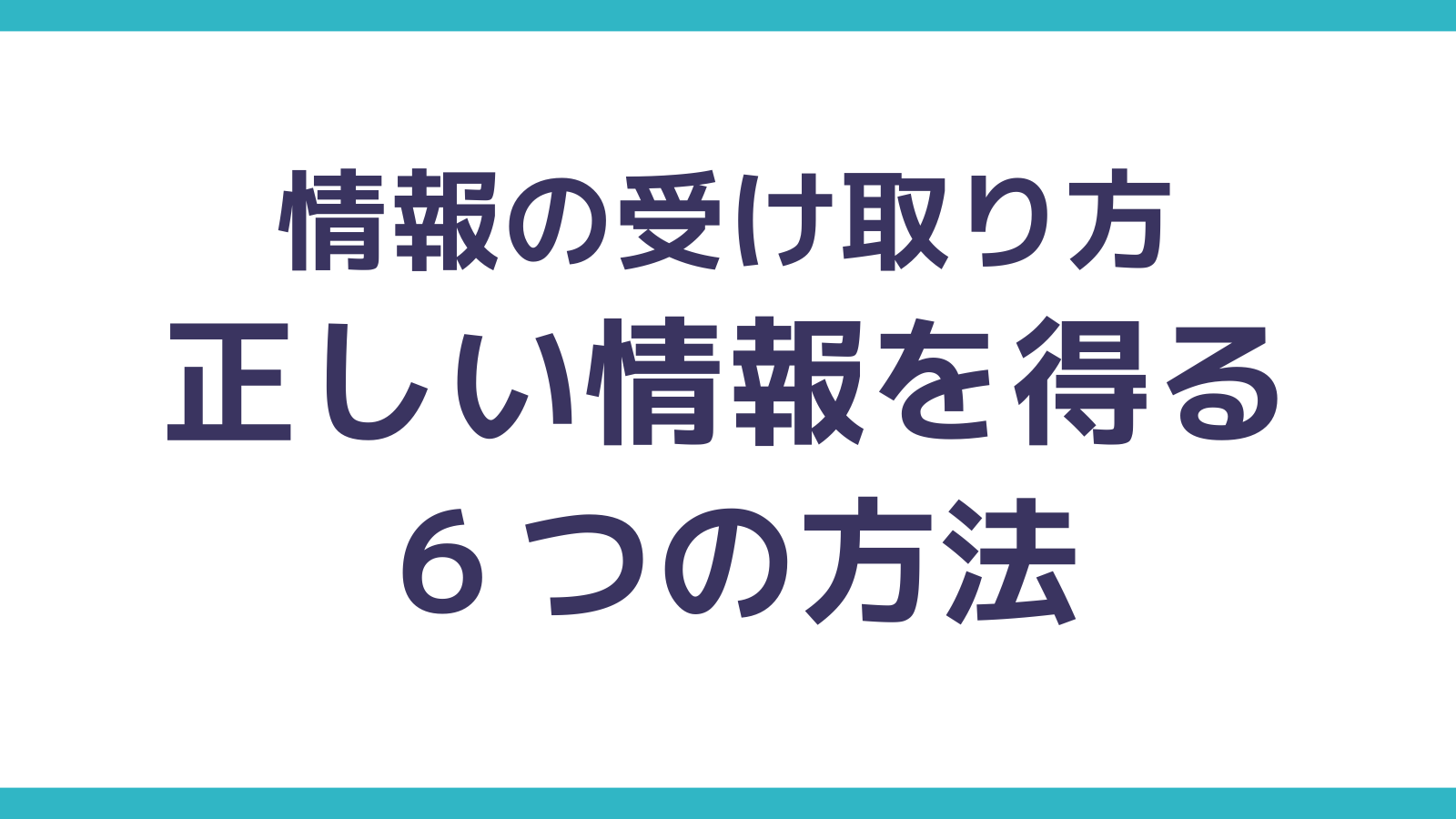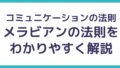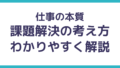TV、新聞、ネット、YouTubeなど、さまざまなメディアから毎日膨大な情報が流れてきます。
その情報を鵜呑みにして困った経験がある方は多いでしょう。
もしかすると、今あなたが信じていることが、実は正しくない情報かもしれません。
特にSNSでは、リコメンド機能によって関心のある内容ばかりが表示され、情報が偏りがちです。
このような情報の洪水の中で、正しい情報を見分けるスキルは必須です。
この記事では、情報過多の時代を生き抜くために、正しい情報を得るための6つの方法をわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション)
正しい情報を得る6つの方法とは?
・メディア情報がかたよる理由を知る
・ミクロとマクロを分ける
・目的か手段かを把握する
・事実・数字で判断する
・分子・分母を意識する
・分野ごとの第一人者をおさえておく
正しい情報を得るには、上記6つの方法ををおこなうことで、正しい情報を得る可能性が高まります。
それぞれを解説します。
メディア情報がかたよる理由を知る
情報発信者の儲ける手段で情報がかたよる
メディアや人が発信する情報の内容を受け取る際に、どのような儲け方をしているかを知っておくことが大事です。
情報を発信するということは、多くの場合対価を得ることを目的にしています。対価を得ることが出来ない情報は発信しなくなります。これにより情報のかたよりがおきます。
情報を得る手段である代表的メディアであるテレビ、新聞、インターネット(SNS、ユーチューブ含む)ごとに見ていきましょう。
テレビの収益化から見る「情報のかたより」
たくさんの人を集めることが最重要
テレビの主な収入源はCMです。そのため、多くの人に視聴してもらうことが最重要課題となります。視聴率が高ければ、広告主から高額な広告費を得られるからです。
結果として、テレビ局は公平性よりも、派手で人目を引く内容を放送するインセンティブが働きます。若者のテレビ離れが進む中、特に高齢者が好む内容を重視する傾向にあります。
また、広告主への配慮も存在します。広告主が問題を起こした場合、報道はするものの、その内容はオブラートに包まれ、しつこく繰り返し放送されることはありません。
更に、大手TV局でもリストラが行われている=経営状態が良くない状況なので、視聴率を獲得するために、上記の傾向に拍車がかかっています。
ここがテレビのかたよりのポイントです。
大事かつ重要なものではなく、人を引き付ける内容の情報を徹底的に繰り返し放送します。俗に言う「あおり」が多くなります。
新聞の収益化から見る「情報のかたより」
昔から新聞を購読してる高齢者がターゲット
新聞は、新聞自体の販売収入と、新聞内に掲載する広告と、新聞に挟まれているチラシの折込代が収入源です。
テレビと同じく、どれだけ沢山の人に見てもらうことができるか?で広告費の額が決まります。
沢山の人に購読してもらうことで、購読費及び広告費の売上が上がっていきます。
ただ、皆さんご存知の通り新聞はとても苦しんでいます。
日本新聞協会によると、発行部数は20年間で40%弱減っています。
ちなみに近くにいる20代30代の知り合いで、新聞を定期購読している人がいますでしょうか?ほぼいないです。
その結果、ほとんどの購読者は、昔から新聞を取っている高齢者の方がメイン購読者となっています。
ここが新聞のかたよりのポイントです。
当然記事内容も、高齢者が喜ぶ内容が主となることと、限られた紙面なので、どうしても説明量が少ない内容となります。
Webサイトの収益化から見る「かたより」
google検索で上位表示されることが最重要
ここでは情報の受取り方がテーマなので、情報を発信している企業サイトや個人サイトについて記載します。楽天等のECサイトは除外します。
Webサイトの基本的な儲け方は、自社ホームページに来訪してもらい、自社商品・他社商品(仕入販売)を購入してもらうことです。
その他では、来訪者への広告表示数や広告クリック数に応じた対価を広告主からもらう方法です。
どちらにしても自社のWebサイトに来訪してもらうことがとても大事です。
そのために検索エンジン最適化=SEOを行うことで、グーグルを中心とする検索エンジンで上位表示を目指しています。
上位に表示されるほど流入数が増えるからです。逆に上位表示されないと存在しないことと同じです。
具体的には、様々な検索キーワードで上位表示するために、自社商品関連の記事を検索キーワードに合わせてWebサイトに掲載します。
グーグルさんが、消費者に役に立つサイトであると認識すると上位表示されます。
ここがWebサイトのかたよりのポイントです。
掲載上位の記事内容はGoogleが正しいと判断する内容のものが沢山掲載されている=Googleの判断だということと、最終的には自社商品を購入してもらう記事となっています。
もう一つは、個人の記事がそのまま校正検閲を受けずに掲載されていることが多くあります。
SNS、ユーチューブの収益化から見る「かたより」
たくさんの人に見てもらうことが最重要
基本的な収益は、企業案件(商品等の広告)の広告収入及び、自分のホームページ等への流入による広告や販売収入となります。
ユーチューブでは、グーグルアドセンスという広告表示ごとに一定の額を頂ける広告掲載仕組みが主となっています。
これらで稼ぐためには、訪問者数が沢山いることが大事なことになりますので、フォローワー数やチャンネル登録数がとても大事になります。
これらの数を増やすためには、役に立つ情報を発信する必要がある反面、興味をひきやすいように、ある意味過剰な表現を行う場合が多くあります。
また、最近は#PRと入るようになりましたが、企業案件と言われる、インフルエンサーの個人の感想ではなく、企業から依頼されて宣伝している場合も沢山あります。
このことが、SNS、ユーチューブのかたよりのポイントです。
テレビと同じように、派手なものなどに注目が集まりやすかったり、広告案件なのに、広告表示が小さいために、広告とわからずに情報を受けとる場合があります。
また、煽り系の記事も多く混在しています。
その上、企業・個人の記事含めて、どこまで校正校閲がかかっているかは判定できない情報(正しいか間違っているかわからない)となります。
各メディアの情報の偏りの「まとめ」
上記から、情報発信者の意図を想定しながら、記事を補正して読む必要があります。
また、テレビ・新聞はネットのように記事を沢山掲載することができない、限られた時間とスペースでの掲載となりますので、各社の方針に従った編集された情報となります。
ミクロとマクロを分ける
全体視点か個別視点かで受け止め方が変わる
視点の違いでまったく意見の受けとめ方が変わります。
例えば、「過去最安値を更新 円が155円に」という情報を得たとしましょう。
マクロ(日本全体)の視点で見ると、円安は日本の景気を押し上げる要因となります。輸出企業を中心に企業の収益が向上し、結果的に株価が上昇することからも分かります。
一方、ミクロ(個別企業)の視点では、輸出企業は大きな利益を得る反面、輸入企業には大きなデメリットが生じます。
メディアは「円安=日本の価値が安くなる」というイメージを強調するため、輸入企業が悪影響を受ける個別の事例に焦点を当てて報道しがちです。
これにより、円安が国全体にとって悪いことのように聞こえますが、実際には全体のごく一部にすぎません。
目的か手段かを把握する
得た情報が手段の目的化をおこしている
メディアはセンセーショナルなものを報じます。視聴率を取りたい意思があるからです。
例えば、「過去最高の感染者数が発生」という情報を得たとしましょう。
このような表現だと何か悪いことが起きているように感じます。
ではそもそも感染者数をチェックする目的は、なんでしょうか?
死者を出さないようにすることです。そのために、感染者数を減らすことが大事になるのです。
感染者数の最高数値はわかりました。確かにリスクはありそうです。では、そもそもの目的の死者数は?という見方をすると、また別の見方ができます。
このようなことはとてもよくおきます。このことを手段の目的化といいます。元々手段だったのに、気が付けば手段が目的化することです。
(手段の目的化の詳細は、「手段の目的化」の原因と対策を具体例を含めて解説を参照)
事実及び数字で判断する
感想ではなく事実と数字をおさえる
事実はごまかせません。昨日は雨が降ったという事実があれば、昨日は晴れでしたというのは嘘とわかります。
事実はファクトとも言われます。また、数字も同じですが、1は1です。100は100です。
しかし、今景気は悪いと言えば、人によりどのようにでも取れます。悪いという基準がそれぞれだからです。
したがって、事実と数字をおさえないと、情報発信者の伝えたいことが理解できません。
もっと言うと、情報発信者の言いなりになります。
ごまかしのきかない事実と数字で物事を把握することで、受け取る情報の真の姿が見えてきます。
ただし、以下の2点に注意が必要です。
1.「事実」が「真実」かどうかわからない
事実が必ず真実とは言えない
例えば、明治維新が歴史的な出来事であることは事実です。しかし、その解釈や背景が現在信じられている通りであるかという「真実」は、簡単に判明するものではありません。
このように事実は事実で本当のことですが、それが真実かどうかはわからないのです。
(詳しくは、「真実と事実と意見」の違いを分かりやすく解説を参照)
2.数字にはマジックがある
集計方法で答えが変わる
アンケート結果などの数字は、一見正しく見えますが、集計方法によって結果が大きく変わる場合があります。
ただ、例えば、「Aについて賛成か反対か?」というアンケートを各メディアがとると、全然違う数字となる場合があります。
これは、アンケートの回答者の偏りと、アンケートの聞き方の2つが原因です。
アンケートには当然回答者が必要です。回答者はある程度の数が必要です。そうすると必ず、かたよりがおきやすいのです。
例えば、各世代100名ずつ聞きました。というアンケートがあるとします。
一見良さそうな感じに聞こえますが、実際の人口構成と違うため、世相を表す集計結果とは言えなくなります。
また、「Aについて、どちらですか? A賛成 B反対 Cどちらでもない」と聞くのと、「Aについて賛成ですか? A賛成 B反対 Cどちらでもない」と聞くのでは同じ人に聞いたとしても、集計結果は変わります。
したがって、どのように出てきた数字か?どんなかたよりがありそうか?は必ず確認する必要があります。
しかし、残念ながらアンケートの母数について詳細に発表しているメディアはほぼないのが現状です。それらを詳細に記していないものは、あまり信じない方が良いでしょう。
実際、私は一回もテレビ局からの世論調査を受けたことがないですが、テレビではよく世論調査の結果が流れています。きっとかたよっているのでしょう。
また、回答者をランダムに選んでいると言っていますが、確かにランダムに選んだとしても、回答するかどうかはその人の判断が入ります。
好きなメディアなら答えるかもですが、嫌いなメディアであれば答えないというかたよりも出るでしょう。
分子・分母を意識する
発生件数とその確率を把握する
「ある国が日本を非難」という情報を得たとしましょう。
この際に、ある国が日本を非難ということにスポットを当てるのか?全世界約200の国の0.5%でししかない1国が避難していると受け取るのかで全然印象が変わります。
「銀座の高級店で窃盗事件がおきました」という情報を得たとしましょう。日本も物騒な国になったと思うでしょう。
確かに物騒な事件ですが、窃盗事件は、年間どれ位起きているのでしょうか?
2021年の年間窃盗事件数は、38万件以上起きています。上記はその1件ですから、0.0003%です。銀座の高級店で窃盗事件が起きたので、たまたま報道されただけです。
事実をおさえることは大事ですが、その事実の分子と分母を意識することで、その事実を客観的にとらえることができます。
分野ごとの第一人者をおさえておく
信頼できる情報ソースを持っておく
さまざまな情報の裏を取りにいくことで、情報に振りまわされることは少なくなりますが、時間がかかります。
対策として、知りたい分野で、正しい(と思われる)ことを発言する人(SNS等)を事前に見つけておくのがおススメです。
私は6名の方のSNSを常に追っています。
ただ、デメリットは人の選択を間違うことです。どうしても人は好き嫌いがありますので、正しい正しくないではなく、好き嫌いで選んでしまうからです。
そうならないように選択する方法ですが、①数字で語っているか?②ミクロ・マクロ、手段・目的を分けて発言しているか?③どんな商売をしている人なのか?をおさえておくと人選の精度が大きくあがります。
また、わからない場合は、主張がいつも異なる人をそれぞれフォローしておくのもおすすめです。
また、定点観測していくと、この人はこのようなかたよりがあるとわかるので、情報の補正をしやすくなります。
正しい情報を得る6つの方法の「まとめ」
・メディア情報がかたよる理由を知る
・ミクロとマクロを分ける
・目的か手段かを把握する
・事実・数字でおさえる
・分子・分母を意識する
・分野ごとの第一人者をおさえておく
情報があふれる世の中です。逆に言えば、知らないことでも、ちゃんと調べることができるスキルがあれば、正しい情報を無料で得ることができる環境が整っています。
ぜひとも、派手な情報やキャッチ―な情報に惑わされずに正しい情報をこの6つの方法で得てください。
他にもビジネススキルが上がる「思考方法」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
- 打ち手を考える前に必ず必要な「たった一つのこと」
- 「前提をそろえる」
- 「分解して考える」
- 「枝葉でなく幹をつかむ」
- すぐに検索せずに「一旦考える」
- 「極端に振って考える」
- 「具体化と抽象化」を使い分ける
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。