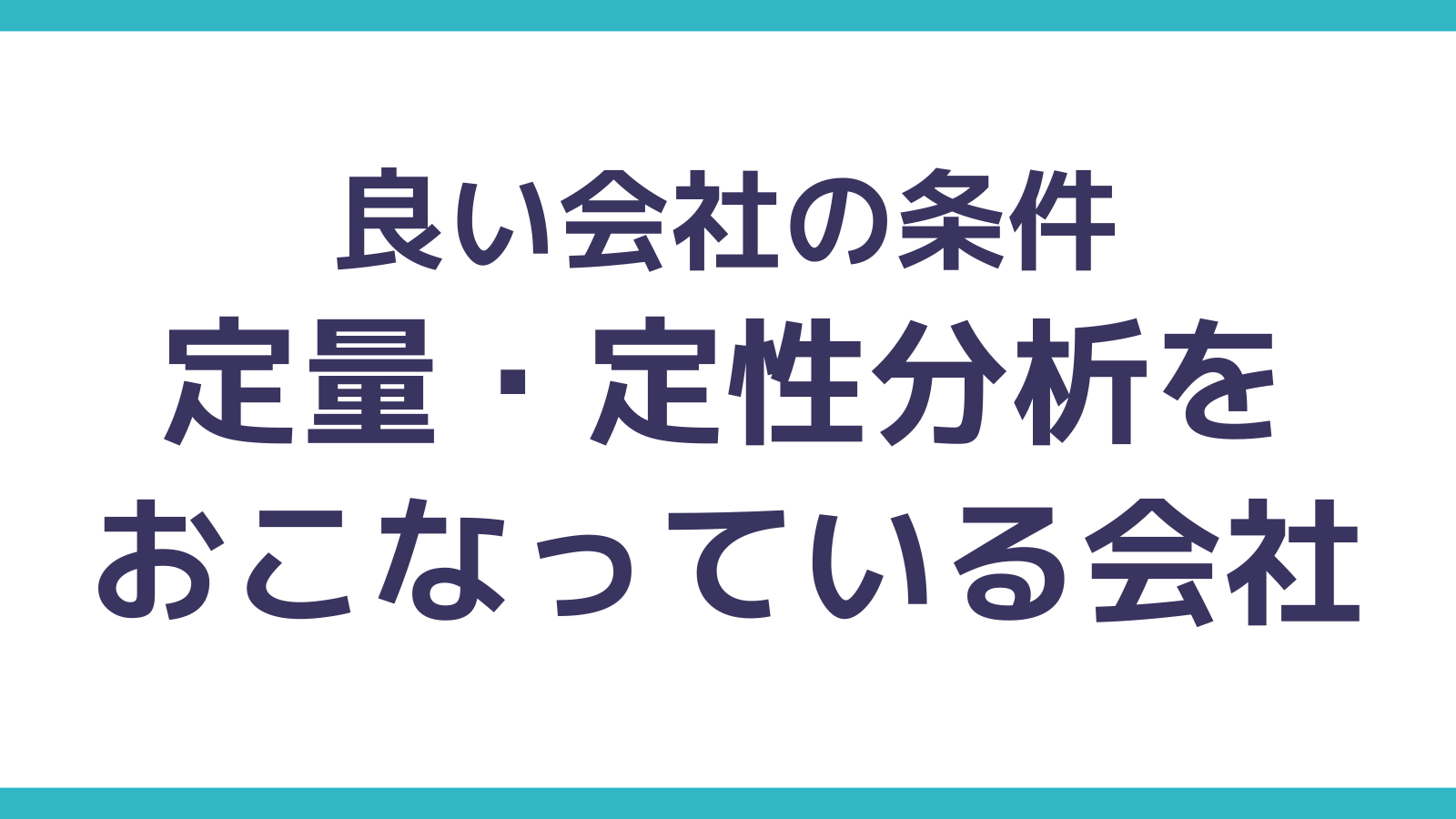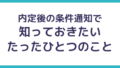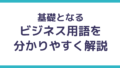これまで5社で30年以上働き、営業として数千社を訪問する中で、多くのことを学んできました。
その一つが、「良い会社には共通点がある」という事実です。
逆に、その共通点がなければ、良い会社とは言えません。
この記事では、良い会社の共通点の中でも特に重要な、「定量分析と定性分析の両方を活用している会社」がなぜ優れているのかを詳しく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【会社の環境】良い会社の特徴)
定量・定性分析を両方おこなう会社がなぜ良い会社?
業績と給料アップにつながるから
定量・定性分析両方を扱っているということは、
経営者が深く考え、仕事をしている
この証になります。
経営者が深く考え、適切な判断材料に基づいて意思決定を行えば、業績が向上する可能性が高まります。
その結果、給料が上がるだけでなく、顧客に喜ばれるサービス提供を通じて、従業員のやりがいも生まれる好循環が期待できるからです。
言うまでもなく、業績の悪い中小企業の多くは、経営者が十分に考えていないケースが少なくありません。それが業績不振の大きな理由です。
まずは定量分析と定性分析それぞれの特徴を説明した上で、なぜ深く考える経営者がこれらの分析に行き着くのかを詳しく解説していきます。
定量分析と定性分析の違い
まずは、両者の違いについて解説します。
定量分析とは?
数値をベースに分析を行うこと
現状把握、仮説の立案、仮説検証、結論の裏付けなど、客観的なデータに基づいた判断に活用されます。
定量分析のメリット・デメリットとは?
メリット
数値という事実に基づいているため、主観が入り込みにくく、客観的に判断できます。これにより、解釈のズレも起こりにくくなります。
デメリット
情報源が数値のみのため、人の感情、意見(口コミなど)といった主観的な情報を分析しにくい点です。結果として、全体像(総論)は把握できても、個別の詳細(各論)までは捉えにくいというデメリットがあります。
定性分析とは?
数値では表せない情報を分析すること
「質的データを分析する」とも言いますが、簡単に言えば、定量分析で扱う数値以外の情報、特に人の主観的な情報(感情、意見など)を用いて分析する方法です。
定性分析のメリット・デメリットとは?
メリット
数値では表現できない感情や意見(口コミなど)といった主観的な情報を深く分析できる点です。
デメリット
数値ではない大量の情報を分析するには、多くの時間とコストがかかります。
また、情報量が少ない場合、分析者の主観が大きく影響し、結果に偏りが生じる可能性があります。
定量・定性分析のメリット・デメリットの関係
互いの弱点を補完し合う関係
定量分析と定性分析は、互いのメリット・デメリットを補完し合う関係にあります。
定量分析のメリットは定性分析のデメリットを補い、定性分析のメリットは定量分析のデメリットを補います。
つまり、両方の分析を組み合わせることで、それぞれの弱点を打ち消し合い、より精度の高い分析が可能になるのです。
経営者がちゃんと考えて仕事をしている
・自然と二つの分析に行き着くから
・会社に二つの分析が根付くから
上記理由で会社全体で定量・定性分析を両方やっているのは、経営者がちゃんと考えているからだとわかります。
それぞれ説明します。
自然と二つの分析に行き着くから
適切な判断材料を求めるから
経営者が会社の将来を真剣に考えるほど、適切な判断材料を求めるようになります。
直感のみに頼った判断では、長期的な繁栄は望めません。なぜなら、正しい判断の確率が上がらず、重要な局面で誤った判断を下すリスクが高まるからです。
そのため、経営者はできるだけ確度の高い判断をするために、多角的な情報を欲します。
その結果、全体像を把握する「総論」と、個別の詳細を深掘りする「各論」の両方を分析する必要性を感じ、自然と定量分析と定性分析の両方を求めるようになるのです。
会社に二つの分析が根付くから
経営者が継続的に分析を求めるから
これは、経営者が継続的に分析を求めるからに他なりません。
分析作業は、正直に言って手間がかかり、面倒に感じるものです。そのため、経営者自身も、従業員も、基本的には自ら進んでやりたがらない傾向があります。
しかし、経営者から継続的に分析を求められれば、従業員は応えざるを得ません。
こうして、経営者の強い意志が原動力となり、会社全体に定量・定性分析を両方行う文化が根付いていくのです。
定量・定性分析両方ができているかの見分け方
経営者を含め、Excelを使いこなせる人が多いか?
この点で見分けられます。
定性分析は、日々の業務の中で会話を通じて最低限行われていることが多いでしょう。
一方、定量分析では、数字の集計や加工を通じて仮説を立てたり、その仮説を検証したりする作業が伴います。
定量分析作業を通じてExcelを使う機会が増え、スキルが上達するのです。
もちろん、経営者が部下に分析を指示することもできますが、特に立ち上げ期の社員が少ない会社では、経営者自身が分析を行う場面も少なくありません。
その過程で定量分析を実践していれば、自然とExcelを使いこなせるようになります。
つまり、社内にExcelを使いこなせる人が多いということは、それだけ日頃から定量分析が活発に行われている証拠と言えるでしょう。
ちなみに、ここで言う「Excelを使いこなせる」とは、単にデータ入力ができるレベルではなく、「やりたいことをGoogleなどで調べ、自分で関数や数式を組んで問題を解決できる」レベルを指します。
(あわせて読みたい、「エクセルを使えない人が多い会社」は悪い会社をわかりやすく解説)
定量・定性分析を両方おこなう会社がなぜ良い会社か?の「まとめ」
業績が上がり給料が上がる可能性が高まるから
定量・定性分析両方を扱っているということは、定量・定性分析の両方を活用していることは、まさに「経営者が深く考えている」ことの何よりの証明です。
結果、業績が上がり、給料が上がる会社となる可能性が高まります。
他にも「良い会社の見分け方」で以下の記事を書いています。参照下さい。
転職のことを詳しく知りたくなった方へ
転職には知識とノウハウが必要です。たくさんの要素を総合的に判断しなければなりません。
まずは、以下の記事を参照下さい。
他にもキャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録して相談してみるのもおススメです。
登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。