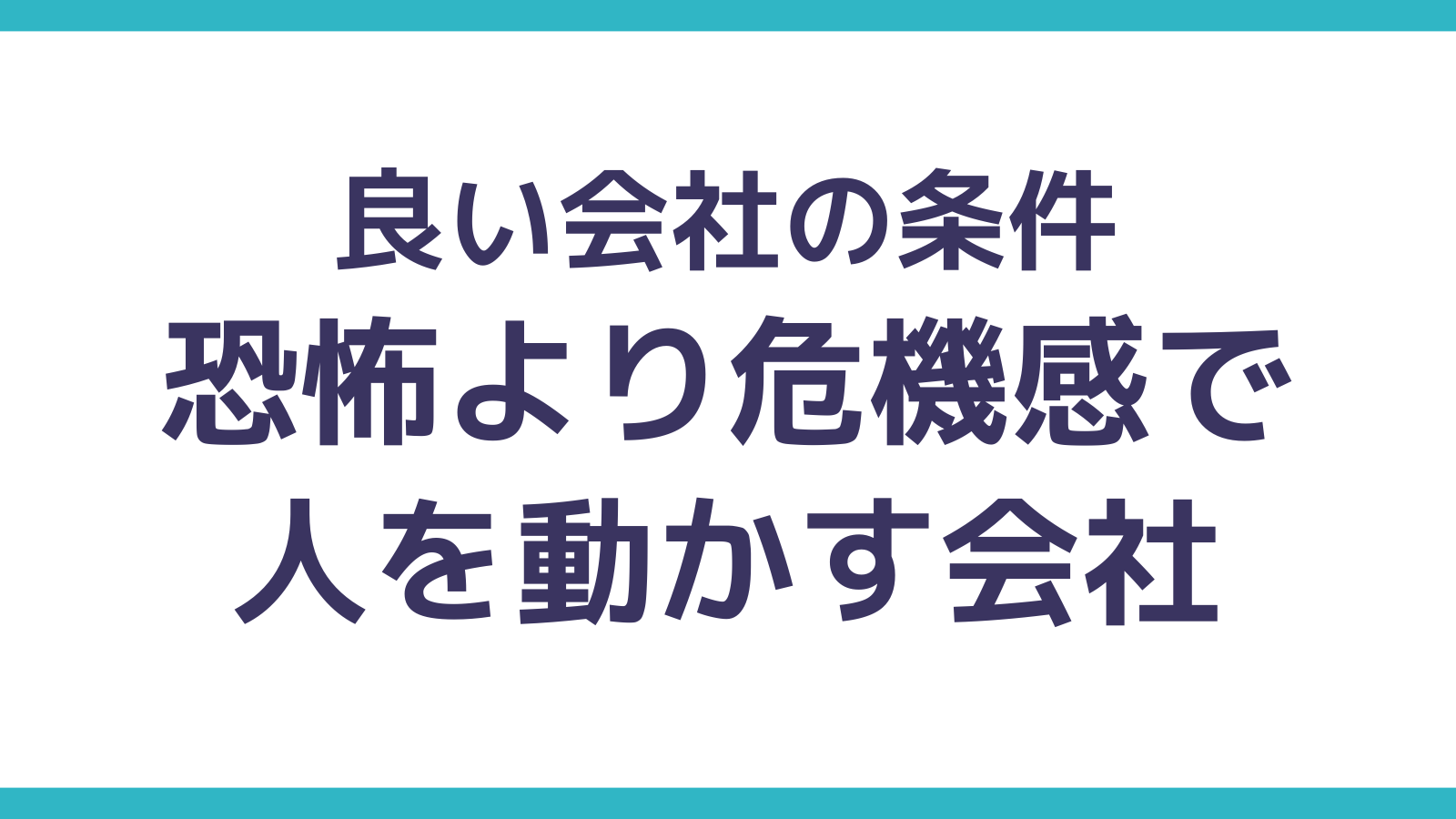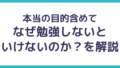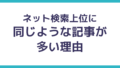これまで5社での勤務経験がありますが、その中で特に印象的だったのは、危機感に満ちた1社目の会社と、恐怖感が蔓延していた3社目、4社目の会社です。
両方の実体験から、その違いを明確にお伝えできます。
「厳しい会社」「ドライな会社」「結果主義」といった言葉と混同されがちな「恐怖」と「危機感」ですが、その区分けは非常に重要です。
また、良い会社であっても「最低限の緊張感」が存在することも、この二つの概念を分かりにくくしている要因でしょう。
本記事では、恐怖と危機感の違いを明確にし、なぜ恐怖ではなく危機感で人を動かす会社が良い会社なのかを分かりやすく解説します。
この記事は、
・3回の転職経験
・中途採用の責任者の経験
・多数の書類選考・面接の経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ著者であるよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【会社の環境】良い会社の特徴)
なぜ恐怖より危機感で人を動かす会社が良い会社か?
恐怖ではなく危機感で人を動かす会社が良いとされる理由は、主に以下の3点です。
・個人の成長を促す環境がある
・本物のリーダー・マネージャーが存在する
・健全で良い会社の雰囲気が醸成される
まず「恐怖」と「危機感」それぞれの詳細を説明し、その上で上記の3つの理由について詳しく解説していきます。
恐怖と危機感の詳細説明
人を動かす手法には、「恐怖で動かす」方法と「危機感で動かす」方法があります。ここでは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
恐怖で人を動かす会社とは?
外圧によるモチベーション
恐怖で人を動かす会社は、罰を与える、威嚇する、怒鳴るといった外部からの圧力によって、従業員を強制的に行動させようとします。
本人の意思とは無関係に、動かざるを得ない状況に追い込み、結果として行動を引き出す手法が多用されます。
恐怖で人を動かす会社の特徴
・叱られることがほとんど
・結果だけを求められる
・意見を言えない
・しきたりが多い
・笑顔がない
・おしゃべりがない
・常に上司を見て過ごす
このような特徴があります。
なぜ恐怖で人を動かす組織になるのか?
安易な選択と負の連鎖
恐怖によって人を動かすことは、最も手っ取り早い方法です。
役職者がその立場を利用して部下に圧力をかければ、一時的に人は動くでしょう。時には、緊急時などにおいて必要な手段となることもあります。
しかし、本来あるべき適切な方法は、業務の主旨や求める結果、その理由を丁寧に説明し、部下が自律的に行動するよう促すことです。
この方法は、指示を出す側には手間と根気が求められるため、つい安易な恐怖によるマネジメントに流れてしまいがちです。
結果として、恐怖に頼るマネジメントが定着してしまいます。
さらに、恐怖を経験して育ったマネージャーは、その方法しか知りません。こうして、親亀が子亀に、そして孫亀に脈々と恐怖によるマネジメントが受け継がれていくのです。
恐怖によるマネジメントしか経験していない人が一定数を超えると、組織全体に恐怖の風土が形成されます。
危機感で人を動かす会社とは?
内発的動機付けの促進
危機感で人を動かす会社は、「置いていかれる」「遅れをとる」「貢献したい」といった個人の内側から湧き出る内発的な動機付けを引き出し、行動を促します。
従業員が自身の意思で動きを選択する傾向が強いのが特徴です。
危機感で人を動かす会社の特徴
・ほめられることが多い
・結果だけなく、プロセスも求められる
・意見を言わないといけない
・しきたりが少ない
・笑顔が多い
・おしゃべりが多い
・常に顧客を見ている
・引き締まった雰囲気がある
このような特徴があります。
なぜ危機感で人を動かく会社になるのか?
リーダー・マネージャーによる意図的な組織づくり
危機感のある組織は、リーダー・マネージャーが意図的に作り出すものです。
具体的には、リーダー・マネージャーは以下の点を徹底します。
・個人ごとの業務内容と責任を明確に分割し、部下にその内容を深く納得させる。
・個人の行動結果に対して、明確な評価(=成果による差異化)を行う仕組みを構築する。
これらの条件が整うことで、組織内に健全な危機感が生まれます。
他者との明確な差異を認識し、その差に直面することで、従業員は「目指すべき目標」に納得感を持ち、自ら「頑張らなければ」という気持ちを自然と抱くようになり、危機感が醸成されるのです。
恐怖より危機感であふれる組織は良い会社の「詳細」
恐怖ではなく危機感に満ちた組織が良い会社とされる理由は、以下の3つの側面に集約されます。
・個人の成長を促す環境がある
・本物のリーダー・マネージャーが存在する
・健全で良い会社の雰囲気が醸成される
ここからは、これら3つの理由についてさらに詳しく解説していきます。
個人の成長を促す環境がある
良質な経験の蓄積
自分の役割が明確で、内発的なやる気に満ち、適切なマネジメントを受け、「このままでは置いていかれる」という健全な危機感があれば、必然的に行動量は増加します。
行動量が増えれば、それに比例して多くの経験を積むことができます。人の成長には、この経験の数が不可欠です。
さらに、自身の内発的な動機によって行動する際、人は常に「どうすれば最善か」を自ら考え抜きます。
これにより、自ら立案した行動に対するPDCAサイクルを数多く回す経験を積むことが可能です。
結果として、質が高く多様な経験を積むことで、個人の成長を強力に促進するのです。
本物のリーダー・マネージャーが存在する
本来のマネジメント業務の遂行
恐怖が蔓延する会社では、リーダー・マネージャーが本来果たすべき役割を十分に果たしていません。
では、リーダー・マネージャーの「本来の仕事」とは何でしょうか?それは以下の通りです。
・個人ごとの業務内容と責任を明確に分割する
・部下がその業務内容を心から納得できるよう説明する
・行動の結果を明確に評価する仕組みを構築する
・部下の行動を全力でサポートする
これらの本来の業務を遂行できるのは、真に優秀な「本物のリーダー・マネージャー」に他なりません。
危機感によって人を動かす会社には、上記の要件を満たすリーダー・マネージャーが不可欠です。
このようなリーダー・マネージャーの存在が、健全な危機感で人を動かす組織を築き上げるのです。
健全で良い会社の雰囲気が醸成される
真剣な人間関係の構築
「仲が良い」とは少し異なりますが、社員同士が互いに真剣に向き合う関係性を築いている組織では、無関心、ギスギスした雰囲気、あるいは派閥争いといった問題が生じにくくなります。
時には緊張感のあるピリピリとした雰囲気となることもありますが、それは後に尾を引くようなネガティブなものではありません。
このような良好な人間関係が全社に波及することで、会社全体の雰囲気がより良いものへと変化していきます。
恐怖より危機感で人を動かす会社は良い会社の「まとめ」
恐怖ではなく危機感に満ちた組織が良い会社とされる理由は、以下の3点に集約されます。
・個人の成長を促す環境がある
・本物のリーダー・マネージャーが存在する
・健全で良い会社の雰囲気が醸成される
外からの圧力によって「やらされている」と感じる雰囲気ではなく、自身の内側から「動きたい」という気持ちが生まれる組織、すなわち健全な危機感のある会社で働くことは、このような多大なメリットをもたらします。
私自身の両方の組織での経験から言えるのは、恐怖で人を動かす組織では人は決して成長しないということです。むしろ、言われた以上のことをしようとすると、逆に叱責される経験さえあります。
その結果、従業員は「言われたことしかしない」という習慣が身についてしまいます。一度この習慣がついてしまうと、それはなかなか払拭できません。なぜなら、その方が楽だからです。
これは、長年の現場経験から得られた確かな知見です。
他にも「良い会社の見分け方」で以下の記事を書いています。参照下さい。
転職のことを詳しく知りたくなった方へ
転職には知識とノウハウが必要です。たくさんの要素を総合的に判断しなければなりません。
まずは、以下の記事を参照下さい。
他にもキャリアアドバイザーに相談できる転職エージェントに登録して相談してみるのもおススメです。
登録無料でキャリアアドバイザーに無料相談ができ、多数の非公開求人が無料閲覧できる実績No.1のリクルートエージェントがおススメです。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。