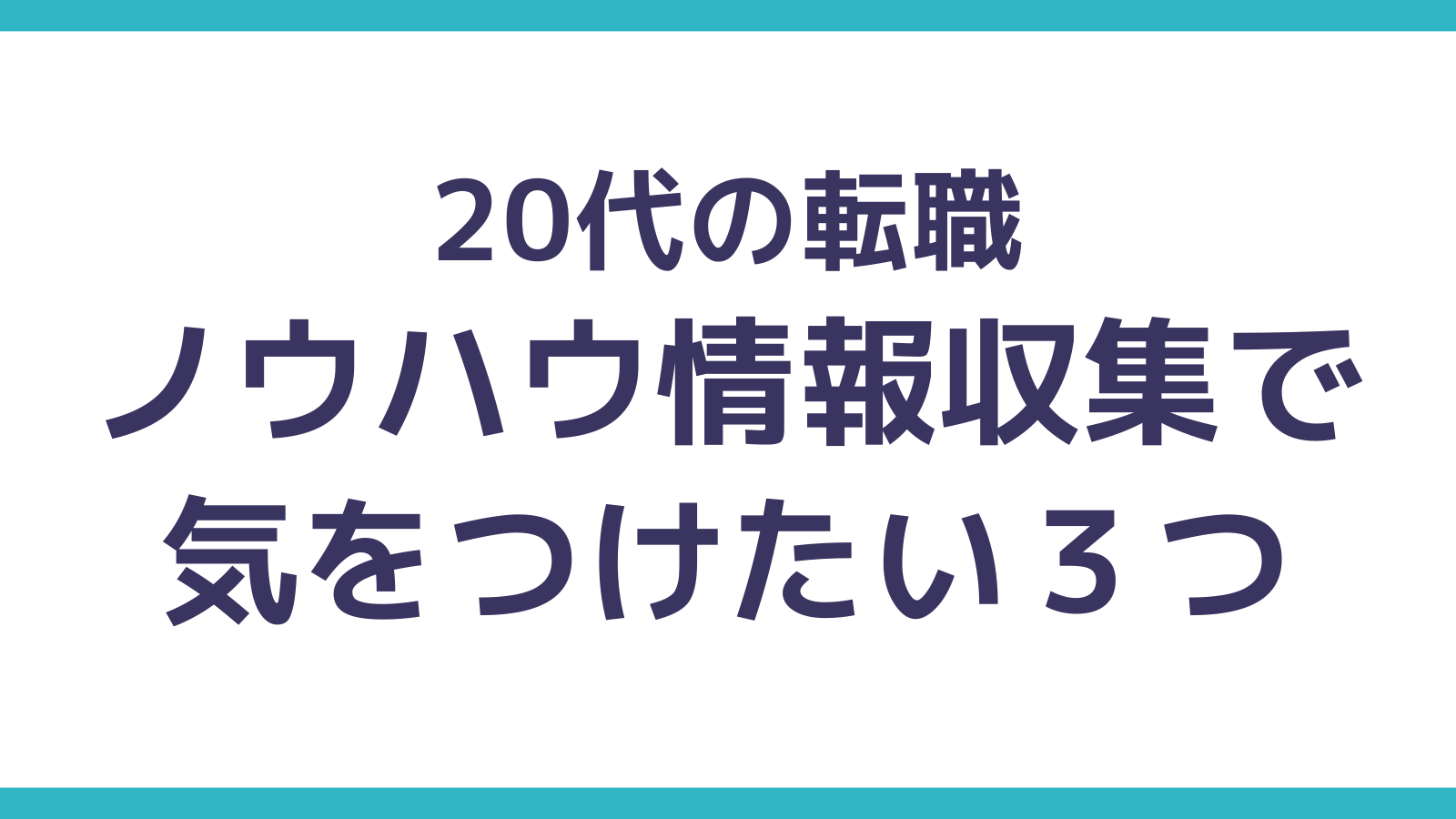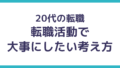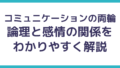転職を検討し始めたら、まずどのように情報収集しますか?
多くの人は、求人情報はもちろん、転職活動の進め方についてもWeb検索や知人からのアドバイスを頼りにしているのではないでしょうか。
私自身も3回の転職経験がありますが、その際にこれらの情報源を活用してきました。
会社探しにおいては、転職サイトや転職エージェントの利用が不可欠なので、これらを効果的に活用することが重要です。
しかし、転職活動のノウハウに関する情報収集では、Web検索や知人のアドバイスには注意が必要です。なぜなら、誤った情報や的外れな情報が含まれている可能性があるからです。
この記事では、あなたが手に入れた情報に惑わされないよう、情報収集時に気をつけたい3つのポイントをわかりやすく解説します。
この記事は、
・3回の転職経験
・中途採用の責任者の経験
・多数の書類選考・面接の経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい 転職の知識(転職判断から入社まで)
情報収集で気をつけてほしい3つのこと
検索結果の上位の記事を信用しすぎない
知人のアドバイスを鵜呑みにしない
会社口コミサイトのかたよりを知っておく
この3つが気を付けてほしいことです。
これらの情報源には信頼できる情報も多数ありますが、それぞれの特性上、内容に偏りが生じやすい傾向があります。
検索上位の記事には記載できる内容に制約があり、知人の知識は自身の転職経験数によって偏りがあり、口コミは投稿者個々の主観や思考の癖が反映されるためです。
したがって、得た情報にどのような「偏り」があるのかを事前に知っておくことが非常に重要です。この3つのポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。
記事検索結果の上位の記事を信用しすぎない
・検索上位は転職会社ばかり
・転職会社は転職のプロ?
この2に分けて解説します。
検索上位は転職関連会社ばかり
転職関連会社の記事にはビジネス上のかたよりがある
まずはGoogleで「転職」と検索し、上位表示されるサイトの会社名を確認してみてください。ほとんどが転職関連会社の記事であることがわかるはずです。
転職関連会社の記事には役立つ情報も多く、誤った情報が書かれていることは稀です。ただし、記事を作成する際には制約がかかります。
多くの転職関連会社は、求職者を企業に紹介することで、企業から報酬を得ています。
例えば、転職エージェントは、採用が決定した求職者の年収の約35%を報酬として受け取ります。年収300万円の人が採用されれば105万円、年収1000万円の人であれば350万円が報酬となる計算です。
企業から報酬を得ている以上、記事内で特定の企業の優劣をつけたり、取引先企業の不利になるような内容を紹介することは難しいのが実情です。
例えば、「粗利率が高い会社を選びましょう」とは言えません。なぜなら、取引先の中には粗利率の低い企業も存在するからです。また、当然ながら個別企業に絞って特定の情報を書くこともできません。
これらの制約が、記事内容に影響を与えています。
20代の皆さんは、具体的な会社の選び方や判断基準を知りたいはずですが、残念ながらそういった情報は記事として記載されにくいのです。
なぜ上位を転職会社が占めているか?
なぜ検索上位が転職関連会社ばかりなのでしょうか? それは、各社が検索エンジンの上位に表示されるよう、多額の費用と労力をかけているからです。
転職関連会社のビジネスは、採用したい企業を集めるだけでなく、求職者も集めて初めて成立します。企業と求職者をマッチングさせる必要があるからです。
現在、多くの企業で人材不足が課題となっており、採用したい企業を集めることは比較的容易です。しかし、求職者を集めるのは簡単ではありません。転職を検討している人がどこにいるのか、見つけにくいからです。
それでも、求職者が必ず行う行動があります。それが、情報収集のために転職関連キーワードでWeb検索をすることです。
検索結果の上位に表示されることで、求職者は自社サイトに訪れてくれます。さらに登録してもらえれば、企業に紹介できるチャンスが生まれます。
このような理由から、各転職会社は多大なコストと労力を投じて検索上位表示を目指しています。
その結果、検索上位には転職会社の記事が並び、前述のような制約がある記事が掲載されることになるのです。
(詳しくは、ネット検索結果の上位に同じような記事が多い理由を参照)
転職会社は転職のプロ?
転職会社は転職のプロと感じますが本当にそうでしょうか?
冷静に考えてみれば、真の転職のプロとは、何度も転職を経験し、その都度成功を収めている人ではないでしょうか。転職会社はあくまで、転職という「手段」のプロなのです。
転職の目的は、現在の会社よりも良い環境で働くこと。転職先の会社で実際に働いてみて、その会社が本当に「良い会社」だと感じられた時に初めて、転職は成功したと言えます。
転職会社は、新しい会社に入社するまでのサポートは行いますが、その後の結果について責任を負うことはありません。
この違いは非常に重要です。転職を成功させたいのであれば、転職関連会社の記事やキャリアカウンセラーのアドバイスを鵜呑みにしすぎないようにしましょう。
また、一部の会社では、強引に転職を決定させようとするところもあるので注意が必要です。
(詳しくは、転職のプロとは?を分かりやすく解説を参照)
他人のアドバイスを鵜呑みにしない
他人のアドバイスで参考になるのは、実際に転職を経験している人だけ
転職したことがない人は、転職に関する実践的な知識を持っていません。
当たり前のことですが、友人や尊敬する先輩のアドバイスは信じやすいものです。だからこそ、時には聞き流すことも必要だと心得ておきましょう。
また、転職の意思を上司に打ち明けた際、引き止めにあうこともあります。その際も、その上司に転職経験があるかどうかで、アドバイスを参考にするかどうかを判断するようにしましょう。
ご両親からのアドバイスについても同様です。
会社口コミサイトのかたよりを知っておく
・会社のほんの一面だけを見た記載内容
・本心が赤裸々に記載されている口コミが少ない
会社口コミサイトが沢山ありますが、上記2点でかたよっていますので、参考にしすぎないようにしましょう。
私は、5社で働いています。その5社の口コミを全サイトチェックしていますが、実態を表した口コミが少ないと感じています。
その理由がこの2つです。
それぞれを解説します。
会社のほんの一面だけを見た記載内容
新人からベテラン、部署経験数の違いなどさまざまな人が投稿
判断基準がバラバラ
口コミサイトには、新人からベテラン、部署経験数の違いなど、様々な経歴を持つ人が投稿しており、その判断基準もバラバラです。
全く異なるバックグラウンドを持つ人々が、会社の風土、福利厚生、経営者、上司、年齢構成、売上状況など、多岐にわたる項目について自身の主観で評価しています。
商品レビューであれば、商品という特定の対象に絞った評価であるため、評価基準が統一されやすく、信頼できる情報になりやすいです。
しかし、会社の口コミの場合、多くの会社で働いた経験を持つ人が客観的に評価しているのであれば別ですが、投稿者は必ずしもそうではありません。
例えば、会社が高成長していることに対して、「安定した会社が良い」と考える人は、「会社が無理をしているのでは?」と感じたり、「仕事が多くて残業が多いのは嫌だ!」とネガティブに捉えるかもしれません。
一方で、「活気あふれる会社で働きたい」と望む人ならば、「とても良い会社だ」とポジティブに捉えるでしょう。
このように、人によって感じ方は千差万別です。その上、評価項目も多数にわたります。
したがって、口コミを鵜呑みにしてはいけないのです。
本心が赤裸々に記載されている口コミが少ない
実態を表した口コミが少ない
実態を表した口コミが少ないと感じるのが、私の5社での勤務経験に基づく率直な感想です。
口コミサイトに投稿する人の多くは、転職を検討している時期です。
多くの会社口コミサイトでは、会員登録後、現在勤めている会社の口コミを投稿しないと、他社の口コミを閲覧できない仕組みになっています。
そのため、「他社の口コミを見たい=転職を検討している」人が、仕方なく口コミを投稿しているケースが多く見られます。
元社員でよほどの恨みがあれば厳しい内容を書くかもしれませんが、そうでなければどうでしょうか? お世話になった上司や同僚がいる会社に対し、迷惑になるような口コミを書くでしょうか?
また、あまり具体的な内容を書きすぎると、匿名であっても内容から誰が書いたかが特定されるリスクがあります。
在籍しながら転職活動をする場合、そのようなリスクを冒そうとする人は少ないでしょう。
結果として、多くの人が内容をぼかして投稿するため、赤裸々な本音の口コミが少ないというのが、私が5社で働いて実感した実態です。
(詳細は、会社口コミサイトを信じてはいけない「2つの理由」をわかりやすく解説を参照)
情報収集で気をつけてほしい3つのことの「まとめ」
検索結果の上位の記事を信用しすぎない
他人のアドバイスを鵜呑みにしない
会社口コミサイトのかたよりを知っておく
この3つが情報収集の際に気を付けてほしいことです。
使える情報であることも多いのですが、情報には情報源によってかたよりがあることは知っておきましょう。
その他にも転職活動の前に知っておきたいことの記事を書いています。参照下さい。
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。