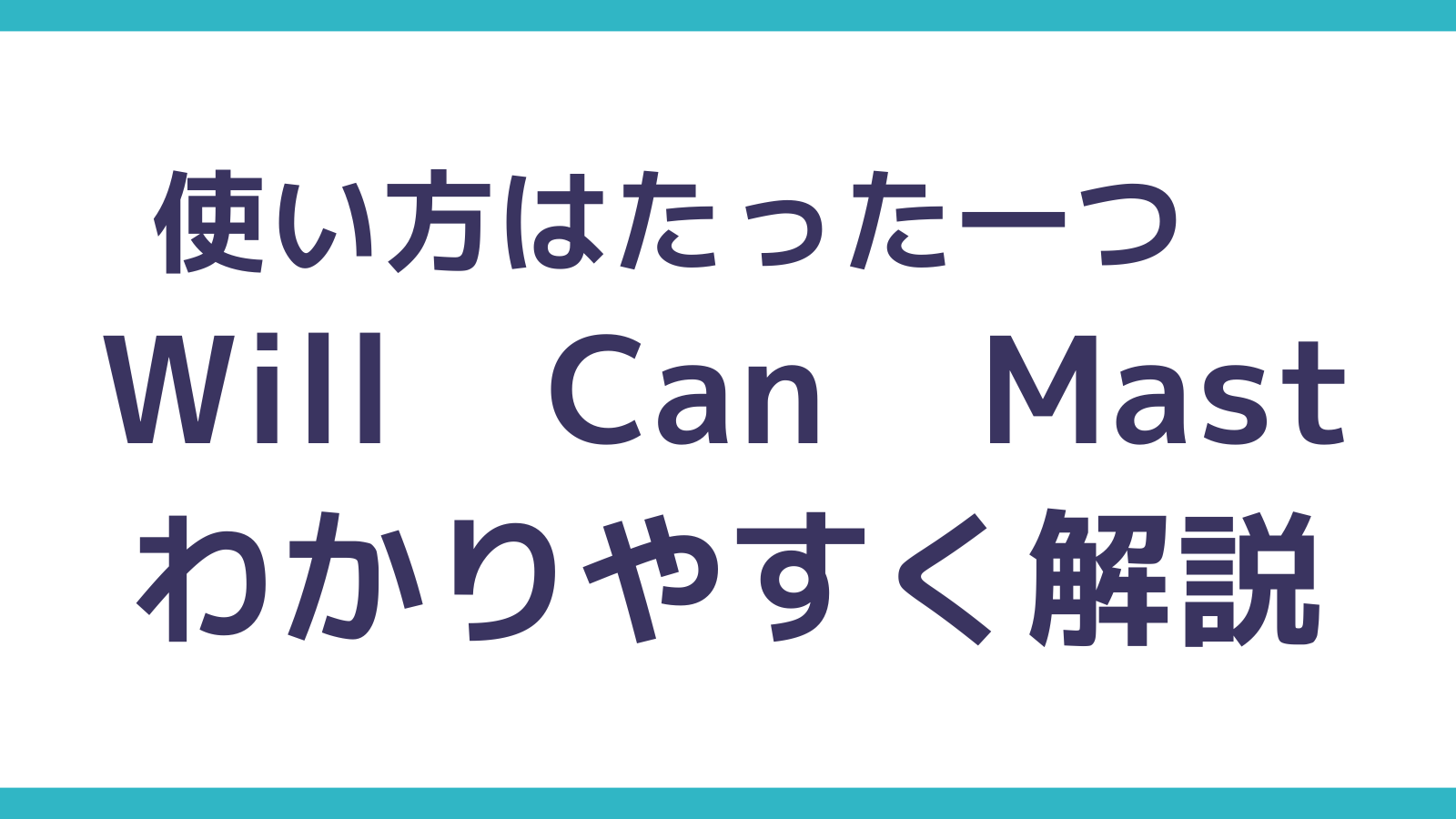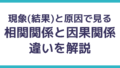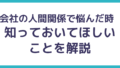「Will Can Must(ウィル・キャン・マスト)」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、株式会社リクルートが人事評価に導入したことで知られるフレームワークです。
現在では、人事評価のみならず、個人の就職や転職における目標設定にも活用され始めていますが、その基本は人事評価にあります。
この記事では、この「Will Can Must」の3つの要素の関係性と、具体的な使い方をわかりやすく解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【ビジネス用語】基礎用語解説)
「Will Can Mast」のフレームワークとは?
・「従業員が組織に貢献すること」
・「従業員自身が成長すること」
上記二つを同時に実現するフレームワークです。
「Will Can Must」を活用すれば、個人の「したいこと(Will)」、「できること(Can)」、そして会社が求める「すべきこと(Must)」の3つを同時に考慮できます。
この3つがリンクすることで、上記二つが実現するのです。
・Will Can Mastそれぞれの意味
・Will Can Mast3つの関連性
・このフレームワークの注意点
上記に分けて解説します。
Will Can Mastそれぞれの意味
それぞれの意味を解説します。
Willとは?
従業員個人が「したいこと、なりたいこと」です。
「したいこと(Will)」が見つからない人も少なくありませんが、それを見つけるためには、これまで経験したことのない新しいことに挑戦することが必要です。
Canとは?
従業員個人が「できること」です。
個人が今持っている能力のことです。
「できること(Can)」を増やすには、経験値を積むことが不可欠です。様々な経験を通じて、個人の能力は向上していきます。
Mastとは?
従業員が「すべきこと」です。
会社に所属していれば必ずある担当業務のことです。
会社はこれらの業務を高いレベルで遂行することを期待しており、従業員の「できること(Can)」が増えることでそれが実現します。
Will Can Mast3つの関連性
3つがリンクすることで個人も会社も成長できる
会社が業務を経験する機会である、すべきこと(Mast)を提供し、その経験で個人のできること(Can)が増えます。
したいこと(Will)とすべきこと(Mast)が重なる部分が大きければ、個人はモチベーション高く行動できます。
モチベーション高く行動できれば、すべきこと(Mast)の経験からたくさん得ることができることで、できること(Can)が増えます。
「したいこと(Will)」と「すべきこと(Mast)」が大きく重なり合えば、個人は高いモチベーションを持って行動できます。
また、「したいこと(Will)」を見つけるには、これまでにない経験を積むことが必要です。
そうした経験は、「すべきこと(Must)」となる業務の中から発見できることもあります。
このように、3つの要素がしっかりリンクすることで、従業員の成長だけでなく、従業員が組織に貢献できる状態を創り出すことが可能です。
結果として、「従業員が組織に貢献すること」と「従業員自身が成長すること」が同時に実現されます。
実はこの2つは、人事評価の目的とまったく同じです。
従業員に組織貢献してもらうためには、まずは、従業員への適切な仕事の分配(分業)を行います。
従業員がその内容を認識し、その仕事をおこないます。
その仕事を通じて、従業員に成長してもらうことと、人事評価を同時におこないます。
この結果、従業員と会社のWIN-WINの関係を築くことにつながります。
(詳しくは、「人事評価(人事考課)の目的」をわかりやすく解説を参照)
このフレームワークの注意点
・ちゃんと運用するには質の高い面談が必要
・WillCanとMastをつなげる必要がある
上記2つが注意点です。
それぞれ解説します。
運用するには質の高い面談が必要
これまでの「Will Can Must」の説明を読んで、皆さんの身近に、これを理想的に実践できている会社や上司はいるでしょうか?
おそらく、ほとんどいないのが実情ではないでしょうか。
このフレームワークは、個人の内面に深く切り込むことを前提としています。
そのため、上司は部下が心の内を開示できるような関係性を築く必要があります。
多くの会社でこのフレームワークが導入されているようですが、残念ながら表面的な制度にとどまっているケースも少なくありません。
「Will Can Must」フレームワークを効果的に導入するための前提条件は、個人面談の時間の長さと、何よりもその質の高さです。
例えば、半年ごとの査定で、上司と部下による振り返りミーティング、査定フィードバック、そして目標設定ミーティングにそれぞれ最低1時間、合計2時間を確保できるような会社でなければ、その運用は難しいかもしれません。
面談に1時間程度かけることで、質の高い議論ができる可能性が高まります。
この前提がなければ、「Will Can Must」を効果的に連携させるための深いコミュニケーションには至らないでしょう。
ちなみに最初に導入したリクルートさんは、人事評価について元々時間をかけて取り組んでいます。その風土と経験があるので導入できているのです。
ただ、「Will Can Mast」のフレームワークが導入されているのであれば、制度がうまく回っていなかったとしても、Willを半年に一回強制的に考える機会があることは幸いだと思います。
Willにまっすぐ向き合う機会は本当に少ないので、大事な機会となります。
「Will Can」と「Mast」をつなげる必要がある
Mast(業務としてすべきこと)をおこなうこと(=経験すること)で個人が成長(=WillとCan)する関係となります。
人は、何事も経験しないとできるようになりません。
さらに、この2つをつなぐ役割として上長の役割が大きな要素となります。
Mastに対して、どのような気持ちで取り組むかにより、得られるものが大きく変わるからです。
ただ、会社の業務に対して、すべきこととはわかっていても、したいことまでの意味を見出しにくい場合が多くあります。
そこで、第三者であり、広い視野や知見を持つ上長のサポートが必要になるのです。
部下の成長(=WillとCan)と会社の成長(Mast)の両輪をどのようにして最大化するか?が上長の仕事です。
個人だけではだめ、会社だけでもだめという二律背反をどう実現するか?という難易度の高い仕事となります。
「Will Can Mast」のフレームワークのまとめ
「従業員が組織に貢献すること」と「従業員自身が成長すること」を同時に実現するためのフレームワーク
もう少しかみ砕くと、「しなければならないこと」を行うことで、「したいこと」を見つけたり、「できること」を増やすフレームワークとも言えます。
また、「本人」・「上司」・「業務の目標設定」の3つが揃わないと使えないフレーワワークでもあります。
難易度が高いフレームワークですが、個人の成長と会社の成長を両立させるものであることだけは知っておきましょう。
他にもビジネス用語に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。