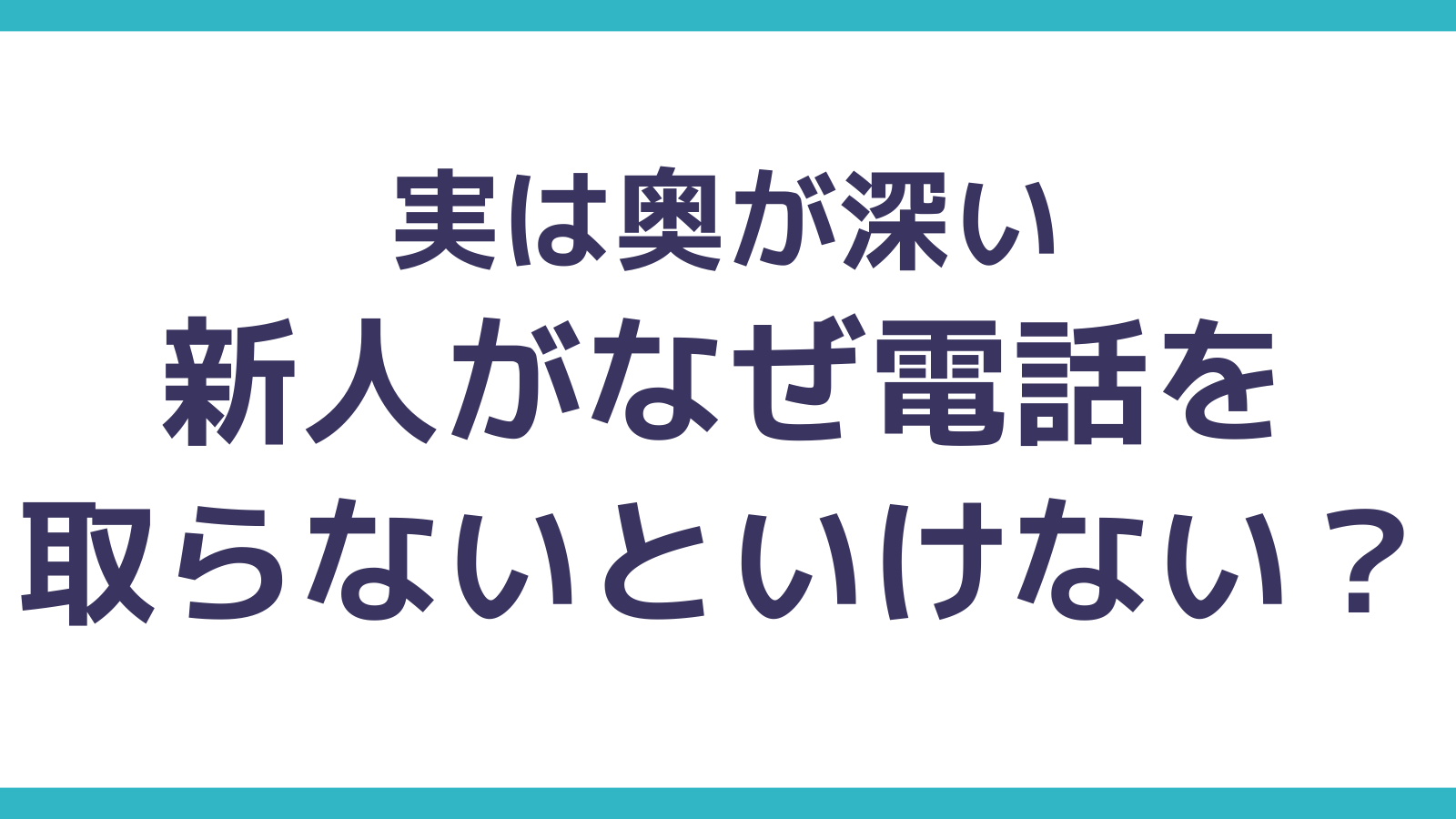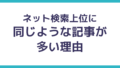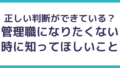会社にかかってくる電話を取るのは、気が重いものですよね。
携帯電話に慣れた世代にとって、相手が分からず、かつ多岐にわたる内容に対応しなければならない電話対応は、慣れないうちは特に苦労するものです。
「経験豊富な社員が取った方が、会社全体として効率的なのでは?」と感じることも多いでしょう。
それは一見正しい考え方です。
しかし、私は長期的な視点、そして会社全体の効率を考えると、「新入社員が電話を取る必要がある」と考えています。
なぜそのように考えるのか?をこの記事ではできるだけわかりやすく説明します。
実はこの業務にはメリットがあります。それは、「会社組織の本質」を知るきっかけになること、そして、その会社独自の仕事の進め方を把握し、働き続けるべき会社かどうかを見極めることができる場合があるからです。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【社会人の悩み】素朴な悩み・よくある悩みと対策)
新入社員が電話を取らないといけない理由
会社に貢献できる「役割」だから
電話対応業務を行うメリットは以下3つです。
・会社内の理解が進む
・会社組織の本質を考えるきっかけになる
・会社の良し悪しがわかる場合がある
電話対応業務は、必ず発生する業務ですが、誰でもすぐにできるようになる業務でもあります。
このような性質を持つ業務だからこそ、毎年入社してくる新入社員に担当してもらうことが、新入社員の成長と会社の効率化、双方にとって最善だと考えます。
なぜなら、新入社員には最初の1年で会社への理解と貢献を終え、2年目以降はより専門性の高い、本質的な業務へとシフトしてほしいからです。
電話対応は他の人に取り次ぐ、もしくは折り返させる、取り次がない判断をする業務となります。
最初は緊張するかと思いますが、慣れれば誰でもできます。30年以上様々な会社を経験しましたが、できない人はいませんでした。
その上、他の人が自分の仕事に集中できる環境を作ることができます。
これにより、新入社員が会社に貢献できるのです。
もし新入社員が毎年入ってこない場合、その背景には様々な事情があると考えられますが、本記事の主旨とは異なるため、ここでは別の課題とします。
電話対応業務を説明した後に、上記メリットをそれぞれ解説します。
電話対応業務とは?
会社にかかってくる電話を適切に処理する業務
これは、お客様や仕入先からの連絡だけでなく、営業電話も含まれます。電話番号を公開しているほとんどの会社で、必ず発生する業務です。
電話業務を体験するメリット
・会社内の理解が進む
・会社組織の本質を考えるきっかけになる
・会社の良し悪しがわかる場合がある
それぞれを説明します。
会社内の理解が進む
・取引先を知ることができる
・社内の担当者を知ることができる
・普段話さない人と話す機会ができる
・仕事に早く慣れる
よく言われることは上記になります。これらにより、知らなければならないことを知ることができますし、コミュニケーションのきっかけにもなります。
確かにこれらは大事ではありますが、それ以上に大事なことが残りの2つだと私は考えています。
会社組織の本質を考えるきっかけになる
会社組織の本質は1人ではできないことができることです。これが会社の本質となります。
これを実現するため、会社は適切な分業体制を組み、抜け・もれ・ダブりなく効率的に業務を行います。
目的、分業体制、仕組み、ルールを決めて従業員が働くことで、「1 + 1 が 2 より大きくなる」相乗効果を生み出すのです。
(詳しくは、「会社組織」の本質とは?をわかりやすく解説を参照)
電話対応は、専門知識が不要でマニュアル化しやすい『作業』であり、これを新人が一括して担うことで、先輩社員は高度な『課題解決(=専門性の高い仕事)』という別の分業役割に専念できます。
このように分業をおこなうことで、最終的な会社の成果につながる体験となります。
会社の良し悪しがわかる場合がある
・「作業」を最小化している
・上記で空いた時間を課題解決に使う
・結果、儲かる可能性が高い会社になる
良い会社は、上記3つの流れが確立されています。逆に、これができていない会社は、非効率な「悪い会社」と判断できます。
会社は、お客様の課題解決を行うことで、対価(お金)をいただくことができます。
しかし、仕事には課題解決以外に、どうしても「作業」が発生します。この記事のテーマである電話対応をはじめ、伝票作成、日報作成などです。
その作業をどのように減らし、本来の仕事である課題解決に使う時間を増やすことができるかは、会社にとってとても大きな課題です。
経営層は社員に課題解決をおこなってほしいので、作業をできるだけ効率化することを考えます。
電話対応は作業に当たりますので、良い会社は対策が打たれています。対策が打てているかどうかは、以下のポイントで分かります。
・電話対応マニュアルがあるか?
・先輩が懇切丁寧に教えてくれるか?
それぞれを説明します。
電話対応マニュアルがあるか?
電話対応業務の効率化の唯一の方法はマニュアル化です。
電話対応は作業です。作業ということは、誰が対応しても同じ対応であるべきです。
言い換えると、トークフローを作ることができます。
例えば、「〇〇さんお願いします」と言われれば、その人につなげばいい。不在なら連絡を取り、折り返しをさせれば済みます。
「〇〇担当の方いますか?」は、ほぼ間違いなく営業電話です。「外出して戻りません」と言って断ればいい。
おおよそこの2つを知っておけば対応できます。
また、電話に出る際は、「お電話ありがとうございます。株式会社〇〇です。」
相手が名乗らなければ、「失礼ですが」と聞けばいい。このようにすべてトークフローになります。
トークフローがあれば、先輩社員がその都度いちいち教える必要はありません。
もしなければ、先輩社員が時間を使って教えないといけません。
これを無駄と思うかどうか?で作業に対する会社の考え方がわかります。
先輩が懇切丁寧に教えてくれるか?
作業を懇切丁寧に教えてくれるほど無駄な時間を使っています。
間違いないように言いますが、作業を懇切丁寧に教えてくれる会社は悪い会社である可能性が高いです。
先輩が優しく教えてくれるのは素晴らしいことです。しかし、『会社』という組織の仕組みとして見た場合、マニュアル化できる作業に時間を割くのは、本来やるべき課題解決の時間を奪っているとも言えます。
つまり、個人としての先輩は良いが、組織としての仕組みが非効率的である、という視点で会社を見ることができます。
まとめ
電話対応業務は、新入社員が組織に貢献するための最初の、重要な業務です。
ただし、これはあくまで新入社員の期間に限定された役割です。
また、以下の観点を持っておくことをおすすめします。
・会社内の理解が進む
・会社組織の本質を考えるきっかけになる
・会社の良し悪しがわかる場合がある
まずは1年間、「組織への貢献」と「自己の成長機会という二つの視点を持って、この業務に積極的に取り組んでみましょう。
他にも社会人の悩み「素朴な悩みと対策」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。