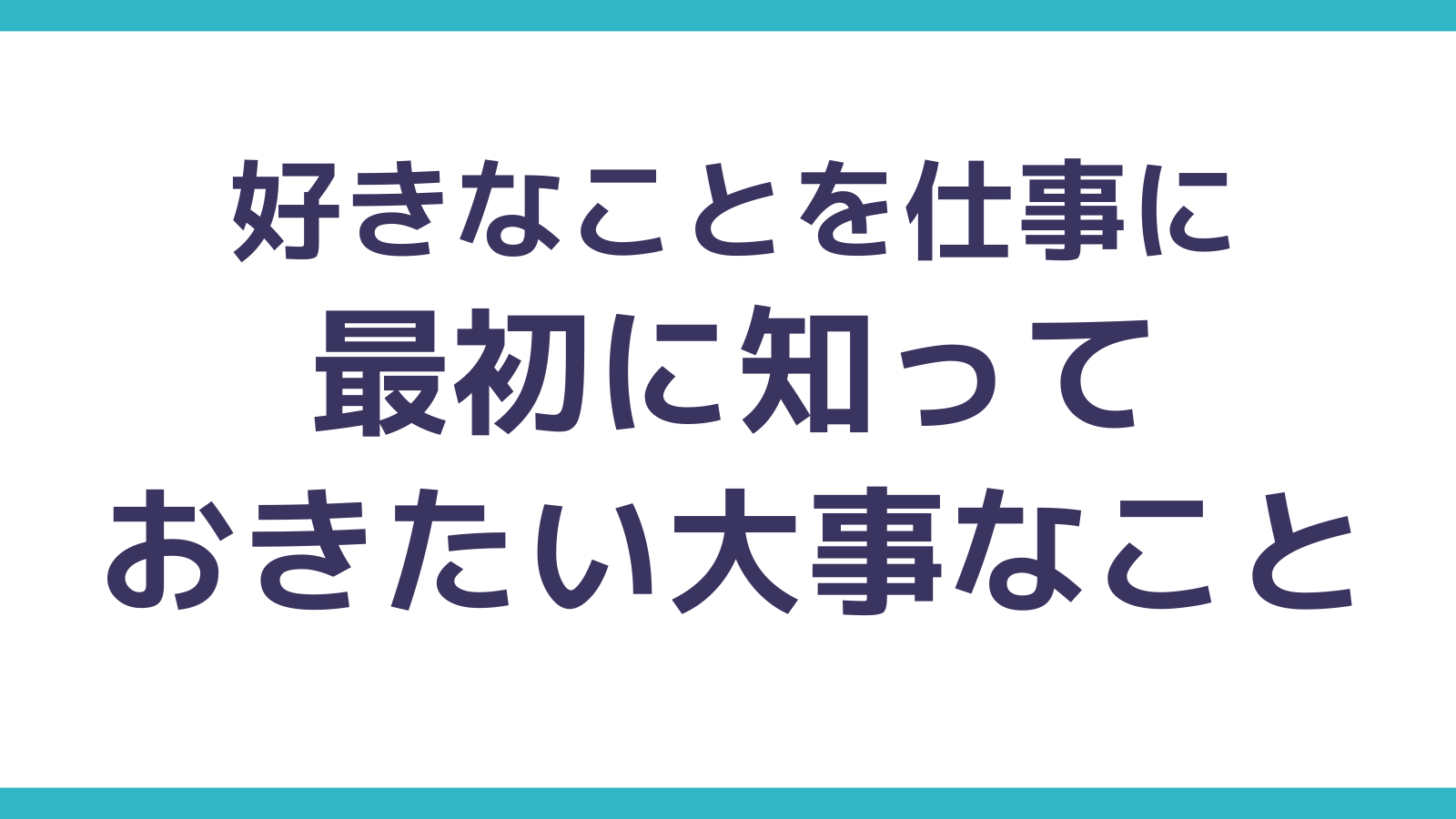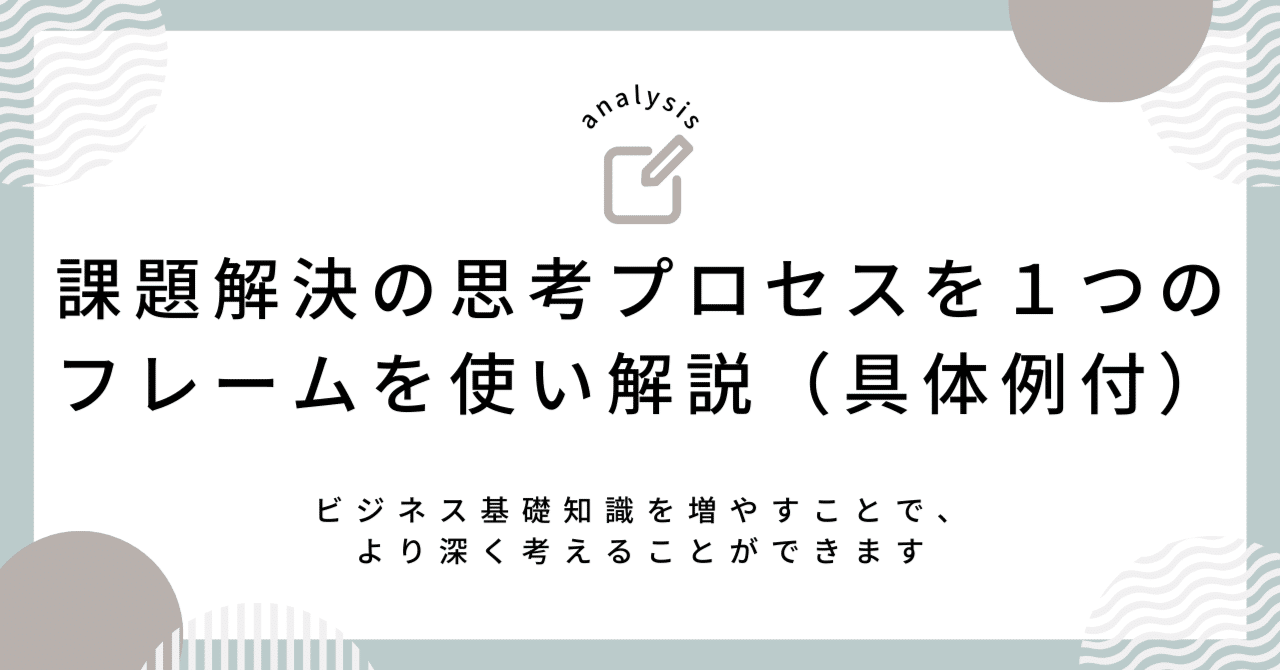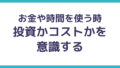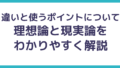多くの人が、働く時間を充実したものにしたいと考えているでしょう。
そのために、就職や転職の際、好きなことを仕事にできればと思っている方も多いはずです。
確かに好きなことを仕事にできると、充実感があり、やりがいが高い状態で働けるように感じます。
ただ、そのように思った時に、知っておいてほしいことがあります。知っておくだけで、選択を間違う確率を減らすことができるからです。
この記事では、この知っておいてほしいことをわかりやすく解説します。
この記事は、以下の経験を持つ「よしつ」が実体験から得た知見をもとに書いています。
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
(あわせて読みたい【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ)
好きなことを仕事にしたいと思った時に最初に知っておきたいこと
・好きなことが明確であれば仕事にすることを検討
・好きなことが少しでも不明確な場合は再検討
これが最初に知っておいてほしいことです。
選択を間違うことで自分の可能性を狭めてしまう可能性があるからです。
まずは、好きなことを仕事にしたいと思った時に、なぜそう思ったのか?を以下の1から3から選んで下さい。
1.好きなことが自分の強みだから
2.好きなことで頑張りたい
3.嫌なことはしたくない
上記で選んだ答えに、好きなことを仕事にしたいと思った理由やきっかけが含まれていますので、それぞれの思いに応じた対応が必要です。
まずは、このテーマを扱う上で、間違いやすい考え方を紹介した上で、それぞれの答えの深堀と対応方法を紹介します。
間違えやすい考え方
「好きなことをおこなう」と「好きなことでお金をもらう」は根本的に違う
よく間違いやすいことです。
前者は「自己満足」、後者は「他者満足」を求めることになります。
前者は好きだけが条件ですが、後者は、「好き」と「収益化できること」の両方が必要です。
例えば、「自分が着る服にこだわるのが好き」は前者になります。服装が好きだからと言って直接収益にはつながらないからです。
後者の例は、他の人の服をコーディネートするのが好き=アパレルで働いて収益化するとなります。
他の例では、ゴルフが好きは前者になります。プロになるという究極の収益化はありますが、稀なことです。
後者の例は、ゴルフを教えるのが好き=レッスンで収益化できるとなります。
このように好きがどうかだけでなく、他者に満足を与える要素が入っていることがポイントになります。
この違いがあることを前提に、以下の3つの答えの解説を読み進めてください。
1.好きなことが自分の強み
好きなことを極めていきましょう
働き方は、プロ、フリーランス、会社に入った後すぐに独立を想定、会社に入ったとしても専門職などです。
強みであれば、自己満足を追求することで他者満足を満たす可能性があります。
また、このように思えるのは、学生時代含めて多くの時間を過去に使い、他の人より明らかに才能があると認識できているからでしょう。
好きなことで生計を立てるのは大変ですが、スタートラインには立っています。スタートするかどうかは皆さん次第です。
2.好きなことで頑張りたい
リスクを事前に知りましょう
この答えを選ぶ方は、好きなことに関連した会社に入って働く選択をしたい人がほとんどでしょう。
多くの人が望むパターンで、うまくはまればいいですが、リスクが3点あります。
・5年後も好きでいられるか?
・好きなことが制約される可能性
・入社した会社で望まない業務に配属される
それぞれ解説します。
5年後も好きでいられるか?
今の好きなことが本当に好きですか?
今本当に好きだと言い切れる場合、5年後も好きでいることができるでしょう。
ただ、言い切れないと少しでも感じた場合、年齢を重ねることで好きでなくなっている可能性があります。
年齢を重ねることでたくさんのことに出会います。視点も変わったり、本当にしたいことに出会うことがあるからです。
好きなことが制約される可能性
好きなことが自由にできなくなる
例えば、ゴルフが好きでゴルフ用品業界の会社で働いたとします。
当然働く会社の商品以外は使えなくなります。これでも大丈夫でしょうか?
単純に好きであれば何の制約もないですが、仕事にすることで制約が発生することが多くあります。
入社した会社で望まない業務に配属される
希望しない部署への配属や異動の可能性
好きな業界の会社に入っても、経理配属の可能性もあれば、新規事業の配属の可能性、好きな業界とは違う部門への異動の可能性もあります。
結果、好きなことを仕事にしたいという思いは実現しなくなります。
残念ながら、会社が会社都合で決めることです。
リスクを感じる場合
好きではなく、嫌いを排除する
上記3点で少しでもリスクを感じるのであれば、「好き」で選ぶのではなく、「嫌いを除いた」残りをすべて対象とすることがオススメです。
私もこの選び方をしました。
私の場合は、自社で扱う商品を家族に売ることをしたくなかったので、BtoCの業界はすべて排除しました。
次に、金融と不動産は金儲けの権化のように感じ、好きになれそうもなかったのですべて排除しました。
そして残った業界の中から選ぶようにしました。
30年以上前の判断ですが今でも同じ基準です。嫌いなことは基本変わらないのでしょう。
生理的にあうか?友達・家族に商品を勧めることができるか?という観点で見てみると、嫌なものが浮かび上がると思います。
もっというと、なんか嫌という感覚でも大丈夫です。好きなことへの思いを少し抑えて、視野を広げましょう。
まだまだ出会っていないことが、世の中はたくさんあり、新しい本当に好きなことに出会える可能性があります。
3.嫌なことはしたくない
考え方が間違っている可能性
この選択肢を選ぶ方は、好きなことに関連した会社に入って働こうとしますが、実は好きなことが明確に見つかっていない場合が多いと思います。
本来嫌なことはしたくないと思うのであれば、嫌なことを避けることが正しい打ち手となります。
嫌いなことを避けるために、いきなり好きなことを選ぶと、今は好きでも嫌いでもないことで、将来好きになる可能性のあることを排除してしまうことになります。
上記の「好きなことでがんばりたい」と思う人でリスクを感じる人と同じく、好きで選ぶのではなく、嫌いを排除する方法がおススメです。
好きなことの見つけ方
試してみる
この一択です。やってみないと好きかどうか判別できません。
世の中には本当にたくさんのことがあります。一生かかっても全てを経験できません。
だからこそ、なんでもチャレンジしてみましょう。その中に好きになることが隠れている場合があります。
そのためにも、好きになる可能性のあることと出会える可能性は広げるために、いきなり絞るのではなく、いったん広げてから絞りましょう。
残念ながら、早く出会える場合とそうではない場合があります。
ここに効率よくという方法はないので、二の足を踏まずに経験をしていきましょう。
また、いきなり見つけようとするのではなく、副業などメインの仕事に関係しない方法でやってみるのもひとつの方法です。
まとめ
・好きなことが明確であれば仕事にすることを検討
・好きなことが少しでも不明確な場合は再検討
これが最初に知っておいてほしいことです。
そして、自己満足を求めるのか?他者満足を求めるのか?も大事な視点となります。
自分の心の奥底に答えを持っている場合も多いので、その答えを大事にすることで、間違った判断が減り、選択肢が減るリスクが低減します。
他にもキャリアプランの「軸とタイミング」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
- 20代で一番大事なこと 「時間当たりの課題解決経験」
- 「会社を好きになる」たった2つの理由
- 社会人になった時に知っておきたい「本当に大事なこと」
- 「やりたいことを見つける方法」
- 「3年は我慢すべきか?」の判断基準
- 「仕事の環境を変えるタイミングとは?」
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。