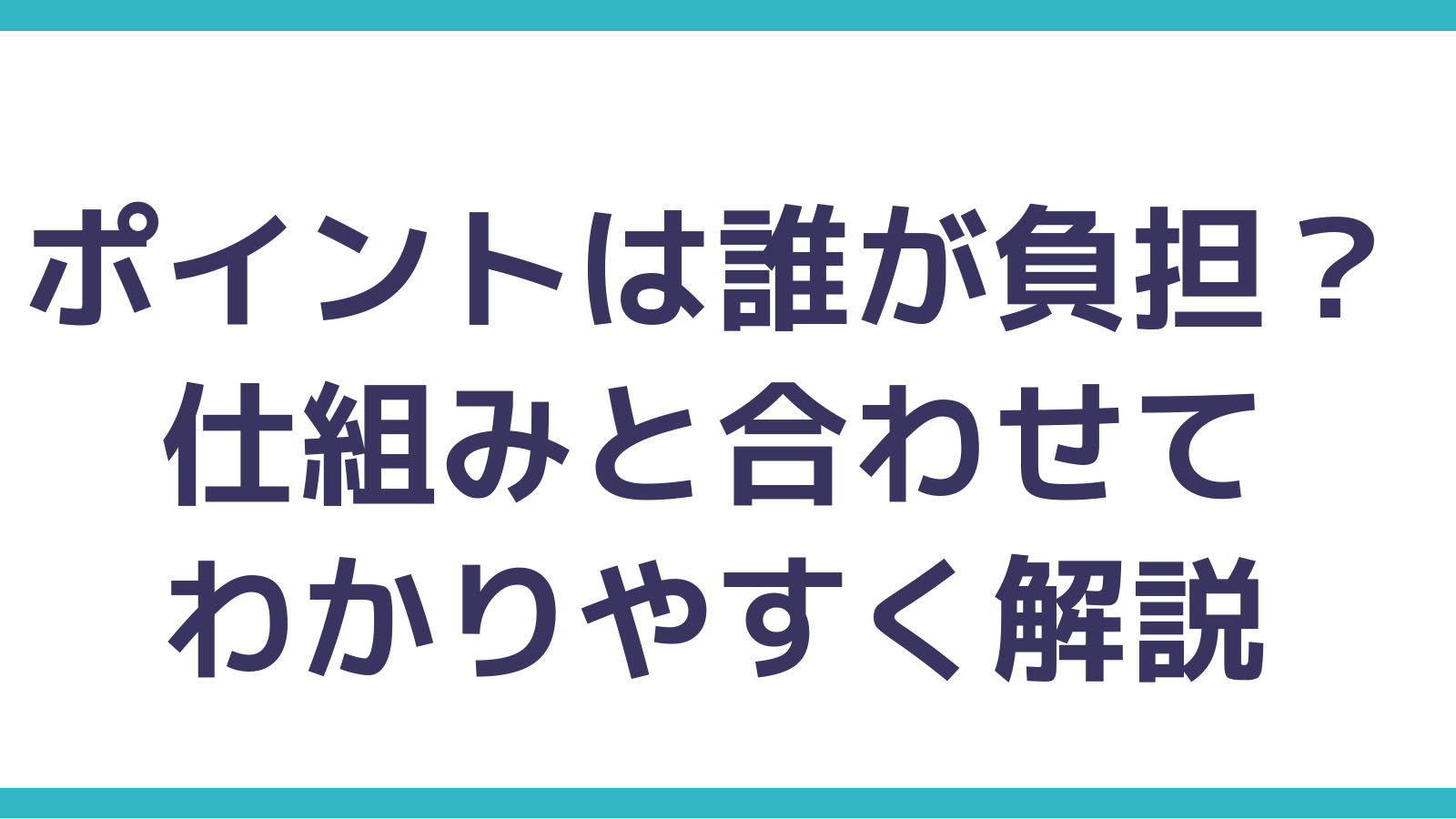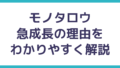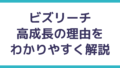とてもお得に感じるポイント制度。
ポイントを使って安く品物を手に入れたときはお得感がありますよね。
このポイント分を誰が負担しているかわかりますでしょうか?
この記事では、この疑問をポイント制度の仕組みを含めてわかりやすく解説します。
様々な企業で導入されていますが、有名な楽天市場を中心に解説します。
この記事は、
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【ビジネス用語】基礎用語解説)
ポイントは誰が負担している?
・基本は出店者が負担
・ポイントアップは、運営者もしくは出店者の自己判断
これが基本となります。
ポイント制度は、共通ポイントと自社ポイントの2つがあります。
自社ポイントは1つの企業だけで、ポイント運営をしています。各店舗等で発行しているポイントカードが1番わかりやすいですね。
共通ポイントとは、様々な企業やサイトで溜めたり使ったりできるポイントです。楽天ポイント、Tポイント、Pontaポイント、dポイントが有名です。
この記事では共通ポイントの中で楽天市場を中心に解説します。
まずは、ポイント制度について解説した後に、上記2つを紹介します。
ポイント制度の概要
・ポイント割引の目的
・共通ポイント制度の仕組み
上記2つに分けて解説します。
ポイント割引を設定する目的
「顧客の囲い込み」と、「個人情報の獲得」
ECサイト等がポイントを発行するのは上記を狙っているからです。
顧客の囲い込みは、ポイントが貯まって割引に使えることで、1つのサイトで繰り返しの商品購入が狙えます。
また、ポイント制度に登録してもらうことで個人情報を獲得できます。
これにより、直接消費者に商品案内等のアプローチができます。
その上、過去の購買履歴がわかりますので、どのタイミングでアプローチしたら購買行動をとってもらいやすいかを想定しアプローチすることができます。
例えば、商品の残量がなくなりそうなタイミングでアプローチすることで、リピート発注が狙いやすくなるなどです。
共通ポイントの仕組み
・ポイント利用の流れ
・ポイント制度の仕組み
・ポイントアップの仕組み
上記3つに分けて紹介します。
ポイント利用の流れ
楽天さんの共通ポイントを元に説明します。
消費者が1,000円の品物を買うとします。ポイントが1%(1P=1円とする)付くとすると、10P=10円分のポイントが商品取引完了後に付与されます。
次回購入時に、同じ1,000円の商品を買うとした場合に、貯まっている10P=10円分のポイントを利用して購入すると990円で買うことができます。
各店舗では、そのお客様と過去の取引に関係なく、10円引きで販売しないといけません。
ただ、このポイント割引分である10円は後に楽天から戻ってきます。
ポイント制度の仕組み
ポイントは、各店舗が負担し楽天が流通させています。
例えば、購入金額の1%分がポイントとして付く場合、各店舗が商品を販売した際に、販売価格の1%分を楽天に預けます。
楽天はそのポイントをプールします。
例えば、店舗が10,000円の商品を消費者に購入してもらったら、100P分を楽天に預けます。
次回以降に消費者が「ポイントを使って」商品を購入したら、一旦店舗はポイント分を割り引いた価格で販売します。
その後楽天は各店舗から預かってプールされているポイントの中から、ポイント換算金額を店舗に戻しています。
このような仕組みなので、どの店舗でも販売額の1%の負担が課されることになります。
もし、ポイントが使われた際に各店舗の負担にした場合、例えば、A店舗で高額な商品を購入して得たポイントを、B店舗で大量に使われた場合、B店舗は大きな損が出てしまいます。
したがって、各店舗で完結ではなく、楽天全体でのプール方式になっているのです。
ポイントアップ等の仕組み
次に、ポイントアップを説明します。何かに加入したら、2,000ポイントプレゼントとか、今購入したら、ポイントが倍になる等のキャンペーンがよく実施されています。
この場合は、広告宣伝費的な扱いとなります。
楽天自体が、ポイントプレゼント分の金額を負担して消費者に還元することで、購入促進や会員入会促進をおこなっています。
また、各店舗の判断でポイントを倍にする場合があります。
基本の1%は通常の仕組みですが、追加の1%分は店が負担して支払うことで成り立っています。
このように私たちがお得に感じるポイントアップ分は楽天もしくは店舗の広告宣伝の一環なのです。
したがって、カード2枚目に加入すると〇〇ポイント付与とか、ポイント3倍とかの商品が存在するのです。
楽天とアマゾンのポイント制度の違い
楽天さんは、消費者は基本的に購入価格の1%が付与されます。
但し、アマゾンはポイントがつく商品とつかない商品があります。
楽天は、店側に必須でポイントを負担させていますが、アマゾンは、店側がポイント分を負担するかどうかを判断しているから、付く場合とつかない場合があるのです。
ポイント割引の仕組みの「まとめ」
・基本は出店者が負担
・ポイントアップは、運営者もしくは出店者の自己判断
このような仕組みで私たちはお得な買い物ができる反面、ショッピングサイトに囲いこまれているとも言えます。
ただ、この仕組みがあることで、お得に商品を購入できているとも言えます。
他にもビジネス用語に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。