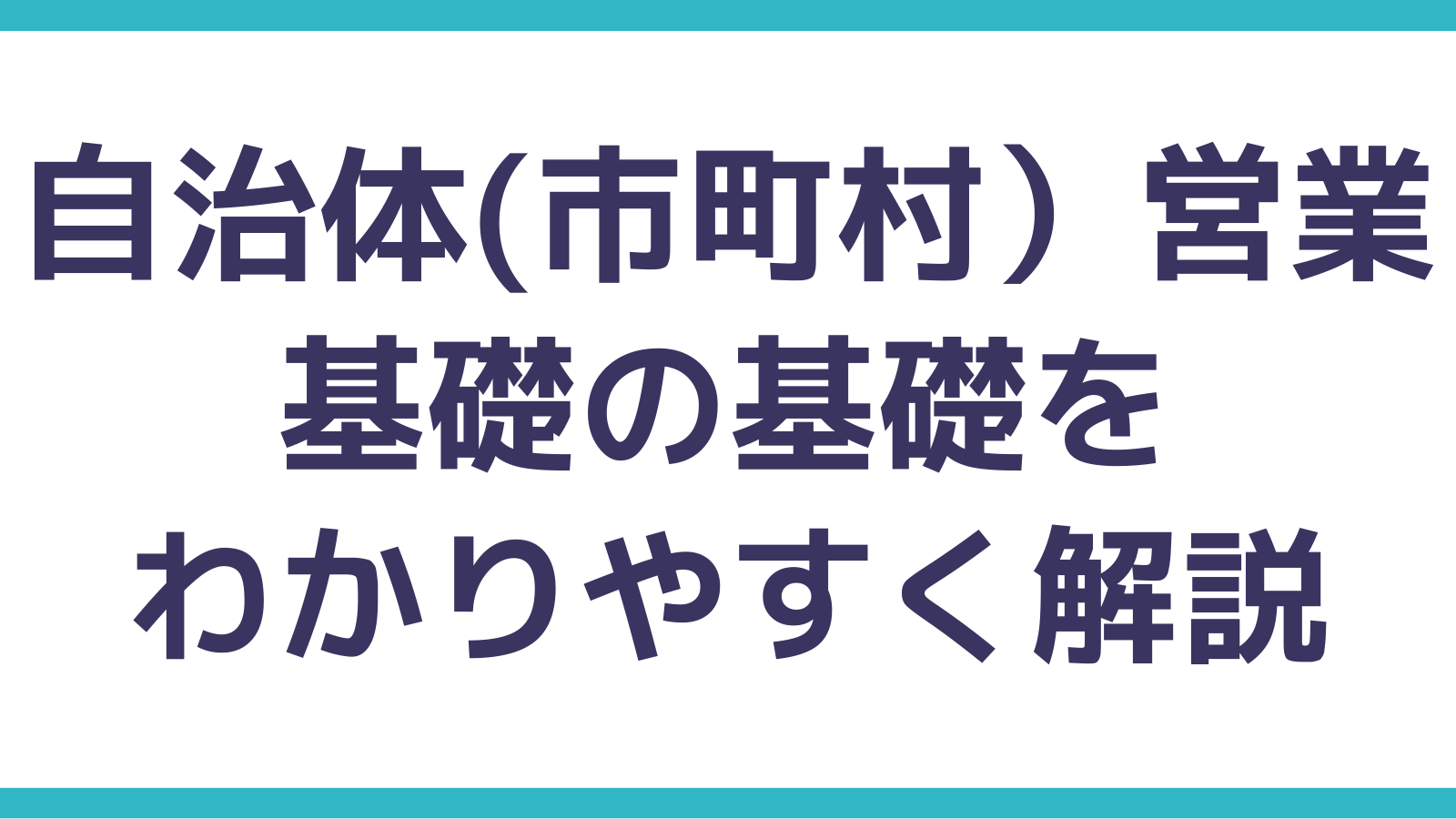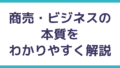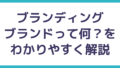企業への営業と、自治体(市町村)への営業は大きく違います。
企業への営業と同じく、良い商品だから普通に営業すれば売れるだろうと考えると、とても苦労します。
なぜなら、お金を使う考え方・判断の基準・決定までのプロセスが全く違うからです。
この記事では、自治体へ営業を検討している方向けに、自治体マーケットに参入するかどうかの判断基準と、企業への営業と自治体(市町村)への営業の違いとポイントを解説します。
この記事は、
・「全」自治体と取引してる事業の責任者をしていた経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
・1,000冊近い読書経験
これらの経験を持つよしつが実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい、知っておきたい ビジネス基礎知識)
自治体マーケットに参入するかどうかの判断基準
・ほとんどの案件が相見積低価格
・相見積案件以外は実績が大きな優位性
・新しい案件は営業開始後受注まで最低1年から2年かかる
上記3つを受け入れることができるかどうかが判断基準です。
それぞれを解説します。
ほとんどの案件が相見積低価格入札案件
新規リピート関係なく相見積で一番安くないと受注できない
これが、ほとんどの案件の受注基準です。新規はもちろん、1回受注できた案件のリピートでも入札となります。
自治体の職員は、発注先の選定基準が明確である必要があります。税金を使うので、必要に応じて住民に説明する必要があることと、発注先選定基準に納得してもらう必要があるからです。
結果、ほとんどの案件が相見積の入札案件となります。一番安かったという理由が一番説得力が高いためです。
相見積もりの入札案件は基本毎年価格が下がります。落札価格がわかるので、落札価格より下げて入札する会社が多いためです。
新規案件ならまだいいのですが、複数年同じ仕様の継続案件は、毎年価格が下がりとても安い価格になっています。
相見積案件以外は実績が大きな優位性
「同事業の他自治体での実績」がとても大事になる
相見積もり低価格入札案件以外にも、少しだけプロポーザル(提案)案件があります。詳細は後述します。
ただ、このプロポーザル案件の選定基準の中に「同事業の他自治体での実績」がとても大きなウエイトを占めています。
プロポーザル案件は、価格〇点、提案内容〇点、同事業の実績〇点などのように項目分けされた合計点のトップが受注先となります。この項目の中に同事業の優位性が必ず入ります。
提案される自治体職員は、基本3年程度で異動となりますので専門知識はありません。また、自治体で大事なことは住民サービスに瑕疵がおきないことです。
結果、失敗しない会社に発注したいとなりますので、同じ事業で他の自治体での実績が多い会社に点数が多く入る配点となります。
実績がないと受注できず、実績があれば受注しやすくなります。実績がない状態をどう実績がある状態にもっていくかが大きな壁となります。
新しい案件は営業開始後受注まで最低1年から2年かかる
新規事業は前年度に次年度の予算要求をしないと事業化できない
例えば、2025年度(4月~3月)に売上を上げたいとします。売上を上げたいサービスは、今自治体がおこなっていない新規事業だとします。
売上までの流れは次の通りです。
2024年度の夏までに営業をかけ、夏から秋にかけて自治体職員に予算要求をしてもらい、要求が通ったら3月の議会で最終承認されて初めて次年度の予算化ができます。
これでやっと2025年度に使えるお金ができるのですが、これで受注にはなりません。入札やプロポーザルなどの選定で他社に勝って初めて受注となります。
したがって、どんなに短くても半年、通常は1年以上かかるのです。
自治体は、予算設定は事業内容を明確にして設定されているので、通常の企業のように予算のやりくりをして受注となることはありません。
予算化が必ず必要ですし、予算設定のためには、前年の夏までには自治体職員に営業をし終えていないといけないのです。
この3つを受け入れて初めてスタートラインに立てるのが自治体営業です。
ただし、大きなメリットもあります。入金は保証されますし、案件は基本オープンで、莫大なマーケットに対して簡単に参入できます。
自治体マーケットの特徴
全自治体で同じ事業がおこなわれる場合が多い
国や県からの仕事+自治体独自のサービスを、各住民に直接提供することが自治体の仕事なので、どの自治体も同じ内容の仕事をしています。
予算を持っている自治体数は1718自治体(市町村)+東京の特別区23区=1741となります。
各自治体とも、住民票を発行、マイナンバーカードの発行、ワクチン接種、児童手当の支給、国民年金などをおこなっています。
これらだけでなく、さまざまな予算化された事業を着実にこなすことが自治体職員には求められます。
当然、限られた職員では対応できずに事業の運営すべてを外注することが多くなります。ここにニーズが発生しビジネスチャンスとなります。
実績が重要視されますので、何かの事業を委託できれば、同じ事業を他の自治体すべてに横展開できます。
ちなみに世間一般で「事業」というと大きな仕事をイメージしますが、自治体で使う「事業」とは「案件」という意味合いです。
例えば1つのポスターの印刷発注も「事業」ですし、単に広告掲載するだけでも「事業」となります。
事業は、単年度だけでなく、複数年度で実施することも多数あります。但し基本は単年度契約となります。
予算の仕組み
予算の仕組みについて説明していきます。
予算の大前提
予算化されないと1円もお金を使えません
まずは、最初に知っておいてほしいことが上記です。予算(事業ごとに予算化されたもの)がなければ、絶対にお金は使えないです。
もちろん急な出費のために期中に予算化する制度もありますが、余程の緊急性がないと議会を通りません。
これを知っておくことが自治体営業の大前提となります。
民間企業のように、売上が想定より上がった場合など、使う予定でないものを年度内に購入することがありますが、自治体では絶対ありません。
事業(=案件)ごとに年度の最初に当初予算として、何にいくら使うかが完全に確定してしまっているからです。
ちなみに期は4月~3月で統一されております。
予算決定の流れ
- 毎年5月~9月 翌年度に行いたい事業の下準備と計画策定
- 毎年8月~10月 翌年度に行いたい事業計画を各課から、取りまとめ部署へ提案
- 毎年10月~2月 来年度の予算決定に向けた、取りまとめ部署と各課との調整の上、自治体全体としての最終案の策定
- 毎年3月 3月の議会で翌年度の予算案の承認
- 毎年4月~3月 決まった事業を実施
上記流れを毎年繰り返します。予算については、大前提1年ごとに作成となります。
複数年にまたがる事業についても、基本は1年ごとの予算設定となっています。
上記流れなので、自治体職員が新しい事業をおこないたい場合、予算を使う前年度の8月までには計画し、見積りを取り、事業計画を提出しなければなりません。
ちなみにどのような事業にいくら予算化されているかは、各自治体の資料室に予算書があり、閲覧することができます。
自治体への営業方法
営業活動の基本
予算確定している事業を見つけて受注する
営業活動の基本は、予算が確定した事業を実施する際におこなわれる選定で勝ち抜き受注することです。
いくら前年度に自治体職員が予算申請をする際に手助けをしても、翌年度の予算を使う際には、入札やプロポーザル等で競合他社に勝たないと発注できません。
入札等には、以下の4つがあります。
・一般競争入札・・・誰でも入札でき、その中で一番安い金額の業者が落札
・指名競争入札・・・指名された業者のみが参加でき、その中で一番安い金額を入れた業者が落札
・随意契約・・・1社に声をかけ、その会社に発注(大半が事業総予算数万円以下のみ)
・プロポーザル(企画競争)・・・価格だけでなく、提案内容含めてトータルで判断
ほとんどの事業が、一般競争入札か指名競争入札です。
受注までのながれは2つ
受注するまでの流れは2つです。提供したいサービスを新事業として立ち上げてもらい受注する方法と、予算が確定している事業を調べて入札で受注する方法です。それぞれを説明します。
新事業として立ち上げてもらう方法
まずは次年度の予算化営業
提供したいサービスが事業化されていない場合は、新事業として予算化されることが大前提となります。
自治体職員の方に、前年の8月までに事業化提案を庁内にしてもらい、承認される必要があります。
営業のポイントは、まずは新事業内容がいかに住民にメリットがあるか?を理解いただくこと。
提案の方向で話が進んだら、事業内容をいかに自社に有利な事業にできるか?=事業の仕様書をいかに自社に有利な内容にするか?です。
最終事業内容は、仕様書という形で各業者に伝えられます。
この仕様書に自社しかできないことや、少数しかできないことを入れてもらうと、翌年度の入札等で有利になります。
当然、自治体職員は、1つの会社に有利になるようなことは一切しないので、住民のためになる提案と自社の強みをどう組み合わせて提案できるか?が重要となります。
これらは通常、仕様書提案や仕様書営業と言います。
予算確定している事業に入札して受注する方法
事業化されている案件を見つける
こちらの営業のポイントは、事業化されている案件の把握です。自治体は、公平性の観点から事業の募集内容を告知しないといけません。
ただ、これを集めるのがとっても大変です。事業は1年間で何千何万もあります。
その事業が、各自治体のHPで小さく告知していたり、庁内で告知していたりしており、各自治体で周知方法が異なるからです。
この課題を解決するには、民間の入札情報サービスNJS等の会員のサービスを受けることです。
各自治体の事業入札の募集がオープンになったものだけでなく、過去の事業の仕様書や落札価格を手に入れることができます。
年間70万円前後のサービスで、決して安くないですが、本格的に自治体営業するのであれば必須となります。
散らばっている入札情報を集めることは本当に大変な仕事だからです。
ちなみに東京23区・市町村は以下の共通サイトで入札情報を提供しています。但し、全案件ではないことと、仕様書が掲載されていませんのでご注意ください。
営業活動のポイント
実績作り
まずは事業者登録を各自治体で行います。登録しないと入札等の権利が発生しません。詳細は各自治体に直接聞けば教えてくれます。
大手の超優良サービスや、中小でも明確に他社と差別化できており、かつ非常に役に立つサービスは直接担当部署へ営業してください。その他の会社の方はまずは実績作りです。
営業時に実感しますが、自治体の担当者は、その自治体や他の自治体での同事業の実績があるかどうかを必ず聞いてきます。
実績があるといった場合、職員の方は安どの表情を見せますが、ないと言った場合はほぼ脈なしの対応に変わります。
この落差は経験するとよくわかります。自治体の職員は失敗できないので、経験がないところに仕事を出すリスクを負いたくないからです。
実績を積むには、一般競争入札において安値で受注することです。その結果、指名入札の指名を受けることができるようになります。
一般競争入札は完全オープンですが、指名競争入札の場合は、経験値が高い業者にしぼって声がけしてくれる方法だからです。
プロポーザルも、他自治体で同事業を行った経験があるか?が、選定の大きなポイントとなります。
鶏が先が卵が先かとなりますが、この壁を乗る超えることができないと大きな売上にはなりません。
新しい動きがあれば、各社横一線です。できるだけ早いタイミングで受注を獲得することで、他社よりも優位に立てます。
例えば、マイナンバーが始まると聞けば、各自治体は受付事務が発生します。できるだけ早く営業をおこなうことが大事になります。
また、自治体により、同じ事業でも、入札にする場合とプロポーザルにする場合がありますので、まずは入札でおこなう自治体を見つけて、安値で受注することもひとつの方法です。
見積依頼を受ける関係作り
自治体の職員は以下の場合に見積が必要です。
・新規事業を立ち上げる際の事業化申請時(毎年8月~10月)
・継続事業の来年度の見積(毎年8月から10月)
・事業実施年度に業者選定をおこなうための見積提出
とにかく上記3つがないと仕事が進みません。3はもちろん1、2についても相場観を反映させるために、「複数業者」から見積を取らないといけません。
まずは見積依頼を受ける関係性を作る(=覚えてもらう)ことが最重要となります。事業内容が固まる前にさまざまな話が聞けることと、提案の余地があるからです。
また、見積依頼が来た際は上記1から3のどれかを把握する必要があります。1、2はそれほど勝負価格で出さなくても大丈夫ですが、3は勝負価格で出さないと受注できません。
このように実績ができて、見積依頼を受ける関係性ができて初めてスタートラインに立てます。
そこから、更に実績を積み上げることにより、経験値及び事業理解を把握することで、関係性が強化されていきます。
自治体営業は、ここまで来てやっと競合と対等に戦う状態になります。
したがってとても時間がかかる営業となります。ただ、実績とノウハウがあるとても受注しやすくなる営業でもあります。
自治体営業基礎の基礎「まとめ」
・ほとんどの案件が相見積低価格
・相見積案件以外は実績が大きな優位性
・新しい案件は営業開始後受注まで最低1年から2年かかる
自治体への営業に参入するかどうかの判断基準は、上記内容を受け入れることができるかどうかがポイントです。
継続受注(年度またぎ)の場合も相見積です。このシビアな状況と、確実な入金+膨大なマーケットのメリットデメリットを踏まえて、営業を開始してください。
他にも、ビジネス基礎知識の記事をたくさん書いています。まずは、知っておきたい ビジネス基礎知識51選を参照してみてください。
ビジネスの知識を増やすには、本を読むことがおススメです。
失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。参照下さい。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。参照下さい。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。参照下さい。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
他にもたくさんの記事を書いています。参照下さい。

記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。