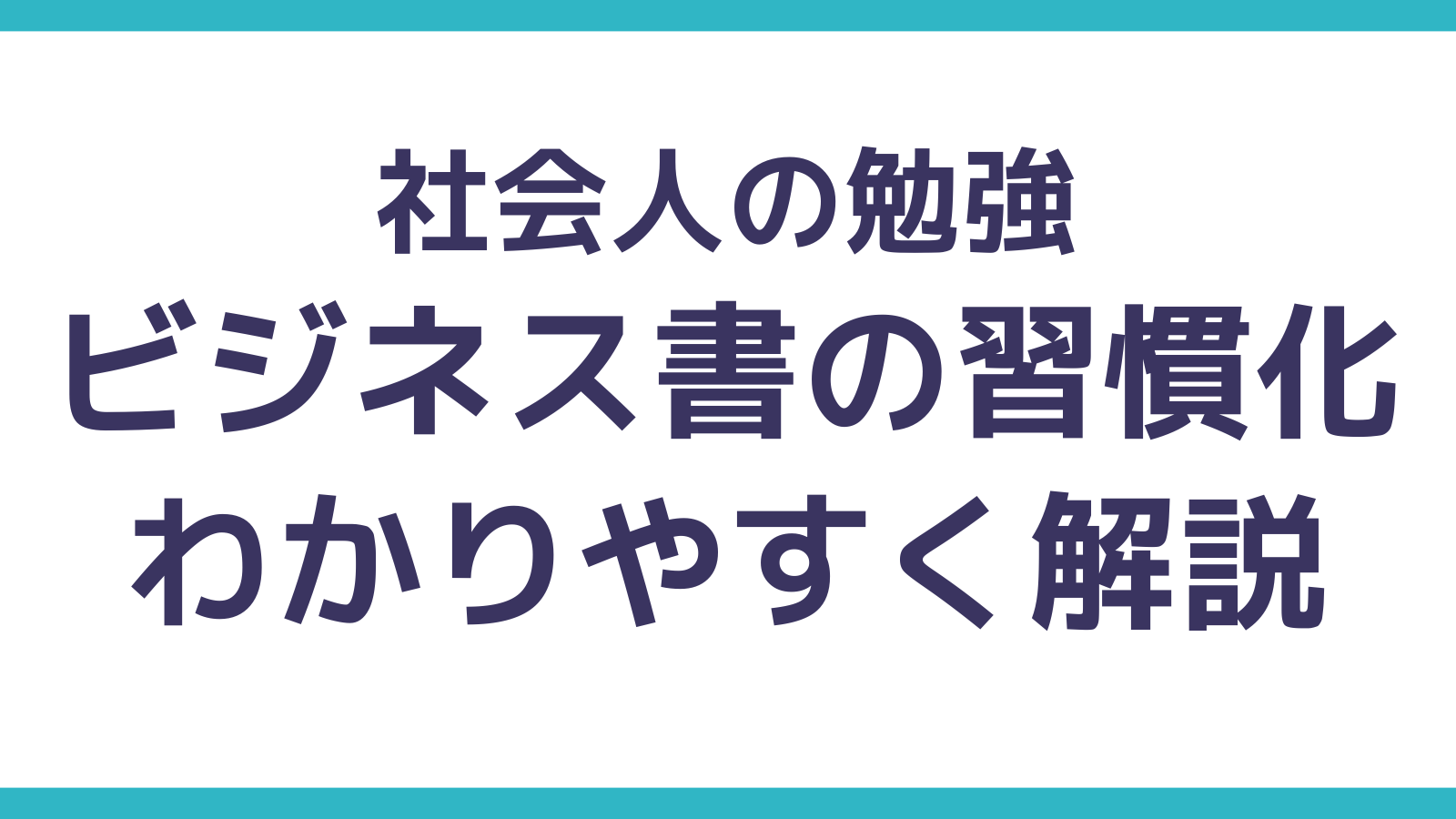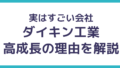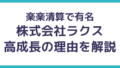社会人になって「何か学びたい」と思い、ビジネス書を手に取る人は多いでしょう。
しかし、いざ買ってみても、読み切れずに挫折してしまう人も少なくありません。
その多くは、最初の段階で誰もが陥りがちな3つの失敗パターンにハマっています。
この記事では、読む習慣化がつかない3つの理由を明確にし、それぞれの対策をわかりやすく解説しています。
この記事は、
・1,000冊近い読書経験
・営業担当・課長・部長・本部長・執行役員の経験
・風土の違う5社での経験
・数百名のマネジメント経験
・数千社への営業経験
・100回を超える勉強会の講師経験
これらの経験を持つ「よしつ」が実体験から得たことを元に書いています。
(あわせて読みたい【自己成長】定義から効率的な学びの方法を紹介)
ビジネス書を読む習慣がつかない3つの理由とは?
・最初に読むビジネス書を間違えた
・ビジネス書の読み方を間違えていた
・習慣化のコツを知らずに読んでしまった
習慣化できない理由は上記3つです。
まずは、ビジネス書を読む習慣化のメリットを紹介した後に、上記3つを解説します。
ビジネス書を読む習慣の大きなメリットは?
知識と学びの好循環が生まれる
ビジネス書を読む習慣がつくと、以下のような好循環サイクルに入ることができます。
・知識が身につく
・学びたい分野が見つかる
・さらに別の本も読みたくなる
このサイクルが回り始めると、1つのテーマを深く掘り下げるだけでなく、関連する他の分野にも自然と興味が広がり、深く幅広い知識を効率的に身につけられるようになります。
最初に読むビジネス書を間違えた
ビジネス書を読む習慣がつかない一番の理由
一番多いのがこのパターンです。スキルや能力が高い人は何とかしますが、私を含めた普通の人は、最初に読むビジネス書を間違うと絶対読む習慣がつきません。
最初に読むビジネス書の1つの正解と6つの不正解を具体例を含めて紹介します。
1つの正解
小説タイプのビジネス書
最初に読むのが正解のビジネス書は、「小説タイプ」のビジネス書です。
小説ではなく小説タイプです。普通のビジネス書とは違い、読みやすいように物語形式で展開し、合間に解説ページで内容の理解を深めることができるビジネス書のことです。最近とても多い形式です。
とても読みやすく書かれていることと、読むだけで学ぶべき内容が理解できるように工夫されています。
解説部分は読まずに小説部分のみ読んで見るのがおすすめです。
もっと言うと、学ぼうとせずに小説のように読むだけでOKです。
まずは、ビジネス書に慣れることが大事だからです。
解説部分は気になったら読んでみましょう。
6つの不正解
ここで挙げる6つのタイプは、あくまで読書習慣のない人が最初に読むと挫折しやすい、という意味です。
これらの本自体が悪いわけではないことをご理解ください。
ハウツー本
ハウツーが使えない場合が多い
ハウツー本は、最初に読む本としては良さそうに感じます。しかし、大きな限界があるのも事実です。
その理由は、解決方法が総論的になり、自分の課題に直接役立つ内容が少ないからです。
限られたページ数で、できるだけ多くの人に当てはまる内容を書く必要があるため、具体的な解決策ではなく、誰もが知っているような「総論」に終始しがちです。
「ハウツー本なのに、なぜか答えが見つからない」と感じるのは、このためです。
大学教授が書いた本
実務解説ではなく抽象化されている
私たち実務者は実務で役立つ情報を求めます。特に若手の方は、出来るだけ実務に直結している内容でないと役に立ちません。
ただ、大学教授が書くビジネス書は抽象化されたものです。
なぜなら、大学教授の仕事は現象を抽象化し理論化することだからです。
したがって、最初に読むと実務に役に立ちにくくなります。
ある程度実務を重ねると、抽象化や理論化が必要になります。その時に読みましょう。
他人のことを書いた本
取材の限界がある
有名人や経営者など、他人のことを書いたビジネス書も多く出版されています。
しかし、こうした本は、本人たちが本当に伝えたかったことと違う内容になることがあります。
編集者には意図があり、いくら取材しても本人以外が本人のことを深く理解するのは難しいからです。
たとえ分かりやすく書かれていても、取材内容に限界があるため、読書習慣がない人が最初に読むのはおすすめできません。
外国の方が書いた本の翻訳
文化的背景が違うため理解しづらい
外国の方を卑下しているわけではありませんが、前提となる考え方や伝える方法及び翻訳の限界があります。
日本と欧米では、生活における基準となる環境・習慣・人と人とのつながり方・考え方、仕事の分担方法などかなり異なります。
結果、日本基準で考えると、対応できないことが書かれている場合もあります。
その上、読むとわかりますが、日本の文章に慣れている人にとって、どうしてもすぅーと文章が頭に入ってこない読みにくい文章になっています。言語と翻訳の限界です。
とても良いことを書いている場合も多いですが、最初は避けましょう。
資格を取るための本
実務に役に立つ資格は少ない
いきなり資格にはいかないこと。そして資格を取ろうと考えないことが大事です。
なぜなら、資格はあくまで知識でしかありません。資格を持っていることイコール能力があるわけではありません。
資格を取った状態とは、あくまでスタートラインに立つだけです。実務で使って始めてスキルや能力に変わるからです。
(知識と能力の違いは「知識と能力とスキルの関係」をわかりやすく解説を参照)
例えば、採用面談の場面で、資格が記載された履歴書を見ても、採用する側はほぼ参考にしません。特に役に立たないからです。
もちろん、士業(弁護士、税理士等)などで資格がないと仕事ができないものや、資格があることで、仕事の範囲が広がるものは別として、資格取得は時間をおいて考えましょう。
ビジネス書の読み方を間違えていた
・無理に最後まで読もうとする
・次に読む本を用意しておかない
・内容をしっかり理解しようとする
これらの間違いは、せっかくの読書を「辛いタスク」に変えてしまいます。
ここからは、それぞれの対策を解説します。
無理に最後まで読もうとする
失敗と思った瞬間に読むのをやめる
読みにくい(=失敗した)と思ったらその本はすぐに読むのをやめてください。
とにかくやめる。これ一択です。
無理に読もうとすると、絶対に読み進めることができず、読む習慣がつかずに読むことをやめてしまいます。
私の家にも数十冊も読んでいない本が眠っています。
せっかく買ったのに読まないのはもったいないと思いますが、とにかくあきらめましょう。
対策は、新品ではなく中古でビジネス書を買いましょう。特にアマゾンで1円など安く販売しているビジネス書がそすすめです。
※著者の皆さんごめんなさい・・・。
少し古いビジネス書となりますが、内容的には問題がないことが多いです。
更に、本が家に届いた時に少しでも違うと思ったら、読まないようにしましょう。それが、出来るのも1円(送料別)だからです。
次に読む本を用意しておかない
常に複数の本を用意する
必ず、次に読む複数のビジネス書を手元に置くようにしましょう。
読み終わったタイミングで、すぐに次のビジネス書を読めるようにしておくことで、読む習慣を定着させることが理由です。
もし余裕があれば、難しい内容のビジネス書とやさしい内容のビジネス書をカバンの中に入れておくことをおすすめします。
その日の気分によって、難しいビジネス書は読みたくない日が誰でもあります。
その時に、軽めのビジネス書が手元にあると、読む習慣を継続することができるからです。
内容をしっかり理解しようとする
1回目はさっと読む
1回目の読み方は、内容を理解しようとしなくてもいいです。まずは読む習慣をつけることが大事です。
理解できない部分が必ずありますので、そこにこだわると読む習慣が止まってしまいます。
私は、1つのビジネス書を2回読むようにしています。
1回目はとにかく何も考えずに読み進める。理解できなくても読み終えてしまいます。
そして、時間を空けてから2回目を読みます。
2回目は内容をしっかり理解しながら読むようにします。
途中で理解できないことが出て調べたりしても、1回読んで全体の流れを理解できているため、すぐに流れに戻れるからです。
習慣化のコツを知らずに読んでしまった
・終了時間を決めて実行
・電車の中は学びの時間と決める
・回りの人に言ってしまう
上記が習慣化のコツです。それぞれを解説します。
終了時間を決めて実行
平日の〇時までは学ぶと決める
業務終了後から○時まではビジネス書を読む時間と決めましょう。
よく似た方法で、業務終了後何分間ビジネス書を読むと決める方法がありますがおすすめしません。
仕事が遅くなる=疲れた時に苦痛となり、続かなくなるからです。
したがって、〇時までと決めます。あわせて場所も決めておきます。
会社の最寄り駅の近くがおススメです。電車にのってしまうとスイッチがきれてしまうからです。
私は会社近くの飲食店で時間を決めてコーヒーを飲みながら知識をインプットする時間にしています。
電車の中は学びの時間と決める
通勤の行き帰りの電車に乗っている時間を活用
人により時間は変わると思いますが、電車の時間を学びの時間と決めましょう。電車に乗った瞬間にスマホではなく、ビジネス書をカバンから出しましょう。
まずはビジネス書を持つことが大事です。これにより、スマホを見る癖が解消できます。
これは本当に習慣だと思います。スマホを触る癖がつけば、ずっとスマホを触っているし、ビジネス書を触る癖がつけばずっとビジネス書を読む癖となります。
私は、会社に行く時は物事を考える時間(ブログのテーマや内容等)、自宅に帰る時は、ビジネス書を読むようにしています。
回りの人に言ってしまう
周りの人にビジネス書を読んでいることを言ってしまう
周りの人に継続したいことをしゃべってしまうのもとても有効的な方法です。
言うことで、やめることが恥ずかしくなりやめにくくなるからです。
ビジネス書を読む習慣がつかない3つの理由と対策の「まとめ」
・最初に読むビジネス書を間違えた
・ビジネス書の読み方を間違えていた
・習慣化のコツを知らずに読んでしまった
この3つの失敗をせずにビジネス書を読むと習慣化できる可能性が高まります。ぜひとも試してみて下さい。
読書週間がつくと、1日30分平日のみだけでも、月600分=10時間、年120時間となります。
塵も積もればすごいことになり、その時間分知識量が増ます。
上記で書いているように、失敗してもいいように中古で買う、電車に乗ったらまずは本を開く、理解できなかったらその本を読むのをやめる位の気軽な感じで始めてみましょう。
他にも自己成長の「2つのおススメする方法」に関する以下の記事を書いています。参照下さい。
- 「社会人の勉強」おススメする2つの方法
- ビジネス書を読む「3つのメリット」
- 文章を書く2つの「メリット」と文章力の2つの「鍛え方」
- 読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人
- 「Kindle端末」の選び方とおススメ機種
- オーディオブック「Amazon Audible」「audiobook.jp」を比較
当サイトでは以下のカテゴリーで200以上の記事を掲載しています。気になる内容があれば参照下さい。
・【 概念の本質 】ビジネスの根幹・基礎用語の本質・人の本質
・【キャリアプラン】軸とタイミング・成長ロードマップ
・【 自己成長 】定義から効率的な学びの方法を紹介
・【社会人の悩み 】素朴な悩み・よくある悩みと対策
・【 課題解決 】問題課題、戦略戦術フレームワーク・法則
・【ビジネススキル】必須スキル・思考方法・コミュニケーション
・【ビジネス用語 】基礎用語解説
・【 企業会計 】一つの軸で理解・収益構造とコスト分析
・【企業実例研究 】成長企業の成長理由
・【 会社の環境 】良い会社の特徴
・【 転職 】転職前の心構えと知識・具体的な方法
・【 読書ガイド 】テーマ別おススメ本
以下で失敗しない本選びのために、何回も読んだおススメ本を紹介しています。

何何回も読んだおススメ本!ビジネスに必要な4領域13テーマに分けて紹介はこちら
本の購入費が気になる方は、アマゾンさんが電子書籍の定額読み放題サービスをおこなっています。

読み放題「Kindle Unlimited」をおススメする人しない人はこちら
本を読むのが苦手な方には、プロのナレーターが本を朗読してくれるサービスがあります。

オーディオブック2強「Amazon Audible」「audiobook.jp」を徹底比較はこちら
本の置き場や持ち運びが嫌な人は、アマゾンさんのKindle(キンドル)端末がおススメです。
(詳細は、Kindle端末の選び方とおススメをわかりやすく紹介を参照)
記事を用語から探したいなら、以下を参照下さい。